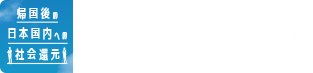(上)任国のオフィスにて同僚との仕事風景
(下)現地の様子を同僚と確認する市川隊員
- 知識やスキルを生かして
自分自身の可能性を広げる 私は大学卒業後、建設コンサルタント会社に入社しました。主に地盤調査や地質調査の業務を行う日々の中で、自然災害から人命や社会生活を守る土木工学を学び、今生きている私たちの生活に密着するこの分野にとても魅力を感じました。
入社2年目のとき、自分の学んだ知識や能力が役に立つ、何か新しいことに挑戦してみたい、と考えるようになります。そのタイミングで、大学時代の後輩からJICA海外協力隊の存在を教えてもらい、休職して応募することに決めました。
国境を越えて働いてみたいと思った理由は、今成長している国の姿を自分の目で確かめたかったからです。日本国内には至るところに建物があり、今後はその維持や管理をする時代に突入しています。ですが、今まさに建設ラッシュの渦中の開発途上国に行くことは、これから建設業界で生きていく上でも、自分の経験値と専門性を高められるよいきっかけになると考えました。
赴任地は、フィリピンのルソン島北部、ラ・トリニダードという町でした。派遣先で私が目標にしたのは、現地の人たちだけでも持続可能な防災の仕組みづくりです。当初は避難基準や避難計画などの作成を支援するという要請で現地入りしたのですが、赴任後、フィリピン国内のボランティアをコーディネートする機関から、赴任地周辺の小学5・6年生へ防災教育を行うことも求められました。
その活動をする中で、より広く地域住民に向けて自分の知識を生かした活動ができるのではないかと考え、現地スタッフと一緒に「地域住民への防災意識の啓蒙」を長期スパンのプロジェクトとして行う計画を立てました。JICA海外協力隊の長期派遣は一人の任期は基本2年間ですが、プロジェクトによっては、一人の隊員が任期を終えたあと次の隊員に活動を引き継いでいくことを前提に、複数年に渡って計画することもあります。 そこで、私が担当する最初の2年はハザードマップ作成や防災支援のためのIT技術導入、学生への防災教育用の資料作成などをメインに行い、次の2年を担当する隊員は、それら資料を使った防災支援や啓蒙活動、そして最後の2年の隊員は、それまでの活動分析や資料の改善をする、という具体的なPDCAサイクルを確立して、地域住民がアクセスしやすい防災情報の基盤づくり、そして現地の人たちが継続して運用できる仕組みづくりを計画しました。