2024年3月5日、八王子市立石川中学校の3年生の生徒約170名の皆さんに向けた、JICA国際協力出前講座を行い、JICA海外協力隊員の舘野眞歩さんからマダガスカルの様子と教育問題について学びました。3年生の5クラスがそれぞれ5つの教室から参加しました。午後の授業の5校時と6校時を連結させて話を聞くことができた充実した出前講座でした。
まず、舘野さんがマダガスカル語で「Manao ahoana!(こんにちは)」とあいさつして授業が始まりました。次に簡単な自己紹介タイムがあり、舘野さんがどうして国際協力に興味をもつようになったかの経緯についてお話されました。自己紹介のあとは、さらに詳しくマダガスカルについての説明をしていただきました。国内の低い就学率や栄養失調の問題、犯罪や事件、環境破壊といった社会課題が根深くあることも教えていただきました。
現地で舘野さんがとられた写真もいくつか紹介され、生徒は興味深く写真を見ていました生徒たちが、なぜマダガスカルの人々は地面に洗ったばかりの洗濯物を置いて乾かそうとするのかと不思議そうな顔をしてお話を聞いている姿が印象的でした。現地で生活をしながら感じる不便なこととして、頻繁に停電になることや、雨が降ると舗装されていない土のままの道路がひどくぬかるんでしまい自転車での走行が難しくなるといったエピソードが紹介され、いろいろな「不便」が日常茶飯事なのだとのお話がありました。実際に、雨でぬかるんだ赤土の道の写真を見ながら、どこへ行ってもほとんど路面の舗装がされている日本の道路とは違う現地ならではの事情について知ることができました。
少しずつマダガスカルの街並みや暮らしの様子についてイメージがつかめた頃に、舘野さんが従事されているお仕事について紹介をいただきました。農村に暮らす女性たちに焦点をあてて、生活改善や生活向上のために、小規模ビジネスの発案、識字・計算教室の開講、小規模貯蓄・貸付といった取り組みを進められていることをお話いただきました。
授業の後半はいよいよ出前講座のテーマであるマダガスカル社会と教育のお話に進みました。農村でよく見られる事例として、就学年齢にある12歳の少年アラン君のお話を紹介してくださいました。学校に通わずに両親の農業の手伝いをしたり、日雇いの仕事をしたりして家族の生活費を稼ぐ12歳のアラン君。どうしてマダガスカルの子どもたちがアラン君のように勉強を続けることが困難な状況に置かれてしまうのか、その背景にある根深い問題を説明いただきました。今着ている服や履いている靴はどこでどんな人が作ったのか、その国で自分たちと同じぐらいの年齢の子どもたちが働いていることはないだろうか、人々は低賃金で劣悪な環境で働かされてはいないだろうか、などと語りかけました。
最後に舘野さんからメッセージがありました。“学ぶことは、世界を広げること。学ぶことは、社会を豊かにすること”―というメッセージが生徒たちに贈られました。卒業をひかえた中学校3年生の生徒の皆さんへの力強いメッセージでした。新しい場所で、いろいろな新しい経験をしながら、日々チャレンジする舘野さんのメッセージを生徒たちはしっかりと聞いていました。その後、15分ほどの質疑応答タイムになり、各教室の生徒から舘野さんへの質問がありました。「マダガスカルで流行っている日本のものはありますか?」「マダガスカルで美味しいと感じる食べ物は何ですか?逆に、苦手な食べ物はありますか?」「子どもたちはどんなことをして遊んでいますか?」などの質問が次々と出ました。マダガスカルはフランス領であったため、おいしいフランス料理を日本よりも安価で食べることができるという話を紹介されると、生徒たちは食文化と歴史の関連を感じ「なるほど!」と興味深そうに、うらやましそうに聞いたのが印象的でした。質疑応答タイムは、リラックスした様子で興味がわいたことを直球で質問でき、すぐに舘野さんから現地ならではのエピソードを交えた答えを伺えて、生徒たちはとても充実した時間だったのではないでしょうか。

私たちはなぜ学ぶのか。講師からのメッセージ

アフリカのとこわざ。「早く行きたければ、一人で進め。 遠くまで行きたければ、みんなで進め」

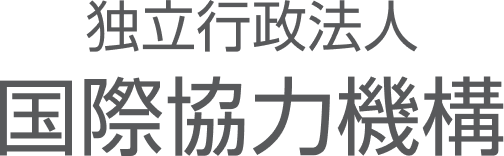









scroll