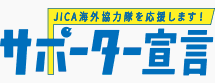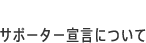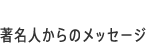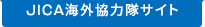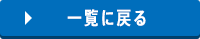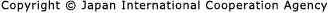一般財団法人あしなが育英会「一般財団法人あしなが育英会」
あしなが運動から始まる、50年以上の歴史を誇る教育団体
あしなが育英会は、病気や災害等で親を失った子どもや親が障害を負っていて十分に働けない家庭の子どもたちを救済し自立を支援する団体である。阪神・淡路大震災で日本が受けた支援への恩返しとして、本会が海外で初めて実施したウガンダでの教育支援事業は、今ではアフリカ47か国300人を超える奨学生支援へと成長を遂げている。これを牽引しているのがJICA海外協力隊の経験を持つ一人の女性だと聞き、早速お話を伺うために東京・千代田区にある当会本部を訪れた。今回、事務局長の関亨江さんと、元協力隊でアフリカ事業部100年構想第1課課長の沼志帆子さん、お二人の声をご紹介する。
事務局長 関亨江さん
創始者の体験から始まった社会運動から
あしなが育英会へ
本会のような非営利組織の運営は、企業や個人の寄付金によって支えられています。しかし本会に寄せられる寄付金の90%以上が個人からだというと、多くの人に驚かれます。このような形で50年以上にわたり組織が運営できているのは、私たちの事業が社会運動という側面を持っているからだといえます。
そして、そこには今も現役で活躍する創始者の玉井義臣の存在があるからではないでしょうか。玉井は若い頃に交通事故で母親を亡くしました。それをきっかけに、日本で初の交通評論家となってあらゆる交通犠牲者の問題を告発すると共に、同じ志を持つ仲間と交通事故によって親を亡くした子どもたちを救済する活動を始めました。これが本会の出発点です。この活動は「あしなが運動」と呼ばれ、やがて自動車業界や国を巻き込み、救急医療体制の確立、道路交通法の改正、交通遺児育英会の発足など、大きな社会的な動きへと広がっていきました。
「あしなが運動」が始まった頃、玉井と共に行動した人々のなかに7人の若者がいました。私たちが「七人の侍」と呼んでいる彼らは、玉井の熱い想いに突き動かされ、調査から事務作業まで寝る間も惜しんで活動に取り組んだそうです。高度経済成長期を象徴する言葉に「月月火水木金金」というのがありますが、まさに休みもない状況だったと聞いています。多様な働き方が推奨される今日においては想像もつきませんが、解決すべき課題に向けて人やお金を動かしていかなければならない状況では、ときにはルールやプロセスに縛られず心血を注いで行動することも必要なのかもしれません。
玉井というのは、課題解決のためにお金が必要だと分かったら、有るものを全て出すだけでなく無くても出そうとしてしまう人間です。宵越しの金は持たない、とでもいうような潔い人柄に人々は魅了されて無我夢中でついていってしまう……。こうした動きこそが運動と呼ぶべきものであり、本会の原動力となっているものです。
「あしなが運動」は、その後、交通事故だけでなく、病気や災害などで親を失った子どもたちも支援するようになります。こうして時代の変化に合わせて、交通事故以外の遺児も応援することを目的に本体からスピンオフして作られたのが、現在の「あしなが育英会」です。
活動のメインは遺児の高校生、大学生、専門学校生等に対する奨学金の給付ですが、奨学生たちの自立をゴールとしており、そのために仲間づくりの場や研修プログラムなど、様々な選択の機会を提供しています。なかでも「つどい」というプログラムは、遺児たちが孤独を感じることなく広く社会の目に開くようにと企画された宿泊型のイベントで、長年多くの奨学生たちが参加してきました。私たちが単なる奨学団体ではなく、教育団体と名乗っている理由はこうした仕組みにあるのです。
 事務局長の関亨江さん
事務局長の関亨江さん
国境を超えたあしなが運動
グローバルな視野を持つ協力隊への期待
2000年代初頭、世界中でエイズ感染による死亡者数が急増していました。この状況に対処するため、私たちは最も死者数が多かったとされた国の一つのウガンダで教育支援活動を始めました。これが、本会が海外に向けて舵を切った最初の一歩となりました。
そこから遡ること5年ほど前、1995年に起きた阪神・淡路大震災では569人の遺児が生まれ、世界中からたくさんの支援を受けました。その恩返しとして海外に向けて何かできないかと考えたのは、やはり玉井でした。2003年には支援拠点である「レインボーハウス」が首都カンパラ郊外のナンサナに完成し、2006年には当国の遺児が初めて日本の大学への留学を果たしました。
こうして始まった海外事業は、2014年に「あしながアフリカ遺児高等教育支援100年構想(以下、100年構想事業)」というプログラムとして、サブサハラ・アフリカに広がっていきました。なお、玉井がアフリカに目を向けたのには、元国連難民高等弁務官でJICA初代理事長を務めた緒方貞子氏の影響も大きかったと聞いています。
海外事業をスタートさせたとはいえ、当時の本会には海外でのノウハウがほとんどありませんでした。そこで強力な助っ人として登場したのが、協力隊経験者の沼でした。彼女は幼少期を海外で過ごし、ニジェールで青少年活動に従事した経験を持っており、当時の職員の中では稀有な存在でした。得意な英語で玉井の通訳を務めるなど、ほとんどの出張に同行し、海外事業を現在の形へと導いてくれました。
本会の海外事業は、ビジネスではなく社会運動に近いものであり、語学能力はもちろん、玉井の思いに共感し常に行動を共にできる機動力が求められます。実は私自身も元奨学生であり、外資系企業での勤務経験を買われて入局した一人です。そんな私であっても、玉井との仕事は相当なパワーを必要としました。それを物ともしない沼の活躍ぶりは、同じ女性としてとても嬉しく思っています。
本会では、「100年構想事業」を充実させるために、現在6か国に海外事務所を置いています。この事業をさらに展開していくためには、グローバルな視野で活躍できる人材が必要です。そこで期待を寄せているのが協力隊の経験値です。アフリカで協力隊を経験した人であれば、当地の奨学生に対して、現地語や文化を理解し、寄り添える感覚を持っているはずです。また、外国人スタッフが多い当事業の共通言語は英語であるため、語学力を生かして多様な価値観を持った人々と協力しながら働けることでしょう。帰国隊員の皆さんには、ぜひ、JICAのPARTNER(国際キャリア総合情報サイト)を始めとした本会の求人情報に注目していただきたいです。
アフリカ事業部100年構想第1課課長
沼志帆子さん
(ニジェール/青少年活動/2002年度派遣)
幼少期を過ごした欧米と
価値観が全く異なったニジェールでの暮らし
ニジェールに到着し初めて地平線を見たときは大きな感動を覚え、『とうとうアフリカに来たぞ!』という実感が湧きました。街を少し出ると、壮大な自然が広がっており、時折キリンが歩いているのを見かけました。任地で見た美しい夕陽と星空は今でも目に焼き付いています。
家族の都合で幼少期をドイツやアメリカで過ごした私にとって、アフリカ大陸で暮らすことは子どもの頃からの夢でした。高学生のときに、ボランティアでタンザニアに行くチャンスがあったのですが、アメリカへの引っ越しと重なり、断念せざるを得なくなってしまいました。アメリカに渡ってからは、いつかアフリカに行くことを夢見て青少年向けのボランティア活動に没頭した学生時代を過ごしました。そして大学卒業を控えた頃、「アメリカ平和部隊」の存在を知りました。しかし、残念ながらアメリカ国籍でない私には応募が叶わず、そこで日本人の私が参加できる制度を探して見つけたのが協力隊でした。
こうして参加した協力隊だったので、ニジェールに派遣されたときも、新しい環境に身を置くことに全く抵抗感がなく、自然に受け入れることができました。ただ唯一戸惑ったのは、金銭的な価値観の違いだったかもしれません。市場などで値段を交渉するというのは、金額が決まったお店でしか買い物をしたことのなかった私にとっては初めての経験でした。それでも、多少誤魔化されたことに腹が立ちつつも、現地語を磨くチャンスと捉え、現地の人々との交流を思う存分楽しむことができました。
ところで、ニジェールには日本大使館が置かれていません。そのためか、現地では日本はとても遠い国という印象があり、協力隊員を通じて日本を知ったというニジェール人も少なくありませんでした。そんななか私が配属されたのは、日本でいう地域の児童館のような施設でした。
公用語のフランス語さえ分からない子どもたちとの接点となり、協力隊の訓練中に知り合った日本の小学校との交流の場を作ったり、日本文化を伝えるお祭りを開催したりして、子どもたちが放課後楽しく過ごせる場を作ることに尽力しました。そのおかげで、私の現地語も上達しました。それにしても、同じ言葉を二回繰り返して強調するというのは、日本語にも共通していて不思議ですね。こうした些細なことで世界が繋がっているということを実感できるのは、とても面白いと思います。
ニジェールでは、全力で駆け抜けた2年間でしたが、ずっと心の片隅にあったのは、短い期間では外国人の私にできることは決して多くないということでした。そして、大きな衝撃を受けたのは、帰国後に一緒に暮らしていた双子の子どもの1人が亡くなったという知らせでした。十分な治療が受けられないことや識字率が低いなど、アフリカにおける医療や教育をめぐる深刻な課題を目の当たりにした協力隊活動となりました。
 アフリカ事業部100年構想第1課課長の沼志帆子さん
アフリカ事業部100年構想第1課課長の沼志帆子さん
協力隊経験者、女性、母親として
自分にできることとは何か
現在は、あしなが育英会で「100年構想事業」のプロジェクトリーダーとしてマネジメント業務に従事し、アフリカの未来を担う次世代リーダーの育成活動に専念しています。日本のプロジェクトチームには15人のスタッフがいますが、三分の一がアフリカ地域の出身者なので、日本だけの価値観にとらわれずに多様性をもって仕事ができることにとても満足しています。全員が揃う日はアフリカファッションデーと勝手に決めたりもしていて、自分らしく振る舞える環境がさらに仕事を充実したものにさせてくれています。
私と本会との出会いは、ニジェールから帰国してすぐ短期サマーキャンプの通訳ボランティアに参加したことに遡ります。その後、2005年に開催された「愛知万博」のスタッフを経て本会に戻り、2006年に正式な職員となりました。ちょうど本会が初めての留学生を受け入れるという年でもあり、海外経験のある職員が必要だったと聞いていましたが、入局してみたら所管の国際課には課長と私の2人しかおらず、必死で課題をこなしていったことを思い出します。
当時の職員は元奨学生が多く、ほとんど男性で占められていたこともあり、海外どころか日本的な体育会系のノリを思わせる雰囲気がありました。こうしたなかで女性の私が海外事業を牽引することは、本会にとっても大きなチャレンジだったと思います。だからこそ、本会の海外事業においてパイオニア的な役割を果たせたことは私の自負であり、今後の女性の活躍に貢献していくことや働きやすい職場づくりが私に課せられた次の役目であると感じています。
さて、入局から4年後、私は本会ウガンダ事務所の現地代表として2度目のアフリカを経験することになります。いつかアフリカに戻りたいと思っていたので上司から打診されたときは二つ返事で現地へ向かいましたが、いざ着いてみると協力隊のときとはだいぶ勝手が違っていました。
一番大きかったのは立場の違いです。現地代表という責任は重く、ニジェールのときのように現地語で買い物を楽しむ余裕など全くありませんでした。それどころか、政府機関との細かい調整や金額交渉に神経をすり減らす毎日でした。このように状況の異なる2度のアフリカ生活が私を大きく成長させてくれたことは間違いないでしょう。
担当している「100年構想事業」が10年目を迎える今年、0から1を創り出すのを得意とする私にとっては1を2にしていくという新たなミッションがスタートします。まずはアフリカに貢献する人材と事業への支援者を増やすことが目下の課題です。
こうしたプレッシャーのなかでも、私が3人の子どもを育てながら責任のある立場を務められるのは、逞しくも美しいアフリカのお母さんたちを知っているからに他なりません。子育てしながら働くことや、そこで自分らしく生きようとする女性の思いは日本もアフリカも同じです。どんな状況でも女性が自分らしく生きられる社会であってほしいというのが私の思いであり、あえて「女性が……」と一言添えなくても済むくらい、心地よく出産や育児などのライフステージを迎えられる社会の実現を願って止みません。
そして、願うだけでなく具体的な行動を起こすことが私らしい生き方でもあり、今、育児休暇中に取得したキャリアメンターの資格を活かして女性の活躍をサポートする活動も続けています。
 ニジェールで青少年活動隊員として活動した沼さん
ニジェールで青少年活動隊員として活動した沼さん
※このインタビューは、2023年8月に行われたものです。

- 一般財団法人あしなが育英会
- 所在地:東京都千代田区平河町2丁目7-5 砂防会館4F
事業内容:国内外の遺児等の進学・教育支援
協力隊経験者:5名在籍
HP:https://www.ashinaga.org/