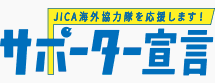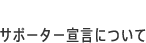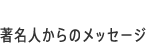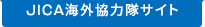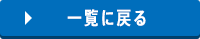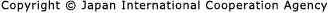公益財団法人日本生産性本部 日本が世界に誇る「カイゼン」を、世界に。JOCV経験者とともに描く、持続可能な未来
1955年に設立された公益財団法人日本生産性本部(当時は財団法人日本生産性本部)は、生産性向上を推進する機関として日本の高度経済成長を支えました。近年ではJICA海外協力隊(以下、JOCV)の経験者も在籍し、JICAの技術協力プロジェクトなどを通じて世界の生産性向上に貢献しています。2025年には、中小企業のデジタル化を支援する「デジタルカイゼン」の普及を目的としたパイロットプロジェクトをアジアで実施予定。JOCV経験者のような若き人材の力と長い歴史のなかで培ってきた高い専門性を掛け合わせ、新たなイノベーションを生み出しています。
国際協力部 部長
海外プロジェクトにおけるJOCV経験者への期待
まずは、団体の発足やあゆみについて教えていただけますか?
第二次世界大戦後、アメリカから生産性向上手法を学び、経済発展を目指すため、1955年に財団法人日本生産性本部が設立されました。その後、日本はアジア諸国の生産性向上を支援し、1961年にはアジア生産性機構(以下、APO)が設立されました。アジア諸国のなかでも生産性運動に高い関心を持ったのがシンガポールでした。シンガポール政府が日本政府に技術移転を依頼したことを契機に、JICAからの要請を受けて1983年から7年間「シンガポール生産性向上プロジェクト」を担当しました。
シンガポールがスタートだったのですね。現在はどういった地域、国が生産性向上に関心を寄せているのでしょうか?
2024年度は、ケニア、チュニジアといったアフリカの国々を中心にブータンを含め9ヵ国でJICAの生産性向上に関するプロジェクトや調査に携わっています。主に、日本から専門家を派遣し、相手国の政府機関の職員や経営コンサルタントに対して、カイゼンやマーケティング、財務などの知識とスキルを、座学と現地パイロット企業でのコンサルティングを通じて指導し育成しています。APO加盟各国からの政府視察団受け入れや訪日研修なども実施しています。
そうした海外プロジェクトを担当するのが「国際協力部」なのですね。
はい。部員は社会人経験がある者が多く、ほとんどが海外での勤務経験を持ち合わせています。メーカーや金融など前職の業種は様々ですが、JOCV経験を持つのは現在のところ稲葉だけです。
多様なバックグラウンドを持つ方がおられるなかで、JOCV経験者の稲葉さんを採用したきっかけは何ですか?
「JICA PARTNER」サイトから応募がありました。当時の採用担当者からは“JOCV時代に農産物の加工販売を住民と共に実施し付加価値向上に貢献した経験が印象的だった”“現地経験と事業会社での実務経験を併せ持つため即戦力として期待できる”ということが採用の決め手だったと聞いています。
稲葉のことをコミュニケーション力に優れていると評価しています。業務チャットでも、単なる連絡・報告だけでなく、“現地で髪の毛を切りました!”というプライベートな話題を提供してくれたり、旅先の写真が送られてきたりすることもあります。現地の関係者とも、日本人スタッフとも、チームの関係が良くなるよう、随所でコミュニケーション力を発揮していると感じます。
「コミュニケーション力」はJOCV経験者らしさとして挙げられるキーワードです。稲葉さんにJOCV経験者らしさを感じる具体的なエピソードがあったら教えてください。
日本にいるときも常にアンテナを張って、担当プロジェクトに役立ちそうなことを探し回っているようです。あるプロジェクトで「道の駅」が参考になると思うやいなや、休日にバイクを飛ばして行ってきたことがありました。翌週、お土産を持って出社。目的の人と会えて話したことを楽しそうに報告してくれました。フットワークが軽く、気さくに地域住民と関われることは、海外プロジェクトにはとても有効です。
パラグアイでのJOCV経験もあり、英語とスペイン語に堪能ですが、業務に必要だからと新たにポルトガル語の勉強を始めたいと相談されたときは驚きました。自主的に習得し、いまでは打ち合わせや講義を実施したりしています。通訳を介する必要がないので、現地の方々の信頼も勝ち得ているようです。
ありがとうございます。最後に、貴財団にとってのJOCV経験者の魅力について教えてください。
JOCVの活動は、受け身の姿勢では物事が進まないので、どんどん自分で可能性を切り拓いていく能力が培われるのだと思います。弊財団は来年で設立70周年を迎えますが、社会が激しく変化するなか、待ちの姿勢で立ち止まっていることはできません。また、成長著しい新興国から、今度はこちらが積極的に学んでいかねばならないと感じています。JOCV経験者の力を借りて、一緒に新たな生産性運動を盛り上げていければと期待しています。
国際協力部 稲葉健一さん
コーディネーション力を活かした国際協力のキャリア
(パラグアイ/コミュニティ開発/2015年度1次隊)

 パラグアイでコミュニティ開発隊員として活動した稲葉さん
パラグアイでコミュニティ開発隊員として活動した稲葉さん
パラグアイの「コミュニティ開発」隊員としての活動内容を聞かせて下さい。
小さな農村に配属されました。住民の生活改善がミッションだったので、積極的に農村に足を運び、コミュニケーションに努めました。住民から信頼を得ていくプロセスを経験し、そこから多くを学んだことで、自分の強みがコーディネーション力にあると気づくことができました。これは、今後のキャリアを考える上で大きなヒントとなりました。
帰国後の就職先として、貴財団を選ばれたのはどうしてですか?
JOCV参加前、事業会社の海外購買部門で、アジアの海外サプライヤーとの商談や、生産現場での生産性・品質向上の業務に携わっていました。JOCVの活動を通じて、帰国後の進路として国際協力分野での仕事に関心を持つようになりました。JOCV経験だけでなく、前職の経験も活かせると考え、いまの仕事を選びました。
現在は、「国際協力部」でどんなお仕事を担当しているのですか?
JICAから受託している中小零細企業支援分野の技術協力プロジェクト等に参加しています。入職してしばらくは、他の専門家の活動に同行することが多かったので、現場経験を積むことができました。いまは、その経験をもとに私自身が主に中小零細企業向けの経営支援と、関係者の育成に携わっています。
海外プロジェクトに関わるのにあたり、JOCV経験が活かされていると感じるのはどんな時ですか?
食品加工企業向けの経営支援を行うことが多いのですが、JOCV時代の農産品加工販売所での運営支援は、小規模生産者が抱える生産やマーケティング、会計といった経営課題だけでなく、食文化や流通といった社会構造を理解する上での基礎となっています。
最後に、稲葉さんにとってのJOCVの魅力について教えて下さい。
JOCV時代は、参加住民との間で課題を直接的に指摘して現地の人から反発されたこともありました。反対に、よく観察し、関係者とコミュニケーションを取ったからこそ、理解を得られたこともありました。2年間という長い時間をかけて、試行錯誤を重ねながら、現地の人との関係を築けたのはJOCVだからできたかけがえのない経験でした。
※このインタビューは2024年7月~11月に行われたものです。

- 公益財団法人日本生産性本部
-
所在地:東京都千代田区平河町2-13-12
事業内容:社会経済システムおよび生産性に関する調査研究、情報の収集および提供、普及および啓発、研究会、セミナー等の開催等
協力隊経験者:1名在籍
HP:https://www.jpc-net.jp/