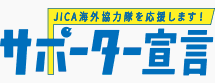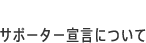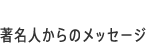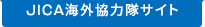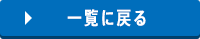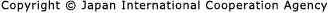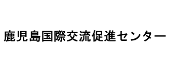
鹿児島国際交流促進センターJICA海外協力隊経験者たちが模索する
令和における「地域の国際化」
JICA海外協力隊の都道府県別OB会のなかで、事業者として活動している団体はまだ少ない。そのなかで、青年海外協力隊鹿児島県OB会が実働部隊として県の施設を管理運営しているのが、鹿児島国際交流促進センターだ。地域の国際化が叫ばれて早30年。この令和の時代に求められる地域の国際化とは何か。自身も協力隊の経験者であり、管理運営先の鹿児島県国際交流センターの代表も務める桑山昌洋さん(ボツワナ/コンピューター技術/2000年度派遣)に話を伺った。
OB会のネットワークが支える
県の国際交流・国際協力事業
鹿児島国際交流促進センターは、2020年に特定非営利活動法人九州海外協力協会と青年海外協力隊鹿児島県OB会が共同設立した新しい組織で、職員の約8割がJICA海外協力隊の経験者です。その特異性を活かして、鹿児島県の施設である国際交流センターとアジア・太平洋農村研修センター(通称:カピックセンター)の指定管理業務を行っています。
同県出身の京セラ創業者・故稲盛和夫氏が、鹿児島の若者たちを国際人に育ててほしいと県と市に多額の寄付をしてくださり、それを原資に市が国際交流施設を、県が留学生や研究者用の宿泊施設を設置し、かごしま国際交流センターとして2020年にオープンさせました。我々の鹿児島国際交流促進センターは、その宿泊施設の管理運営を任され、住人同士の交流、または県民との交流を通して、国際相互理解の促進を図るための事業を行っています。
宿泊用の部屋は全部で64部屋あり、コロナ禍の2020年に2割程しか利用されていませんでしたが、今では8割が埋まっています。鹿児島大学の学生が中心で、中国、韓国、ベトナムなどアジアからの留学生が多く、大学院生や研究者の中には夫婦で来日する人たちもいるので、夫婦部屋も用意しています。また、外国人のサポート役として日本人学生も10名ほど住めるようになっており、日本の若者がここで外国人と交流し、さまざまな体験をすることによって、国内外で活躍する新しい日本人像を作っていけるのではないかと期待しているところです。
職員の多くが協力隊経験者という組織は、少し偏っているのではと思われるかもしれません。しかし、協力隊経験者は元々のバックグランドが違いますし、派遣国も活動内容もバラバラ。体験してきたことも個々で全く異なるため、多様性のある組織だと思います。もちろん、異文化に対する理解が深いところや、コミュニケーションが得意なところは共通する強みのため、留学生たちのお世話をはじめ年4回開催している彼らの歓送迎会には力を入れています。
もうひとつの指定管理先であるカピックセンターは、大隅半島の山間部にある研修施設で、アジア・太平洋諸国などからの研修生受け入れや、教育機関をはじめ各種団体が実施する国際理解研修などにも利用されています。日本文化や海外の文化に触れ、理解を深めるための事業を行っており、こちらも協力隊体験やOB会のネットワークが活かされています。
2つの施設管理運営をするなかで、職員以外の協力隊経験者の方々にもご協力いただいて、業務の幅が広がっています。例えば研修生に日本語を教えてくれる人を探す場合、我々の母体である青年海外協力隊鹿児島県OB会のメンバーからすぐに日本語教育隊員を見つけることが出来ます。また、タンザニアから留学生が来た場合は、スワヒリ語が話せる協力隊経験者を紹介して、相談相手になってもらったりすることも出来ます。このような連携が頼もしくもあり、嬉しくもあります。
もちろん、同じ協力隊経験者といっても、これだけ世界全体が変わってきているので、私が派遣されていた20年前と現在の隊員とでは、経験内容や受け止め方も全く異なっています。それでも、今の隊員たちは今の新しい世界に合わせた形の協力隊活動をしてきている。そんな彼らの見てきた世界の話を聞くことは楽しく、長年、青年海外協力隊鹿児島県OB会の顧問として活動を続けてきた理由の一つです。
 鹿児島県国際交流センター代表の桑山昌洋さん
鹿児島県国際交流センター代表の桑山昌洋さん
コミュニケーションの大切さを知った協力隊時代
協力隊に参加する前の私は、鹿児島大学大学院で物理学を学び、その後、医学部で研究員として遺伝子や病気の研究をしていました。研究で南米のコロンビアやチリを訪れた時、子どもたちが学校に行かずに働いているのを見て驚きました。それがきっかけでいろいろ調べてみると、ストリートチルドレンやお金がなくて学校にいけない子、家の手伝いを優先させられている子などの存在を知りました。そんな国の人々のために自分が役立つことはないだろうか。そう考えるようになったことが、協力隊に参加したきっかけです。
システムエンジニアとしてアフリカのボツワナに派遣され、教育大学の学生にコンピューターシステムなどについて教えました。ボツワナは英語のレベルが非常に高かったので、派遣前の訓練では人生の中で一番勉強したのではないかと思うくらい、英語の鍛錬に集中しました。当時は「2年間限定だけれど、集中して頑張ろう」と思っており、さまざまなことを学ばせてもらいましたが、何よりたくさんの人たちに支えてもらっていたことに、今でも感謝の気持ちが大きいです。
日本では、研究室に閉じこもっているような生活をしていましたが、ボツワナに派遣されたことでコミュニケーションの大切さを実感し、自分自身が変わりました。今、こうして人と関わる仕事をするようになり、当時の経験がとても役立っています。また、ボツワナでは何をするにも待たされることが多く、忍耐力もつきました。水道の開始を依頼しても3ヶ月待たないと水が出ず、毎日隣の家から水をもらっていたことは懐かしい思い出です。
 ボツワナでコンピュータ技術隊員として活動した桑山さん
ボツワナでコンピュータ技術隊員として活動した桑山さん
外国人居住者のサポート
帰国後は鹿児島大学に戻り、工学部電気電子工学科で教員をしていました。同時に青年海外協OB鹿児島県OB会でも活動していたため、JICAや国際交流団体とのつながりもありましたし、大学では留学生や研究者の存在が身近にありました。縁あって今の仕事に就くことになり、全てがつながっているなと感じます。
振り返ると、自分は好きなことだけをやってきました。好きなことを仕事にしながら「今日よりも明日が良い日になるように」をモットーに生きています。ですから今も、国際交流や国際協力活動の仕事を少しでも手伝うことで、開発途上国の子どもたちが学校に行けるようになればいいなと思いながら、楽しく仕事をさせてもらっています。
県内に住む外国人はそれほど多くはありませんが、近年、技能実習生の枠が広がり、ベトナムやネパールの方々が鹿児島市の中心地以外に多く居住していると聞きます。彼らが暮らしやすく働きやすい地域になるよう、ゆくゆくは彼らのサポートも出来ればと思っています。そのためには企業との連携も必要だと思うので、今後そのあたりを研究しながら進めていこうと考えています。
また、県内の協力隊経験者は、Iターン、Uターン、Jターンで移り住んできた方も多く、いろいろな職業に就いています。中には技能実習生の日本語学校に勤めている方もいますので、そんな協力隊経験者のネットワークを活かしながら、各地の外国人居住者の方々に対して、何かサポートが出来るようになりたいですね。
鹿児島国際交流促進センターは、まだ設立されたばかりの新しい団体です。ここ数年はコロナ禍で動き難かった面もありますが、これからが本当のスタート。地域における多文化共生をより一層推し進めていけるよう、頑張っていきたいと思います。
※このインタビューは、2022年11月に行われたものです。
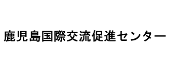
- 鹿児島国際交流促進センター
- 協力隊経験者:複数名在籍