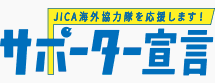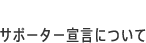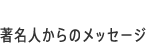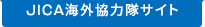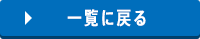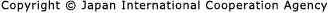陸前高田市陸前高田市×JICA海外協力隊グローカルプログラム
地域と世界を繋ぐ活動の軌跡
JICAと岩手県陸前高田市は、2022年に地域振興と国際協力に関する連携覚書を締結しました。この覚書に基づき、派遣前のJICA海外協力隊(以下、JOCV)候補生を対象とした地域密着型実習『JICA海外協力隊グローカルプログラム(以下、GP)』が開始。同市では、GP実習生を受け入れ、地域活性化や地方創生の取り組みを支援してきました。2024年には、初めて受け入れた元GP実習生が海外での活動を終え帰国しました。本稿では、JOCV派遣前から帰国までの約3年間彼らを見守り続けた陸前高田市、GP受け入れ団体、そして元実習生の声をお届けします。
陸前高田市
商工交流部長 兼 交流推進課長 村上 知幸様

これまで多くのGP実習生を受け入れていただいていますが、陸前高田市がGPの受け入れを始めた背景には、どのような課題や目的があったのでしょうか?
2011年3月11日、東日本大震災が発生し、陸前高田市は甚大な被害を受けました。市役所では、100人を超える職員が犠牲となり、私も多くの先輩、後輩、同僚を失いました。この町で生まれ育った私にとって、震災は言葉では言い表せないほどの悲しみと苦しみをもたらした出来事でした。
しかし、震災直後から、全国の自治体から多くの応援職員が駆けつけてくださり、復旧・復興の大きな力となりました。同時に、海外からも温かい支援が寄せられ、世界を相手に復興を進める動きが加速しました。その中で、国際協力やグローバルな視点を意識せざるを得なくなり、それが後のGP受け入れへと繋がる原点となりました。
そうした状況下で、JICAやグローバル人材の存在を身近に感じたきっかけは、元JICA職員である男性職員の入職でした。当時、外国語が話せるというだけで、彼は私たちにとって特別な存在でした。ものの考え方や視点も私たちとは全く異なり、新鮮な驚きを感じました。その後、JICAとの連携覚書を交わし、GP受け入れに至るまでには、彼の存在が大きな影響を与えたことは間違いありません。
JICA関係者との出会いが、グローバル人材について意識したきっかけだったのですね。
はい。復興に取り組む中で、グローバルな視点を持つ人材の必要性を痛感しました。震災からの復興には、国内外を問わず、様々な人々との協力が不可欠でした。その中で、多様な価値観や文化を理解し、異なる言語を話す人々とも円滑にコミュニケーションを取れる人材の重要性を強く感じました。
JOCVについては、名前は知っていても、具体的な活動内容や現地での暮らしぶりまでは想像もできませんでした。しかし、彼から直接話を聞く中で、JOCVが外国語能力や国際理解力に長けているだけでなく、主体的な行動力の持ち主だということを知りました。また、彼自身の経験談を通して、GPの実習生たちがいかにしてグローバル人材へと成長していくのか、具体的なイメージを持つこともできました。
グローバル人材について、陸前高田市においては、具体的にどのような活躍を期待しておられますか?
復興計画を策定しても、それを実行するのは人です。創造的な復興を実現するために、チャレンジ精神旺盛な人材が不可欠です。その意味で、グローバルな視点を持つ人材は、復興を推進する上で欠かせない存在だと考えています。
関係人口という言葉が示すように、陸前高田市の復興には、市職員、民間企業、NPOなど、様々な立場の人が関わることが重要です。私たちは、そうした人々をつなぎ、共に復興を目指したいと考えています。
GPは、そのための取り組みの一つです。GPに限らず、現在活動中のJOCVで、帰国後に日本国内で自分の力を試したいと考えている方がいらっしゃいましたら、ぜひ陸前高田市に来ていただきたいですね。
チャレンジ精神は多くのJOCVに共通する気質のひとつだといえます。そうしたJOCVに、GPの段階から関わる中で思うことなどあれば、ぜひ聞かせてください。
発展途上国で貢献したいというJOCVの思いと、復興に向けてチャレンジを続ける陸前高田市の思いは、非常に共鳴し合っています。GPは、私たちにとっても、受け入れ団体にとっても、実習生にとっても、互いに成長できる貴重な機会となっています。
陸前高田市では、これまでに21名のGP実習生を受け入れてきました。みなさん多様なバックグラウンドがあり、それぞれが強い意志とチャレンジ精神を持っています。彼らと話していると、私自身も頑張らなきゃという気持ちになりますし、勇気づけられます。
個人的に印象に残っているのは、野球指導でブラジルに派遣された青年との思い出です。実習中、地域の少年野球チームに積極的に関わり、子どもたちと一緒に野球を楽しみながら、指導の勉強にも励んでいました。
そういえば、村上様は野球がお得意で、ドジャースの佐々木朗希投手を指導したこともあると聞きましたが?
はい。かつて少年野球チームの監督をしていたことがあり、そこで佐々木投手との関わりがありました。陸前高田市出身の佐々木投手と、海外に向けてチャレンジする実習生の姿が重なり、個人的にも全力でサポートさせてもらいました。
GP実習生のみなさんには、現地での2年間の活動を精一杯頑張り、その後も陸前高田市との繋がりを持ち続けてほしいと願っています。ここを第二、第三の故郷のように思って、いつでも遊びに来てほしいです。そして、いつか一緒に仕事をする機会があれば、とても嬉しいです。
村上様、GPが人と人との繋がりに支えられていることが分かる、貴重なお話をありがとうございました。
一般社団法人トナリノ 代表理事 佐々木 信秋様

貴団体は、もともと震災の緊急支援として発足したと伺いました。その後、GP実習生の受け入れに至った経緯について、活動内容と合わせてお聞かせいただけますでしょうか。
私たちは、陸前高田市を故郷と思う仲間たちが集まって立ち上げた団体です。震災後の緊急支援から始まり、徐々にまちづくり会社のような形に移行してきました。現在は、「地域の相棒」という理念を掲げ、デジタル、デザイン、コンサルティングなどの事業を行っています。
これまでに、大学生や社会人など多くのボランティアを受け入れてきました。どのようなケースでも、受け入れ方法について組織内で話し合い、来てもらう前から納得いくまで対話を重ねることを大切にしています。これは、私たちの10数年の歩みの中で積み上げてきたやり方です。
GPとの出会いは、陸前高田市からのご紹介でした。「希望者がいればぜひ受け入れたい」とお伝えしたところ、2022年1月に小林恭子さんが来てくれました。GP実習生のみなさんには、主にデジタル分野の事業に関わっていただいていて、小林さんにも高齢者向けのスマートフォン講座をお願いしました。
小林さんの職種は「文化」なので、デジタル分野は専門が異なりますよね。バックグラウンドを問わず、デジタル分野をGP実習生に担当してもらうのはなぜでしょうか?
自治体でもデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでいますが、インフラが整備されても、地域の人々が使えなければ意味がありません。私たちの活動エリアは高齢者が多く、スマートフォンに苦手意識を持つ方ばかりです。こうした方々に対しては、ノウハウよりも、一人ひとりに寄り添うテクニックのようなものが必要です。ボランティアを受け入れてきた長年の経験の中で、課題を見つけて主体的に取り組めるGP実習生は、デジタル事業ととても相性が良いということが分かりました。
様々なボランティアを受け入れる中で、GP実習生の受け入れにおいて工夫していることや課題に感じておられることなどあれば、お聞かせください。
GP実習生に限らず、最も重要なのは、双方で取り組みの概要とゴールを共有することです。そのため、最初に、受け入れの目的やお願いしたいことを明確に説明します。その上で、我々の狙いや現場の期待値を具体的に伝えます。活動中も、お互いの認識がズレないように、定例会などで粘り強くすり合わせを行います。
GPの場合、3ヶ月という短い期間でゴールイメージを共有し、アウトプットに繋げる必要があります。この点が他のボランティアらとは異なるため、双方の認識合わせだけでなく、私たち受け入れ側のコーディネート体制も重要になってきます。
そのような中でも、GP実習生のみなさんは総じて問題解決や地域貢献に対する意識が非常に高いので助かっています。JOCVに応募し、自ら進んでGPに参加されるくらいですから、みなさん能動的に動いてくれます。到着後すぐに活動に移れるのは、活動の意義を事前に理解してから来てるからだと思っています。
他の受け入れ団体にとっても参考になる貴重なお話をありがとうございます。では最後に、GP実習生やJOCVに期待することを教えてください。
まず、何年も実習先として選んでいただいていることに大変感謝しています。GP実習生が来なければ想像することもなかった国もあり、職員一人ひとりにとっても良い刺激になっています。高い意識と行動力を持ったGP実習生を受け入れることは、組織の内省にも繋がると実感しています。
第1期生が帰国した節目を迎え、改めてこの貴重な機会を最大限に活かせているか、他の受け入れ団体とともに問い直したいと考えています。振り返ると、私たち自身も実習期間中の実習生とのプライベートな交流が不足していたり、帰国後の実習生との継続的な繋がりを持てていなかったりと、改善の余地が多くあります。受け入れ側の意識改革や体制整備によって、GPプログラムはさらに実り豊かなものになると確信しています。
小林恭子さん(ボリビア/文化/2022年度派遣)

 地元の人たちと郷土料理あずきばっとうを作る小林さん
地元の人たちと郷土料理あずきばっとうを作る小林さん
GPの第一期生として陸前高田市で活動されましたが、この期間どのようなことを学びましたか?
私は長い間家族の介護をしていましたので、若い頃にやむを得ず退職したあとは働く機会がないまま時間が過ぎてしまいました。そのため、協力隊に行く前の社会復帰と、地方への貢献という2つを考えてGPに参加しました。
陸前高田市ではトナリノさんで研修をさせていただき、高齢者向けのスマートフォン教室の補佐を担当しました。「ここを押したらおかしくなってしまうんじゃないの?」と、デジタル機器に対して気を配る姿に、ひと世代前の人たちが大切にしてきた謙虚さや奥ゆかしさを感じました。皆さんとても良くしてくださって、いろいろなことを教えてくださいました。
研修で特に勉強になったのは、講師の方の教え方が丁寧で、誰ひとり見捨てることなく対応していたところです。「お年寄りだからスマートフォンの操作ができなくても仕方がない」ではなく、最後まできちんと面倒を見る。その姿がとても印象的でした。
研修中は岩手県のいろいろな場所に連れて行ってもらったり、「あずきばっとう」という三陸の郷土料理を習ったり、本当にたくさんの経験をさせていただきました。また、今まで考えたこともなかった「地方創生」についても、考えるようになりました。
さらに、GPの1期生は任地とオンラインをつないで話すことができたのですが、私は配属先から「日本語も教えてほしい」と突然言われて慌てました。でも、派遣前に現地の状況が分かり、日本語教育について勉強してからボリビアに行けたことは、GPに参加して良かったと思う理由のひとつです。
その後ボリビアに派遣されたわけですが、2年間の活動はいかがでしたか?また、GPでの経験が役に立ったなと感じたことはありましたか?
私は若い頃からJOCVに憧れていたのですが、両親の反対で断念した経験がありましたので、ボリビアに着いたときは、願えば叶うものなのだなと感じました。
配属先はボリビア日系協会連合会で、首都ラパスで活動する予定でしたが、標高が3,600mと高く高山病にかかりまして、ラパスより標高の低いサンタクルスに移って活動しました。私は生け花(華道)の教授資格を持っており、サンタクルスの日系人だけでなく、同じ県内にある日系移住地のオキナワやサンフアンにも通い、生け花教室をさせていただきました。オキナワ移住地やサンフアン移住地には花屋がないため、サンタクルスの花市場から買っていくのですが、車で2時間ほどの距離と、外気温が高く40℃以上もあり、移動中に花が枯れてしまうという苦労はありました。
お花を習いに来てくれるのは日系1世や2世の方が多く、ちょうど陸前高田市で交流していた方々と同世代だったので、トナリノさんで教わった「相手と目線を合わせる」「相手の気持ちになって理解する」という経験がとても役に立ちました。
ボリビアの日系人高齢者たちも謙虚で奥ゆかしく、1,2回会っただけではなかなか自分のやりたいことをおっしゃらないのですが、何度も通ううちに、だんだん「実は庭に南天を育てているのだけれど、今度持ってきますね」、などと言ってくれるようになり嬉しかったですね。ボリビアで2年間教える中で、生け花を気に入り続けてくれる人がいたので、4人の方に「入門許可」を家元からいただきました。
ほかにも、サンタクルスの日本語学校で日本語を教えたり、オキナワ移住地では高齢者のデイサービスのサポートもさせていただき、陸前高田市の「あずきばっとう」を作って食べたりして交流もしました。また、日系社会では近年、世代交代がうまく進まないという悩みがあることを知り、陸前高田市で考えた日本の地方創生が頭をよぎったりもしました。
帰国後、陸前高田市とはどのような形で繋がっていきたいとお考えですか?
帰国してからも、日本にいるウクライナの女性や中国残留孤児の方々に日本語を教えているのですが、今はこの日本語教室の縁を大切に、今後も陸前高田市と繋がっていきたいという気持ちがあります。
昨年12月に、ボリビアの日本語教室で撮ったビデオレターを陸前高田市の日本語教室の皆さんに見ていただきました。その感想をその場で撮影しボリビアに送ったところ、ボリビアの生徒さんたちがとても喜んでくれました。オンラインでの直接交流は時差の関係で難しいのですが、ビデオレターを通じた交流ならば今後も続けていけるかもしれない、ぜひ続けていきたいと思っています。
陸前高田ほんまる株式会社 種坂奈保子様

御社は「まちづくり会社」ということですが、どういった事業をされているのでしょうか? GP実習生の関わり方も含めて教えてください。
陸前高田市では、震災で壊滅的な被害を受けたため、2017年からかさ上げした土地で新たなまちづくりが始まりました。しかし、住民と行政だけでは出来ないことも多く、行政とは異なる立場でまちづくりを推進する必要が出てきました。それで設立されたのが私たちの会社です。
主な事業は、中心市街地の活性化で、イベントの企画・運営や情報発信など多岐にわたります。P実習生には、この中心市街地エリアで、課題を見つけて解決策を提案・実行してもらうことをお願いしています。最初は、街の現状を把握してもらうために、イベントのサポートなどをしながら地域住民との交流がメイン。その中で課題を見つけてもらい、その解決に向けた企画を立案し、実行してもらうのが残りの期間での活動です。
多彩なバックグラウンドをもつGP実習生には、それぞれの得意分野や興味関心を活かした活動をしてもらうようにしています。過去には、食に詳しい実習生が地域の食材を使ったイベントを企画したり、環境問題に関心の高い実習生が環境教育のワークショップを開催したりと、様々な活動が行われてきました。
中心市街地の活性化となると、多くの課題と解決策がありそうですね。これまでGP実習生を受け入れてみて、いかがですか?
みなさん個性豊かで、それぞれが素晴らしい才能を持っている方たちだなと感じています。
ジョージアに派遣された方で、食に対する情熱が非常に強い女性がいたのですが、彼女が企画したジョージア料理の会は、あっという間に満席になるほどの人気でした。JOCVに派遣される前だったので、副題に「本物は知らないけど」と付けた正直さがまた、参加者を惹きつけたのだと思います。他にも、蜂蜜に詳しい方が企画したイベントは、大人気で2回に分けて開催するほどでした。教師の経験を活かして、地域の事業者向けに環境経営に関する講演会を開催してくれた方もいました。
GP実習生たちは、それぞれの専門性を活かしながらも、新しいことに積極的に挑戦し、地域の人たちと交流を深めています。短期間で成果を出そうともがいている姿が、私たちスタッフにとっても大きな刺激となり、地域に新しい風を吹き込んでくれていると感じています。
たくさんの思い出がおありなのですね。多くのGP実習生を受け入れてきて、受入先として工夫していることや課題に感じていることがあれば教えてください。
工夫していることは、GP実習生が主体的に活動できるような環境づくりです。実習生の自主性を尊重し、できる限り自由に活動してもらうよう心がけています。
一方で、今後に向けては、地域住民との交流の場を積極的に設けたいと考えています。特に、GP実習生は宿泊先がマンスリーマンションになることが多いので、ホームステイやシェアハウスなどを活用し、より地域に密着した生活を送れるような仕組みづくりが大切なように思います。限られた期間の中で、GP実習生にとっても地域にとっても、より良い関係性が育める場を作っていきたいですね。
外から来た人たちと地域住民の交流の場づくりは大切ですよね。ところで、種坂さんご自身も移住者だと聞きましたが。。。
はい。私は愛知県出身で、大学生の時に一人旅でこの地を訪れたことがあります。その時、街の人たちにとても良くしていただき、温かい思い出が心に残りました。それから数年後、東日本大震災が起こったのです。もういてもたってもいられず、災害ボランティアに参加しました。その中で、仮設商店街の立ち上げスタッフを募集していることを知り、応募したのが、移住を決めたきっかけです。
この街での生活は、想像以上に刺激的で、毎日が発見の連続でした。震災からの復興という大変な状況の中、前向きに生きる人々の姿に感銘を受け、この街で自分にできることをしたいという気持ちが強くなり、いまに至っています。
移住者としての種坂さんの存在が、GP実習生の刺激と成長に繋がっているのではないでしょうか。最後に、GP実習生やJOCVに向けてメッセージをお願いします。
これから海外に旅立つみなさんには、ぜひ、出発前から日本の地域の人々との交流を大切にしてほしいです。地域のお祭りやイベントに参加するなど積極的な交流を通して、日本の文化や暮らしを深く理解してほしい。そして、その経験を海外での活動に活かしてほしいと願っています。
そうしたことで、地域にも新しい風が吹くことになると思うんです。若い世代ならではの視点や発想で、地域の課題解決や活性化に貢献してくれることを期待しています。
いつかまた陸前高田に遊びに来てくれる日を楽しみにしています。
中里大介さん(マダガスカル/コミュニティ開発/2022年度派遣)

 直売所で活動する種坂さん(左から2人目)と中里さん(右から3人目)
直売所で活動する種坂さん(左から2人目)と中里さん(右から3人目)
なぜGPに参加しようと思ったのですか?また、活動場所に陸前高田市を選んだ理由を教えていただけますか?
中学生の頃から、JOCVへの参加を目指して進路を決めてきた自分にとって、このGPはとても魅力的でした。なぜなら協力隊に行く前に、自分の知らない土地で、外から来た人間として活動できるからです。今の自分に何ができて、何ができないのかを整理する意味でも是非チャレンジしたいと思いました。
大学に入学する年に東日本大震災が発災し、自分も大変な思いをしながら東京に出てきたこともあって、学生時代は被災地へボランティアに通いました。陸前高田市も一度訪れたことがあったのですが、その時は街中が何もない状態で、津波の恐ろしさをまざまざと見せつけられたことを覚えています。「あれからどうなっているのだろう」「復興の状況をこの目で見てみたい」という強い気持ちから、陸前高田市で活動することを決めました。
まちづくりの会社「ほんまる株式会社」で研修されたそうですが、どのような活動をして、どんなことを学びましたか?
滞在していた期間がちょうどコロナの真っただ中で、活動はかなり制限されていました。直接人とは会いにくく、ほとんどやることがないような状況が続きました。
それでも前に進んでいくためにどうしたらいいか、と毎日考え続けるうちに、地域の直売所の集客課題を知り、自分にできることはないかと考えた企画が「産直さんのファン作り」でした。さまざまなSNSを駆使してファンを増やす。言うのは簡単ですが、情報発信は初めての経験で、どんなコンテンツを入れるべきか、どんなことをやっていけば多くの人に見てもらえるかを考えるのはとても大変でした。
ある時、地元の特産ヤーコンを使った「オンライン料理教室」を企画したのですが、全く人が集まらなかったんです。1人でもいいから、とにかく人を集めようと、雪の降る中スーパーの前でビラ配りをしたり、いろいろなところで声をかけまくったりして、できることは全部やってみました。もう必死でしたね。
でもよく考えると、地域の課題や困りごとを探りながら自分の中で落とし込み、形にして提案する。まさに協力隊が現地でやることと同じだなと思ったんです。派遣前にこれを経験できたことは強みになると感じました。
もちろん、陸前高田市ではほんまるさんを通じて私の活動が成り立っていましたので、感謝しかありません。ほんまるさんに繋いでもらい、たくさんの人と出会うことができましたし、相手のニーズを丁寧に聞き取りながら柔軟に対応することの重要性を学びました。
その後マダガスカルに派遣され2年間活動されました。GPの経験が生かされた場面はありましたか?
たくさんありました。まずJOCVではよくある話ですが、現地に到着し、配属先で活動を始めようとしても、「何をしにきたの?」「あなたの仕事はないよ」ということになりがちです。しかし、私の場合はGPで似たような経験をしていたので困り果てることはなく、自分の中である程度考える思考ができていたことがとても役立ちました。
マダガスカルでは農機具の製造とそのエンジニアを育てる学校に配属され、そこを拠点に国内で農機具を普及させるための活動を行いました。農機具といってもトラクターのような機械ではなく、手動で動かす除草機や唐箕(とうみ)などが主流です。それらを普及させるために、農家さんたちにデモンストレーションしながら、農業はもっと効率よくできるということを提案させてもらいました。
活動を始めた頃は、配属先に自分のやりたいことが上手く伝わらず、もどかしく思うこともありましたが、私がいた地域には協力隊の先輩隊員がたくさん住んでいたので、その人たちを介して農家さんと繋がりを作り、徐々に活動を広げていくことができました。たとえ配属先が思い通りに動いてくれなくても、自分の周りの関係から、地域とつながっていく。このように柔軟に対応できたことは、やはりGPの経験が生かされたと思いますね。
また、活動中は自分で期限を決めながら進めていかないといけない中で、やはり全てが思い通りには進まないので、陸前高田市での料理教室の人集めの時のような、できることは全部やるといった経験は、とても役に立ったと感じます。
最後に、中里さんにとって陸前高田市はどんな場所ですか?
帰国後、JICA東北からお声掛けいただき陸前高田市で帰国報告会をさせていただきました。皆さんに喜んでもらえて、もう一つ地元ができたようでうれしいですね。
自分と同じ世代の人たちと話をしてみると、地元をもっと盛り上げていきたいと一人ひとりが動いています。彼らの熱意を知る者として、私も自身の経験を活かし彼らの力になれることがあれば、陸前高田市の地域活性化に貢献したいと考えています。
※このインタビューは、2025年2月に行われたものです。

- 陸前髙田市
-
所在地:岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
HP:https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/index.html