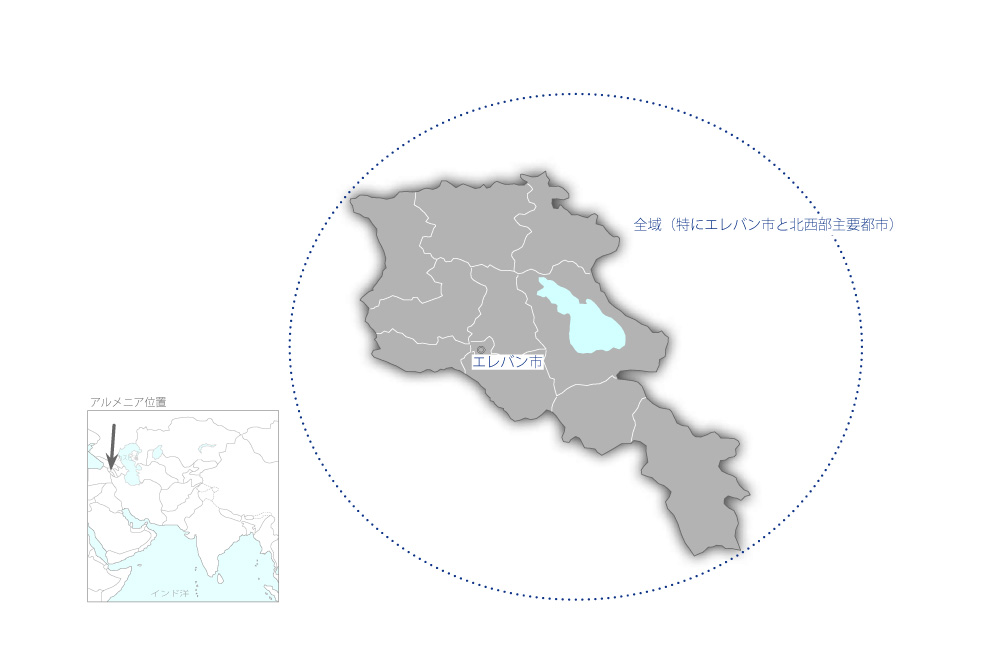ガルニ村北におけるガルニ断層の低断層崖(テントの奥)。ここでガルニ北地点のトレンチ調査(注)を実施し、ガルニ断層の約3000年前の活動を確認した。(注:溝(トレンチ)を握り、地層の観察を行い、活断層の過去の活動の様子や変位量調べる調査)

ボーリング調査の様子。活断層が活動したときに、地表で想定される地震動の大きさと分布を推定するために、地盤の強度を確認した。深さは30メートル。

2010年11月に実施したトレンチ見学会の様子。トレンチ調査の実施方法をアルメニアに技術移転をするため、アルメニア地震研究所(以下、NSSP)の研究員を招待して、技術セミナーを実施した。

PS検層調査の様子。断層が活動したときに、地表で想定される地震動の大きさと分布を推定するために、必要な地盤のS波速度の深度分布を確認した。原理は、ボーリング孔に地震計を設置し地表で起震したS波の到達時間から推定する。深さは30メートル。

ノル・ウギ(Nor Ughi)村でのベディ(Vedi)断層のトレンチ調査。左側の岩盤が右側の未固結な地層に乗り上げている。ベディ断層はこれまで地質断層と考えられていたが、本プロジェクトで活断層であることが確認された。893年のDvin地震で活動した可能性がある。

表面波探査の手法を技術移転するため、NSSPで行われた研修の様子。地表を大きなハンマーで叩いて起震して、調査を行う。

1988年に発生したスピタク地震(死者は約25,000人)の被害状況やその後の復興についてのヒアリングをスピタク市役所で行った。

防災教育のプログラム開発、防災のための人材の育成を行っている国家危機管理アカデミー(Crisis Management State Academy)での聞き取り調査。

日本の経験を十分に伝え、カウンターパートがアルメニアの状況に応じて主体性を持って地震防災計画を策定するために、毎週、コアメンバーと話題に沿った関係者を集めて、活発な議論が行われている。

本プロジェクトで導入中の即時震度表示システムの実演。非常事態省危機管理センターにおいて、大臣をはじめとする関係者へシステムの紹介を行った。多くの新聞やテレビで報道されるなど、アルメニアの関心の高さが示された。システムで得られた震度情報をSMS(ショート・メッセージ・サービス)によって即時に一般に伝えるシステムの追加導入についても大きな期待が寄せられた。