第1回本邦研修(Knowledge Co-Creation Programme)開催報告 -大規模災害に対するOne ASEAN One Responseの実現のための連携強化と災害医療に関する知識創生を目指し-
ASEAN各国の参加者を集めた初回本邦研修を2022年11月22日~12月17日の日程でJICA関西を主な拠点として実施しました。今回はARCHプロジェクトで開発中のCコース(大規模災害時に国境を越えて派遣される緊急医療チーム(I-EMT)調整のための標準コース)試行を期間内に含む4週間という長丁場になりましたが、各国の積極的な参加によってとても実りの大きな研修となりました。
参加者はASEAN各国の保健省もしくは災害医療機関施設、病院、教育機関等に所属する災害関連活動を経験している方々です。
この研修のコンセプトは、ARCHプロジェクトがASEAN地域内での災害保健医療連携強化を進める上で重視している「相互学習」=Mutual Leaningと「知識共創」=Knowledge Co-Creationです。日本を加えたASEAN各国間で経験や知識を交換し、お互いに学び合い、地域の習慣や文化体系に合う災害保健医療体制を構築していく事に貢献する事が望まれます。
全プログラム
| 11月22~24日(神戸) | 研修員来日、ブリーフィング、施設見学(阪神・淡路大震災阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター) |
| 11月25日 | カントリーレポート発表会 |
| 11月28日(大阪) | 日本の保険医療制度 |
| 日本の救急医療(歴史・制度・体制) | |
| 日本の救急医療施設 見学 | |
| グループワーク:「自国の救急医療システムの課題とその解決」 | |
| 11月29日 | 大阪府立消防学校における救急教育 |
| 阪神淡路大震災における消防活動とその後 | |
| 大阪府での災害対応の実際 | |
| グループワーク:「自国のコメディカルの教育とそれをよりよくするには?」 | |
| 大阪城公園見学 | |
| 11月30日 | 日本における多数傷病者事案管理体制 |
| ケーススタディ 福知山脱線事故 | |
| グループワーク:「自国のMCI対応の課題とその解決」 | |
| 12月1日 | BHELP標準コースの紹介と体験 |
| 12月2日 | 日本におけるCOVID19対応 |
| ケーススタディ COVID19対応(病院受け入れ・行政対応) | |
| グループワーク:「自国のCOVID19I対応の課題とその解決」 | |
| 12月5~8日(神戸) | Trial C-course |
| 12月10~11日(東京) | JDR医療チーム導入研修 見学 |
| 12月12日 | 阪神・淡路大震災以降の急性期災害医療体制 |
| 災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team(DMAT)概要 | |
| 広域災害救急医療情報システム Emergency Medical Information System(EMIS) | |
| COVID19対応事例(クルーズ船ほか) | |
| 日本の災害時における国際支援の受入れ方針 | |
| 災害時のこころのケアと災害派遣精神医療チームDisaster Psychiatric Assistance Team(DPAT) | |
| トニー・レドモンド氏講演会 | |
| 12月13日 | 国際赤十字の災害対応枠組み(保健医療緊急対応ユニット、WHOとのRed Channel Agreementを含む) |
| JDR(JDR法、組織体制、医療チームの仕組み、組織、能力、装備品、感染症チームの概要) | |
| 12月15日(神戸) | アクションプラン発表会 |
| 12月16日 | 評価会・閉講式 |
| 12月17日 | 施設見学(北淡震災記念公園) |
コースの主要行程内容
Country Report発表会:11月25日
各国参加者は研修参加前に救急医療、災害医療システムに関する各国の現状を調査し、Country Reportにまとめ、事前提出することを義務付けられており、研修初日に全ての国がその発表を行いました。なお各研修員は、各自が持参したCountry Reportと同発表会の際の質疑応答をベースに、研修期間中に研修で得られる知識等を参考に、2025年までにASEAN各国が達成を目指す7ターゲットに対する自国の現状分析(Country Analytical Work)を行い、同ターゲットに対する課題等を解決し、自国が国別ターゲットを達成するためのAction Planを開発することが求められています。
大阪セッション:11月28日~12月2日
千里救命救急センターを中心に、救急医療体制、災害医療体制を含む日本の医療体制全体像について、救急医療関連施設見学や各分野担当講師を招いた講義などを受けました。また、過去の事例報告や課題ディスカッションなども行われ、特に救急医療の体制強化に対する各国の課題を共有しました。
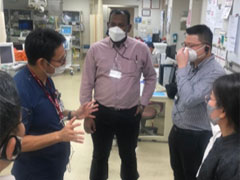
試行C-course:12月5日~8日
ARCHプロジェクトが開発してきた標準カリキュラムの1つであるI-EMT調整のためのコース(Coordination Course)を試行開催しました。このコースの基本コンセプトは被災国側としてI-EMTを受け入れるための調整に関連する知識の習得ですがが、標準カリキュラム開発完了の暁には、ASEAN各国が自国の関係者を対象に、この標準カリキュラムを適用した自国内の現地国内研修を計画実施することを想定しています。27単元からなるこの標準カリキュラムでは、講義のみではなくディスカッション等が多分に盛り込まれた内容となっています。コース開発に伴っては日本のみならず各国の豊富な経験が活かされ、日本がリードしてきた国際基準情報管理システムなど国際支援受け入れに必要なあらゆる情報を共有しました。本Cコースのカリキュラムや実施方法この後、更に改良され、2023年の9月にマレイシアで開催予定の第5回地域災害連携演習(RCD)の準備の一環として、国際災害医療チームの受け入れ調整を担当するマレイシア国際担当者を対象とするマレイシア適用コースの試行実施が計画されています。


東京セッション:12月10日~13日
東京に移動し、JICA国際緊急援助隊(JDR)の導入研修に見学参加しました。参加国にとっては国際緊急医療チームに関連するスキームへの関心も高く、また模擬診療シミュレーション演習には模擬患者として研修員も参加しました。自国で救急医療や災害保健医療に関連する政策や教育活動に従事する研修員の迫真の演技が見られました。その他、日本国内の災害対応を担当する災害派遣医療チーム(DMAT)、災害派遣精神医療チーム(DPAT)、国際赤十字の災害対応、、JDRの管理体制についての講義を実施しました。

Action Plan発表会:12月15日
再び関西JICAセンターに戻り、各国の「Action Plan」を共有しました。
この「Action Plan」は「Country Analytical Work」と共に各国に持ち帰り、省庁関係者や各国のARCHプロジェクト担当者と協議し、追加・改善などを行い各国の行動計画として2025年までのALD国レベル目標達成を目指して実践する事が期待されています。国毎に課題や目標はそれぞれです。研修参加者は達成可能なレベルを良く知っており、それでもまだ様々な困難を乗り越えていく必要がある事も理解しています。それらを含めASEAN各国で共有し、共に協力し合い、時には助けを求めたり提供したりすることもお互いが受け入れながらASEANみんなで頑張っていく、という共通認識が得られる事がこのAction Plan発表会で幕を閉じた研修の大きな達成のひとつなのではないか、と思います。
2025年までにASEAN各国が達成を目指す7目標
(Targets at the National Level (Each AMS is expected to achieve these targets)
- 1 . WHOなどの国際機関が定める必須基準を満たしたI-EMTの保有。
- 2 . 災害対応時にEMTの活動調整を行うEMT連絡調整所(EMTCC)の設置.
- 3 . ASEAN域内における国境を越えたEMT派遣の調整、被災国への受入れや活動調整のための標準手順書が開発
- 4 . EMT標準報告システムの整備
- 5 . 災害医療研修システムの整備.
- 6 . 保健医療関係者の教育における災害医療管理の概念の導入
- 7 . 品質保証メカニズムや災害即応体制の強化など、安全な医療施設の実現に貢献する活動の実施(Safe Hospital事業開始)
閉会式~今後への展望
最終日は閉会式にて研修修了証授与式を行い、終了後には参加者同士の出会いを喜び合っていました。研修を通して参加者より「多くの新たな概念が得られ、今後の自国医療体制改善に非常に参考になった」との感想が多く寄せられました。この経験を活かし、今後もプロジェクトより研修成果のフォローアップを行いながらが各国の国レベル目標達成までの道のりをサポートしていきます。

(注)研修参加者代表Ronald Law氏(フィリピン)の閉会スピーチを主要部分の抜粋にて共有します。
KCCPは我々にとってどの様な意味があったのか?
災害多発国であろうとなかろうと、ASEAN共同体として必要な事は、自助力を高める「準備」であり、お互いに助け合う「団結」である事を自覚しています。日本の災害医療への挑戦は日本独自で出来るものではないのと同様、我々も共に作り上げていかなくてはいけないのです。
我々は何をやり遂げたのか?
日本のシステムにおける最良実践例や日本とASEANからの専門家らとの意見交換などの傍ら、共に過ごした日々は我々が既に「家族」である事を実感させてくれました。新たな学び、新たな友人、そしてアクションプランの草案作成という成果は、このKCCPの成功に大きな影響を与えたと信じています。
我々はこれから何を行っていくのか?
我々は確実にアクションプランを進めていきます。活発な連携を保ち継続的な経験の共有と我々の課題について解決策を見出すために協力していきましょう。そして世界中にARCHプロジェクトと我々のゴールを広めるのです。そうすればOne ASEAN One Responseは実現されるでしょう。
我々の前に広がる道には課題が山積みです。しかし忘れないで下さい。今回のKCCPで我々はいくつかの希望を見出すことも出来ました。ARCHプロジェクトのビジョンは生き続けます-我々は災害保健医療を通してそれを行うためにここにいるのです。そしてKCCP第1期生によって継承させていきましょう。
