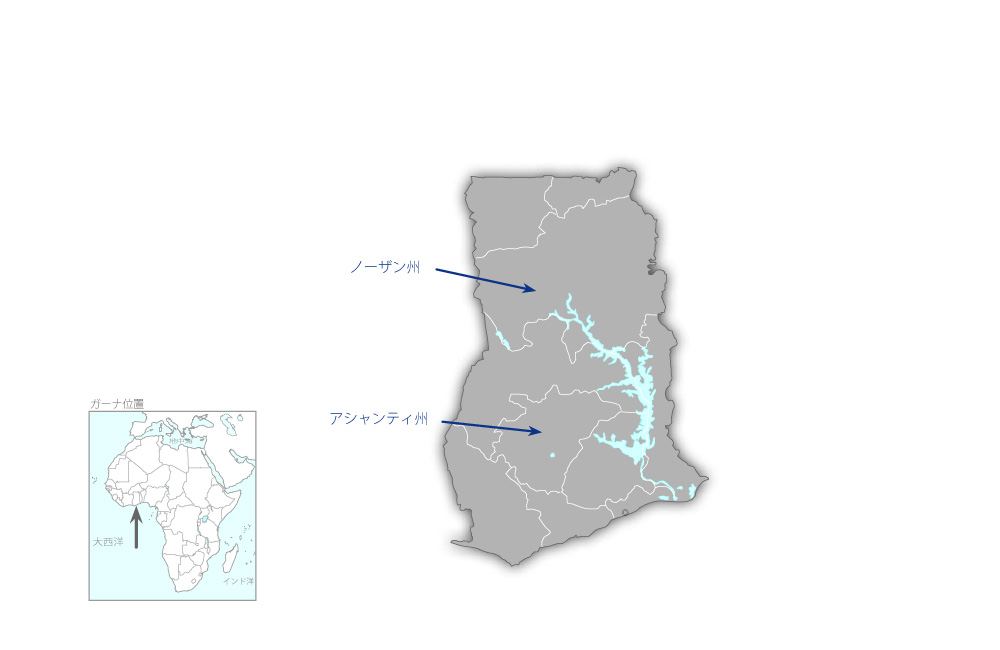地元農民から聞き取り調査をする竹本専門家(左)、辻下専門家(右)と農業普及員。農民たちの稲作に対する悩みや疑問などの相談に乗り、小規模農民の生産性、収益の向上を計る。(写真提供:飯塚 明夫)

日本式の手押し除草機を量産出来ないか話をする農民たち。現地の実情にあった仕組みにするのが大切。(写真提供:飯塚 明夫)

天水稲作圃場。日本の稲作技術を取り入れたモデル圃場。現地の農民たちが自主的にその技術を取り入れ、自分たちの水田を広げている。(写真提供:飯塚 明夫)

米の実り具合を調べる辻下専門家と農業普及員。低湿地の天水を利用した稲作で小規模農民の生産性、収益の向上を計る。ガーナでは、近年コメの消費量が増加している。国内流通量の6割以上を輸入米が占めており、国産米の増産が課題である。(写真提供:飯塚 明夫)

水田の測量を行う農業普及員と辻下専門家。高低差を計り水の流れと圃場均平を考える。農業の現地人専門家を育てるのも目的のひとつ。低湿地の天水を利用した稲作で小規模農民の生産性、収益の向上を計る。ガーナでは、近年コメの消費量が増加している。国内流通量の6割以上を輸入米が占めており、国産米の増産が課題となっている。(写真提供:飯塚 明夫)

農民に日本式の手押し除草機の使い方を指導する農業普及員と辻下専門家。現地に合った技術や知識を伝えてゆく。低湿地の天水を利用した稲作で小規模農民の生産性、収益の向上を計る。ガーナでは、近年コメの消費量が増加している。国内流通量の6割以上を輸入米が占めており、国産米の増産が課題となっている。(写真提供:飯塚 明夫)

低湿地の天水を利用した稲作で小規模農民の生産性、収益の向上を計る。西アフリカは米の原産地、現地の人々は昔から米を食べていた。農民に稲作技術や知識を伝える郡食糧農業省職員農業普及員と辻下専門家。農業の現地人専門家を育てるのも目的のひとつ。(写真提供:飯塚 明夫)

プロジェクトの田園で稲のなり具合をチェックするカウンターパートの男性と農家の夫婦。ジャスミン85という品種が人気があり、植えられている(写真提供:久野 真一)

バナナの林を歩く農家の男性(写真提供:久野 真一)

米の籾殻を取り除く作業をする農家の人々(写真提供:久野 真一)