「プロジェクトニュース(障害者雇用の優良事例)」Case24 ダルハンディテクト病院

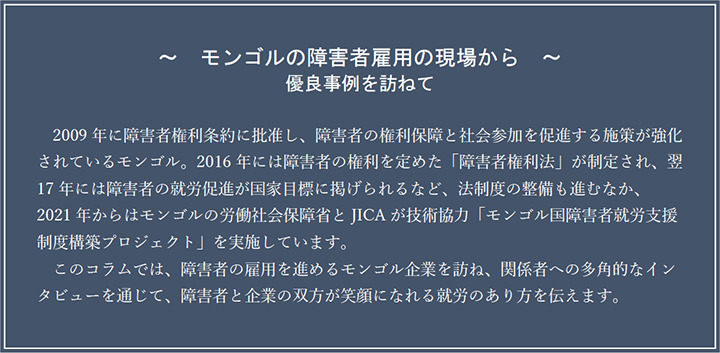
スタッフにも患者にも優しい地域医療の拠点病院を目指して
「一人一人の事情を思いやり、調整を重ねる」

ダルハンディテクト病院のオドバル院長(右端)と、
洗濯場で働くオドンチメグさん(右から2人目)、
産婦人科医のドゥルグーンヘルレンさん(左から2人目)、
そして人事マネジャーのハリウナさん
ランドリールームで働く下肢障害者
ウランバートルの西に位置するバヤンズルフ区の一角に建つダルハンディテクト病院は、もともと軍の駐屯地だった施設を改築し、地域医療の拠点としての役割を担う私立の中核病院として2011年に開業した。9つの診療科と高度な医療機器、そして35床の入院ベッドを備えた総合病院で、患者は子どもから高齢者まで幅広い年齢層にわたる。そのほとんどが近隣のアパートに住む地元の人々だが、保険医療機関として認定を受けている同病院は健康保険の適用を受けることができるため、遠方からわざわざ受診に来る人も少なくない。

12年前に設立されたダルハンディテクト病院は、保険医療機関として認定され、地域医療の拠点となっている(ダルハンディテクト病院提供)

右足に先天的な障害があるオドンチメグさんは、ランドリールームで働いている(2023年11月撮影)
この病院では現在、3人の障害者が働いている。
右足に先天性の障害があるオドンチメグさんは、地下にあるランドリールームで週に6日、働いている。歩行がスムーズではないため、バスで座って通勤しており、火曜と金曜は洗濯と乾燥を、月曜、水曜、木曜、そして土曜はアイロンがけをしている。故郷のバヤンホンゴル県で両親が営む牧畜業を手伝っていたが、2022年に夫と一人娘とともにウランバートルに移住し、同年8月に知人からこの病院の求人を紹介されて応募した。
誰かに雇われて働くのは初めてだったが、不安はなかったというオドンチメグさん。「口数の少ない夫が、時々、私の身体を気遣って、つらくないかと声をかけてくれるのが嬉しいです」とはにかむ姿が可愛らしい。「いい運動になるし、病院スタッフは皆、仲良くしてくれるので、仕事はつらくありません。せっかく採用してもらえたので、一生懸命働きたいです」と、意気込みを語ってくれた。

洗濯やアイロンがけの仕事が好きだと話すオドンチメグさん(2023年11月撮影)
週3回治療を受けながら東洋医学医として勤務
この病院には、医師の中にも障害者がいる。5年前からここで働いているエヌグイさんだ。専門は東洋医学。手首に触れて脈の打ち方や速さを感じながら身体の状態を診断する脈診に基づき、鍼灸治療を行ったり、漢方薬を処方したりしながら、脳卒中患者のまひの治療にあたっている。
エヌグイさんは、ウランバートルにある医学科学大学で東洋医学を専攻し、念願の医師として働いていたが、2019年に腎不全を発症。週3回の人工透析が欠かせなくなり、退職を余儀なくされた。
夢を断たれたショックから、しばらくは透析治療を受けに行く以外は家に閉じこもって鬱々と過ごしていたが、3カ月が経った頃、自宅に近いこの病院を知り合いから紹介された。病気を理由に断られるのではないかという不安もあったが、医師を続けたいという思いを抑えられず思い切って応募すると、院長自ら面接して丁寧に話を聞いてくれ、その場で採用が決まったという。
エヌグイさんは今、週に6日勤務している。うち3日は終日、診療しているが、残り3日は午前中のみ働き、午後は透析治療に通っている。
「腎不全は、1回あたり4時間近くかかる透析治療を週に3回受け続ける必要があり、重いものも運べません。また、仮に午前中のうちに透析治療を終わらせたとしても、午後に働けるかどうかはその日の体調次第なので、職場の理解が不可欠です」「実際、私と一緒に透析治療を受けている若者たちは仕事に就くことができずにいます」——。淡々とした口調でこう話した後、エヌグイさんは熱のこもった声でこう続けた。「私が今、医師の仕事を続けることができているのは、ひとえに院長先生の理解と同僚の先生方のサポートがあるからにほかなりません」
一内科医から院長に
オドンチメグさんとエヌグイさんを採用したのは、院長のオドバルさんだ。モンゴル国立医科大学を卒業し、国立第二病院で働いた後、大学の同級生だった夫とともに栃木県にある自治医科大学大学院に留学。生理学のラボで研究漬けの日々を過ごしながら、2012年に博士課程を修了した。そのまま1年間、ポスドクとして働いてから、モンゴルに帰国したオドバルさんは、世界銀行のプロジェクトで専門家として働いたり、ジグールグランドグループ傘下のグランドメイト病院で内科医として勤務したりしながらキャリアを積み重ねてきた。

ダルハンディテクト病院の院長を務めるオドバルさん。一内科医から院長となり仕事の内容も意識も大きく変わった(2023年11月撮影)
そんな彼女に「ダルハンディテクト病院の院長をやらないか」という声がかかったのは、2019年のことだった。私財を投じてこの病院を設立したのが友人の父親だった縁から、人柄と経歴を見込まれてのオファーだった。
一内科医から病院長になったことで、業務内容はもちろん、意識も大きく変わった。「大病院で働いていた頃は、仕事はチームで分担し、何かあると相談する人がいましたが、今は医師として診療にあたるかたわら、経理から人事まで、病院の運営に関するあらゆることを自分で判断しなければならなくなりました」と、オドバル院長は振り返る。コロナ禍の最中、スタッフに陽性者が出た時には泊まり込みで対応したし、保健医療機関の認定病院として毎日の診療内容を翌朝9時までに報告することと、月々の実績を報告することも義務付けられているため、院長という職務の重責を常に感じているという。

外来診療を待つ患者たち(ダルハンディテクト病院提供)
オドバル院長がもう一つ、力を入れているのが、障害者雇用だ。
院長就任当時、ダルハンディテクト病院はまだ障害者を雇用していなかった。しかし、前職のグランドメイト病院で言語障害がある同僚と働いていたオドバル院長は、個人的に聴覚障害者協会で手話を習うほど、障害者の社会参加に関心を持っていたため、モンゴル国立医科大学時代の同級生からつながった縁でエヌグイさんを紹介された時は、迷うことなく採用を決めた。週3回の透析のことはまったく気にならなかったという。「配慮する、という大げさな意味ではありません。うちは大病院ではないからこそ、一人一人の事情や都合に合わせて働いてもらいたいのです」
一方、オドンチメグさんを採用したのは、2023年10月に参加したDPUB2の企業啓発セミナーがきっかけだった。受講を機に、適切な配慮と調整があれば障害のある人とない人が共に働けることを再認識したオドバル院長は、セミナーで紹介された障害者開発庁の人材登録サービス「e-job」に関心を持ち、スタッフにセミナーの内容を共有したうえで、すぐに登録。2024年11月には、初脊髄損傷により長時間の立ち仕事が難しい産婦人科医のドゥルグーンヘルレンさんをe-jobを通じて採用した。

病院スタッフと入院患者の食事を任されている調理スタッフたち(2023年11月撮影)
スタッフ全員でより良い環境づくりを考える

ダルハンディテクト病院には、内科をはじめ9つの診療科がある(ダルハンディテクト病院提供)
DPUB2の企業啓発セミナーを受講したオドバル院長が、迅速にe-jobに登録できたのは、保健医療機関の認定病院に義務付けられている従業員の継続的な学習機会の一貫として、毎週火曜日に全スタッフを対象に勉強会を開催していることが大きかった。企業啓発セミナーの内容も、勉強会の場で皆に共有して学んだという。
1年前からダルハンディテクト病院で人事兼経理マネジャーとして勤務しているハリウナさんも、その院内勉強会で障害者雇用について学んだ。「院長からは共有してもらった資料を基に、一人一人に合った職場環境を実現するための方法について、皆で定期的に話し合うようになりました」と話す。たとえば、下肢障害がある前出のオドンチメグさんについても、院長と相談したうえで、階段の上り下りやフロアの移動がない洗濯室で働いてもらうことを決めたという。
ハリウナさんは、「以前は、車椅子や白杖を使っているかどうかという外見で障害の有無を判断していたのですが、見た目では分からない障害があるということも、この勉強会で学びました」と振り返ったうえで、「これからも新しい知識を積極的に取り入れながら、皆にとって働きやすい職場づくりを進めます。もちろん障害者からの応募も歓迎します」と、意気込む。
ダルハンディテクト病院は、障害のある患者にとっても、より利用しやすいと思ってもらえる病院を目指し、物理的なアクセシビリティーの改善にも取り組んでいる。もともと軍の駐屯施設だったこの病院にはスロープがないうえ、トイレもバリアフリーではないため、車椅子利用者や下肢障害者にとって利用しづらいのが現状だ。そこでオドバル院長は、外階段の脇にスロープを設置して、正面玄関を自動ドアに替えるとともに、内階段近くにエレベーターを新設することを決断した。現在、外来診療や入院患者の治療の傍ら、改築工事が進められている。
これを受け、工事が終わるまでの間、自分たちにできることはないかとスタッフたちは院内勉強会で話し合い、玄関脇の車椅子利用者が出入りする際に人を呼びやすいよう、玄関脇の低い位置にブザーを設置することが決まったという。「改修工事を行い、物理的なバリアフリーを進めることはもちろん大切ですが、自分たちにできることから調整を進めていこうという機運が院内で高まっているのを感じます」と、嬉しそうにオドバル院長は微笑む。
東洋医学医のエヌグイさんも、「患者の中には、下肢障害や視覚障害、知的障害、てんかんなど、さまざまな障害がある人もいます。看護師に手助けしてもらったり、筆談を取り入れたり、介護者に同席してもらったりして柔軟に配慮したいです」と話す。

入院用ベッドも35床ある(ダルハンディテクト病院提供)

内科の看護師として働くナランゲレル(右)とオドバル院長(左)(2023年11月撮影)
ダルハンディテクト病院のスタッフたちからは、人の置かれている状況を思いやり、自分にできることを考えようとする気持ちが伝わってくる。院内がそんなあたたかい空気に満ちている理由の一つは、「私一人がいくら頑張っても、誰かがやる気をなくしたり、出勤できなくなったりしたら、病院は成り立ちません。そうならないためには、どんな風に働きたいか、何ができて何が難しいのか、最初の段階で遠慮せずに尋ね、要望を理解することが大切なのです」というオドバル院長の理念にあるのかもしれない。そのうえで、「できる」と言われたことは、「本当に大丈夫ですね」と念押しした後、本人に任せるのがオドバル流だ。「障害の有無には関係なく、この病院で働いて良かった、明日も仕事に行きたい、と思ってもらえる病院にしたいのです」と力を込めるオドバル院長。その言葉には、「スタッフが満足していれば、患者にも満足してもらえる医療サービスが提供できるはず」だという信念が込められている。
ダルハンディテクト病院の取り組みからは、人に優しい社会をつくるためには物理的なバリアの解消はもちろん、組織の規則や日々のルーティン上の小さな変革こそが大切だということが分かる。DPUB2の企業啓発セミナーの内容を院内で共有していることからも分かるように、ダルハンディテクト病院は、日頃からスタッフの間で定期的な情報交換の場を設け、風通しよく円滑なコミュニケーションを取りながら、スタッフにも患者にも快適な病院を目指して挑戦を続けており、DPUB2の理念とも共鳴する部分が大きい。人々の暮らしに寄り添い、健康と生命を守る最前線である病院で障害者の雇用が一層進めば、モンゴルの人々にとって障害への理解が一層深まるとともに、包摂的な社会の実現にさらに近づくはずだ。
企業概要
| 企業名 | ダルハンディテクト病院 |
| 事業 | 総合病院 |
| 従業員数(病院全体) | 27人(2024年2月時点) |
| 従業員数(障害者数) | 3人(2024年2月時点) |
| 雇用のきっかけ | ・東洋医学医:元同級生の縁で紹介された ・洗濯担当:知人から病院の求人情報を聞いて応募した ・産婦人科医:e-job |
| 雇用の工夫 | ・障害者から応募があると、一人一人に適した働き方や配属部署を院長と人事担当者が話し合って考える ・週に一度、院内のスタッフ全員を対象に勉強会を開き、学びを深めている ・物理的なアクセシビリティーの改善を進めるかたわら、工事中にできる工夫についても皆で話し合う |
ジョブコーチ就労支援サービスとは
ジョブコーチを通じた障害者と企業向けの専門的な就労支援サービスのことで、モンゴル障害者開発庁が中心となって2022年6月から提供が開始された。
このサービスを通じて、今後、年間数百人の障害者が企業に雇用されることが期待される一方、障害者の雇用が難しい企業には、納付金を納めることで社会的責任を果たすよう求められている。
