「プロジェクトニュース(障害者雇用の優良事例)」Case25 トゥメン・ショヴォート社

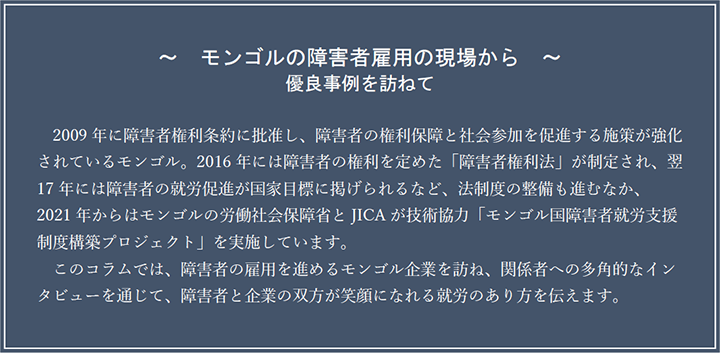
両親、企業、ジョブコーチに見守られながら、
自立に向けて進み始めた知的障害者

知的障害のあるテルムンさん(右から2人)は、大好きな上司、アリマーさん(右端)や、
人事マネジャーのニャムバヤルさん、ジョブコ―チのツォルモンバトルさん、
そして両親のあたたかい応援を受けながら働いている(2023年12月撮影)。
卵ブームの火付け役
栄養の豊富さとバランスの良さから「完全栄養食」とも呼ばれるほど栄養価に優れた卵。人間の身体に必要である良質なタンパク質やミネラル、ビタミン、炭水化物などを豊富にバランスよく含んでおり、滋養強壮食品として、料理やお菓子、調味料の材料として、世界各国で日常的に使われている食材だ。特に、ヨーロッパでは、古代ローマ人もさまざまな形で卵を好んで食べていたという記録が残っているほど長きにわたって人々の食生活に根付いており、1人当たりの卵の摂取量は年間270個に上るという。

トゥメン・ショヴォート社の卵はモンゴルの卵ブームの牽引役だ(2023年12月撮影)
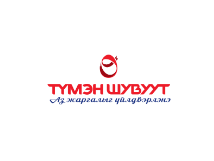
卵をモチーフにしたシンプルで洗練された同社のロゴ
他方、諸外国と異なり、卵を食べる習慣があまりなかったモンゴルでも、近年は急速に需要が拡大している。2000年に年間17個だった1人当たりの卵の摂取量は、2017年に90個へと急増。その後も需要は着実に増え、現在は年間100個を上回っているという統計もあるという。
この卵ブームをけん引しているのが、国際基準にのっとった卵の生産体制をモンゴルでいちはやく確立したトゥメン・ショヴォート社だ。飼料の研究や遊牧民に対する助言など、モンゴルの農牧業の発展に尽くしてきたエルヘムバヤル夫妻によって2004年に設立された同社は、「1万羽の鶏」という意味の社名が物語るとおり、創業以来、一貫して養鶏と採卵を手掛けてきた。近年、モンゴルでも新しい卵会社の誕生が相次ぐ中、インキュベーター(孵卵器)で65万羽の鶏を飼育し、日に50万個の卵を生産・販売している同社は、常にシェア40%以上を誇っている。
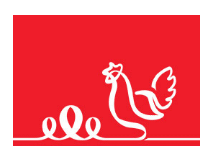
鶏と卵がモチーフの親しみやすいブランディングデザイン
創業当時は11人だった従業員も現在は270人を超える。養鶏場に加え、再生紙を利用して卵の容器を製造する工場や、鶏糞を乾燥・発酵させて肥料を作る工場を擁しているほか、灌漑事業を営む子会社を展開している。特に、鶏糞から作るオーガニック肥料の質は関係者からも高く評価されており、近隣の農家に提供して循環型農業に役立ててもらうなど、環境問題への貢献にも積極的だ。創業15周年を迎えた2019年に一新したという白地に赤のロゴは、卵をモチーフにしたシンプルで洗練されたデザインで、鶏と卵がモチーフのかわいらしいブランディングデザインとともに、人々の親しみを誘っている。
そんな同社では障害者の雇用も進めており、現在、視覚障害や聴覚障害、知的障害がある障害者6人を雇用しているほか、内部障害がある夫婦とも契約を結び、社員の制服の縫製を委託しているという。
仕事が大好き 「僕が運んだ卵かな」

重量やサイズごとに選別された卵は、包装されて各地に出荷される(2023年12月撮影)
2023年12月、ウランバートル市西部のソンギノハイルハン区にある本社を訪ねた。4つの養鶏場からトラックで毎朝運ばれてくる産まれたての卵の重量を計量し、サイズごとに選別する作業が、本社屋の奥に広がる倉庫で行われている。パッキングされた卵は、ここからウランバートル市内やダルハン市、エルデネット市など国内15都市に出荷されて、消費者に届けられる。
ここで働く20人の社員の中に、知的障害者のある男性がいる。25歳のテルムンさんだ。毎朝6時に起床し、バスで30分かけて出勤した後、運ばれてきたトラックから卵を下ろして倉庫内に積んでいる。勤務は、日曜を除く週6日。朝8時から夕方17時までの勤務は楽ではないが、「卵を落としたり割ったりしたことは一度もないですよ」と胸を張る。スーパーに並んでいる卵を見ると、「僕がトラックから下ろした卵かな」と考え、思わず顔がにやけてしまうほどこの仕事が大好きだという。

同僚と一緒に倉庫で働くテルムンさん(右)(2023年12月撮影)
市内の私立高校を卒業後、企業で事務の仕事をしたこともあるが続かず、通っていたジムが主催するボディビル大会でスタッフとしてアルバイトをしていたというテルムンさんが、2023年9月にトゥメン・ショヴォート社に就職し、こうして生き生きと働き続けることができているのは、本人の頑張りはもちろん、周囲の人々からの応援と理解、そして後押しが非常に大きい。
人事マネジャーを動かした両親の思い
テルムンさんの採用を決めたのは、人事マネジャーのニャムバヤルさんだ。
ソンギノハイルハン区の社会福祉課で3年間、障害者や弱者の支援業務に携わっていた経験があるうえ、社会福祉士の資格も取得しており、一人の人間が社会生活を営みながら自立する大切さを重々理解しているニャムバヤルさん。親が障害のある子どもの世話に追われて家を空けられず、仕事に出られないために生活が行き詰まる家庭を数多く見て来た経験から、トゥメン・ショヴォート社に移ってからも障害者の自立の大切さを折に触れて痛感していたという。

社会福祉士の資格をもち、障害者の自立の必要性について日頃から考えていたという人事マネジャーのB.ニャムバヤルさん(2023年12月撮影)
テルムンさんのことは、彼の父親を通じて知った。2023年8月に同社が出した電気修理士の求人にまず父親が応募してきて、面接に呼んだ際、「自分には障害のある一人息子がいるのだが、彼にできる仕事はないでしょうか」と相談されたのだ。意表を衝かれ、その場ではとりあえず息子の履歴書を受け取っただけだったが、日頃の問題意識から巡り合わせを感じたニャムバヤルさん。それから間もなく配達の仕事に空きが出たため、自分から改めて父親に電話を入れ、「息子さんに面接したい」と伝えた。
父親に連れられて来たテルムンさんはいささか緊張した面持ちだったが、父親が一緒に部屋に入ろうとすると、「一人で大丈夫」ときっぱり告げ、ニャムバヤルさんを驚かせたという。独立心の強さを垣間見て、彼を応援したいという思いを深めたニャムバヤルさんは、その後、小学校の先生をしている母親とも電話で話し、「我々はいつかこの子を残して先に逝かなければなりません。その前に息子を自立させたいのです」という言葉に胸を打たれ、採用を決めた。その代わり父親の採用は見送ったが、両親は彼女に繰り返し謝意を伝えてきたという。特に、「もし問題が起きても、どうか代わりにやってあげようとはせず、自分で解決する経験を積ませてやってください」という母親の言葉は、今も鮮明にニャムバヤルさんの耳に残っている。
きめ細やかなフォローアップとフェードアウトを実践

リラックスした笑顔を見せるテルムンさん(左)と、ニャムバヤルさん(右)(2023年12月撮影)
息子の将来を案じる父親と母親の深い思いに突き動かされ、テルムンさんの採用を決めたニャムバヤルさんだったが、同社はその時、聴覚障害のある男性を採用したにも関わらず、わずか数日で退職されたばかりだった。同じことを繰り返すことなく、テルムンさんに安心して長く働きたいと思ってもらうためにどうすればよいかと考えを巡らせる中でニャムバヤルさんが思い出したのが、2023年4月に開かれたDPUB2の企業啓発セミナーで聞いたジョブコーチ制度や、アセスメントの大切さだった。ニャムバヤルさんはすぐに障害開発庁に連絡し、「採用したい障害者がいるので、適切な部署に配属できるようにアセスメントしてほしい」と依頼。1週間後に紹介されたのが、ジョブコ―チのツォルモンバトルさんだった。
警察大学で学んだ後、26年もの間、警察官として勤務したというツォルモンバトルさん。任官する時に父に言われた「人を差別することだけは、してはいけないよ」という言葉が人生の指針だと語る熱血漢だ。
退職後は、教育支援を行うNGOや職業訓練所を立ち上げる傍ら、食事をしながら勉強できる場所を子どもたちに提供しようと故郷のブルガン県にコーヒーショップを開くなど、社会活動に精を出す。2023年6月にDPUB2のジョブコーチ養成研修を受講してからは、ジョブコーチとしても活動しているうえ、自身も前出のコーヒーショップで2人の障害者を雇用している。
トゥメン・ショヴォート社から開発庁を通じてアセスメントの相談を受けた時も、ツォルモンバトルさんは迷うことなく「まず本人と会ってみましょう」と即答。同社を訪問し、本人や同僚と面談をした翌日には、正式に依頼を引き受けた。

2023年6月にDPUB2のジョブコーチ養成研修を受講したツォルモンバトルさん(2023年12月撮影)

上司のアリマーさん(右)、ジョブコーチのツォルモンバトルさん(左)と一緒に卵を段ボールから取り出す作業に精を出すテルムンさん(中央)
テルムンさんは長い受け答えが苦手で、何か尋ねられても、「はい」か「いいえ」で答えることしかできない。それでも、こちらが明確に指示を出せば、十分に理解できるうえ、以前はジムで身体を鍛えていたというだけあって、筋肉がある様子を見て、ツォルモンバトルさんは車で配達するより、卵を自分で運ぶ仕事が向いていると判断し、現在の作業を提案した。さらに、テルムンさんが入社した直後の2023年9月と10月は週に一度、定期的に会社を訪問して様子を確認したり、11月以降は訪問する代わりにニャムバヤルさんとテルムンさんに電話を入れたりと、ジョブコーチ養成研修で学んだことを忠実に実践したうえ、一番古くから働いている社員に社内の雰囲気を確認するなど、精力的に調整に取り組んだという。
そんなツォルモンバトルさんについて、人事のニャムバヤルさんは、「いつも明るくて行動力があるし、社員たちに自分から積極的に声をかけて心を開いてくれるので、とても馴染んでいますよ」と話し、高い信頼を寄せる。今回はテルムンさんの採用を決めてからジョブコーチに相談することになったものの、今後、新たに障害者を採用する際は、マッチングの段階から助言を仰ぐつもりだという。
信頼関係を築いて仕事ぶりを見守る
もう一人、テルムンさんにとって心強い応援者がいる。卵の運搬や仕分け、包装を行う倉庫を統括しているアリマーさんだ。テルムンさんの直属の上司にあたる。
創業当時からトゥメン・ショヴォート社で働き続けてきたアリマーさんにとって、テルムンさんは初めての障害がある部下だ。彼が倉庫に配属されてきた当初は、無神経な発言をして彼を傷つけたりしないだろうかという不安も感じていたと振り返る。まずはテルムンさんのことを知ろうと、最初の2日間は両親の話や住んでいる場所などについて話しかけ、気持ちをほぐしてから、少しずつ仕事の手順を教えた。言いたいことを一度にすべて言おうとせず、内容を細かく分けて、できるようになるまで何度も伝えることを意識したという。

テルムンさんの上司、Ts.アリマーさん
信頼関係の構築を大切にしてきたアリマーさんや、人事マネジャーのニャムバヤルさん、ジョブコーチのツォルモンバトルさんの後押しもあって、少しずつ仕事に慣れたテルムンさんは、今や「仕事が大好き」というのが口ぐせになり、遅刻も欠勤もなく熱心に働いている。アリマーさんは、「真面目に働いてくれる社員のことは皆、かわいいです。障害の有無は関係ありません」と言ったうえで、「特にテルムンさんは、2人の娘と年が近いこともあり、息子のように思っています。オープンな性格で、最近は好きなロックバンドや、ガールフレンドの話もしてくれるようになったんですよ」と、顔をほころばせる。

仲良しのアリマーさん(奥)と共に倉庫で働くテルムンさん(手前)
そんなアリマーさんも、テルムンさんの母親と電話で話したことがあり、息子を思う強い気持ちに胸打たれた一人だ。
「子どもになんらかの障害があると、家に囲い込んで外に出そうとしない親が多くいます。そうすることで子どもを守ろうとしているのかもしれませんが、それではいつまで経っても子どもは何の経験も積めず、生きる力が身につきません」と、顔を曇らせた後、アリマーさんは力を込めてこう続ける。「テルムンさんがこうして毎日、出社して働くことができているのは、知的障害がある我が子を、勇気を出して社会へと送り出すことを決断したご両親のおかげです」
さらにアリマーさんは、テルムンさんが仕事に慣れるまでの間は、同僚たちに「テルムンさんのご両親がどんな思いで彼を育ててきたのか。そして、なぜ今、仕事をさせようと決めたのか、考えてみてください」と繰り返し語りかけたという。
実際、テルムンさんが入社した当初、社内では「仕事のフォローや肩代わりをさせられて残業が増えるのではないか」と危惧する声も上がったという。しかし、アリマーさんをはじめ、ツォルモンバトルさんやニャムバヤルさんたちが同僚たちと面談を重ね、「障害は本人ではなく、環境にあるのだ」と繰り返し説明した。その中で、そうした不安や不満も次第に聞かれなくなり、最近では休憩時間にテルムンさんが同僚たちと一緒にタバコを吸いながら談笑する姿を見かけるようになった。3カ月の仮採用期間が終了して本採用になった時には、「テルムンが今日、自分のロッカーがもらえたよ、と嬉しそうに報告してくれました」と、母親からお礼の電話もかかってきたという。
「障害者の就労を実現するためには、家族が勇気を出して本人を家の外に出すことと、受け入れる側の双方の理解が不可欠です」と話すアリマーさんからは、テルムンさんの背中を押して社会に送り出した両親の思いをしっかり受け止め、成長を見守っていくことを決めた受け入れ企業としての決意とあたたかい愛情が伝わってくる。

作業の合間に、アリマーさん(左から2人目)やニャムバヤルさん(右から2人目)、ツォルモンバトルさん(右端)と笑顔で会話するテルムンさん(左端)
テルムンさんは最近、貯金を始めた。これも、一人息子の将来を案じる両親の計らいだろう。「お金が増えていくのが楽しい」「将来はアパートを買いたい」と、無邪気な笑顔を見せるテルムンさん。その手には、最近、別の会社で警備の仕事を始めた父親がくれたという大ぶりの指輪がはめられており、両親の愛情を象徴しているかのように存在感を放つ。
皆から優しくあたたかい愛情と応援に育まれながら卵を運ぶ中で、笑顔が増え、周囲と交流できるようになり、夢を口にするようになったテルムンさんの姿は、4つのことを示している。1)障害者が社会に出ることが自立に向けていかに大切かということ、2)そのためには家族と職場の両方の理解が欠かせないということ、3)障害者を受け入れることで、同僚たちの障害への理解も促進されるということ、そして4)障害者の雇用にあたり、適切な部署への配属や、職場への適応を側面支援するDPUB2のジョブコーチの役割は効果的だということ、の4点だ。
モンゴルの人々の暮らしにとって急速に身近な存在となっている卵の生産会社で生まれたこの心あたたまるエピソードが広く共有されることで、障害に対する正しい理解が育まれ、障害者の自立に向けた機運を社会全体で盛り上げていく先駆的な事例となることは、間違いないだろう。
企業概要
| 企業名 | トゥメン・ショヴォート 社 |
| 事業 | 卵の生産・販売 |
| 従業員数(本社、倉庫、養鶏場、子会社含む) | 約270人(2024年3月時点) トゥメン・ショヴォート社(本社、養鶏場、パッケージ会社)で約250人が勤務/灌漑事業を営む子会社で約20人が勤務 |
| 従業員数(本社および倉庫) | 約20人(2024年3月時点) |
| 障害者数(本社、倉庫、養鶏場、子会社含む) | 6人(2024年3月時点) |
| 障害者数(本社および倉庫) | 1人(2024年3月時点) |
| 雇用のきっかけ | ・当事者の父親が面接に来て、「息子に合う仕事はないだろうか」と直談判した ・人事マネジャーがもともと障害者を取り巻く環境に問題意識を持ち、自立の必要性を感じていた ・息子の将来を思う両親の愛情に胸を打たれた |
| 雇用の工夫 | ・ジョブコーチがアセスメントを行い、配属部署について助言した ・採用から2カ月はジョブコーチが週に一度、職場を訪問し、3カ月目からは電話で様子を把握した ・上司が本人と丁寧に信頼関係を構築した ・障害者とともに働くことを不安がる同僚たちと面談を重ね、繰り返し説明した |
ジョブコーチ就労支援サービスとは
ジョブコーチを通じた障害者と企業向けの専門的な就労支援サービスのことで、モンゴル障害者開発庁が中心となって2022年6月から提供が開始された。
このサービスを通じて、今後、年間数百人の障害者が企業に雇用されることが期待される一方、障害者の雇用が難しい企業には、納付金を納めることで社会的責任を果たすよう求められている。
