「プロジェクトニュース(障害者雇用の優良事例)」Case31 第127番幼稚園

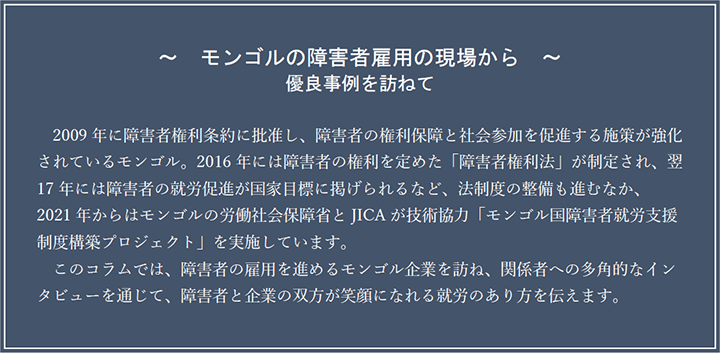
二人の教育者に見守られながら知的障害者が働く幼稚園
「インクルーシブな教育にかける熱い思いが社会を変える」

知的障害があるオトゴンスレンさん(中央)と、
長年にわたりモンゴルの幼稚園教育に携わり、
ともにインクルーシブ教育の普及に取り組む
ジョブコーチのブドハンドさん(右)、
127番幼稚園の園長のンフツェツェグさん(左)バドゾリグさん
(2024年6月撮影)
異なる個性や価値観を受け入れる心を育む
近年、特別な支援が必要な子どもと、そうでない子どもを分けて教育するのではなく、障害や病気の有無、国籍、人種、宗教、性別などさまざまな違いを超えてすべての子どもたちが同じ環境でともに学ぶ「インクルーシブ教育」の導入が世界的に進んでいる。その背景には、成長段階で周囲から切り離されることによって、障害のある子どもがさまざまな人間関係や社会経験を積む機会が奪われると同時に、障害のない子どもたちにとっても、自分と異なる個性や価値観を受け入れる心を育む機会が失われるという問題意識がある。支援が必要な子どもを学校全体で支える体制を築き、障害がある子どももない子どももみんなが大切にされる、多様性を尊重した教育を通じて、誰もが活躍できる共生社会の実現を促すことがインクルーシブ教育の理念だと言える。
モンゴル政府もこうした問題意識を強く持ち、以前からインクルーシブ教育プログラムの策定に取り組んできたが、2009年に国連の「障害者権利条約」を批准すると、関連する国内法を整備するなど取り組みを加速。障害者基本計画にあたる「障害者の権利、参加、発達支援に関する国家プログラム」を策定するなど、障害児や障害者の社会参加の保障を進めてきた。2016年には「障害者権利法」も制定している。
障害者問題の解決のカギを握る教育

モンゴルの幼稚園でインクルーシブ教育の普及を進めてきたブドハンドさん(2024年6月撮影)
そうした時流をとらえ、幼稚園にインクルーシブ教育の導入を進めてきたのが、ブドハンドさんだ。長年にわたり、主に身体障害のある子どもたち向けの「第10番幼稚園」に勤務後、2009年から通常の幼稚園である「第147番幼稚園」で園長を務めた経験がある。
当時、ブドハンドさんは「自分の任期中にインクルーシブ教育を実践しよう」と決意し、第147番幼稚園で障害のある子どもたちを積極的に受け入れたという。「モンゴルの障害者たちは、教育を受ける機会がないために自分に自信を持つことができず、仕事を続けられないし、いつまでも自立できません。障害者を取り巻く問題の根幹は教育にあるのです」。
その後、「障害児親の会」で2年ほどアドバイザーを務めたブドハンドさんは、2022年11月にNGO「新たな一歩センター」を立ち上げた。モンゴルの障害者支援分野のリーダーの一人で、労働法や税法などさまざまな法律に障害者への配慮を盛り込むように国会議員に働きかけたことで知られるオユンバートルさんとともに設立した団体で、重度の知的障害がある成人の就労支援に特化したモンゴルで唯一のNGOだ。
教育者であると同時に、NGOのアドバイザーや設立者としても精力的に活動するブドハンドさん。そんな彼女は、障害者の教育や自立の観点から障害者雇用について学びたいと、2023年3月にDPUB2のジョブコーチ養成研修も受講した。
「研修を通じて、障害者本人だけでなく、雇用主との密なコミュニケーションが重要であることや、一人一人に合わせて職場環境の改革を働きかける必要性について学びました」と振り返る。特に、講義後の演習でロールプレイを行い、雇用する企業側の立場や障害当事者の立場について考えられたことが勉強になったという。

ブドハンドさんは、ジョブコーチとしても活動している(2024年6月撮影)
「“お兄さん”と話しかけられることが嬉しい」
ブドハンドさんがジョブコーチとして支援した一人がソンギノハイルハン区のゲル地区にある「第127番幼稚園」で働いていると聞き、2024年6月に訪ねた。門扉を入ると、園舎の壁や園庭にピンクやブルー、イエローなどの優しいパステルカラーで描かれた「まる」や「さんかく」、「しかく」が目に飛び込んできた。その脇には色鮮やかな滑り台や遊具も設置されており、周囲は目隠しフェンスで囲まれている。子どもたちが外の世界を感じながら安心して遊ぶなかで、図形の違いを自然に認識できるようになるための工夫なのだろう。園舎内の廊下や階段の壁にも、モンゴルの伝統衣装を着た男の子と女の子の絵が描かれるなど、気持ちが明るくなる仕掛けが随所に感じられる。

園舎や園庭に優しいパステルカラーで「まる」や「さんかく」「しかく」が描かれた127番幼稚園の外観(2024年6月撮影)

園庭に設置された滑り台などの遊具の色もポップで可愛い(2024年6月撮影)
オトゴンスレンさんは2023年6月に「新たな一歩センター」に入り、ブドハンドさんの紹介で、同年9月よりこの幼稚園で屋外の清掃担当として働いている。知的障害があり、人に話しかけられると極度に緊張する傾向があることから、平日10時から14時の短時間勤務で、残業はない。
しかし、仕事に慣れるにつれてオトゴンスレンさんにも少しずつ変化が見られるという。事実、「子どもたちから“お兄さん”と呼ばれるのが嬉しいです」とはにかみつつ答える姿からは、人に話しかけられるのを怖がっていた以前の様子は感じられない。さらに、仕事を始めて3カ月が経った頃に開かれたクリスマス会では男性スタッフが足りず、オトゴンスレンさんが急きょ、付け髭をつけてサンタクロースに扮したという。「子どもたちが僕だと気付かず、“サンタのおじいちゃん”と呼んでいたので可愛かったです」と、楽しそうに教えてくれる様子からは、余裕すら伝わってくる。

ジョブコーチのブドハンドさんの支援を受けて127番幼稚園で働いているオトゴンスレンさん(2024年6月撮影)
そんなオトゴンスレンさんに、最近、夢ができた。溶接の仕事をしている父親のように技術者になることだ。幼い頃に両親が離婚し、母親に引き取られたオトゴンスレンさんは、物心ついた頃から父親とは一緒に暮らしていないが、腕一本で人生を切り開いている父親にずっと憧れてきたという。127番幼稚園で働き始めるのと相前後して、オンラインで中学校の授業も受け始めた。「来年、卒業したら電気修理士の資格を取ろうと思います」と、毅然とした口調で話してくれた
障害のある子どもとない子どもが学び合う環境を
将来の夢を語るオトゴンスレンさんの横顔を頼もしそうに見つめるのは、園長のエンフツェツェグさんだ。6年前からここで園長をしている。ブドハンドさんから紹介されて、オトゴンスレンさんの採用を決めた。
通算18年にわたり幼稚園教育に携わってきたエンフツェツェグさんがブドハンドさんと知り合ったのは、ブドハンドさんが園長をしていた第147番幼稚園で彼女も勤務していた時のことだった。インクルーシブ教育の導入に奔走するブドハンドさんの姿勢に触発されて自身も障害に対する意識が高まったというエンフツェツェグさん。そんな彼女は今、園長として、障害のある園児の受け入れと、障害者の雇用を進めている。現在、第127番幼稚園には約400人の園児が通っており、うち自閉症の子どもが3人、ダウン症の子どもが1人いるほか、65人の教職員のうち、オトゴンスレンさんともう1人が障害者だという。

127番の園長を務めるエンフツェツェグさん。18年にわたり幼稚園教育に携わってきた。(2024年6月撮影)

127番幼稚園でともに働く同僚とポーズを取るオトゴンスレンさん(右)(2024年6月撮影)
ブドハンドさんとエンフツェツェグさんがこれほどインクルーシブ教育に情熱をそそぐのは、長年の経験から得た確信があるからだ。早い段階から障害のある人と接する機会がある人ほど偏見や排除から自由だと二人は感じている。
「幼い子どもは、ダウン症の子どもがいても、いじめることなく一緒に遊びます。偏見がないからです」「だからこそ障害のある子どもと障害のない子どもを一緒に育てることは、双方にとって大切です」「子どもは周りの子どもを見て育つのです」と、エンフツェツェグさんは熱く語る。
実は、エンフツェツェグさん自身も、インクルーシブ教育について知るまでは、障害のある人とない人を分けて別々に接するのがそれぞれにとって良いことだと考えていたという。その反省があるからこそ、エンフツェツェグさんはオトゴンスレンさんの採用に先立ち従業員を集め、障害の特性や障害者配慮について話し合いを行った。
それでも、いざオトゴンスレンさんが働き始めると、「言われた場所しか掃除せず、近くにペットボトルが落ちていても拾おうとしない」「知的障害者が働くのは無理なのではないか」などと非難する者が出てきた。あからさまに声を上げなくても、どう接したらいいか分からず様子見する教職員も少なくなかった。
そこでエンフツェツェグさんは再び話し合いの場を設け、複数の話題を一度にしない、仕事は1つずつ指示する、など障害特性に応じた接し方が必要だと重ねて説明し、出勤時や昼休みにオトゴンスレンさんとコミュニケーションを取るよう働きかけた。地道な努力が奏功して教職員の間でも少しずつ理解が広がっており、積極的にオトゴンスレンさんに話しかけたり、障害について勉強したりする人も増えているという。

カラフルに色分けされた階段には、モンゴルの伝統衣装を着た可愛らしい男の子と女の子の絵が描かれている(2024年6月撮影)

オトゴンスレンさんが時計の枠を利用して作ってくれたという壁飾りを手に嬉しそうに微笑むエンフツェツェグ園長(2024年6月撮影)
「オトゴンスレンさんを採用したのを機に、幼稚園の中でも障害への理解が広がりつつあります」と、手応えを話すエンフツェツェグさん。「これを弾みに障害児、特に知的障害のある子どもの受け入れをさらに拡大し、インクルーシブ教育を拡充していきたいです」と意気込む。「将来的にはモンゴルのすべての幼稚園で各クラスに障害児が受け入れられ、一緒に学ぶことが当たり前になってほしいですね」。
DPUB2を通じてジョブコーチになったブドハンドさんと、かつて彼女とともに働き薫陶を受けたエンフツェツェグさんが、二人三脚でインクルーシブ教育の導入と障害者雇用を進めている第127番幼稚園。そこで生まれつつある変化は、障害のある人とない人がともに過ごすことで互いに学び合える教育の実践につながる確かな第一歩だ。その先に広がる、互いの違いを認め合い、尊重し合える成熟した社会の実現に向けて、二人の教育者たちの挑戦は続く。
企業概要
| 企業名 | 127番幼稚園 |
| 事業 | 幼稚園教育 |
| 従業員数(企業全体) | 65 人(2024年6月時点) |
| 障害者数(企業全体) | 2人(2024年6月時点) |
| 雇用のきっかけ | ・園長にインクルーシブ教育に取り組むきっかけをくれた前の幼稚園の園長がジョブコーチとなり、知的障害者を紹介してくれた。 |
| 雇用の工夫 | ・採用前後に園長が複数回にわたり教職員を集め、障害理解について説明したり、コミュニケーションを働きかけたりした。 ・安定して仕事に取り組めるよう、短時間勤務制にした。 |
ジョブコーチ就労支援サービスとは
ジョブコーチを通じた障害者と企業向けの専門的な就労支援サービスのことで、モンゴル障害者開発庁が中心となって2022年6月から提供が開始された。
このサービスを通じて、今後、年間数百人の障害者が企業に雇用されることが期待される一方、障害者の雇用が難しい企業には、納付金を納めることで社会的責任を果たすよう求められている。
