e-BPS(電子建築許可申請システム)の研修を実施しています!
NNBC遵守に対する意識改革の促進を目的とし、建物建設に関わる関係者の能力開発の一環として、e-BPS(電子建築許可申請システム)の研修を実施しています。
e-BPSは本事業とは別に当初UNDPが支援して自治体への導入が始まっており、本事業が対象にする7つのパイロット自治体のうち、3自治体はUNDP開発版の利用を開始しています。従って、3自治体は既にe-BPS操作の基本を理解しており、新たに導入する4自治体を助けられる状態にあります。ただし、本事業以前は建設許可事務手順書(BCWP: Building Construction Working Procedure)を各自治体が定めることになっていたため、各自治体間でe-BPSの機能に違いがありました。
本事業ではBCWP(建築許可実務手順書)を全自治体向けに共通化したうえで、敷地確認や監理記録報告、自治体による検査確認が追加導入されており、その内容に沿ってe-BPSが改訂強化されました。
そこで、e-BPSの新たな機能を使いこなせるように研修が実施されました。まず、マスタートレーナーを育成するためのトレーニング(MTOT: Master Training of Trainers)の中で2日間の操作研修を行いました。
e-BPSのユーザーマニュアルは、BCWPが設計者や監理者、自治体審査担当者といった担当者別のガイドラインを有するのと同じように、利用者別のマニュアルが用意されています。MTOTでは、1件の新築案件について建築許可が申請されてから許可されるまでの一連の流れに沿ってe-BPSが支援する機能をひと通り説明しながら、研修員が実機を操作しながら操作を習得しました。1件の新築案件について、設計者や監理者、自治体審査担当者や現場確認担当者といった複数のユーザーが関わりますので、研修員は全てのユーザーマニュアルを参照しながらe-BPSの全体を俯瞰できるように研修が企図されました。
MTOTのe-BPSの講義1日目(MTOT全体の4日目)では、UNDP開発版で使っている機能の改訂部分を中心に講義と演習が行われました。建築許可申請の流れにおいて、e-BPSは以下のような支援をします。
- 1 . 施主ないし設計者が行う建築許可申請では、新しい耐震設計基準NBC105等の各種建築基準に沿った審査項目をe-BPSへ入力し、また、監理記録報告の導入に伴い施工監理者も資格者登録します。
- 2 . 自治体の申請受付窓口では申請内容の様式がチェックされ、不足があった場合にはコメントを付して差し戻され修正のうえ再度申請します。これはe-BPSのオンライン上で行います。
- 3 . 様式チェックを終えた建築許可申請は自治体の審査担当者へ回付され、一連の建築基準に合致しているかどうか審査されます。不足事項はコメントを付し申請者へ差し戻され、申請者が修正します。上下水道の衛生基準といった自治体独自の要求事項も審査され、e-BPSに適否が記録されます。審査時には申請時に添付されたCADデータを表示参照しながらチェックします。
- 4 . 設計審査を終えた建築許可申請は自治体の現場確認担当者へ回付され、周辺住民の異議受付を行います。周辺住民の異議を含む現場確認結果は、現場確認担当者の報告としてe-BPSに記録されます。
- 5 . 土地や建物の面積や用途に合わせた申請手数料をe-BPSが計算し、申請者は収納課へ納付します。
- 6 . 現地確認を終えた建築許可申請は自治体の審査担当者へ再度回付され、手数料収受確認などを最終チェックしたうえで、上長により建築仮許可が発行されます。許可証は所定書式で印刷され、上長が直筆サインして手交されます。
以上のe-BPS研修は、パイロット7自治体中の3自治体がe-BPSを利用しているため、先行している自治体職員が導入前4自治体の職員を助けながら効果的に操作を習得できました。
MTOTのe-BPSの講義2日目(MTOT全体の5日目)は、JICA開発版で強化された機能を中心に講義と演習が行われました。
- 1 . 本事業にて施工途中の現地確認(検査)が新規に追加され、また、自治体の現地確認に先立ち施工を監理する者がまず検査を行うこととBCWPに規定されました。e-BPSでは、施主に代わって監理者が自治体へ現地確認を申請する際に、監理者自身の検査結果報告を添付します。
- 2 . 申請を受領した自治体は、現地確認申請が出ている案件をGoogle Map上に表示して、移動距離が最短になるように訪問順序を考慮して現地確認担当者を決定します。
- 3 . 現地確認担当者はe-BPSをインストールしたタブレットを携行して現場を訪問し、設計内容や監理者の検査報告を参照しながら確認作業を行い、その現場確認の報告をe-BPSに記録します。
- 4 . 現地確認を終えた建築物件は、建築仮許可証と同様にe-BPSを用いて検査完了証が発行されます。
- 5 . 建築基準やBCWPを定めるDUDBCは、その運用状況を確認できるように、各自治体の建築許可申請に係る全ての情報をe-BPS上でモニタリングすることができます。特に、建築基準に違反する許可証や完了証がないかをモニタリングできるように、現地確認報告内容の登録や変更は、どのユーザーがいつ行ったかが分かる履歴が記録されるようになります。
- 6 . この他に、紙で保存されている過去の建築許可申請について、e-BPSで申請や審査、現場確認が行われた案件と名寄せができるように、申請番号や施主などの主要な情報をデータ化し、検索できるようになることが紹介されました。
MTOTの5日間中の2日間を通じて、各自治体の研修員からe-BPSを使いこなすことで作業が効率化することが期待され、また、公平で透明性の高い現場確認を行う重要性が申し合わされました。
以上のe-BPSの操作説明や演習に加えて、導入済み自治体から成功事例を紹介していただき、建物台帳の整備など、さらなる利活用の取り組みにも言及していただいています。
また、今回改訂強化したJICA開発版e-BPSの機能の中には、本事業後にe-BPSを全国展開することを見越して、サーバーの初期設定を共通化して強化する部分もあります。そのため、各自治体のIT関係者を対象にしたシステム運用研修を、MTOTとは別途開催しました。
最後に、自治体によってはより特化した範囲で追加のe-BPSの操作に習熟する研修を希望する場合もあります。e-BPSの開発委託先やUNDP等の他事業関係者と調整しながらきめ細かい支援を行い、e-BPSを活用した建築許可業務が円滑に導入されるように事業を実施しているところです。
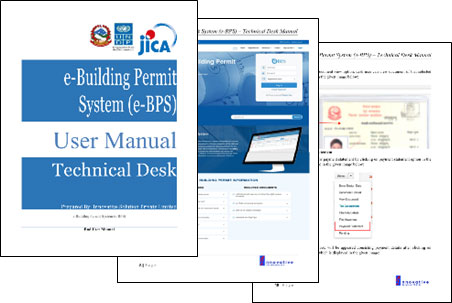
MTOTで使用したe-BPSのマニュアル

MTOTでのe-BPSの実習の様子
