22. 配水網および水汲み後の管理に渡る飲料水の水質変化の解明
みなさん、こんにちは。京都大学修士2年の髙橋侃凱(やすとき)です。私は、7月中旬から9月いっぱいにかけ、「配水網および水汲み後の管理に渡る飲料水の水質変化の解明」をテーマにした調査をチャワマ地区で実施しました。
調査地では、水供給システムの脆弱さにより間欠給水(1日中常に水が供給されているわけではなく、1日の中で24時間に満たない時間のみ水が供給されることを言います)が行われていました。間欠給水により管内での水の滞留時間が延び、水質が劣化していたり、管外からの汚染物質が流入したりしている可能性のある状況でした。そこで、改善された水源、とされている給水栓が実際に安全な水を供給しているのか調査しました。また調査地では、住民はバケツなどの容器への貯留による水利用を余儀なくされていました。水は、給水栓から得た時点では清潔だとしても、運搬や貯留などの間に汚染されれば、病原性微生物の曝露の要因となります。そこで、給水栓の水が取水されて運搬・貯留・利用される過程で、どのように汚染が進むのか調査しました。
今回の研究では、調査地で採取した水サンプルや、コップやバケツといった生活用品から得た拭き取りサンプルから大腸菌の培養実験をしました。その過程で、どの程度サンプルを希釈して実験に用いるかを決定することに苦心しました。適切な希釈を施さないと正確な結果を得られません。サンプルを採取した家ごとに、そのサンプルの汚染度合は大きく異なっており、適当な希釈率を決めるまでに大きな労力と時間を費やしました。
研究を進めるにあたって驚いたのは、多くの家庭のスポンジから高濃度の大腸菌が検出されたことです。 一口に“スポンジ”と言っても、日本でよく見かけるいわゆるスポンジから、何かを洗うには心もとないぼろぼろの布切れのようなものに至るまで、様々なものがありました。いずれにしても 衛生用品が逆にモノを不衛生にしている可能性があることは自分にとって思いがけないことでした。
あと、調査とは関係ないですが、今回の渡航は、去年の調査に続いて2回目のザンビア渡航となりました。今回の渡航では、停電がひどく、1日の内で3時間程度しか電気が供給されないという日々を過ごしました。冷蔵庫にものを保存できないせいで、日本では欠かすことなく飲んでいる大好きな牛乳を飲めない日々が続き、大変でした。電気を当たり前のように使えている状況が、当たり前ではないことを身に染みて感じることができました。
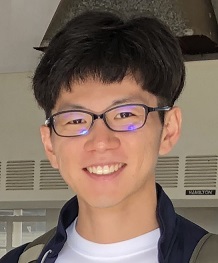
京都大学修士2年 髙橋侃凱(やすとき)

家庭で使われているスポンジをジップロック内のリン酸緩衝液に浸してサンプル採取

家庭で使われているコップの内側をスワブ(拭い取り)してサンプル採取

調査対象地の共同トイレ

家庭で使われている飲料生活水の殺菌のための塩素剤

共同水栓は配水管の水圧が低いため蛇口を低い位置につけ直していることが多い
