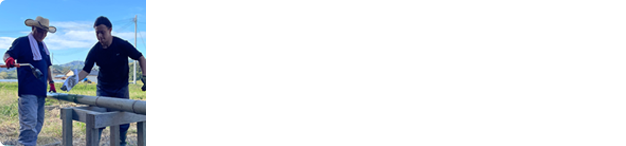太平洋の島々は天候がとても不安定。その島々の中でも、大洋州地域の気象データ収集において、地理的に重要な位置にあるのがサモアです。国内に設置された9ヵ所の測候ポイントで気象観測データを測定し、そのデータはネットワークを介して、自動的に気象局本部に送られるシステムが構築されています。私は、その観測装置のメンテナンスとシステム管理を担当しています。
活動を進める中で、この島国では観測データや気象局の情報を「どのように住民に伝達するか」が重要だと気付き、それには自分の持っているスキル、ICT技術が役立てられると思いました。
着任当初に驚いたのは、サモアでは気象予報をテキスト(文字情報)で配信していたことです。表現も「今日は雨が降るけれども、雷になるかもしれないし、晴れるかもしれません」といったような曖昧なものでした。
さらに、天候が不安定で自然災害などのリスクも高いサモアでは、気象局の観測データをもっと日々の生活と防災に生かすべきだと感じました。気象局長からは「サモアには災害発生時の情報解析能力はあるが、それを素早く、正確に国民に届ける方法が万全ではない」といった相談を受けました。それもそのはず、気象局のスタッフは気象のプロではありますが、ICTを利用した情報配信のスキルは持ち合わせていないのです。気象局にとっては難しい課題だったのかもしれません。
まずテキスト配信だった気象予報に、天気を一目で把握できるよう「晴れ/雨」等アイコン導入を提案。コンピュータ技術職の専門性を生かし、私がスマホアプリを開発。同僚局員が自分で予報をアイコン入力し表示できるよう指導しました。アイコン表示は分かりやすいと高評価で、気象局のホームページでも使われることに。また、このアプリを利用し、サイクロン来襲時に警報を配信し島民への情報伝達に役立てました。
さらに、防災教育の一環で現地スタッフと学校を巡回し、AR(拡張現実)アプリを使った津波や洪水の疑似体験も実施。子どもたちの反応もよく、防災局や消防局からも啓発活動で使いたいと好評でした。
協力(津波体験ARアプリ):愛知工科大学 工学部 情報メディア学科 板宮研究室
気象局に配属され、現地の課題解決にチャレンジしていく中で、「気象」というジャンル、ビジネス分野に興味が生まれました。私の持っていたICT技術を天気予報のアイコン導入や防災教育などでアウトプットし、地元の人たちに喜ばれ、評価されたことも大きいです。青年海外協力隊に参加したことで、これまでの自分の経験には無かった全く新しい分野への挑戦ができました。
帰国後はサモアで得た経験を生かし、気象分野のコンサルタントを目指し、発展途上国に貢献したいと思っています。