新しい国だけに知識や経験の不足もあった。ギャップを埋めると改革は加速した。
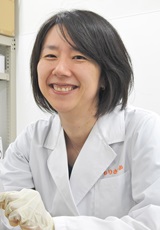
PROFILE
帯広畜産大学に在学中、経験者やJICA職員の話に触れる。特に隊員としてマラウイ派遣中の研究室OBから定期的に送られてくる絵葉書や、一時帰国の際に主食の「シマ」を振る舞ってもらいながら聞いた体験談にも心を動かされる。大学院修士課程で野生動物の生態学を学んだ後、協力隊へ。帰国後、東京大学大学院博士課程で動物生態学の研究を継続した。日本野鳥の会職員や国立科学博物館研究員を経て、現在、酪農学園大学准教授。マダガスカル研究懇談会所属。

PROFILE
教育学部卒業後、教育関連会社に勤務。友人を訪ねてタイを訪れ、貧困といわれる国で住民が楽しそうに暮らしている姿を見て、自分の想像と違っていたことに驚く。その後、東南アジアを旅行する中で貧困の現実も知り、生活者の視点で現地を見たいと協力隊に参加。隊員活動終了後、国際理解教育などを経験し、現在はマダガスカルでJICA専門家として稲の収量拡大を展開。技術を学んだ農民がさらに多くの農民を育てる手法で成果を上げている。マダガスカル研究懇談会所属。

PROFILE
大学生の時、カンボジアに行き、地雷原やトゥール・スレン虐殺博物館を見て悲惨な歴史を知る。海外へ行ってさまざまな世界を知りたいとの気持ちは強く、教職のキャリアと両立できる選択肢として、協力隊への参加か、日本人学校での勤務を意識するようになった。より現地の人に関われると、現職教員特別参加制度を利用して協力隊に応募した。復職後も、マダガスカルについての情報発信や授業を続ける。

PROFILE
小さい頃から、「協力隊はいいぞ」と父に聞いて育つ。協力隊での派遣を意識して音楽大学に進学。新卒で協力隊に参加し、コートジボワールで音楽隊員として活動した。帰国後、結婚、出産の後、子育て中に資格を取り保育士に。子育てが一段落し、再度協力隊に参加、マダガスカルに派遣中。もう一度海外で働きたいという夢を実現した。

写真のキツネザルなどの哺乳類、鳥類、昆虫、植物の野外調査を行った
大学院の修士課程で野生動物の生態を研究していた森 さやかさんは2002年12月、マダガスカルの首都アンタナナリボの国立チンバザザ動植物園に生態調査の初代隊員として着任した。もともとは半年前に着任予定だったが、政変のため派遣が遅れた。同期は派遣国を変更したが、森さんはマダガスカルが世界でもここにしかいない動植物(固有種)にあふれた国で、他に生態調査の要請がなかったため、「機会を逃したくない」と派遣再開を待った。
「マダガスカル政府は、固有の生態系が国の財産であると認識していました。また、マダガスカル人だけで研究や教育を進めるのは難しいとも考えていました」と森さん。そのため、各国の研究者がマダガスカル人と共に研究し、研究成果も共同で教育の場に還元していく方針が採られていた。
同園は研究・教育の拠点で、要請では、その活動全般を支えることが求められていた。一方で具体的な内容は少なく、森さんは人間関係をつくりながら、課題の把握にも努めた。
動植物園内では森さんの専門である鳥類の担当グループと一緒に、日々の鳥の飼育施設の掃除や整備、餌の用意や餌やりをした。警備員や園内施設の整備員とも挨拶を交わし、世間話をした。やがて、園のみんなに頼りにされている動物の栄養士の女性と親しくなった。知識も豊富で、人柄も良く、研修で日本の上野動物園などを訪れたこともあった。
「自分の得意なこととか、やりたいこととか、いろんなことを彼女に話しているうちに、園が抱えている課題を教えてくれたり、『こういうことなら、できるんじゃない』と一緒に考えてくれたりするようになりました」
彼女に教えられた園の課題の一つが、展示している動植物の説明看板がほとんどなく、種名すら十分に紹介されていないことだった。そこで森さんは、ドイツの鳥類園からの派遣員と協力して説明看板の製作と設置を進めた。解説はマダガスカル語で、名称や学名は英語とフランス語を加えた3カ国語で表記した。

展示する動植物の説明書きをラミネート加工も施して作成した
時々展示する動植物の入れ替えがあることから、プリンターで印刷してすぐに差し替えできるように、JICAに隊員活動支援経費を申請して、ラミネート加工ができる機械も導入した。現地では当時、「ラミネート屋」に依頼するのが一般的だったため、自分たちが作りたい時にラミネート加工できる機械は重宝した。
「展示は動植物園の基本。マダガスカル人に自国の財産である動植物のことを知ってほしいと思っていたので、小学生などが園を訪れた際に見てもらえるようになってよかったです」
動物の隔離小屋を造ったのも、上野動物園で同様の施設を見た彼女の助言が発端だった。
同園では、新しい動物を園の環境に慣れさせたり、病気になった時に隔離したりするための施設がなく、必要な時には展示スペースの一部をビニールシートで覆っていた。建設費用は、一般社団法人協力隊を育てる会の「小さなハートプロジェクト」などの支援制度を活用した。
彼女を通じて、動植物園が国内外の研究者や団体とどんな共同研究を進めているのかも把握でき、自分の専門を生かせる研究には2週間から1カ月間、同行した。「新種かと疑われる鳥がいる」との情報で、生息地を何度も調査した。日本の国立科学博物館などにも相談して新種の確定に必要なデータ収集やDNA採取の準備もしたが、捕獲には至らなかった。
帰国時に「日本人として、日本の動植物の保全に力を入れたい」と考えた森さんは、日本で鳥の研究を続けた。博士課程修了後、国立科学博物館ではDNA調査について教えてくれた研究者の下で勤務し、現在は大学で鳥類の保全に関わる教育研究を進めている。

離任時に稚魚生産農家にビデオと技術本を渡した
途上国の現実に向き合いたいと考えた羽原隆造さんは2005年、村落開発普及員の職種でマダガスカルに着任した。
配属先は、首都アンタナナリボから約500キロメートルの山間部にある、ババテニナ市の市役所。要請は、先代隊員が始めた養鶏とコイの養殖を通じて、農民たちの収入向上と栄養改善を行うことだった。
しかし、着任してみると、養鶏事業は失敗していて、コイの養殖もほとんど広がっていなかった。市役所の中に事業を担当する部署もなく、他の担当者もいない。カウンターパートとなる市長からは「自由にやってください」と一任された。
コイ養殖は、田んぼに稚魚を入れ、成長させる。稚魚は雑草やプランクトンを食べながら大きくなり、コイの排泄するフンがコメの肥料にもなるという農法だ。
普及のため、羽原さんはアンタナナリボでJICA専門家(水産)に魚の養殖に詳しいマダガスカル人を紹介してもらい、各村で講習会を開くことにした。協力隊に参加する前、企業で広報やマーケティングを担当していた経験を生かし、講習会前にはラジオで告知を流し、参加者を集めた。ラジオは効果的だった。
より効率的に事業を広めるため、羽原さんは、コイの飼い方など、講師の説明を録画し、編集して、ビデオ教材を作り、村々で上映することを考えた。
「村の中で何軒か、電気を使えて、テレビを持っている家がありました。そこに集まってテレビを見るのが、住民の娯楽の一つでした。そうした家に乗り込んでいって、『こんなビデオがあるけど、見ない?』と講習のビデオを勧めました」
自転車や、時には徒歩で2時間かけて村を回った。そうした中で、住民からこう聞かれることがあった。
「次の稚魚はいつ売ってくれるの?」
コイ養殖では、稚魚の調達が一番のボトルネックだった。稚魚は遠方から調達するため、数も少なく、高価だったからだ。

羽原さんがコイの産卵用にヤシの繊維で作製した装置
現地で稚魚生産すれば、周辺の住民に格安で販売することができる。そうすれば、もっとコイ養殖を広げることができると考えた。稚魚生産のためには、田んぼの周りの土手を高くして専用の池をつくり、ヤシの繊維を設置、親魚にそこで産卵させればよい。
羽原さんは、「稚魚をつくろう」と声をかけ、協力してくれる農家を探した。賛同してくれた農家にはマンツーマンで池のつくり方や産卵の方法を指導した。メス1匹と、オス2~3匹を池に入れると、やがて大量の稚魚がかえった。それを村内や近隣の村で売ると、取り組みは広がっていった。
羽原さんは協力隊の任期満了後、一時期、日本で国際理解教育に関わったが、その後にマダガスカルに戻り、バイオ燃料の原料となる木の植林事業を経て、現在はJICA専門家として稲作技術の普及・向上に尽力する。そこには、ある思いがある。
「マダガスカルの人々は本当に真面目なんです。大変な農作業も、そのための工事も、一生懸命やります。だから私も、こうやったらもっとうまくいくという方法を伝えたいと思うんです。コイから木、そしてイネへと対象は変わりましたが、僕のその思いは変わりません」
マダガスカルでは、安全な水やトイレが使えない人も少なくない。そのマダガスカルで、子どもたちの健康・保健啓発活動に取り組んだのが青少年活動隊員として2018年に着任した竹村祐哉さんだ。
配属先は首都アンタナナリボから車で5時間ほどのヴァキナンカラチャ県ベタフ郡学区事務所。要請は、健康・保健活動と、図書文化推進センターの図書館での日本文化紹介の2本柱。かなり異なる内容だったため、竹村さんは、午前中は小学校を巡回して健康・保健啓発活動を行い、午後は同センターの図書館での活動というスケジュールで活動した。
保健の活動に取り組むにも、どれくらいの子どもたちが手洗いや歯磨きをしているのか、そもそも歯ブラシやせっけんがあるのかもわからなかった。そこで、こうした状況の確認から始めることにした。
活動エリアの子ども約250人を調査したところ、手洗いをしている子、歯磨きをしている子は半数以下で、習慣にはなっていないことが確認できた。歯ブラシを持っていない子や家にせっけんのない子が半数以上だった。公立小学校の多くは敷地内にも近くにも水道がなかった。
給食があれば、食事の前に手洗いを指導することもしやすいが、現地の学校では給食がなかった。

ラジオ番組に出演すると、巡回先の先生方からより認知されるようになった
竹村さんは、学校を巡回しながら、「トイレの後は手を洗おうね」「ご飯は手を洗ってから食べようね」と繰り返した。しかし、同じ学校に行くのは1~2カ月に1度ということもあり、習慣化は難しかった。
そこで考えたのが、「手洗いソング」の活用だった。マダガスカルでは、かつて隊員が作った手洗いソングを現地の有名歌手が歌い、国民的に知られるようになっていた。この曲に乗せてダンスを踊るビデオがインターネットにアップされていたため、そこに手洗いの手順を加えたのだ。
「1番は手のひら、2番は指と指の間、3番は爪、4番は手の甲、5番は手首、最後に手を乾かそう」などと前奏部分に乗せた。効果は、明らかだった。竹村さんが学校に行って、「覚えた?」と聞くと、子どもたちは何度も歌って踊ってみせてくれた。
こうした竹村さんの活動の後押しになったのは、偶然の出会いから始まったラジオだった。
ある日、町で、竹村さんの前任の看護師隊員とも活動したこともある、乳児の健康管理員を担っている女性と会った。そして女性に誘われ、女性が出演している地元のラジオ番組「栄養満点レシピ」に週1回出演し、栄養素について話すことになった。ラジオの聴取率は高く、初めて行く学校や、自転車と徒歩で1時間半かかる離れた学校でも、先生方から「ラジオに出ている人ね」「聴いたことあるよ」と言われるようになった。
「前もって自分のことを知ってもらっているのは大きかったです。現地に日本人は僕だけでしたが、『誰?』と警戒されることはなくなりました」
センターの図書館での活動では、日本文化の紹介のほか、スタッフに整理整頓なども伝え、活動を終えた。
帰国後、教員に戻った竹村さんは、毎月、「マダガスカル新聞」を作成し、アプリで全校生徒と保護者に送っている。さらに昨年度、帰国後初めてマダガスカル人と共に授業を行った。
かつてコートジボワールで音楽隊員として活動した菊池千登世さんは2021年9月、マダガスカル首都郊外のアンブジャチムへ着任し、幼児教育に新しい風を吹き込んでいる。

菊池さんが巡回する保育園で指導する先生たち
要請内容は、数やアルファベットを楽しく学ばせるなどの新しい指導法を紹介し、現地教員の指導力向上に貢献すること。担当する五つの公立幼稚園を訪ねると、園児たちは長時間、ずっと席に座っていた。そして、ただ先生の話を聞いていた。
読み聞かせの時間も、ただ先生が読み上げる物語を聴くことだけだった。菊池さんは、読み聞かせの改革から始めた。先生たちに楽しく効果的な読み聞かせの時間を提案し、「絵が大きい本を用意しよう」「登場人物になり切って読んでみよう」と伝えた。物語が聞きやすいようにゴザを敷いたり、椅子の配置を変えて子どもたちを座らせた。読み聞かせの時間は子どもたちの一番の楽しみの時間になり、園児はもちろん、先生たちもすごく嬉しそうだった。
公立幼稚園で初めてのクリスマスコンサートも企画した。「子どもには無理」という声ばかりだったが、「練習すればできるよ」と歌や踊りの練習を重ね、成功させた。先生が楽しんでいると、子どもたちが輝く。その姿を見て、先生は楽しく充実した気持ちになる。「楽しい」の相乗効果で、幼稚園はどんどん良くなっていった。
マダガスカルでは10日程度の研修で幼稚園の先生になれるという。幼児を対象とした数や文字の具体的な教授法をしっかり学ぶことはない。「先生たちも、これじゃいけないと思いながらやっていたそうです。でも、教授法を学ぶ場所もなく、どうしていいかわからなかったのです」。
活動を始めて1年余り。効果的かつ楽しく数字やアルファベットを学べる方法を知った先生たちの「自分の取り組みを、他の園の先生にも紹介したい」という気持ちが高まったため、講習会を開くことにした。菊池さんが教えるのではない。講師役は共働してきた先生たちで、それぞれの得意分野を担当してもらった。約90人が集まり、「すごく良かった」と感想が聞かれた。
研修会は2カ月に1回のペースで継続している。資料代として参加費を集めるにもかかわらず、毎回60人から、多い時には100人を超える先生たちが参加する。

保育参観日で、わが子の様子に見入る保護者たち
「みんな新しい情報に飢えているんです。参加費以上に価値のある情報をいっぱい用意しています。集まった先生方が満足して楽しんで帰ってもらえるように工夫しています」
座学や実践報告に加え、時には演技の得意な先生が「理想の先生、悪い先生」のような劇を披露する。参加した先生たちからは「今度は自分に講師をやらせて」といった声も上がる。
菊池さんは研修会の実施後、研修会に参加した先生が勤務する幼稚園の巡回を始めた。基本は3回続けて同じ園に行く。1回目と2回目は授業の様子や机の配置、掲示物などを確認し、アドバイスをする。3回目は保育参観日。現地では保育参観の習慣がなかったため、幼稚園での子どもの様子や、先生の保育や教育の仕方を見てもらうことで、保護者の理解を得ることができるようになった。さらに子育てを保護者と園で連携していく体制を構築できるようになった。先生たちも保育参観のためにもう一度日頃の授業を振り返り、自己研さんするきっかけになった。
新しい教授法の実践者や研修会で講師をできる先生が増え続けている。菊池さんは任期を延長したが、離任の日も近づいている。現地の先生たちだけで研修会やフォローアップができるようになれば、園児たちの笑顔はこれからも広がっていくだろう。

赴任時に配った名刺

大家さん一家と
人間関係をつくり、現地に溶け込むためには、どうするか?青少年活動隊員だった竹村祐哉さんは、先輩隊員からのアドバイスも受けて、いくつもの方法を実践した。
最初にやったのは、自分の写真入りの名刺を作ること。これを配属先の同僚や巡回する学校で配った。渡す際、相手に「写真を撮らせて」と声をかけ、スマートフォンで一人ひとりの写真を撮り、「名前も教えて」とお願いした。こうして、顔と名前を覚えた。
学校長にはメールアドレスと電話番号を教えてもらうこともした。「訪問する前々日か前日にメールを送ると、『待ってるよ』とか『その日はいないけど、他の先生に伝えておくよ』などと返信が来ました」。
マダガスカル語の習得も必須。先輩隊員から代々受け継がれてきたエクセル辞書に使える言葉を足して、約5000以上の単語・例文集を作った。
一人暮らしだったが、現地語の習得のため、最初の数カ月は大家さんにお金を払って食事を出してもらい、食事前や食事中、家族らと会話しながら言葉を覚えた。「町の屋台より少し高いくらいの料金でしたが、言語だけでなく、現地の生活に慣れましたし、お代わりも自由だったので、高くは感じませんでした」と振り返る。

ダンスも披露

5人の隊員で日本の歌謡曲の演奏も
2024年2月中旬、マダガスカル第3の都市、アンチラベのカフェレストランに、衣装もばっちり決めた日本人中心のグループの姿があった。現地派遣中の隊員有志らでつくる「パフォーマンス分科会」のライブだった。
リーダーを務めるのは、幼児教育職種で派遣中の菊池千登世さん。音楽大学出身の菊池さんは、プッチーニ作曲のオペラ「ラ・ボエーム」より、ソプラノのアリア、「ムゼッタのワルツ」などを歌い上げた。
当日の出演者は、マダガスカル人を含む12人。体育隊員のキレのあるダンスや、魅惑のギター演奏なども披露された。お揃いの衣装はコミュニティ開発隊員が制作した。
ステージは、会場を替えて、今回が5回目。過去には阿波踊りを見せたこともあるという。「パフォーマンス活動を通じて、他の隊員のきらりとした新たな一面が見られます」(菊池さん)。
Text=三澤一孔 Edit=ホシカワミナコ 写真提供=ご協力いただいた各位