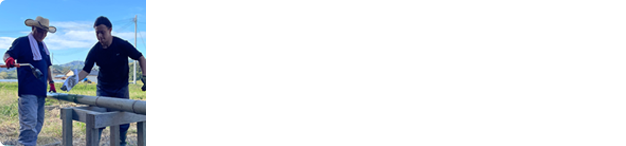2024年元日、最大震度7の地震が能登半島を襲いました。震災直後から佛子園と青年海外協力協会(以下、JOCA)は、金沢市にあるコミュニティ施設「シェア金沢」を本部に、輪島市と能登町の施設をハブ拠点にし、奥能登2市2町を支援しています。JOCAの呼びかけで、今もなお全国の協力隊経験者がボランティアとして活動しています。
今回の被災で建てられた仮設住宅5,800戸のうち、3,800戸を佛子園とJOCAが訪問・見守り支援を請け負っています。見守りに参加した人数は14カ月で延べ1万2,000人。その回数は4万2,000回に上っています。これだけの人材を投入することは一般の企業でもなかなか難しい。それを可能にしているのが、全国にいる協力隊OVの存在なのです。
私が協力隊に参加したのは1986年。障害福祉の指導者育成のため、養護隊員としてドミニカ共和国に赴任しました。配属先の特別支援学校は、まだ電気や水道が通っていなくて、机や椅子もない。周辺は荒れ地でした。そこを測量隊員と開墾し、現地の人たちと共に養鶏場や畑を造り、鶏肉や野菜を売ったお金で木を買って机や椅子を作り、設備を整えつつ、障害者が働ける仕組み作りに取り組みました。
協力隊で学んだことは“ごちゃまぜ”の強さでした。開発途上国では、子どももお年寄りも、障害のある人もない人も、皆ごちゃまぜでした。福祉制度が確立していない中でも、皆が助け合って強く生きている。帰国後の私がごちゃまぜをキーワードに活動しているのは、この経験がベースにあるのです。
私はわずか2年間の協力隊活動で、何かを成し遂げたり、完結させたとは思っていません。できなかったことのほうが多い。今、思い出しても、「もっとやれたのに」とか「恥ずかしかった」と思うことは、いっぱいあります。現地語で会話した内容をわかったふりして、それが失敗を引き起こして笑われることもあるでしょう。そうした経験ができたことが大切で、自分の成長につなげられます。
そのためにも、“笑われる力”を磨いてほしい。現地語がわからなくて笑われる、的外れな動きをして笑われる。自分の間違いや欠点を正された時、抵抗せず素直に受け止めることが大事です。謙虚に相手に聞き、コミュニケーションを取ることで、クリエイティブな仕事ができるようになります。笑われる力というのは、自分という鎧を脱ぎ、苦手なことに一生懸命に向かっていく力なのです。
多くの人たちからの応援を受けて活動を終えたら、日本でスキルを磨いて恩返しできるようにしてほしい。協力隊は2年間ですが、災害支援に携わると、5年、10年と長期化するのです。人生100年時代、働きながらボランティア活動をするなど、多様な生き方を組み合わせられる。チャレンジを繰り返して進んでいくことで、協力隊経験の真価が生まれてくるでしょう。