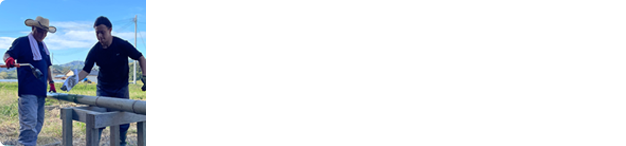JICA海外協力隊発足60周年を迎えました。これまでに5万7,000人以上の協力隊員が延べ99カ国に派遣されましたが、派遣国に与えた影響は数字以上のものがあると感じています。例えばフィリピンは60年前、最初に派遣された国の一つですが、戦後約20年を経た当時でも、隊員が現地で受け入れられることは容易ではなかった。それでも一から信頼を築き上げながら活動を続け、2016年には協力隊はアジアのノーベル賞とも呼ばれるラモン・マグサイサイ賞をマニラで受賞しました。国と国との関係性を構築するには、政治や経済の関係だけでは難しい。草の根レベルで互いに尊敬し合う土台ができてこそ、真の信頼関係が生まれてくるのです。そう考えると、協力隊員の果たした役割は大きいと思います。
私はタンザニアで理数科教師隊員として活動したのですが、赴任当初、授業に生徒が集まらない時もあり、悩みました。雨の日には学校全体で誰も来ないこともありました。ところがある雨の日、偶然立ち寄った生徒と話をしたところ、「なぜ先生は毎日学校にいるの?」と言うのです。その時、彼らから見れば自分が特殊だったことに気づきました。傘がない、働かなければいけない、学費が払えない…。学校に来ることができない事情を聞いて初めて、私は彼らに合わせて夕方に特別授業を行うことにしました。そこから私の活動は始まったのです。“当たり前”というものはないということに気づいた瞬間でした。こうした気づき、営まれる協働や信頼関係の構築といった隊員活動の本質は、昔も今も変わりません。
一方で日本国内の環境は大きく様変わりしつつあり、少子高齢化や地域が抱える問題への意識が高まっています。この6月には「地方創生2.0基本構想」が閣議決定され、その中で協力隊員の経験を日本社会に生かしていこうということが示されました。社会が変化していく中で、多様な価値観のつなぎ手となっていくことが求められているのです。
60周年のテーマである「世界と日本を変える力」。それこそが協力隊の力です。現地の人とのコミュニケーションを通じてお互いを理解し、信頼し合い、双方に行動や意識の変容を及ぼす。そうした経験を日本に持ち帰り、同じようなアプローチで社会に還元していただきたいと思います。
互いに学びながら新しい価値観、信頼関係をつくるプロセスをJICAでは“共創”と呼びます。そこに新しいアイデアを取り入れて“革新”し、その経験を社会で生かし、次の共創に繋げていく“環流”。この3つをキーワードにJICAは事業を進めていて、それを最も具現化しているのが協力隊事業だといえます。私自身、隊員経験者として、今後も協力隊事業をしっかり育て、大きく発展させていきたいと考えています。