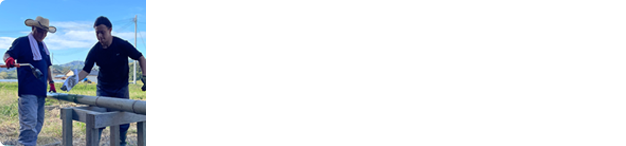第3回社会還元表彰

2025年7月に行われた表彰式の様子

「JICA海外協力隊 帰国隊員社会還元表彰」が今年で3回目を迎え、応募した帰国後20年以内のOVたちの中から7人の受賞者が選出されました。6月に閣議決定された「地方創生2.0」の基本構想で協力隊経験者のようなグローバル人材の活用が謳われるなど、開発途上国での活動を経たOVの活躍に期待が高まっています。この特集では、そうした社会還元を体現する受賞者たちが、今に至るまでにどのような葛藤や紆余曲折を経てきたのかを伺いました。現役隊員・OVを問わず、今後のキャリアのヒントにしていただければと思います。