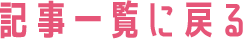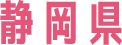今井 奈保子さん
青年海外協力隊
Nahoko Imai
フェアトレード・ショップ「 Teebom(テーボム)」主宰
- 【職場】
- 静岡県
- 【職業】
- フェアトレードショップ・オーナー
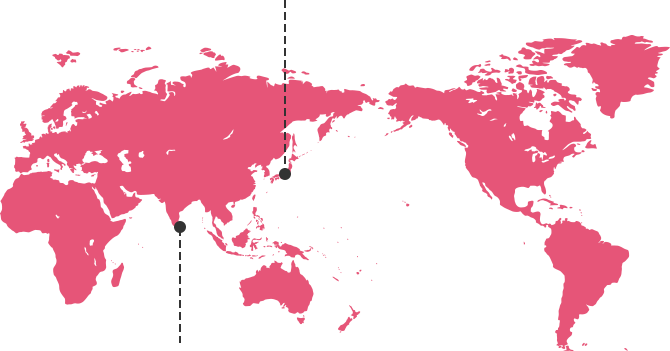
- 赴任国
-
スリランカ民主社会主義共和国

- 【赴任地】
- ガンパハ・デワラポラ
- 【職種】
- 村落開発普及員
- 【派遣期間】
- 1993年12月~ 1995年12月
フェアトレード
それは人と人を繋ぐコーディネート
物語がある商品を、生産者にも適正な価格で、消費者に届ける。
スリランカの村とそこで暮らす人々との出会いが、フェアトレードの仕事に繋がった。
オルタナティブな生き方は、閉塞感ある日本社会に生きる若者たちにも風穴を開けるかもしれない。
スリランカの村の人たちに現金収入の道を

今井さんは1993年、青年海外協力隊としてスリランカへ派遣された。
「JICAの募集ポスターを見た時、直感が閃いたんです。企業に就職して5年目で、仕事は忙しかったけれど、ボランティア休暇をとって参加しました」
スリランカでは首都コロンボ近郊の農村に配属された。村人の暮らしを見て「現金収入を増やしたい」と思い、さまざまな活動を村人と共に行った。村の青年たちと電柱を建てる工事を請け負ったり、女性たちを対象にパッチワーク教室を開いたり。特に女性たちは熱心で、パッチワーク作品を商品化して首都で売るようになった。自分たちの手で継続していこうという意欲も生まれた。
「スリランカの女性は、コミュニティの中でも差別されやすい。だから、自らお金を稼ぎ、有益に使えるようになったのは大きな意味があったし、女性たちには嬉しいことだった」
女性たちへの思いがフェアトレードに繋がる
村の人たちは、貧しくても何とか生活している。そこへ何か新しいことを持ち込むと、また新たな課題が発生する。そんな経験を積み重ねた2年間だった。
協力隊の任期を終え復職した今井さんは、所属先企業などの仕事で、その後も10年以上スリランカで過ごした。
「仕事をしながら、どこかで村の女性たちのことが気にかかっていました。もっと草の根的な、人々の役に立つ方法はないか、模索していたんです」
フェアトレードに意識が向いていたわけではないが、思いきってオーストラリアのシドニー大学大学院に留学。社会企業やフェアトレードについて学んだ。
2010年、地元の静岡で「Teebom」をオープン。主な商品はコーヒー、紅茶、お菓子などの食品と、コンセプトショップ「Autentico」が担当する服飾雑貨。オープンの際「20年は続けよう」を目標にした。
協力隊の任期を終え復職した今井さんは、所属先企業などの仕事で、その後も10年以上スリランカで過ごした。
「仕事をしながら、どこかで村の女性たちのことが気にかかっていました。もっと草の根的な、人々の役に立つ方法はないか、模索していたんです」
フェアトレードに意識が向いていたわけではないが、思いきってオーストラリアのシドニー大学大学院に留学。社会企業やフェアトレードについて学んだ。
2010年、地元の静岡で「Teebom」をオープン。主な商品はコーヒー、紅茶、お菓子などの食品と、コンセプトショップ「Autentico」が担当する服飾雑貨。オープンの際「20年は続けよう」を目標にした。
作り手の思いを伝える物語のある商品を
「Teebom」は「ストーリーのあるもの」「作り手の語り部になる」という考え方を大切にしている。原材料は何か、いつ、誰が、どんな技法で作ったのか……。
「協力隊時代に村のお母さんたちと共に経験したことがなければ、生産者の思いや販売者の生き方を発信するショップ、という発想は生まれなかったと思います。人と人を繋ぎ合う場にしていきたいという思いは、協力隊での経験があればこそなんですね」
生産者と協力して商品を作る。障がいを持つ人やハンセン病患者を支援しているNPOが製作しているものを扱う。どの商品にも、背景に物語がある。
これからは、もっと哲学を大切にする必要があると、今井さんは考えている。どこに向かって生きていくのか、ポリシーを持って生きなければ、と。
静岡大学で非常勤講師も務める今井さん。学生たちに協力隊時代のことや途上国の話をすると、「そういう生き方はリスクが高すぎる」と言われたりする。
「新しいものを得る時や、どちらか選ばなければならない時、私はリスクが高いほうを捨てるより、リスクがあっても新しい選択にチャレンジしたいと、学生たちに話すんですよ。外を見ることによって価値観が変わる。それが何かに活かせたり、引き出しとして蓄えられたりして、豊かさに繋がるということを、伝え続けていきたいと思います」
「協力隊時代に村のお母さんたちと共に経験したことがなければ、生産者の思いや販売者の生き方を発信するショップ、という発想は生まれなかったと思います。人と人を繋ぎ合う場にしていきたいという思いは、協力隊での経験があればこそなんですね」
生産者と協力して商品を作る。障がいを持つ人やハンセン病患者を支援しているNPOが製作しているものを扱う。どの商品にも、背景に物語がある。
これからは、もっと哲学を大切にする必要があると、今井さんは考えている。どこに向かって生きていくのか、ポリシーを持って生きなければ、と。
静岡大学で非常勤講師も務める今井さん。学生たちに協力隊時代のことや途上国の話をすると、「そういう生き方はリスクが高すぎる」と言われたりする。
「新しいものを得る時や、どちらか選ばなければならない時、私はリスクが高いほうを捨てるより、リスクがあっても新しい選択にチャレンジしたいと、学生たちに話すんですよ。外を見ることによって価値観が変わる。それが何かに活かせたり、引き出しとして蓄えられたりして、豊かさに繋がるということを、伝え続けていきたいと思います」
地域との繋がりに目を向け新たなチャレンジ
今は地域との繋がりにも取り組み始めたところだ。2018年12月に静岡県の「経営革新計画」に採択。静岡の職人と連携して、フェアトレード服飾品の開発と販売を手がけている。高知県の鞄店ともトートバッグ作りを始めた。自分たちの作りたい鞄作りを目指すというこの会社の方針に、今井さんの考え方が活かされた。
「これからの私の役割は、製品を手に取ってもらう工夫をすること。長く続いてきた伝統的な工芸品には、残ってきた意味があるはずです」
少しでも多くの人にフェアトレードを知ってほしい。そして、生産者、販売する自分たち自身、消費者、三者それぞれがよりよく繋がっていけたらと、今井さんは願っている。生産者が思いをこめて作ったものを、その物語も一緒に消費者に手渡す。物語あるもの作りというチャレンジは、今も続いている。
「これからの私の役割は、製品を手に取ってもらう工夫をすること。長く続いてきた伝統的な工芸品には、残ってきた意味があるはずです」
少しでも多くの人にフェアトレードを知ってほしい。そして、生産者、販売する自分たち自身、消費者、三者それぞれがよりよく繋がっていけたらと、今井さんは願っている。生産者が思いをこめて作ったものを、その物語も一緒に消費者に手渡す。物語あるもの作りというチャレンジは、今も続いている。
-
 店内を明るく彩る、ガーナの籠や香辛料。どれも今井さんのお気に入りだ。
店内を明るく彩る、ガーナの籠や香辛料。どれも今井さんのお気に入りだ。 -
 ブラジルやインドネシアから届いた、希少価値の高いコーヒーも扱っている。
ブラジルやインドネシアから届いた、希少価値の高いコーヒーも扱っている。 -
 今井さんの経営方針「フェアトレードが当たり前」が、だんだんと注目されるようになってきた。
今井さんの経営方針「フェアトレードが当たり前」が、だんだんと注目されるようになってきた。
-
今井 奈保子さん
Profile - 東京都出身。幼少時に静岡県へ移り住む。1993年より青年海外協力隊に参加、村落開発普及員としてスリランカで活動。IT企業、企画調査員を経た後に、シドニー大学大学院で社会企業について学ぶ。2010年、静岡県にフェアトレード・ショップ「Teebom」オープン。2014年より静岡大学非常勤講師、認定NPO法人カレーズの会理事。
-
 フェアトレードが当たり前の世の中を目指し、走り続けてほしい
フェアトレードが当たり前の世の中を目指し、走り続けてほしい
- ファッションの会社で2年ほど働き、毎週新しい商品が入荷される消費社会に疑問を抱き始めた頃、今井さんと出会いました。今では今井さんのショップで服飾雑貨を担当し、日々刺激を受けています。商品の背後にあるストーリーを知るにつれて、フェアトレードに対する私自身の考え方や行動にも、変化が生まれてきました。今井さんの考え方や発信力は、私たち若い世代にも新鮮です。

- フェアトレード・ショップ
「Teebom」スタッフ - 内山 苑子さん