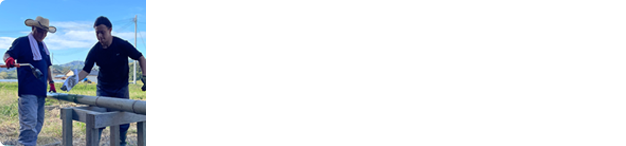(上)養蜂家・フェリシアーノ氏とその家族
(下)フェリシアーノ氏と一緒に作った重箱式巣箱
- 食料生産を支えるミツバチを
守るため、世界の養蜂事情を自分の目で見る 養蜂家を志したのは、長崎県の実家にある床下の通気口に出入りするニホンミツバチを見つけたのがきっかけです。幼少時は「怖いもの」という存在だったのですが、大人になって改めて観察すると、健気に蜜を運ぶ姿に愛情が芽生えてきました。調べてみると、ミツバチは私たちが日頃食べている野菜や果物の花粉媒介者としてとても大切な存在であるものの、近年は世界中で個体数が減り続ける深刻な状況だということを知りました。
最初は、人づてで紹介してもらった養蜂家の方にニホンミツバチの巣箱の仕組みや作り方を習いにいきましたが、その後は図書館で参考文献を読み漁ったり、インターネットで情報収集したりして、自分なりの視点で養蜂を学びました。そして、もっと養蜂を深く学びたい・世界のミツバチを見てみたいと考えていた矢先に、ミツバチの研究で有名な大学教授のFacebookの投稿で「JICA海外協力隊で養蜂分野の募集が久々に出ている」という情報を見つけ、すぐに応募を決意しました。
派遣先となったモザンビークでは当初、世界で主流になっているラングストロス式巣箱※の技術支援が目的だったものの、実際現地に行ってみると、既存のラングストロス式巣箱が野ざらしで放置されていたり、壊れたまま使っていたりと、管理が行き届かず現地の人が使いこなせていない現状を目の当たりにしました。そこで、より簡単な構造で、効率的にハチミツを採取できる重箱式巣箱※の普及に力を入れることに方針を切り替え、重箱式巣箱を一緒に作ってくれる協力者探しを始めることにしました。最初は巣箱の作り方や必要な材料などを図式化した資料を作って、現地の養蜂家のお宅を10軒以上訪問して提案し続けました。なかなか相手にしてもらえない日々が続きましたが、新しいことをやってみようという意欲を持つ現地の養蜂家・フェリシアーノとの出会いがあり、その後、彼とは相棒とも言える良い関係を築くことができました。
※ラングストロス式巣箱:世界でも主流な巣箱の形。セイヨウミツバチの飼育に使われることが多い。
※重箱式巣箱:主にニホンミツバチの飼育に使われる日本の伝統的な巣箱のひとつで、比較的構造が簡単で、採蜜の方法も容易とされる。