
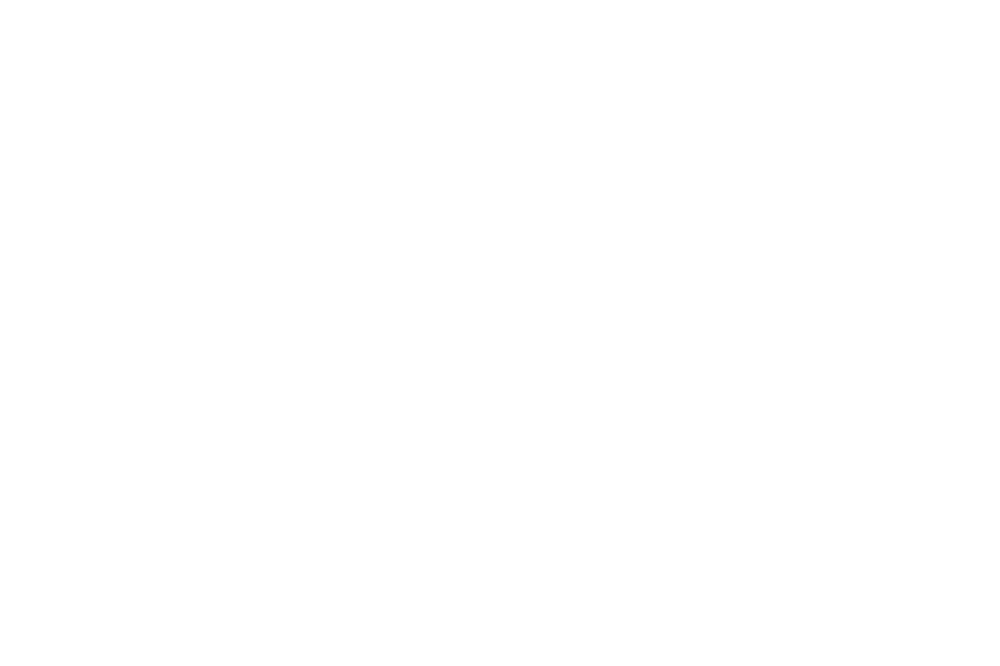
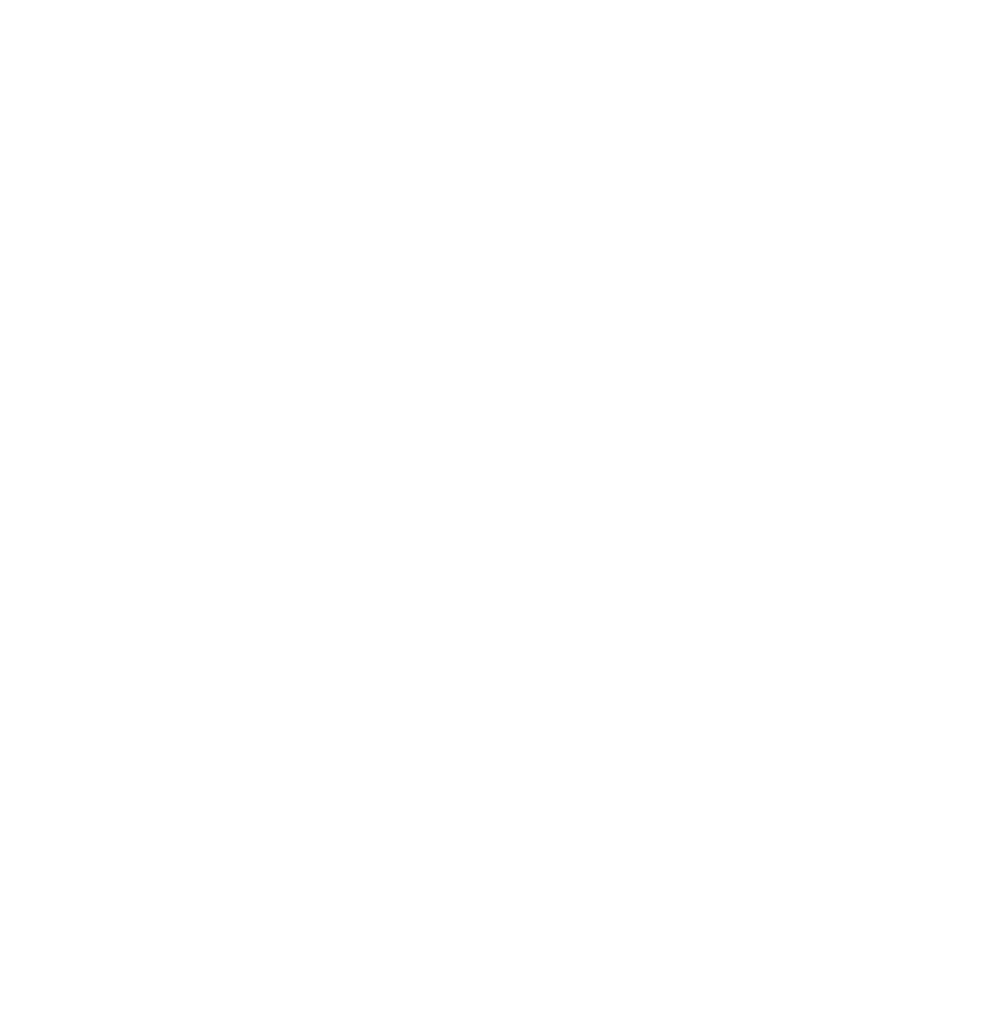



キルギスのおばあちゃんが
教えてくれた、幸せの形。
東京で仕事一筋だった五十嵐早矢加さん。「お金さえあればいい、結婚もしなくていい」と思っていた。そんな彼女がJICA海外協力隊に応募したのは、海外で働いてみたい、という気持ちが強くなったから。社会に貢献しながら自分の力を試してみたいと、マーケティング知識を生かせる場所を志望。キルギス共和国のイシククリ州県役場に派遣され、現地の特産品を開発・販売することになった。
村落開発普及員として活動しながら、普段はホームステイ先の家族と共に過ごした。キルギスは山に囲まれた自然豊かな場所で、「神様の別荘地」と呼ばれるほど。そこで家族と一緒にジャガイモを植え、羊を捌き、パンを焼く。それまで農業経験などなかったので、すべてが新鮮でわくわくした。また、自分の手で育てたものを食べることで体がどんどん健康になっていくのも感じた。
そんなある日、早矢加さんはホームステイ先のおばあちゃん、グルジャマールとお店へ行く機会があった。帰り道、家族の財布をのぞくと3キルギスソム、日本円でたった6円しか入っていない。早矢加さんは慌てたが、グルジャマールは笑って言った。「家には羊がいるし、畑もあるから大丈夫。家族が幸せに楽しく笑って生きていればいいの」。それまでお金を稼ぐことに重きを置いていた早矢加さんにとっては衝撃的な考え方だった。「幸せはお金じゃない」。そのことに気づかせてくれたグルジャマールの笑顔こそが、早矢加さんのMy Episode 0。
「家族で農業を営み、仲睦まじく暮らしていきたい」。そう考え始めた早矢加さんに共感したのが、隊員として一年前からキルギスに来ていた大介さんだった。家畜の飼育管理の指導員として派遣されていた大介さんは、日本にいる頃から自然や動物と共に生活したいと考えていた。隊員同士の交流会で意気投合し、二人は帰国後に交際、結婚することになる。

家族みんなで、
日本とキルギスの架け橋になる。
帰国後はそれぞれ会社員として働いていたが、結婚を機に農家になる決意をした大介さんと早矢加さん。理想は、二人が出会ったキルギスで見た、家族で営む農園だ。しかし、未経験者が新たに農業を始めるのは難しい。ツテがなく、畑を持とうにも見知らぬ二人に譲ってくれる人はなかなかいない。設備や機械も一式揃える必要がある。一度は北海道での就農を考えたが、農地の確保が難しく断念した。
新たな地を探しているときに出会ったのが千葉県南房総。キルギスで食用・薬用として馴染みのあるカレンデュラ生産が盛んだったことが決め手となった。日本では「キンセンカ」と呼ばれる仏花で、他の使い道はあまり知られていない。自分たちの手で可能性を広げられるのでは、と考えた。また南房総には新規就農プログラムがあり、カレンデュラ農家に弟子入りして研修を受けられたことも大きかった。教えを受けた師匠は理解が深く、二人のために畑を借りてくれたため、研修当初から自力での生産に挑戦することができた。おかげで、農地確保に悩むことなく独立への一歩を踏み出せた。
受け継いだ地に、二人は「ベレケの村」と名を付ける。「ベレケ」はキルギス語で「恵み」。自然の恵みに感謝しながら共存共生を目指す場所だ。カレンデュラでコスメやドレッシングを製造、米やそら豆なども栽培・販売している。今は二人で営んでいるが、ゆくゆくはキルギスから農業研修生を受け入れたり、障害者雇用もできればと考えている。キルギス料理を出す宿も構想にある。
「幸せの形を教えてくれたキルギスに恩返しをしたい」。日本とキルギスの架け橋になるべく、大介さん早矢加さんの家族はベレケの村で自然と共に生きている。





マニラ麻でジーンズをつくる、
という挑戦。
会社経営をしていた祖父の影響で、中西敦士さんは幼い頃から起業に興味を持っていた。大学時代にはロボットベンチャーを始めるも頓挫、その後新規事業の立ち上げサポートをするコンサルティング会社に就職した。だが、本当にやりたいのは自ら事業を起こすこと。悶々としていた時期に目に留まったのがJICA海外協力隊員募集のポスターだった。何かを変えたいと、応募を決めた。
派遣されたのはフィリピン・ルソン島のソルソゴン州グバット町。村落開発普及員として、バナナの茎に似た「マニラ麻」という植物を使い、村民の収入向上を目指すのが任務だ。試行錯誤の末、目をつけたのはジーンズ。だが、マニラ麻製でジーンズをつくった人など周りにはいなかった。中西さんはフィリピン国内の縫製工場をはじめ、日本の製糸会社にかけあったり、同時期に派遣されていた服飾隊員に協力を求めたり、一年半かけて耐久性と通気性に優れたマニラ麻ジーンズをつくりあげた。
収入をより安定させるため、中西さんはマニラ麻生産の拡大にも着手した。日本の商社に何度も提案書を持ち込み、資金援助を依頼。商社のフィリピン支店長が元JICA海外協力隊員だったという縁もあり、2012年、新たな農園を整備することができた。
そんなある日、中西さんは現地の家族が薬代わりにマンゴーを食べているのを目にする。フィリピンは薬の多くを輸入に頼っているため、価格が高く、ほとんどの人が購入できない現状があった。病院にもなかなか行けず、一度体調を崩すと死が目前にある。ヘルスケアがみんなに行き渡らない環境をなんとかできないか。マンゴーを食べる家族の姿が、今の中西さんの活動につながるMy Episode 0となる。

自分の失敗が、
新事業へのアイデアに。
JICA海外協力隊の活動を終えた3週間後、中西さんはカリフォルニアの大学にいた。幼い頃から抱いていた起業という夢を叶えるため、次は金融や経済について学ぶことにしたのだ。今度は勉強漬けの毎日。そんな中西さんにある事件が起きる。引っ越しをしている最中に「漏らして」しまったのだ。
まさか大人になってトイレに間に合わない経験をするとは。そのショックを、中西さんは事業アイデアへと転換する。排泄タイミングを事前に予測するデバイスをつくれないかと考えたのだ。実は2013年当時は日本で大人用おむつの売り上げが子ども用を上回った年で、介護業界でも排泄ケアが課題になっていた。インターン先のメンバーからも先進的な考えだとあと押しを受け、日本に帰国後会社を立ち上げ、開発を進めることにした。念願だった起業を果たしたのだ。
そして構想から8年をかけ、排尿タイミングを知らせてくれるデバイス「DFree」を発売。介護施設や病院などでも活用され、「2年ぶりにトイレでできた」と涙を流して報告してくれる方もいた。
ウェアラブルデバイスであるDFreeは、超音波で膀胱や大腸の動きを捉え可視化することで成り立っている。そのため、今後は心臓や肺など他の臓器にも転用が見込める。データによって、日常的に、かつ気軽に健康管理ができれば、高齢化が進む日本の課題を解決できると確信している。また、より安価にできればヘルスケアが整っていない途上国の助けにもなるかもしれない。「世界を一歩前に進める」を企業ミッションに掲げている中西さん。自身も、20代の頃JICA海外協力隊員として一歩進んだことで、今、多くの人の笑顔を生み出している。





誰も野球を知らない国で、
野球を広める。
自らを「猪突猛進型」と話す出合裕太さんが、JICA海外協力隊に興味を持ったのは高校2年生のとき。ニカラグアで野球を教える隊員の新聞記事に感銘を受け、「いつかは自分も!」と思うようになった。一度は札幌市内のパン屋に就職するも、思いを遂げるために応募、西アフリカ・ブルキナファソ野球連盟への派遣が決まった。
連盟は「ベースボールをメジャーなスポーツにしたい」と言うものの、グラウンドも道具もなく、そもそも地元の人は野球というスポーツそのものを知らない。赴任後にこの事実に直面し、出合さんは心が折れそうになった。
しかし、出合さんの運命を変えるMy Episode 0は突然訪れる。それは、アミールとの出会いだった。
派遣開始から半年ほど経った頃、近所の少年・アミールが声をかけてきた。白の野球ユニフォームを着ている出合さんを空手の先生だと思い込み、弟子入りを申し込んできたのだ。誤解はすぐに解けたが、それがきっかけで二人はキャッチボールを始めることに。アミールの友だち11人も加わり、彼らはどんどん野球にのめり込んでいった。
プロ選手たちの動画を見せると、純粋な質問も飛び出してきた。「どうやったらあの日本人選手みたいな球が投げられるんだ。僕もあんなふうに投げたい!」。キラキラした目で返答を待っているのに適当に答えるわけにはいかないと、出合さんは「投球とは何か」というところから深堀りし、論理的にフォームを教えていった。子どもたちはどんどん上達、プロ選手を目指す子まで現れた。12人がチームとして確立すると、他の地域にも野球を普及すべく、彼らを連れての遠征も実施。最終的には6つのチームが誕生し、リーグ戦を開催するまでに至った。人生で初めて、何かを達成できたと実感した瞬間だった。「日本で野球ができるように呼び寄せるから」プロ選手を目指すようになった子どもたちにそう約束して、出合さんは帰国した。

地域を元気にし、
若者に夢を与える構想を。
地元である北海道富良野市に戻った出合さんは再びパン屋に就職するが、子どもたちとの約束は常に頭の中にあった。彼らが日本で野球をするための方法を探ってみたが、現実は厳しい。ならば自分がその場を提供すればいい、と立ち上がることにした。ブルキナファソでの経験を経た出合さんには、無理だと思う気持ちなんてなかった。
まずは自分の周りに目を向けてみた。富良野は若者離れが進み、過疎化が深刻になっている。ここに野球をしたい若者を集め、地域に貢献しながら練習してもらうのはどうだろう。2017年、その構想を「北海道ベースボールアカデミー」として始動した。住む場所と練習環境を用意し、若者を募集。彼らは地元企業の仕事を手伝いながらプロ選手を目指す、というシステムだ。野球をしたい若者と、人手を欲している企業を結びつけるWin-winな関係。「ブルキナファソで子どもたちを指導するうちに論理的な思考が身につき、ここまで実現できました」と、出合さんは笑う。
ブルキナファソからも子どもたちが参加し、今では独立リーグで活躍している選手が2名いる。アミールは23歳になり、ブルキナファソのナショナルチーム代表になった。
2020年、アカデミーは北海道の独立リーグとして「北海道ベースボールリーグ」と名称を変え、さらに注目が集まっている。今は野球に限らず、さまざまなスポーツにこの形を応用できれば、と考えている。
「たくさんのスポーツを楽しめる『多種目スポーツリーグ』で、地域活性と人材育成、どちらも実現したい」。 出合さんの構想は、日本の地域を元気にし、スポーツを愛する世界中の若者たちに夢を与えるだろう。





異国の地、
ひとりで始めたドジョウ養殖。
幼い頃から魚が大好きだった渡辺樹里さん。入学した水産高校で、エビ養殖のために東南アジアのマングローブが伐採されていることを知り、「『環境にやさしい養殖』を広めたい」と思うようになる。JICA海外協力隊に応募したのは、その第一歩だった。
派遣先はフィリピンのイフガオ州マヨヤオ町。収入向上のため棚田を使ったドジョウ養殖を、というのが町の要望だった。以前は食文化として根付いていたが、乱獲により絶滅寸前になっており「あの味が恋しい!」と言う町民たちの声が背景にある。育てるのが非常に難しい魚だが、「みんなの希望に応えたい」と渡辺さんは挑戦を決めた。
目指したのはやはり、「環境にやさしい養殖」。現地の人も入手しやすい家畜の糞尿を肥料にして水田のプランクトンや虫を増やし、ドジョウの自然な餌にした。最初は手伝ってくれる人もおらず、失敗を繰り返してばかり。でも、子どものように育てたドジョウたちの数が増えていくのが愛しく、やりがいを感じた。少しずつだが、手を貸してくれる人も増え始めた。転機になったのは、放置されていた町営養殖場をドジョウ生産の場として復活させたことだった。池が割れ、水も涸れていた場所を町民たちと一緒に建て直したことで、町のプロジェクトとして回り出したのだ。
ドジョウ養殖が軌道に乗るのを見届けるため、渡辺さんは派遣期間を任期の二年から延ばし、帰国を一度挟み、再びフィリピンの地を踏んだ。そのときに見た光景が、彼女のMy Episode 0となる。それは、自分がいなくてもきちんと運営している養殖場に再会できたことだった。

長岡市を拠点に、世界に
「環境にやさしい養殖」を広げていく。
赴任当初は協力者がいなかったドジョウ養殖。自分が不在になれば活動も終わるのでは、という危惧もあった。しかしそこには、自分たちの手でドジョウを育てることに誇りと喜びを感じているマヨヤオ町の人々がいた。さらには、噂を聞きつけた周辺の町や村落でも渡辺さんの養殖法を学びたいと声が上がり始めた。今までの活動が実を結んだのを実感したと同時に、「環境にやさしい養殖」の普及ができることを渡辺さんは確信した。その後、後任のJICA海外協力隊員にドジョウ養殖を引き継ぎ、日本へ戻った。
帰国後すぐに水産分野のコンサルタント会社で働いたが、もっと養殖技術を身につけ開発途上国に行ける専門家になりたいと、縁あって新潟県長岡市山古志の地域おこし協力隊として長岡市錦鯉養殖組合で働き始めた。錦鯉は観賞魚だが、食用魚の養殖にも使える技術が凝縮されており、より知識を深めたい渡辺さんにはぴったりの場所だった。山古志の棚田の風景が、マヨヤオ町と似ていたことも惹かれた理由の一つだ。
山古志は錦鯉発祥の地だが、2004年の新潟県中越地震の際には壊滅的な被害を受け、錦鯉養殖も一度消えかかった。そんな環境下でも、「もう一度山古志ブランドの錦鯉を、世界に」と奮闘した職人たちがいたから、今がある。フィリピンでドジョウを復活させた渡辺さんと通じるものがある。彼女の仕事は、そんな錦鯉の魅力を発信し、ファンを増やすこと。もちろん、養殖技術を学ぶことも欠かさない。
これからは、長岡市を拠点にしながら海外でも「環境にやさしい養殖」を広めたいと考えている。魚好きだった少女は、今、日本と世界で養殖技術を支える人材に成長している。





同僚の意外な一面で気づいた、
新たな価値観。
地域活性化を目指し岐阜で活動している田中勲さん。彼が地域に目を向けるようになったきっかけは、地球の反対側・ボリビアでの経験にあった。
大学生の頃から「国際協力で社会貢献したい」という強い思いを持っていた田中さん。一度就職したものの、JICA海外協力隊に参加するため二ヶ月で会社をやめ、ボリビア・サンタクルス県へと旅立った。派遣先はサンファン市役所のスポーツ文化観光課。得意のサッカーを生かし、サッカー教室の運営やコーチの育成に取り組んだ。言語の壁や雨季による練習中断などさまざまな問題に直面したが、特に頭を悩ませたのは同僚・カリートの存在だった。仕事面での相棒のはずが、返事ばかりよくて行動には移さない。田中さんの不満は募っていった。
そんなくすぶった気持ちを抱えていたある日、実はカリートは市役所に勤務する傍ら、家族を養うために休日はタクシー運転手をしている、ということを知った。カリートを「仕事をサボってばかりのヤツ」と思っていたが、それは自分の偏った見方だったのだと愕然とした。世界を変えようとボリビアに来たはずが、自分の視野の狭さを思い知った瞬間だった。
田中さんのMy Episode 0。それは、カリートの意外な一面を発見したことで気づいた、目の前にいる人と向き合うことの大切さ。
そこから田中さんはカリートとの距離を縮め始めた。自分の価値観を押しつけるのをやめたことでカリートも心を開き、仕事もうまく回り始めた。最後の一年は、自分もみんなの仲間になれたと実感できた。

自分たちの地域を、
自分たちでよくしていく。
ボリビアでの日々は、帰国後の田中さんにも大きく影響を与えた。目の前にいる人が本当に望むものが何かを考え行動するのであれば国際協力も地域活性化も変わらないと気づき、地域に貢献できる仕事をしたいと思い始めた。そこで紹介されたのが、NPO法人G-net。理念に共感を覚え、期間限定で働くことにした。G-netでは地域の中小企業の魅力を引き出し、熱意ある若者と結びつける活動をしている。田中さんは「就職・採用支援事業(通称『ミギウデ』)」という新規事業を立ち上げ、中小企業の新卒採用の取り組みに関わった。企業と就活生双方に寄り添い、マッチングさせることへの苦労もあったが、目の前の人と真剣に向き合い、本当に望むものが何かを追求したボリビアでの経験が生きた。
お試しで働き始めたG-netだが、今や副代表理事。さらに地域を元気にするために新たな会社を立ち上げたり、お寺の住職のためのキャリアスクール・TERA WORK
SCHOOLというプロジェクトを始めたりと、田中さんの活動は止まらない。「トップダウンの政策ではなく、自分たちの地域を自分たちでよくしていくハブ機関をつくっていきたい」。地域に根ざしたお寺がその役割を果たせると今は考えている。「言葉通り『駆け込み寺』として気軽に相談してもらったり、地域の情報が集約される場所になったら」。
目の前にいる人と向き合うことで動き出したプロジェクトたち。それは、ボリビアでの日々がなければ気づけなかったかもしれない。「日本を元気にするためには、まず足もとから」。きっと、田中さんが証明してくれる。





JICA海外協力隊の活動中、
忘れられない言葉。
早水綾野さんがソロモン諸島の地を踏んだのは26歳のとき、JICA海外協力隊員としてだった。配属されたのは、ガダルカナル州保健局マラリア課。蚊帳を配ったり、啓発活動を行なったりと、マラリアの感染を抑えることが役目だ。
早水さんは決められた仕事をこなすのではなく、みんなを巻き込むことを大事にした。村民参加型の健康委員会を立ち上げたり、トップダウンだったプロジェクトの権限を現場のスタッフに渡したり。とはいえ、そこは日本とは仕事観の違うソロモン。みんなが動いてくれず、憤りを覚えることもあった。
そんな彼女の「My Episode 0」は、Sallyとの出会い。
仕事に追われ悩んでいた同僚のSallyが「アヤノが来てから仕事が楽しくなった。毎日頑張ろうって思える」と言ってくれたのだ。事実、仕事もスムーズに運ぶようになり、ガダルカナル州のマラリア感染者数がたった一年で半分に激減する、という成果をあげた。人と関わり合いながら結果を出し、誰かの気持ちを変えることができた。その経験が、早水さんの心に深く刻まれた。
隊員としての活動を終えたあと、国際協力のNGOに所属しアフリカにも行ったが、そこではエクセルと向き合う日々。歯がゆさを覚えた彼女は、一ヶ月の休暇をとりソロモンに戻った。懐かしい風景と変わらない人々に再会し、「ソロモンとつながっていたい」という気持ちが湧いてきた。

ソロモンから始まった夢は、日本へ。
そして世界へ。
ソロモンとずっとつながっていくためには、ボランティアではなく、ビジネスをする必要があると考えた。「みんなの収入を増やすことが、いろんな物事の解決につながる。自分のプロジェクトで、そこに貢献できれば」。そこで早水さんがたどり着いたのが、ソロモンの伝統工芸である貝細工。見た目が美しく、デザインさえ工夫すれば日本でも売れると思った。現地の職人と直接話し、ジュエリーとしてデザイン・製作、フェアトレードで仕入れる。プロジェクト名は「Sally」。同僚だったSallyは今では大親友で、ソロモンからビジネスを手伝ってくれている。
最近、ソロモンに進出している日本企業が支援したいと言ってくれた。次はマラウイにも活動を広げたいと考えている。「Sallyのように、自分の仕事に誇りを持つ生き生きとした女性が増えたら」。ソロモンから始まった夢は、日本へ、そして世界へと広がっていく。





異国の地で任された大役に、
がむしゃらに向き合う日々。
奥結香さんは20歳のとき、介護福祉士として勤務した障害者入所施設での対応に疑問を感じ、日本の福祉を変えたいと思うようになった。
「そのためにまずは10年間、知識と経験を積む」。そう決めた奥さんは、デイサービスや特別支援学校などさまざまな現場に入っていった。JICA海外協力隊に応募したのも、経験値と視野を広げたいと思ったからだ。
しかし派遣先のマレーシア・ボルネオ島のサラワク特別支援教育サービスセンターでは学校現場での指導だけでなく、「州の特別支援教育を変える」という大役を与えられることとなる。マレーシアでは障害のある子どもへの無理解から、力で抑えつけることもあるのが現状。どうにかしなければ!という思いだけで、がむしゃらに走り出した。
奥さんのMy Episode 0。それは、どんな状況であっても「自分次第でなんでもできる」と気づかせてくれた、同僚との会話。
活動を進める中、イスラム教徒の同僚がこんな言葉を教えてくれた。「自分の理想がないなら、自分でつくっていけばいい。イスラム教ではそんな教えがあるのよ」。
当初は教員向けの教材作成や勉強会の実施をメインにしていた奥さん。だが本当の課題は学校と地域が連携できていないことだと気づき、子どもたちのことをもっと理解してもらうために福祉・民間と手を組み始めた。図書館での大規模なフォーラムの実施、サポートブックの作成、日本の療育関係の本の翻訳…。思いつくことはすべて行動に移した。
自分の限界を決めず、思いついたらやってみる。奥さんの熱意が伝わったことで教員たちの子どもへの接し方が変わっていき、熱く語り合える仲間もできた。

地域に、つながり合い助け合える
場所をつくりたい。
思い悩むこともあったが、奥さんは自分の本当にしたかったことのヒントをマレーシアで見つけることができた。それは、「福祉と地域を結びつけること」。
障害のある子どもへの接し方も、学校内で完結させるのではなく、地域も巻き込んでいくことで光が見えた。帰国後もそんな活動がしたいと、縁あった大分県竹田市の地域おこし協力隊に参加することにした。
そこで見えてきたのは、障害のある人もない人も、若者も高齢者も、誰もが気軽に集える場所を求めているということ。ともにつながり、助け合える環境をつくりたいという自分の想いと通じるものを感じ、2018年、奥さんは仲間とともに「みんなのいえカラフル」を立ち上げる。ここでは赤ちゃんからお年寄りまで、障害の有無も地元民も観光客も関係なく、みんなウェルカム。普段は関わりを持たないような人でも、ここに集まれば自然とお互いを知ることができ、差別や偏見をなくす一歩になるのではないか。奥さんはそんな期待もしている。
「カラフル」を始めて3年。今では0歳から103歳まで多様な方が訪れ、ごはんを作ったり勉強したり、ちょっとした相談ごとをしたりと、すっかり地域に定着してきた。
「ひとりぼっちを生み出さない地域社会をつくりたい。そして、誰もが未来を描くことができる社会を実現したい」。日本を本当の意味で多様な国にするため、マレーシアで教わった「理想がなければ、つくればいい」を胸に奥さんは進み続ける。



農業の目的を見出すため、
ザンビアへ。
日本キウイのパイオニア農園の次男、農業高校を卒業し、「耕す志」という意味が込められた名前。農家になるために生まれてきたような平野耕志さんだが、20代の頃は日本の農業に目的を見出せずにいた。自分が納得できる農業を学ぶためにアメリカに渡ったが、理想と現実を目の当たりにし、悩みは深くなっていくばかりだった。
そんなとき、実家の農園で受け入れている海外研修生のことを思い出した。彼らはみな真面目でとてもやる気があり、情熱を持って農業に取り組んでいる。彼らのような人にもっと会いたい、さらに社会的に人を助けるようなことをしたい、と思いJICA海外協力隊に参加することにした。
平野さんが派遣されたのはザンビアの首都ルサカ市。一年目は国際協力NGO「AMDA-MINDS」、二年目はAMDA-MINDSの連携先である保健省に移った。主な活動場所は「コンパウンド」と呼ばれる低所得者層が住む地域で、HIVや小児結核の予防啓発が仕事だ。一見農業と関係なさそうだが、HIVや結核は体の免疫力が低下することで悪化する。野菜栽培を通じて栄養指導・収入確保の援助などをするのが平野さんの役目だった。
しかし、野菜の販売だけで収益を得るのは非常に難しいのが現実。養鶏や養殖、キノコ栽培を通じた循環型農法を確立することで、低コスト化と安定収入の確保を目指した。また洋裁教室、駐車場経営などにも挑戦。事業管理やマーケティングもサポートすることで月の収入が3倍になった農家が増え、地域に還元できた気がした。
そんな平野さんは、現地の住人たちとよく食事を共にした。八歳の少女が、放し飼いにしている鶏を自分で捕まえ、捌き、調理し、感謝しながら食べる。その姿に衝撃を受けながらも、ザンビアの子どもたちの「生きる強さ」を感じた。
たくましく生きる子どもたちとの出会い。それが、平野さんのMy Episode 0。

日本の子どもたちに、
「生きる力」を教えたい。
ザンビアの子どもたちは「命をいただく」という食の本質を、日々の生活の中で身をもって体験している。その姿を見て、今の日本に必要なこと、自分が将来何をすべきか、が見えてきた。
「開発途上国で農業を伝えることも大切。でも今は日本で、農業を通じて『生きる力』を教えるべきではないか」。そう考えた平野さんは帰国後、改めてキウイ農園に戻った。
だが、日本ではお金を出してまで農業体験・自然体験をしたい人が少ないのが現実。そこでヒントにしたのが、ザンビアの友人たちの生活だった。ザンビアでは、畑は人々の交流の場。ちょっとしたアイデアで、畑は美容院や教会、レストラン、ダンス会場などに姿を変える。その発想を取り入れ、農園でナイトヨガや餅つき、音楽イベント、結婚式、青空美容室などもチャレンジしてみた。農園が、ただ農作物を作る場所ではなく、みんなが集まる場所として変わり始めた。
そこで出会った子どもたちの中には、牛乳が牛からとれることを知らなかったり、火が熱いことを知らずに触ってしまったり、という子もいた。やはりザンビアで感じたことは間違いではなかったと、平野さんは確信した。今は若者にもっとアプローチするため、学生たちと一緒に地域の社会問題を考える修学旅行を行うなど、さまざまな切り口を模索している。
「物事の本質が損なわれると、農業や地域がより衰退してしまう。また、将来大規模な災害が起きたときに『生きる力』がないと日本は生きながらえることができないかもしれない。こういった社会問題を少しでも改善できる職業が農業(農家)なんだと、改めて気づかされました」。
目的が見出せなかった農業。でも今は、平野さんの想いを伝える大事な仕事になっている。



患者が求めたのは、快適な歩行より、
礼拝ができる義足だった。
岩根朋也さんが義足の存在を認識したのは幼少期のこと。モンゴルから義足製作のために来日した、両下肢切断の少年を目の当たりにしたのがきっかけだった。現地で満足のいく義肢装具を手にすることができない人のために活動したいと考え、義肢装具士免許を取得し、JICA海外協力隊として海を渡ることにした。
すでに技術や知識を持っていた岩根さんは、ウズベキスタン・タシケントの国立障害者リハビリテーションセンター付属
義肢装具センターに技術隊員として派遣された。役割は、現地で手に入る素材を利用して製品の質の向上を目指すこと、そして日本の技術や工夫を同僚たちに伝えることだ。
そんな平野さんのMy Episode 0は、「義足は歩くためだけのものではない」と気づかされた、患者さんとのやりとり。
派遣されてまもなく、ある患者さんの義足を新調する機会があった。新しい義足は前のものから改善され、たどたどしかった歩行も上手にできるようになった。本人も満足そうだったが、地面にうまく座れないことがわかると急に顔が曇った。「正座のように膝を深く曲げられる義足に変えてくれないか」。その言葉に平野さんは困惑したが、聞けば、患者さんは熱心なイスラム教徒だという。日々のお祈りが欠かせない彼にとっては、歩くことと同じくらい、祈ることが大事だったのだ。岩根さんは衝撃を受けたが、それからはよりいっそう使う人の想いを考えて設計するようになった。
若手の育成にも関わった岩根さん。新しい技術を学んでほしいと、そのうちの二人がドイツ研修に行けるよう後押しもした。英語がまったくできない彼らのために自ら英会話を教えるなど、献身的にサポート。将来のことを考えるとわくわくした。
だが、そんな岩根さんに予想外の事態が起こる。世界的なコロナ流行のため、活動途中で帰国せざるを得なくなったのだ。
どんな場所にいても、
夢見られる社会を。
志なかばで帰国を余儀なくされた岩根さん。もう一度ウズベキスタンに戻れると信じて待っていたが、現実は甘くなかった。若手のドイツ行きも中止になったと聞いた。
悔しい思いを昇華させたい、自分の経験が生かせる場所にいきたい、と模索する中で、今の職場・インスタリムと出会う。インスタリムは3Dプリンターで義足の開発・販売を行う会社。安価に製造できるため、フィリピンの低所得者層向けに提供している。経験したことのない領域も含まれていたが、自分のスキルアップにもつながると思い入社することを決めた。
ウズベキスタンにいた頃は手に入らない材料や機材があり、あるもので工夫しながら手作業で義足をつくる日々。今はまったく逆で、パソコンと向き合う時間も短くない。一見無関係にも思えるが、日本を出たからこそ途上国と先進国の義肢装具事情を比較することができる。知識と経験の積み重ねがあるからこそ、改善や開発に役立っていると感じる。
JICA海外協力隊の活動が中途半端になってしまったことで成果も達成感もゼロ、と落ち込んでいた岩根さんだが、帰国から時間が経った今でも、当時の同僚たちが連絡をくれることがある。遠くで、同じように義足と向き合っている友人たちの報告がうれしい。大きな成果を望んでいたが、自分が接した人たちの記憶に少しでも残っていることが大切なのだと実感した。
途上国に限らず、日本にいても僻地や離島に住む患者さんに十分なサービスを届けることは難しい。「どんな場所に住んでいる人でも、平等に義肢装具が行き届く社会をつくりたい」。それは、障害を負ったことで人生を投げ出し、夢見ることを諦めた人たちを救っていくこと。岩根さんの挑戦は、まだまだ続く。