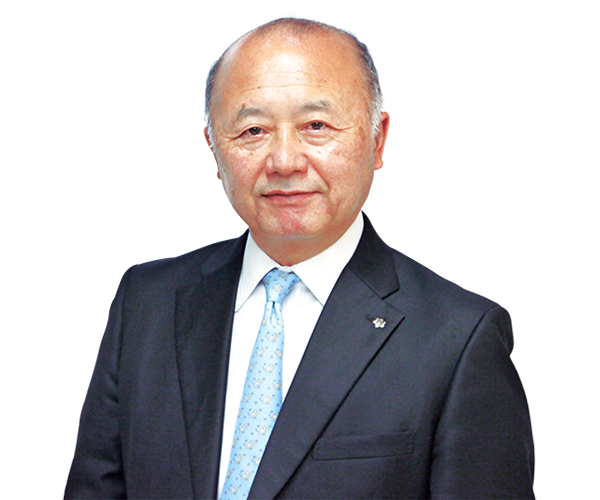
| 【連携開始】 | 2014年1月 |
|---|---|
| 【派遣国】 | 指定なし(フィジー、セネガル) |
| 【協力分野】 | 指定なし(上下水道、日本語教育) |
| 【派遣形態】 | 国際協力に関心がある社員1名を隔年で2年間派遣 |
| 【累計派遣】 | 計2名(~2020年度) |
自社のホームページに「おがわの国際協力」を掲載し、環境分野での社会的課題の解決と貢献に力を入れている株式会社小川工務店。父親から会社を継ぐ前に青年海外協力隊に参加してケニアで3年間活動した開発途上国での経験を基に積極的に社員を協力隊員として派遣している代表取締役の小川寛氏とセネガルに派遣された大塚麻実氏にお話を伺いました。
※文章内の制度名、派遣名称は派遣当時のものです。
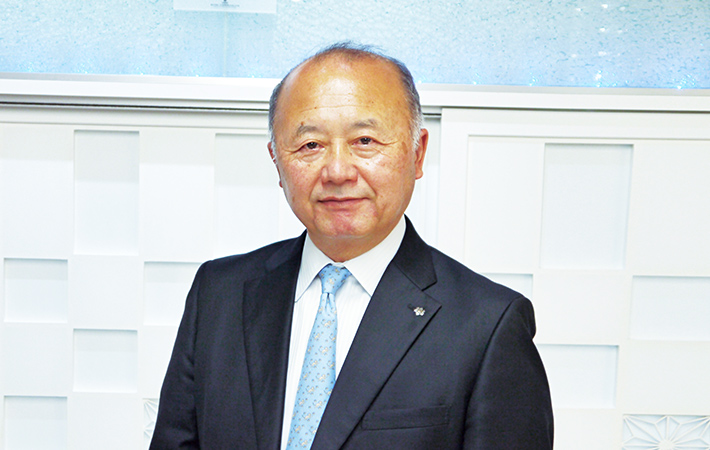
代表取締役
小川 寛氏
29歳でJICA海外協力隊に参加し、帰国後、39歳で父の家業を継ぎ社長となりました。協力隊の活動ではケニアで診療所や小学校の建設に携わりました。海外ボランティアを経験したことで、物の豊かさに比例しないことや、文化や価値観の違いを認め合っていかなければならないという気づきを得ました。こうした体験から、社長として社員に志があれば、海外ボランティアを通じて見識を広める機会を提供したいと思っています。その中で民間連携ボランティアの制度を知ることになりました。企業にとっては社員を派遣することで国際協力に加え、人材育成や現地でのネットワーク構築などが可能となり、将来的な海外展開も視野に入れることができます。参加する本人にとっても、日本の常識が通用しない中で、困難や逆境に立ち向かいながら、生活様式や文化、習慣の異なる現地の人と共に活動することで、グローバルな視野、創意工夫・企画力、語学力、コミュニケーション力が培われ、現地でのネットワークを築くことができると思っているし、違った世界を見ることは社員の人生にとっても有意義のあることだと思っています。これは素晴らしい制度だと思い、民間連携ボランティアとして締結に至りました。
自分の協力隊経験から、一度きりの人生、価値観が違う世界を広く知ることで、現実の障害(課題)にも視点を変えて解決できる力をつけ、社員自身が充実した人生を送ることの一助になれば良いと思っています。協力隊の経験は、「人間力をアップさせる」ということだと思っています。途上国では、貧しい中でもなぜ人々は幸せに生きているように見えるのか。自分が協力隊として派遣される前は「物質的に豊かであること」が幸せの条件であると思っていましたが、ケニアでは、家族でお祈りをしてから皆で朝食を食べ、仕事に行き、仕事が終われば家族で夕食を囲んでまたお祈りをし、感謝して日々を送っていました。これが本当の幸せの基本ではないかと感じました。物欲には限りがないですが、「足るを知る」ことも人生には大事だと考えており、志のある社員にはJICA海外協力隊員の経験でそれも感じて欲しいと願っています。
弊社は、JICAとの連携派遣プログラムをとても高く評価しています。自分が協力隊員だった時代とは違い、今はインターネット環境があるので、社内の文書アプリに「セネガル活動報告」などと題して写真付きで日々の報告をし、全社員31名へ情報共有しています。大塚さんの場合、担当した日本語の授業が一日90分3コマ、その後は希望者へ日本文化を紹介する「日本語クラブ」を主宰し、当初は週2回だった部活が、好評で毎日活動するようになるなど、忙しい毎日を本当によくやっていたと評価しています。生徒からの信頼も厚かったことが報告から伺えました。また、協力隊員としての業務だけでなく「セネガルYouTubeチャンネル」を作り、早口言葉や歌の紹介等も行っていました。彼女がセネガルで教えている生徒が弊社へメッセージを送ってくれたことも嬉しかったです。
派遣した社員の帰国後の様子を見ると、多様性を理解したことで、許容力・人間力が確実に上がっていることが分かります。外資系ホテル王の言葉に「お客様は、間違っていても正しい」というのがありましたが、そんな言葉を前向きに捉えられる懐の深さが身についたと感じています。今後も、他の社員を対象に、連携派遣に応募する前段階として「スタディツアー(現地視察)」を継続し、違う世界を見る機会を提供していきたいと思っています。
※このインタビューは2020年11月に行われたものです。

大塚 麻実氏

高校時代から国際協力に興味を持っていました。JICAと連携している会社ということで、自分から積極的に働き掛けてインターンとして受け入れてもらい、その後、業務と社風が自身に向いていると考えて正式入社しました。インターンシップ以来担当させてもらっている事務職について、当初は「地味な仕事」というイメージを持っていましたが、実は、事務こそコミュニケーション能力が必要であることに気付かされ、自分がやりたい業務だと思いました。帰国後の今も、総務部の職員として、とても楽しく仕事をしています。
学生時代留学したフランスで、「日本って凄いね。」とよく賛辞を受けましたが、それは私たちの祖父母・父母世代が築いた日本への評価であって、自分の努力を表すものではないと思っています。従って、自分の子孫の世代が世界から同じように好かれ評価されるかどうかは、自分たちの世代の行いにかかっていると感じました。その想いを発揮する場を探してきたことが、この会社への就職、そしてJICA海外協力隊への応募に繋がったと思っています。
自分が協力隊員として佐世保の職場から抜けることについて、同僚の負担が増す、迷惑を掛けるといった周囲からのマイナスのプレッシャーを受けたことはまったくありません。インターネットを通じて、毎日のように業務のカバーやフォローについて仲間たちと繋がっていたので、派遣中も「常に社員の一員」という感覚が互いにあったと思います。


自分のセネガルでの配属先だった3年制のビジネス大学には、かつて一般募集の協力隊員が派遣されていましたが、日本語教育という希少職種での合格者がいなかったようで、その後1年間隊員が派遣されない空白期間がありました。そのため、いわゆる「0から1を生み出す」ような苦労はありませんでしたが、協力活動では「芽を伸ばし、少しずつ大きく育てていく」ということを意識しました。
教える学生たちは、国の将来を背負って立つ立場を目指す比較的経済的に恵まれた階層で、中には自国の貧困問題を知らなかったりもします。自分は、日本語を教えることを通じて、「世界の多様性」を彼らに見せることを意識しました。日本でも「アフリカ=栄養不良の子供たちが貧しい生活をしている」といった先入観がありますが、そんなイメージを持たれることは、アフリカの人々にとってショックなはずです。違う世界を垣間見ること、そして海外から自分たちがどのように見られているか、真実を分かってもらうためにはどうするべきか、なども学生たちに考えてもらいたかったです。
活動中、小川社長がセネガルまで視察に来てくれました。社内でセネガルへの関心も高まり、前回のサッカーワールドカップ(日本VSセネガル)のとき、小川工務店の社員は「日本」と「セネガル」の双方を応援したほどです。
帰国した2年後には、きっと自分も成長できているだろうと思っていました。確かに、様々な経験を通じて多様な視点を持てるようになったとは思いますが、帰国して気付いたのは「周囲の人もちゃんと2年の間に成長していた」ということ。今や、後輩が会社の総務業務の中心を担い、課題をどんどん捌いています。協力隊への参加経験に限らず、目的意識さえしっかりしていれば、どんな経験にも価値があると気付かされた。逆に言えば、こんな大切なことを実感できたのは、自分が協力隊に行ったが故のことだろうと思います。
一歩引いて、相手の気持ち、その背景に思いを寄せる姿勢を心掛けるようになったのが、自身の変化の一つです。以前に比べて、すぐイライラしなくなり、怒らなくなったと思います。「君は正しいかもしれない。ただ、彼らが間違っているとは限らない。」小川社長から頂戴した、自分が行き詰ったときに助けられた言葉。副社長からの言葉「万事塞翁が馬(人生の幸不幸は予測できないもの)」も、忘れられない言葉です。
「協力隊で海外に行ってた凄い社員が帰ってきた。」という印象を持たれると、その経験が特別視され、逆に周囲に受入れられにくい自慢話のような「共有できない経験」となってしまいます。自分の場合は、派遣中も同僚たちとずっと繋がっていたので、今でもセネガルの話を社内では普通に受け取ってくれています。人が繋がること、共有することの大切さが広まっていくことを願っています。
※このインタビューは2020年11月に行われたものです。