
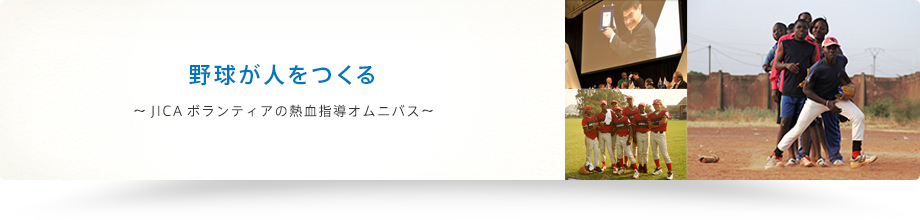


国際野球連盟・特別表彰の盾を手にする黒川JICA理事
ソフトボールの指導に取り組むJICAボランティアが初めて派遣されたのは1968年で、相手国はエルサルバドル。1970年には、野球の指導に取り組む初めてのJICAボランティアがフィリピンに赴任する。以来、延べ278人のJICAボランティアが中南米、アジア、アフリカ、大洋州、東欧、中東の計36ヵ国で両競技の指導を展開してきた(注)。
こうした貢献に対して2013年4月、130の国と地域の野球協会が加盟する国際組織、国際野球連盟(IBAF)がJICAに特別表彰を授与した。授賞式では黒川恒男JICA理事があいさつに立ち、両競技におけるJICAボランティアの近年の成果を報告するとともに、各国の指導者や選手、野球協会などJICAボランティアの活動を支えた人々への謝意を表明。一方、授賞に関してIBAF副会長でアフリカ大陸代表のイショラ・ウィリアムス氏からは、「アフリカ諸国の多くでは、JICAボランティアなしに野球とソフトボールの発展は考えられない。彼らの活動を通じて、アフリカの人々は日本の若者を『アフリカの友人』と呼び、非常に親しみを持っている」といったコメントが寄せられた。
野球やソフトボールの指導者として派遣されるJICAボランティアのバックグラウンドはさまざまだ。しかし、野球やソフトボールに青春時代を捧げ、そこから生きるうえで必要なさまざまなことを学んできたという点は、多くのボランティアに共通する。だからこそ、派遣国の若者に対する彼らの指導はおのずと真剣勝負になる。以下、その一端を拾ってみる。


香川オリーブガイナーズ在籍中のシェパードさん
2005年にスタートした日本のプロ野球独立リーグ「四国アイランドリーグplus」(2007年までの名称は「四国アイランドリーグ」)。ここにJICAボランティアの教え子が海を越えてやってきたのは2006年のシーズンだ。当時21歳だったシェパード・シバンダさん。ジンバブエ出身の野手である。190センチを超える恵まれた体格とその優れた身体能力を武器に、香川オリーブガイナーズのトライアウト(入団テスト)に挑戦し、合格した。2006年と2007年にそれぞれ約30試合ずつ出場。本塁打も放ったが、2年で契約は終了となる。2008年には、北陸を中心とした6県のチームで構成されるプロ野球独立リーグ「ベースボール・チャレンジ・リーグ」の福井ミラクルエレファンツにトライアウトで入団。同年のシリーズで30試合に出場して契約継続に望みをつないだが、祖国で子どもが生まれたこともあり、退団して帰国することとなった。
シェパードさんが野球を知ったのは1997年。小学生のときだ。きっかけは、青年海外協力隊の野球隊員、堤尚彦さんと松本裕一さんによる普及活動だった。シェパードさんが暮らしていたジンバブエ第2の都市ブラワヨで、堤さんらは100校以上ある小学校とセカンダリースクール(日本の中学と高校にあたる学校)をしらみつぶしに回り、野球を伝える活動に取り組んでいた。当時、同国でスポーツといえばサッカーとクリケット。シェパードさんもそれまではクリケットのチームに入っており、野球のことなど何ひとつ知らなかった。そんななか、彼が通う小学校を堤さんらが訪れる。「何やら、2人の中国人が野球というものを教えにきたらしい」。学校中が騒然となるなか、シェパードさんも堤さんらのデモンストレーションを見学。キャッチボールに挑戦したところ、「行けそうだ」と感じる。以来、学校で結成された野球クラブの練習に参加するようになったのだった。
シェパードさんが本格的に野球の練習に取り組み始めたのは、セカンダリースクールに進学した後。松本さんが立ち上げた地域のクラブチームのメンバーになってからだ。コーチは、同じく野球隊員の根岸勇二さん。東京六大学野球連盟の強豪、明治大学硬式野球部で活躍した人物だ。根岸さんの指導は、「勝つこと」を目標にした厳しいもの。ノックでは容赦なく強い球を打ち、常に選手たちの「競争心」を刺激した。
「『スポーツの目的は勝つことだけではない』と言われます。しかし、野球のおもしろさは、上手に打ったり、守ったりできるようになって初めて感じることができるものだと思うのです」(根岸さん)
この思いは選手たちの心に響いた。シェパードさんは根岸さんの指導方法についてこう振り返る。「練習が厳しいからこそ、ぼくらは野球に集中できた。『誰が一番ファンシーなプレーをできるか』という競争心を持ったからこそ、努力もした。根岸さんの指導で確実に上達できたからこそ、ぼくらは野球を楽しむことができたのです」

中学生のころのシェパードさん(右から3人目)と、当時指導をしていた根岸さん(右端)
根岸さんの指導を受け始めるとシェパードさんはみるみる腕を上げ、2000年にはジンバブエ代表チームのメンバー入りを果たす。当時、代表チームの監督を務めていたのは、1992年から2年間、同国で野球の普及に取り組んだ初代野球隊員の村井洋介さんだ。村井さんは任期終了後に再びジンバブエに戻り、ビジネスの傍らアフリカ野球協会の顧問兼コーチとして活動していた。
ジンバブエの野球の発展にとって不運だったのは、2000年代に入ると同国の経済が急激に悪化し始めたことだ。2005年には村井さんも南アフリカ共和国に移り住むことになり、ジンバブエ代表チームの指導が不可能に。そこで村井さんは、それまで村井さんを通してジンバブエに野球のための寄付を続けていた日本の有志団体「ジンバブエ野球会」に相談。その結果、いずれジンバブエで野球の指導者となれるような人材を日本の独立リーグに挑戦させるという、新たな形の支援を同会が行うことに。身体能力が優れているうえに性格もまじめなシェパードさんに、白羽の矢が立ったのだった。
ジンバブエの経済がようやく回復の兆しを見せ始めたのは2012年のこと。2008年に日本を離れたシェパードさんも、その後は家族を養うために会社勤めをするなど、まだ野球どころではないという状態だ。しかし彼には夢がある。
「いつか、ジンバブエに『野球アカデミー』のようなものをつくりたい。大きな野球場を建て、必要な道具をそろえて、誰でもそこに行けば野球を教わることができるような施設です。そうして、協力隊員たちが築いてくれた野球の土台を無にしたくはないのです」(シェパードさん)


兵庫ブルーサンダーズのトライアウトを受けたころのワフラさん(2012年撮影)
「四国アイランドリーグplus」「ベースボール・チャレンジ・リーグ」に次ぐ3番目のプロ野球独立リーグとして2009年に誕生した「関西独立リーグ」。現在、近畿地方の3チームが参加しているが、そのうちの一つ、兵庫ブルーサンダーズに2013年のシーズンからウガンダの選手が加入している。ワフラ・ポール選手、22歳。190センチ近いがっしりとした体格の野手だ。2012年11月に同球団のトライアウトを受けて合格。4月27日には初めてライト・9番でスターティングメンバー入りした。そうして新天地での挑戦を始めた彼もまた、青年海外協力隊員に野球選手として育てられた一人である。
「協力隊員のコーチたちは、技術はもちろん、『グラウンドでどう振舞うべきか』を教えてくれた。ぼくの野球スタイルは、礼儀正しく、敬意を忘れない『日本式野球』。日本のプロ野球界で活躍するのはぼくの夢なのです」(ワフラさん)

野球を始めて間もない時期のワフラさん(左端)と、当時指導をしていた今野さん(後列右端)
ワフラさんが初めて野球隊員の指導を受けたのは13歳のとき。当時、首都カンパラではアメリカ人による技術指導や道具の支援を受けながら、4つのクラブチームが大学のクリケット場などを借りて練習を続けていた。そのメンバーの一部が、郊外にチームを発足。ワフラさんが所属していたのは、この郊外のチームだ。2003年に赴任した同国の初代野球隊員、今野了さんが、首都のクラブチームの指導をする傍ら、この郊外のチームを週に1回程度、指導に訪れた。当時のワフラさんは、見よう見まねで野球を始めたばかり。技術的に特別な点はなかったが、すでに同世代のなかでは身長が高く、運動神経の良さや足の速さが目立つ選手だった。
ワフラさんが再び野球隊員の指導を受けるようになったのは2011年、二十歳のときだ。指導をしたのは、日本の社会人野球のチーム、京都ファイアーバーズ(現・京都城陽ファイアーバーズ)でプレーヤー兼コーチとして活躍した田中勝久さん。着任して間もない時期、メジャーリーグが南アフリカで実施する強化キャンプの参加選手選抜会を見学した際、数十人の候補者のなかで目にとまったのがワフラさんだった。
「打撃にしろ、守備にしろ、技術レベルはまだまだだった。しかし、彼の恵まれた体格やパワーはひときわ目立ったうえ、体のやわらかさも兼ね備えていました」(田中さん)
彼の潜在能力の高さを感じた田中さんは、彼を含め、素質の高い選手を徹底的に指導し、日本のチームで活躍できるまでに育てたいと考える。日本の野球を経験すれば、後にウガンダで野球をメジャーなスポーツに引き上げる中心的存在となってくれるに違いないからだ。そうして田中さんは、ワフラさんを含む数人の選手に声を掛け、毎朝の特訓を開始した。

「ワフラ選手には野球に対する敬意があった」と語る田中さん
田中さんがワフラさんらへの指導で取った方針は、「内野守備の練習に重点を置く」というものだ。田中さんが野球の師と仰ぐのは、元阪神タイガースの内野手、榊原良行さん。京都ファイアーバーズ時代のコーチだった。「守備の達人」と言われた元阪神タイガースの監督、吉田義男さんの薫陶を受けた榊原さんの指導は、打球を捕って1塁に送球するまでの一連の体の流れを徹底的に仕込む、いわば「職人」の育て方だった。田中さんはこれをワフラさんらに対して実践した。
「『守備』は『打撃』に比べれば地味なもの。しかし、榊原さんの指導は教え子がみな『野球の本当の魅力がわかった』と口をそろえるものでした。それをウガンダの選手たちに体験させてあげたかった。そんな私の意図を一番よく感じ取ってくれたのがワフラ選手だったのです。守備の上達には下半身を鍛えることが重要だと理解し、『走り込み』にも積極的に取り組む。実は、指導をするなかで、彼にとってかつて教わった今野さんの影響がいかに大きいかがわかってきました。一生懸命練習に取り組むし、時間を守る。野球に対しても、他者に対しても、『敬う』という姿勢が身に付いていた。これこそが、彼の野球技術の向上につながっていったのではないかと思います」(田中さん)
そうして、1年ほどの指導によって彼の可能性を確信した田中さんは、日本の知人らに寄付を募り、ワフラさんを兵庫ブルーサンダーズのトライアウトに送り出したのだった。同チームは、田中さんのかつてのチームメイトが職員を務める球団でもあった。
ウガンダで青年海外協力隊員が野球の指導を初めて約10年。その教え子たちのなかには、大使館の職員や大学教員など、しっかりとした職業に就いている例も少なくない。それを知って「野球は人間を育てる」と実感した田中さんは、2013年に入ると、学校に行けない子どもへの野球指導の機会を増やした。たとえ経済的な理由で学校に行けなくても、野球を通じて「社会に必要とされる人材」に育ってほしいと願ってのことだ。
一方、ウガンダでは田中さんの働きかけもあり、日本政府の草の根文化無償資金協力による支援が決まり、2013年末には同国初の野球専用グラウンドが完成する予定だ。田中さんは、ワフラさんが日本で高いレベルの野球を学んだ後、今度は彼が中心となってこの新球場を舞台に「野球を通じた人づくり」を進めてくれることを期待している。


来日する選手の選抜を行った際のラシィナさん(2012年撮影)
「四国アイランドリーグplus」には、2013年6月、ジンバブエのシェパードさんに次いで二人目となる野球隊員の教え子がやってくる。ブルキナファソの15歳の少年、サンホ・ラシィナさんだ。チームは高知ファイティングドッグス。1ヵ月間、チームの練習に参加し、そこで素質を認められれば登録選手になれる「練習生」という立場である。
ラシィナさんが初めて野球を教わったのは2008年、11歳のときだ。指導したのは、北海道の強豪・札幌大学野球部出身の野球隊員、出合祐太さん。赴任して半年ほど経ったある日、ラシィナさんの友人が「あなたは何をしにここに来た外国人なのか」と出合さんの家を突然たずねてきた。それをきっかけに、出合さんはラシィナさんを含めた近所の9~14歳の少年12人で野球チームを立ち上げ、その指導にあたることにしたのだった。
出合さんが驚いたのは、子どもらの「自立」の姿勢だ。彼らは野球を始めると間もなく、自発的に「速いボールを投げるにはどうしたらいいのか」「ボールを遠くに飛ばすにはどうしたらいいのか」と自分の頭で考え始めたのだ。そこで出合さんも、彼らに考えるヒントを与えるため、日本の小・中学生が知らないような体のメカニズムなども積極的に教えていった。
そうして子どもらの技術は急速に上達。「10年後、この子らがブルキナファソの野球を担ってくれるかもしれない」。そう感じた出合さんは、このチームの子どもらに賭けてみようと決意。取り組みの一つとして計画したのが、「日本の野球を経験する機会を提供する」というものだ。
2010年に青年海外協力隊の任期を終えて帰国する際、子どもらにこう言い残した。「2年後にここに戻ってくる。それまでにもっとうまくなっていなさい。そうすれば日本でプレーするチャンスがある」。帰国すると、出身地の北海道を中心に、高校や大学の野球部からプロ野球の球団まで、さまざまなチームにブルキナファソの少年の受け入れを打診して回った。ようやく「練習生」としての受け入れを承諾してくれたチームが、高知ファイティングドッグスだった。
2012年11月、日本に呼ぶ選手を選ぶため、出合さんはブルキナファソへ。かつて自分が教えた選手に広く応募を呼びかけたところ、選抜会には42人が集合。2日間のテストで最終的に選んだのが、ラシィナさんだった。「『伸び幅』が一番大きかったのが彼。2年間、自分で自分を育ててきたのだなということがよくわかりました」(出合さん)

「子どもたちの成長に私自身が学ばされた」と語る出合さん
15歳で独立リーグの登録選手になるというのは至難の業というのが現実だ。しかし、出合さんは5年先を見据えている。ラシィナさんが今回、練習生として経験したことをブルキナファソに持ち帰り、同国の選手たちに還元する。そうして彼らの世代が二十歳になり、体も出来上がったころ、今度こそ日本のプロ野球で活躍する選手が現れるかもしれない。出合さんは、そのころまで彼らに付き合う覚悟はできている。


日本の社会人野球、都市対抗野球大会で3塁塁審を務めたスジーワさん(2012年撮影)
野球隊員の教え子のなかには、日本野球への憧れから日本で「審判員」として活躍する例もある。高校野球、大学野球、社会人野球の公認審判員として活躍するスリランカ人、スジーワ・ウィジャヤナーヤカさん(29)だ。福岡県内の亀の井ホテルに勤務する傍ら、年間約80試合ほどで審判を務めている。
スリランカで最もメジャーなスポーツであるクリケットの選手だったスジーワさんが野球を始めたのは高校時代。3年生のときに、同国初の野球隊員である植田一久さんの教えを受け、野球のおもしろさに目覚めたという。
「植田さんは、野球の技術だけでなく、相手チームの選手を尊重することや、スポーツを楽しむ姿勢なども教えてくれたのです」(スジーワさん)
高校を卒業すると、母校の監督を務めながら、2代目の野球隊員である後田剛史郎さんが監督を務める同国代表チームのエースとして活躍。ますます野球にのめりこんでいった。「スリランカの野球を発展させるためにも、日本で野球を学びたい」。2006年には、ついに大分県にある立命館アジア太平洋大学に自費で留学し、野球部に入部する。しかし、まだ野球を始めて何年も経っていないスジーワさんには、日本の大学野球のレベルは高すぎた。そんななか、「日本で審判の勉強をしてみてはどうか」と勧めたのは、前述の後田さんだ。審判の高い技術をスリランカに持ち帰ることも、同国の野球の発展につながるはず。そんな考えから、学業の傍らで審判の講習会などに通うようになった。

野球専用グラウンドの完成記念式典の際には、神奈川県高校野球連盟選抜チームとスリランカ19歳以下代表チームの交流試合も行われた
スジーワさんは来日後、スリランカ初となる野球専用のグラウンドを建設するためにも奔走。2011年、日本のプロ野球選手会などから寄贈された野球道具を持ってスリランカのスポーツ担当大臣に面会した際、代表チームでさえクリケット場などを借りて練習をしている状況を訴える。それがきっかけとなって、政府から主要都市コロンボ近郊に野球専用グラウンドのための土地を提供してもらえることになったのだった。建設費用は、半分は日本の草の根文化無償資金協力による支援で、残りの半分はスジーワさんの勤務先である株式会社アメイズの穴見社長など有志の寄付でまかなわれることに。そうして2012年12月、スリランカのみならず、南アジアでも初となる野球専用グラウンドが完成した。
「将来はこの球場が『南アジアの甲子園』となって、南アジア全体の野球の発展のために活用されることを願っています」(スジーワさん)
野球隊員が代々、監督を務めてきたスリランカ代表チームは、2011年に初めて行われた南アジア野球選手権大会で銀メダルを獲得するまでになっている。今後は、野球隊員らが蒔いてきた種を、スジーワさんを含めた教え子らが育てていく段階に入っている。


WBCで打撃・走塁コーチとしてブラジル代表チームに参加した黒木さん
野球が伝えられて100年になるものの、サッカー人気の影でいまだにメジャーなスポーツとなりきれていないブラジル。2012年11月に行われたワールド・ベースボール・クラシック(WBC)第3回大会の予選では、数人のメジャーリーガーを擁する強豪パナマを2度にわたって破るなどして、初出場ながら本戦進出を決めた。それまで野球には目もくれなかった同国のマスメディアも、この快挙を大々的に報じ、野球のさらなる普及が見込まれている。
この躍進の裏には、2009年から2年間、日系社会青年ボランティアとして同国で野球の指導に取り組んだ日本人の活躍があった。同大会でブラジル代表チームの打撃・走塁コーチを務めた黒木豪さんだ。野球の名門校・横浜高校で活躍した黒木さんだったが、プロ選手としてプレーした経験はなかった。一方、ブラジル代表チームは日本のプロ野球や社会人野球の選手、マイナーリーグ選手など、プロ選手が大半。そのため、予選会場のパナマでチームに合流した当初、選手からは「お前に何ができるのか」という冷ややかな目で見られた。そこで黒木さんがとった道は、「データ収集」 によるチームへの貢献。インターネットで相手チームの投手の情報をひたすら集めた。チェックしたのは、日本語、ポルトガル語、スペイン語、英語の4ヵ国語のサイトだ。
「なんとか自分の存在を認めてもらわなければと、試合の直前は徹夜続きで情報を集めました」(黒木さん)
ふたを開けてみると、予選の対戦相手の登板投手は黒木さんの予想がすべて的中。各投手の持ち球の特徴や、投球の組み立て方について黒木さんが提供する情報により、ブラジル代表チームはいずれの試合も10近い安打を記録したのだった。
黒木さんが WBCのコーチに呼ばれたのは、日系社会青年ボランティアとしての活動が端緒だった。日系社会のインダイアツーバ市文化協会に配属された黒木さんが指導したのは、協会が運営する野球クラブの13~14歳カテゴリーのチーム。野球のおもしろさを感じてもらうためにも、自分が知る高いレベルの野球を教えたいところだったが、そのために必要な基礎が選手たちには欠けていた。そこで黒木さんはまず、キャッチボールやトスバッティングなどの基礎練習を徹底的に行った。
「最初は、『簡単な技術しか教えないからつまらない』といって、次々に選手が辞めていった。しかし、残った選手たちの体の動きに明らかなキレが出てくると、辞めた選手たちがそれを見て戻ってきたのです」
そうして着任して1年ほど経ったころには、教え子たちが主力メンバーとなった地域代表チームが全国大会で3位入賞を遂げる。黒木さんの指導力に着目したブラジル野球連盟会長は、12歳のカテゴリーのブラジル代表チームのコーチを黒木さんに依頼。日系社会青年ボランティアの任期終了直後に行われた16歳以下の国際大会「AA世界野球選手権大会」でも、コーチを依頼されてチームに同行し、5位入賞に貢献した。WBCのコーチを要請されたのも、こうした一連の活躍で得たブラジル野球連盟会長からの厚い信頼からだった。

WBCでコンディショニング・コーチとしてドミニカ共和国代表チームに参加した百瀬さん
WBC第3回大会では、黒木さんのほかにもコーチとして活躍したJICAボランティア経験者がいた。全勝優勝を果たしたドミニカ共和国でコンディショニング・コーチを務めた百瀬喜与志さんである。
1995~1997年にコスタリカで野球隊員として活動した百瀬さんは、任期終了後、米国・セントラルフロリダ大学で運動生理学を学び、メジャーリーグでコンディショニング・コーチとして働き始める。 現在はピッツバーグ・パイレーツのストレングス・コンディショニング・コーディネーターとして、主にドミニカ共和国やベネズエラのアカデミー(育成機関)の選手を担当している。
「メジャーリーグでは4分の1がスペイン語圏の選手ですし、マイナーリーグでは半数近くがスペイン語を母語にしている選手たち。協力隊時代に身につけたスペイン語が大きな武器になっています」(百瀬さん)
WBCでは当初、プエルトリコで1次ラウンドを戦うドミニカ共和国、プエルトリコ、ベネズエラのメジャーリーグ選手のコンディショニングのサポートをメジャーリーグから依頼されていた。しかし、その仕事ぶりからドミニカ共和国の監督などの要望があがり、決勝ラウンドまで帯同することになったのだった。「楽しみながら、それでいて目標に向かって必死に戦うということのすばらしさを再確認できた経験でした」

野球の指導をするJICAボランティアや、その教え子らからしばしば聞かれる言葉は「敬意」だ。「道具を丁寧に扱う」「グラウンドや対戦相手にお辞儀をする」といった、日本の野球ではごく当たり前の行為の根にある、対戦相手や野球そのものへの「敬意」。JICAボランティアはこれを日本野球のアイデンティティと考え、教え子に伝えようと努める。ブラジル代表チームのコーチを務めた前述の黒木さんはこう話す。
「『野球』が『ベースボール』と違うのは、野球や対戦相手に対する『敬意』の重みではないか。WBCでも、『ベースボール』のプレーヤーがボールを蹴ったりしているのを見て、あらためてそう感じました」
(注)青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、日系社会青年ボランティア、日系社会シニア・ボランティアの4ボランティア(いずれも短期ボランティアを含む)。2013年4月12日現在。