
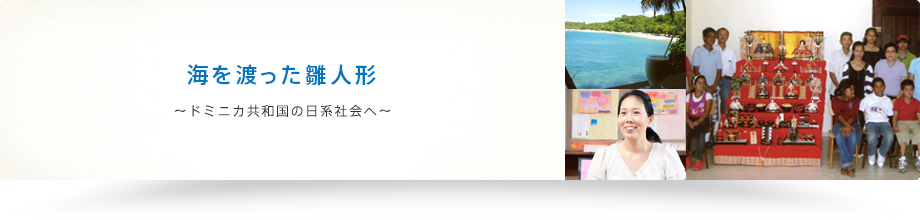


カリブ海に浮かぶドミニカ共和国
プエルトリコの東、ジャマイカの西に位置するイスパニョーラ島。カリブ海に浮かぶこの島の東側3分の2を占めているのがドミニカ共和国であり、かつて、コロンブスが新大陸で最初に上陸し、町を作り上げた国である。植民地時代は農業が主要産業であったが、近年は衣料品やエレクトロニクスなどの軽工業も栄えており、歴史的建造物やビーチリゾートを生かした観光業も急成長を見せている。
「ドミニカ共和国」の名前は知られていても、日本から約2万キロ離れたこの地に、日系社会が存在していることはあまり知られていない。その歴史は敗戦後の日本にさかのぼる。1956年から1959年の3年間で、249家族1319名の日本人がドミニカ共和国の入植地に移住した。しかし、1961年に親日家として知られていた同国のトルヒーリョ大統領が暗殺されると、政情や経済は一気に不安定となり、日本政府は移住者たちに南米転住、ドミニカ共和国残留、日本帰国の3つの選択肢を提示した。その結果、約50%が帰国したとされている。残り約50%の中で、南米(ブラジルやパラグアイ)に転住した日本人が約30%、47家族276名(約20%)の日本人がドミニカ共和国に残留した。彼らは今なお日系1世として現地に根を張り、その血脈は日系4世にまで受け継がれている。


肱岡 安枝さん(2009年度派遣/ドミニカ共和国/日系日本語学校教師)
日本人がドミニカ共和国へ入植してから50数年の時が流れた2009年。肱岡安枝(ひじおかやすえ)さんは、日系社会青年ボランティアとして同国へ派遣された。首都のサント・ドミンゴから130キロ離れた場所にあるラベガ日本語学校、そこからさらに20キロ離れた場所にある公民館に併設されているハラバコア日本語学校、この2校へ通う日系の生徒を対象に、日本語を教えることが肱岡さんの任務だった。
肱岡さんの教え子となる日系3世や4世のなかには、日本語を全く話せない生徒も多い。その一方で、日系1世には、あらゆる面において、50年前の日本がそのまま残っている。相互扶助で生きてきた日系社会を一つの家族ととらえ、日本の文化や行事を守ってきた。それゆえ、日系1世が肱岡さんに寄せる期待は、「孫たちには、日本語のみならず、日本のことを多岐にわたって、しっかり伝えてほしい」という願いにも似たものだった。そんな願いをこめるだけあり、日系1世の多くは、学校行事に必ずといっていいほど参加する。そして、子どもの学習態度が悪いとなれば、それが自分の身内でなくても、注意を促し、たしなめる。そこには、「日系の子どもは日系社会みんなの子ども」という連帯意識と責任感があるからだ。肱岡さんは、「当時、私は日本を背負って、ドミニカ共和国へ来たつもりでいましたが、日系1世の皆さんに襟を正された思いでした」と話す。

ドミニカ共和国で暮らす日系1世から4世の方々。ハラバコア公民館の前で
そんななか、ドミニカ共和国の日本語学校全校が首都にある大学に集まり、各校が1年間の集大成を発表する「学習発表会」の開催が近づいた。日系社会にとっての一大イベントであるこの「学習発表会」で、日系1世と2世からなる保護者会による強い希望もあり、肱岡さんの教え子たちは『かぐや姫』を演じることになった。
その頃、時を同じくして、「世界の笑顔のために」プログラム(※1)の申請時期がやってきた。肱岡さんは悩んだ結果、ハラバコア公民館がとても殺風景であることを思い、日本人形を申請。「日本人形が公民館に一体でもあれば、日本ならではの華やかさが出ると思ったんです」と肱岡さんは当時を振り返る。
(※1)「世界の笑顔のために」プログラムとは、開発途上国で必要とされている教育・福祉・スポーツ・文化などの関連物品について、ご提供くださる方々を日本国内で募集し、JICAが派遣中のボランティアを通じ世界各地へ届けるプログラムのこと。

『かぐや姫』の練習を始めるも、日本文化とは無縁で育った生徒たちに、平安時代のことを伝えるのは至難の業だった。「日本の行儀や作法に対する理解が皆無なので、手取り足取りで教えるしかありません。子どもたちに協調性は無く、私は焦る一方でした」と肱岡さんは苦笑する。

海を越え、ドミニカ共和国の地に届いた雛人形
それでも練習を続け、本番まで1ヶ月となったある日。肱岡さんが申請した日本人形が届いた。それは七段飾りの立派な雛人形のセットだった。皆でダンボールを囲み、頭をぶつけあうようにして中を覗き込みながら、慎重に中のものを取り出した。雛人形は、はるばる2万キロもの旅をしてきたにもかかわらず、顔は白く美しく、髪は一糸も乱れておらず、その場にいた全員が「わー!」と歓声をあげた。次から次へとダンボールから取り出される五人囃子やぼんぼりなどの装飾品の数々。それは『ひなまつり』の歌そのものの世界観だった。
特に感慨深い様子を見せたのは日系1世の年配者だった。敗戦後の貧しい日本で、贅沢品である雛人形を間近に見ることができたのは、ごく限られた人たちだけだったからである。「まさかドミニカでお雛さんを拝めるなんて」と涙ぐむ者さえいた。「落としてはいけない」、そんな緊張感から、手を震わせながら飾り付けをする者もいた。日系1世から4世までが世代を超えて心を一つにした瞬間だった。

かぐや姫の練習をする日系社会の子どもたち
この日を境に、『かぐや姫』の練習に対する生徒たちの気持ちは一変。生徒たちは、みるみるうちにセリフを覚え、衣装に対しても一人ひとりがアイデアを出すようになった。『かぐや姫』の登場人物たちの衣装を製作するときも、雛人形の衣装が大いに参考になった。大使館から借りた帯を合わせると、衣装は舞台栄えする素晴らしいものとなり、そんな衣装に袖を通した生徒たちは、さらにやる気を見せるようになった。練習にも一層身が入り、完璧な状態で本番を迎えた。本番は大成功で幕を閉じ、ホールには、いつまでも拍手が鳴り響いた。「あの雛人形のお陰で、全員の足並みが揃ったことは言うまでもありません」と肱岡さんは話す。


雛人形を送った仁木澄恵さん。ドミニカ共和国から届いた手紙を大切に保管している。
雛人形の送り主である仁木澄恵(にきすみえ)さんが、JICAと関わりを持つようになったのは、娘が協力隊員としてマダガスカルへ派遣となった2005年からである。娘からの依頼で中古の楽器を知人たちと協力しながら集め、マダガスカルへ送った。想像していた以上に喜ばれていることを知った仁木さんは、「使われずに家の片隅で眠っているだけのものが、途上国で命を吹き返すのは素晴らしい」と感じるように。以来仁木さんは、同プログラムを通じて物品提供を続け、その数は、今や数え切れないほどまでになった。「日本にいながらできる小さな国際協力です」と仁木さんは笑顔を見せる。

仁木さんの二人の娘の成長を見守ってきた雛人形
ドミニカ共和国へ送られた雛人形も、その一つ。もともとは、二人の娘のために購入した思い出の雛人形だった。「娘たちが中学生になるころまでは、毎年きちんと出して飾っていたのですが、いつからか、押入れにしまったままになっていました」と仁木さん。こうして雛人形たちは、飾り方の手順が書かれているシートと共に日本を飛び立ち、ドミニカ共和国へと渡ったのである。


ハラバコアの日系人会を代表し、感謝の気持ちを肱岡さんに託した日高武昭さん
肱岡さんの任期満了の日が差し迫ったある日、ハラバコア地区の日系人会代表を務める日高武昭(ひだかたけあき)さんが肱岡さんのもとを訪れた。そして、日高さんは言った。「インターネットで調べたら、宮崎県の先生の実家から、雛人形を送ってくださった方が住む兵庫県までは新幹線の往復で5万円くらいだそうだ。直接お礼を伝えに行ってくれんやろか」。差し出された封筒には、ハラバコアの日系人から集められたという500ドルが入っていた。そして、雛人形のお礼にと、ハラバコアでつくられているコーヒー、ドミニカ共和国の特産品であるラリマールと呼ばれる水色の美しい石が施されたネックレス、直筆の礼状が、肱岡さんに託された。
肱岡さんは、「日系社会の皆さんに『お礼は顔を見てするもの』と、あらためて教えて頂きました」と話す。肱岡さんによれば、ハラバコアのような地方で暮らす一般家庭にとって、500ドルは大きな額だという。「ハラバコアの日系の皆さんは、1杯5ペソ(約10円)のコーヒーに砂糖をたっぷり入れて、毎日の農作業に出かけていきます。それを考えれば、彼らにとっての500ドルの価値が、どれだけのものかをお分かりいただけるかと思います」と肱岡さん。

ハラバコア日系社会の皆さんの感謝を伝えるため、仁木さんと対面した肱岡さん
2011年、夏。肱岡さんと仁木さんは、明石市内で初めて対面した。「限られた時間ではありましたが、現地の日系人たちが雛人形をどれだけ喜んだか、そして、どれだけ大事にしているかを、写真を見せながらお伝えしました」(肱岡さん)。仁木さんは、「わざわざ来てくださった肱岡さんには感謝の気持ちでいっぱいになりました。また、日系1世のみなさんをはじめとした方々が、どれほどの思いを日本に寄せているかを知り、『我が家から送り出した雛人形が素晴らしい役目をしてくれている、行くべきところへお嫁に行ってくれた』、そんな気持ちになりました」と話す。
それから数ヵ月後のある日の晩、仁木さんの自宅の電話が鳴った。その電話は、ハラバコアの日高さんからの国際電話だった。「突然だったので驚きましたが、嬉しいサプライズでした」と仁木さん。わずか5分ほどの会話だったが、互いの声を聞くことで、遠い空の下にいるはずの二人の距離はグッと縮まった。


ハラバコア公民館に飾られている雛人形
日高さんら日本人入植者たちが、ドミニカ共和国で歩んできた50有余年の道のりは、決して平坦なものではなかった。「彼らの思いは、彼らにしか語れない」と肱岡さんは話す。しかし、日系社会の人々が、互いに手を取り合いながら助け合い、古き良き日本の伝統や文化を守ってきたことは紛れもない事実である。雛人形は、そうした意味において、日系社会の人々にとって極めて意義深い存在なのだ。「こんなに立派な雛人形は、ドミニカ共和国全土を探してもハラバコアにしかないでしょう。日系社会でしっかり管理し、守っていく義務がある。また、単に飾っておくのではなく、『上巳(じょうし)の節句』の意味を語りついでいかなくてはならない」と日高さん。
古来、桃の節句は、3月上旬の「巳」の日に行われていたことから、「上巳の節句」と呼ばれていた。今日の日本では、この言葉を知る人のほうが少ないのではないだろうか。今の日本人が失いつつあるものを、50年以上の時を経ても異国の地で守り続けている日本人がいることを、私たちは忘れてはならない。