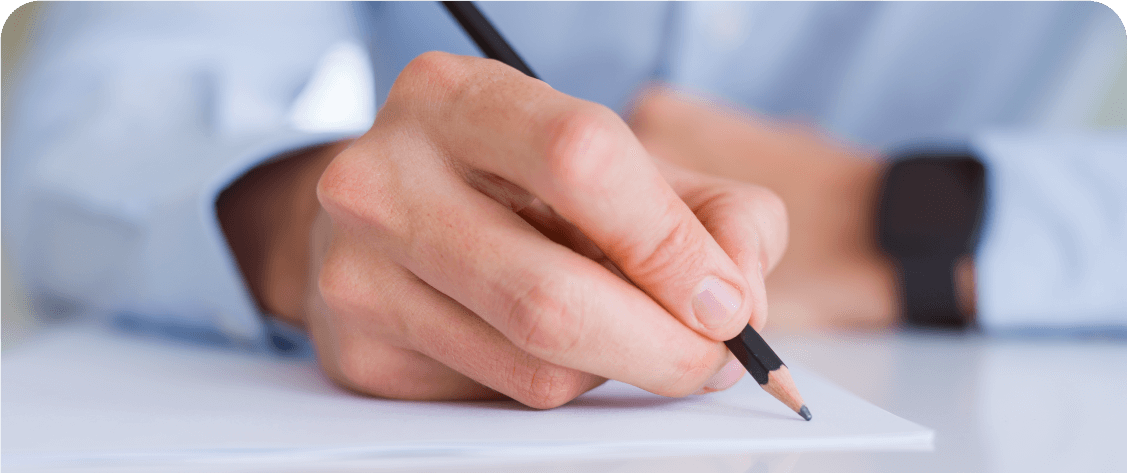専門性を起点として、
より高い視点を獲得する
JICAに入構して最初に配属となったのは、経済基盤開発部運輸交通・情報通信グループ(現在の社会基盤部運輸交通グループ)。主に道路、橋梁といった交通インフラ整備のための調査等を手掛ける部門ですが、ここは、コンサルタント時代の“発注先”でもありました。2ヶ月前までクライアントだった方たちと席を並べることになったわけですが、想像していた通り皆さん本当にフランクで、「ようこそJICAへ」と受け入れていただきました。またエンジニアの世界では、皆が高い専門性を有し、それぞれの専門分野の中でしのぎを削るような文化が根強かったのに対し、JICAではお互いの経験・知見を共有し、組織として成果の最大化を目指すといった価値観が浸透しているように思います。そして、職員全員が途上国開発への熱い想いを持っている……従って、途上国開発に対する情熱を持っている方にとっては、とても働きやすい組織文化だと感じています。
加えて、発信力や影響力が大きいという点も、JICAの大きな魅力であると思います。例えば、ウガンダ駐在時代、首都、カンパラの交通渋滞解消に取り組みましたが、驚いたのは、先方政府が都市開発に関する全体像を持たないまま、各援助機関がそれぞれベストであると考える提案を行っていることでした。そこで私は、都市のマスタープランをしっかりと作ったうえで、先方政府、及び各援助機関はそれに基づいた取り組みをしていくべきではないか、という発信を多くの会議で行いました。結果的に私の提案は受け入れられ、現在では、各援助機関の都市開発セクター担当者が定例ミーティングを持つところまで発展しています。この時の経験からマスタープランの重要性を痛感し、JICAの中でインフラ/都市開発分野のマスタープラン作りを担う現部署への異動を希望することにつながりました。また、現部署でも、ジャカルタをはじめとする途上国の都市における交通渋滞解消に取り組んでいますが、マスタープランの策定やMRT(都市高速鉄道)等のインフラ面で協力するだけでなく、市民に公共交通を活用してもらうにはモビリティマネジメント(※注)の考え方を導入すべきではないか、と同僚と提案しました。そして、有識者やコンサルタントの皆さんと検討を重ねて、『モビリティ・マネジメントハンドブック』を作成し、今後、多くのプロジェクトで活用することを目指しているところです。このように、自身のアイデアを基に幅広い関係者を巻き込んで、よりよい社会をつくっていく……私にとってJICAの仕事の大きな魅力は、こうしたところにあります。
これまでお話ししてきた通り、私は橋梁という専門性を背景としてJICAでのキャリアをスタートしたわけですが、JICAは事業領域が幅広い組織ですから、自身の専門性に固執し過ぎると逆にもったいのではないかと今は考えています。専門性はもちろん大切ですが、それを軸にしてさらに横に拡げていくスタンスを持てれば、より充実したキャリアを築いていくことができるのではないでしょうか。私自身のこれから、という意味では、より高い視点に立った、アジェンダを発信できるような人材を目指していきたい、ということを考えています。JICA・日本を代表して、都市交通、交通インフラに関する開発潮流を世界に発信していく存在……まだまだ学ぶべきことは多いですが、そうした能力を獲得していくことが、自分自身にとっての現在のテーマです。
※注:モビリティマネジメントとは、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取り組み。例えば、公共交通のメリットを広告や学校教育といったさまざまな形で市民に伝えるといったソフト面のアプローチ。