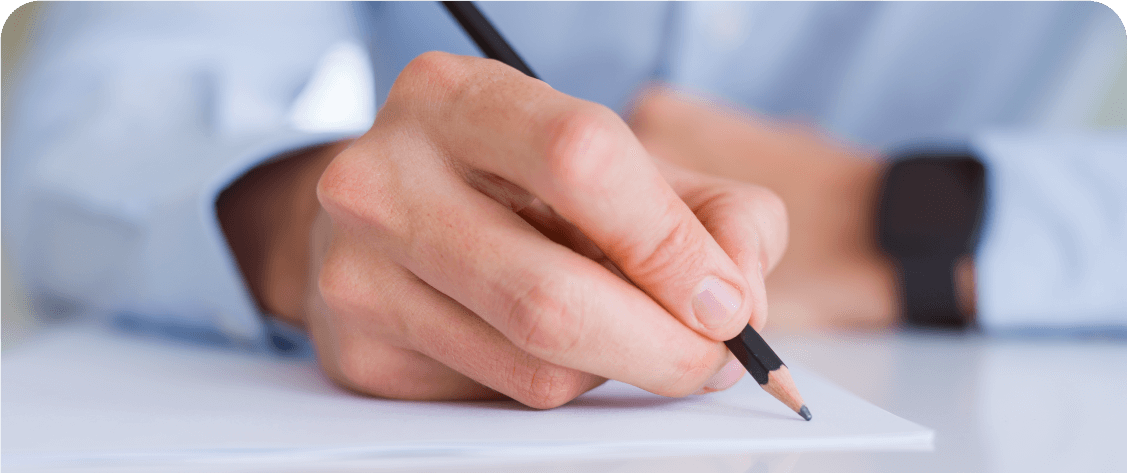試行錯誤の末に出会った、
JICA東京という“現場”
高校〜大学をアメリカで過ごしましたが、特に高校時代は、言葉や文化の違いに戸惑い、また、日本について聞かれてもうまく答えることができず、海外に来て初めて自身のアイデンティティについて考えるようになりました。そこからですね、日本文化について深く学びたいと考えるようになったのは。大学では茶道部に所属して部長を務め、裏千家から派遣されていた茶道講師による実技授業のティーチング・アシスタントをさせていただきましたが、以来、茶道は日本人としてのアイデンティティを感じることのできる私の心の拠り所となっていきました。またその頃から、日本と海外をつなぐ役割を担いたい、茶道でそれができるのではないかと考えるようになったのです。大学卒業後は、講師の薦めもあって京都にある家元直属の裏千家の専門学校に進み、3年間、まさに“お茶漬け”の日々を過ごし、教授者資格の“茶名/宗衣”もいただくことができました。
専門学校を出てからは、茶道をツールとして日本と世界をつなぐ、国際文化交流に関わる仕事がしたいと模索しながら、ホテルの茶室管理を兼ねるレストランサービス部門等、いくつかの仕事を経験しましたが、なかなか“国際的”な仕事にはつながっていかない……。そうしたジレンマを抱えながらしばらく悩んでいたのですが、選択肢の一つとして登録していた人材派遣会社の求人募集でJICA東京を見つけ、海外の方々を受け入れている場所で自分のこれまでの経験を生かすことができるのではと思い、応募を決めました。ですから私の場合、派遣スタッフとして働くことになったのが国際協力に関わるきっかけだったのです。現在私は、人間開発・計画調整課で、研修員受入事業の運営に携わっていますが、2015年に派遣スタッフとしてお世話になったのも、今と同じ人間開発・計画調整課。当時担当していたのは、研修運営担当者の事務サポートで、それ以外にも、来日中の研修員に茶道を通じた国際交流イベントを担当させていただいたこともありました。JICA東京で働く皆さんは、国際経験豊富で多様なバックグラウンド、専門性を持った方ばかりでお話しするたびに刺激を受け、働いているうちに、次第に国際文化交流だけでなく国際協力への関心が高まり、自分も途上国の現場に行ってみたいという思いが募っていったのです。長期休暇を利用して、モンゴル、ベトナム、カンボジアでの短期ボランティアプログラムにも参加しましたが、そうした体験を経ることで、途上国への思いはますます強まっていったように思います。
JICA東京での任期終了後は、外務省国際協力局内の日本の国際協力NGOへの資金協力部署で、期間業務職員として現地での事業終了後の審査や精算業務に携わりました。その後JICA海外協力隊にコミュニティ開発隊員として参加し、ウガンダでの農業支援活動(稲作技術向上)に従事しましたが、私が活動で注力したのは、カウンターパートである農業普及員(現地農協所属の農家への技術指導者)のキャパシティビルディングで、農家の手本となる手法や技術を用いた大規模なテスト圃場の運営や、JICA技術協力プロジェクトにおいて実施される稲作研修への参加、農家へ向けた技術研修の企画・実施等、カウンターパートと共に走り回りました。元々彼は、精米機のオペレーターだったのですが、この2年間で着実に農業普及員として農家に頼られる存在になっていきました。小規模な草の根レベルの活動ではありますが、人づくりに直接携わり、そのやりがい、楽しさを肌で感じる、私にとってはとても大きな経験だったと思います。