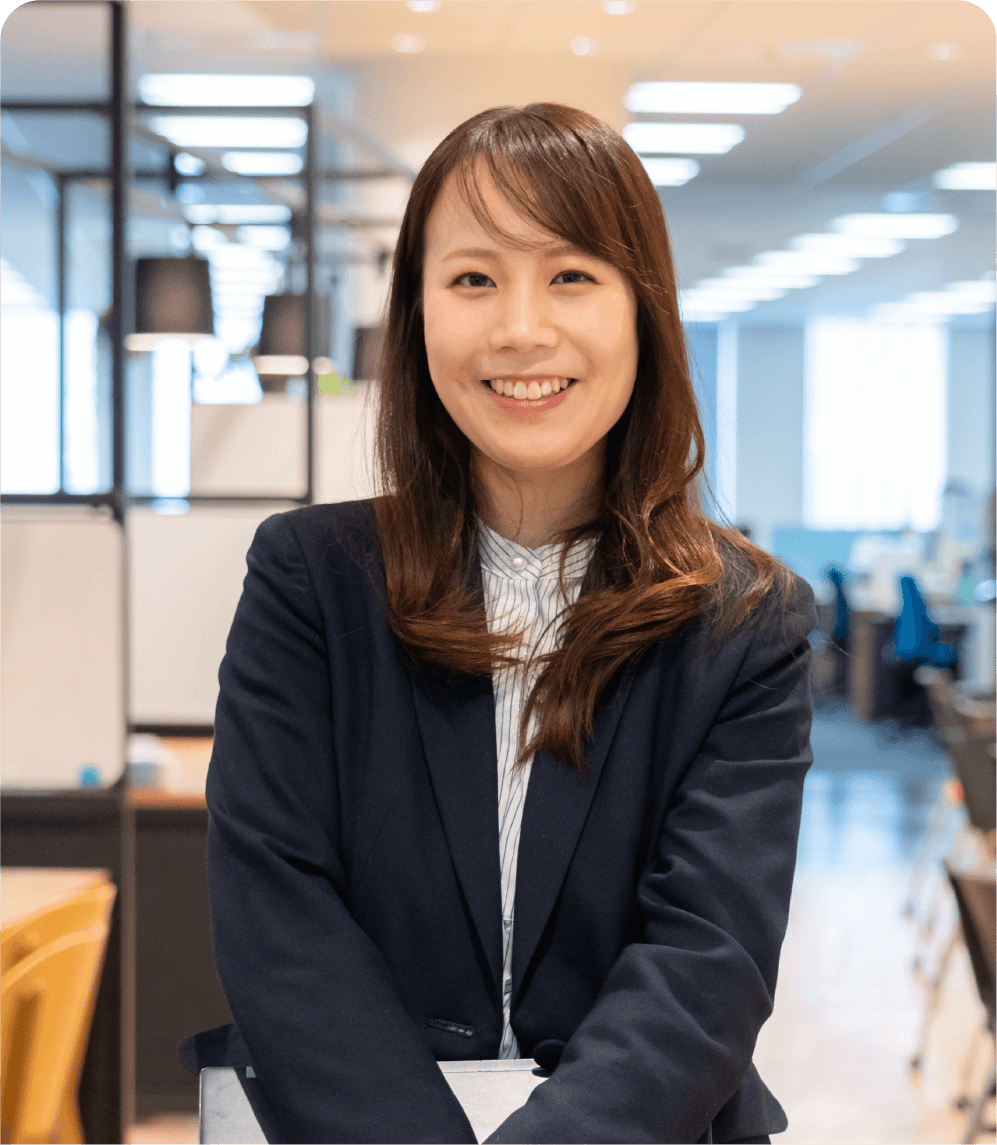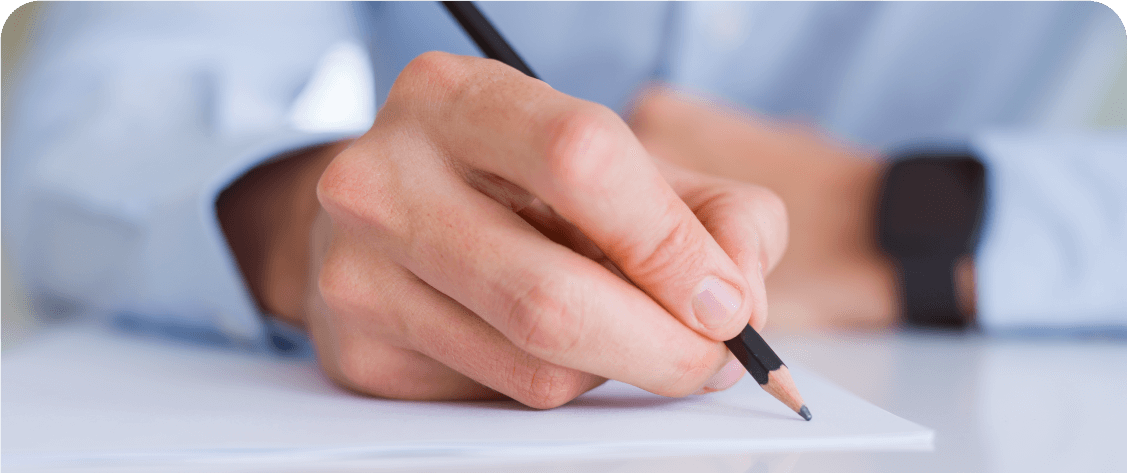祖父の過酷な体験の
記憶をきっかけとして
私は幼い頃に祖父から、第二次大戦後に旧ソ連軍の捕虜となった過酷な体験の話をよく聞いていました。一般的にはあまり知られていませんが、戦後旧満州等で捕虜になった日本人の一部は、シベリア経由でモンゴルに送られ、ウランバートルの都市建設等、酷寒下に過酷な労働を強いられたのです。当時の環境は苛烈を極めたようで、90歳を超えてもなお、16歳から20歳までを過ごした当時の記憶が蘇って眠れない夜を過ごす──そんな祖父と身近に接して来た私は、次第に強制労働や児童労働といったテーマに関心を持つようになり、大学で学ぶ頃には、労働問題に軸足を置きながら国際協力の世界で働いてみたいと考えるようになりました。カンボジアの孤児院で日本語を教えるボランティアに参加したり、スイス、ジュネーブに本部を置く国連機関の一つ、国際労働機関(ILO)でインターンに参加したり、といった経験も重ねましたが、ILOのインターンでは、南アジアの児童労働について2ヶ月間ほど集中して学び、最終的には発表を行うという、とても鍛えられる時間を過ごすこともできました。ですから、就職に際してはもちろん、国際協力の世界に進みたいという思いも強かったのですが、労働問題に関心を持っているのであればやはり、ファーストキャリアとして民間企業で“働く”経験を持つことが必要なのではないかと考えるところもあり、最終的には、民間企業に就職することを選択しました。
就職先として選択したのは大手インターネットサービス企業でしたが、この会社で私が配属となったのは、立ち上げ間もない段階にあったモバイル通信事業。後発として事業参入したため、戦略的にも特に緊急性が高かった通信基地局の整備が、私の部署の担当業務でした。モバイル通信事業の基本インフラとなる基地局の整備は、事業を成立させるうえでの前提となるものですから、私たちに課されたミッションはとても重要なものです。例えば、決められた期間内に決められた数を稼働させるという明確な目標のもとに、全国の営業担当や工事会社の方々と綿密な計画を練り、設置場所を探して地権者の方に営業をかけ、許可がとれれば設置工事を行うということを繰り返していくわけですが、当初は不可能に思えた目標も、チーム一丸となって業務に邁進していくことで、なんとかやり切ることができました。こうした、一見無謀に思えるような目標を数年間にわたってクリアし続けてきたことで、目標達成へのプロセスをしっかりとプランニングし、確かなチームワークのもとに全力で仕事に取り組めば、決して不可能なことはない……そうした実感を持つことができたのは、前職におけるとても大きな収穫でしたし、現在も私の糧になっています。
しかし、こうした日々の業務に追われているうちに、学生時代に考えていた“本当にやりたいこと”──国際協力の世界からどんどん遠ざかってしまっていることにジレンマを感じていたことも確かです。そんな時にJICA採用ホームページで見つけたのが、現職ポストの求人でした。社会人経験も浅く、国際協力の知見も経験もないなかでしたが、先ず国際協力の世界の入り口、スタートラインに立ちたい……そうした想いに押されて応募し、現在に至っています。専門嘱託としての働き方は、自分自身のライフプランにあわせて選択をしたものですが、JICAには多様な働き方があり、業務内容や働く環境を事前にすり合わせたうえで挑戦できることは、とても魅力的だと思っています。