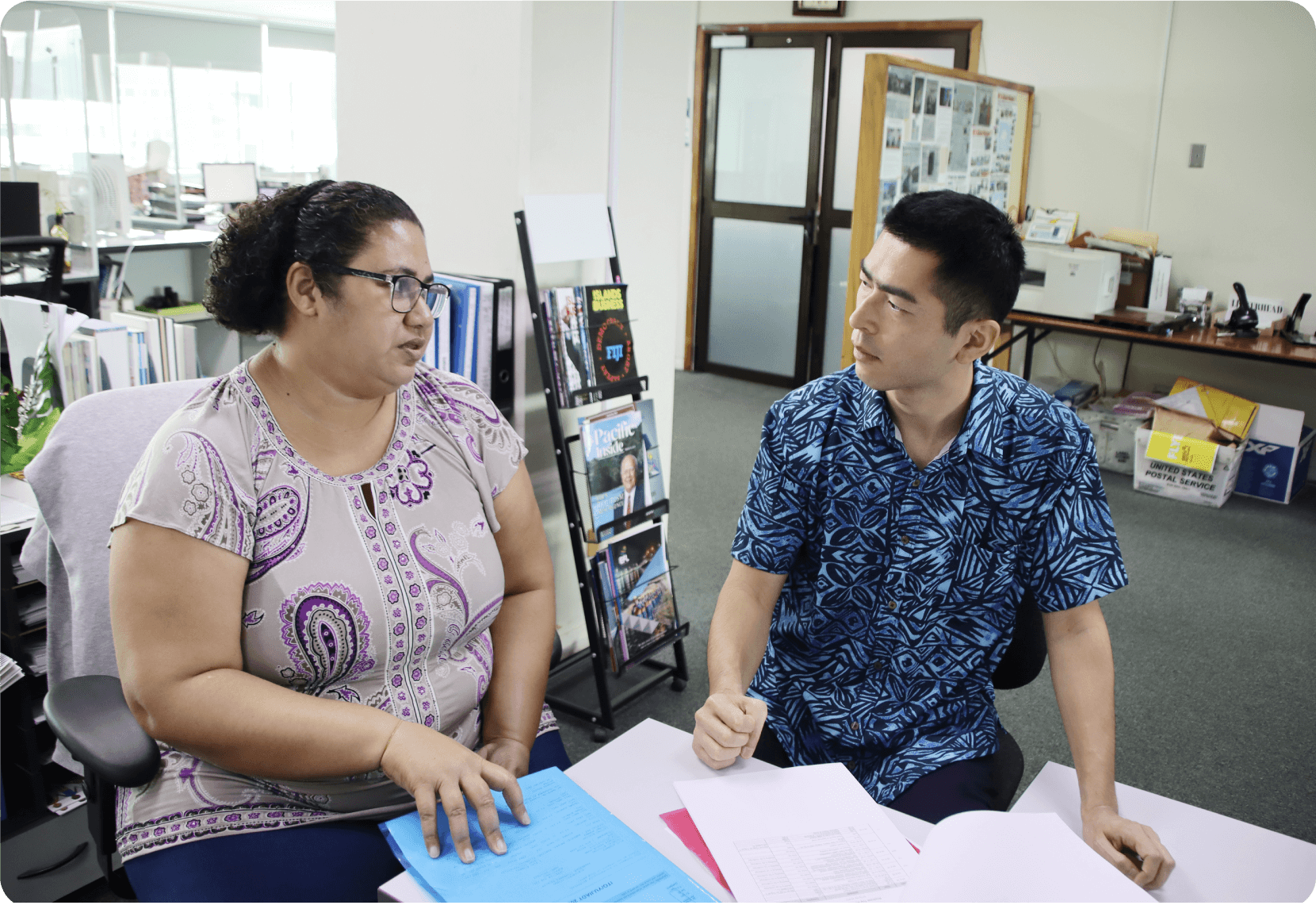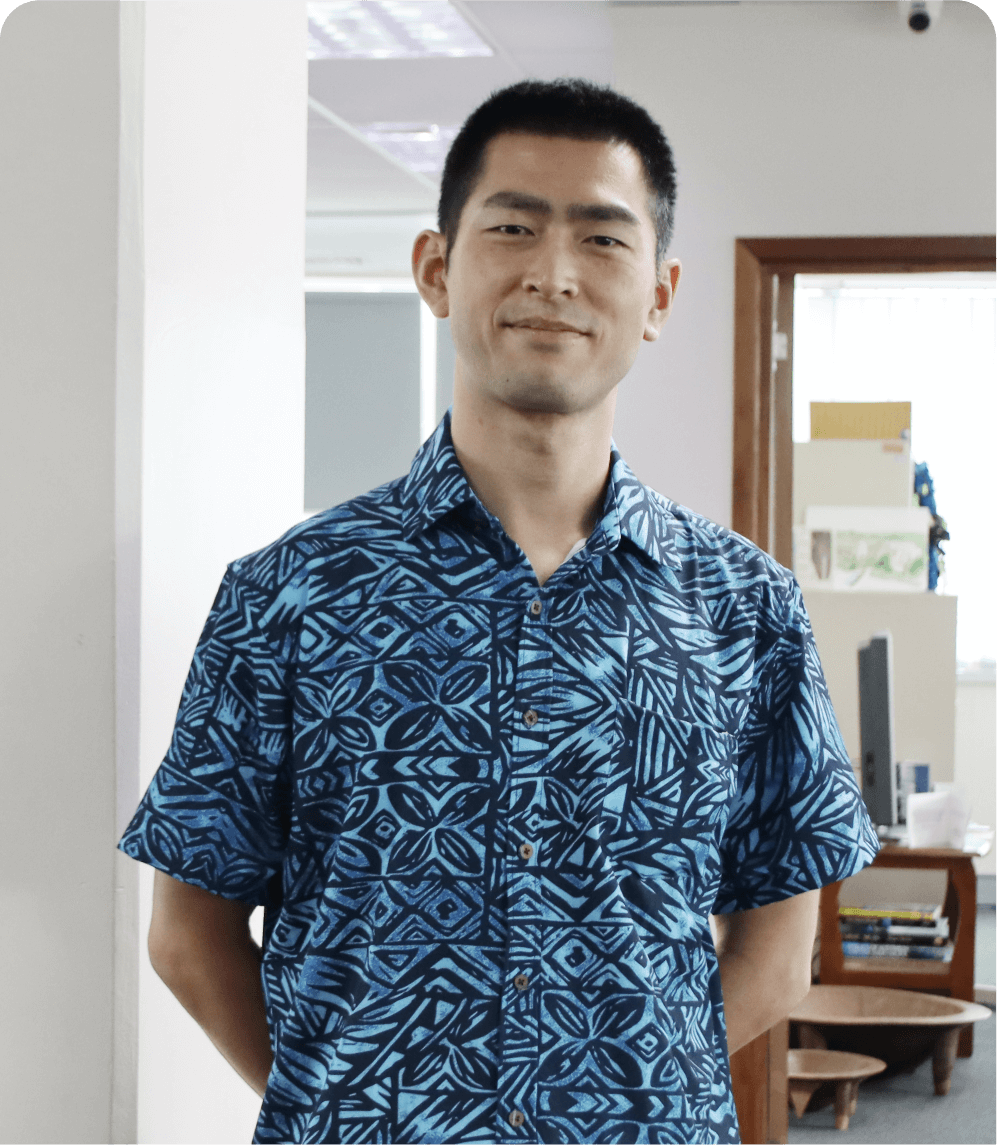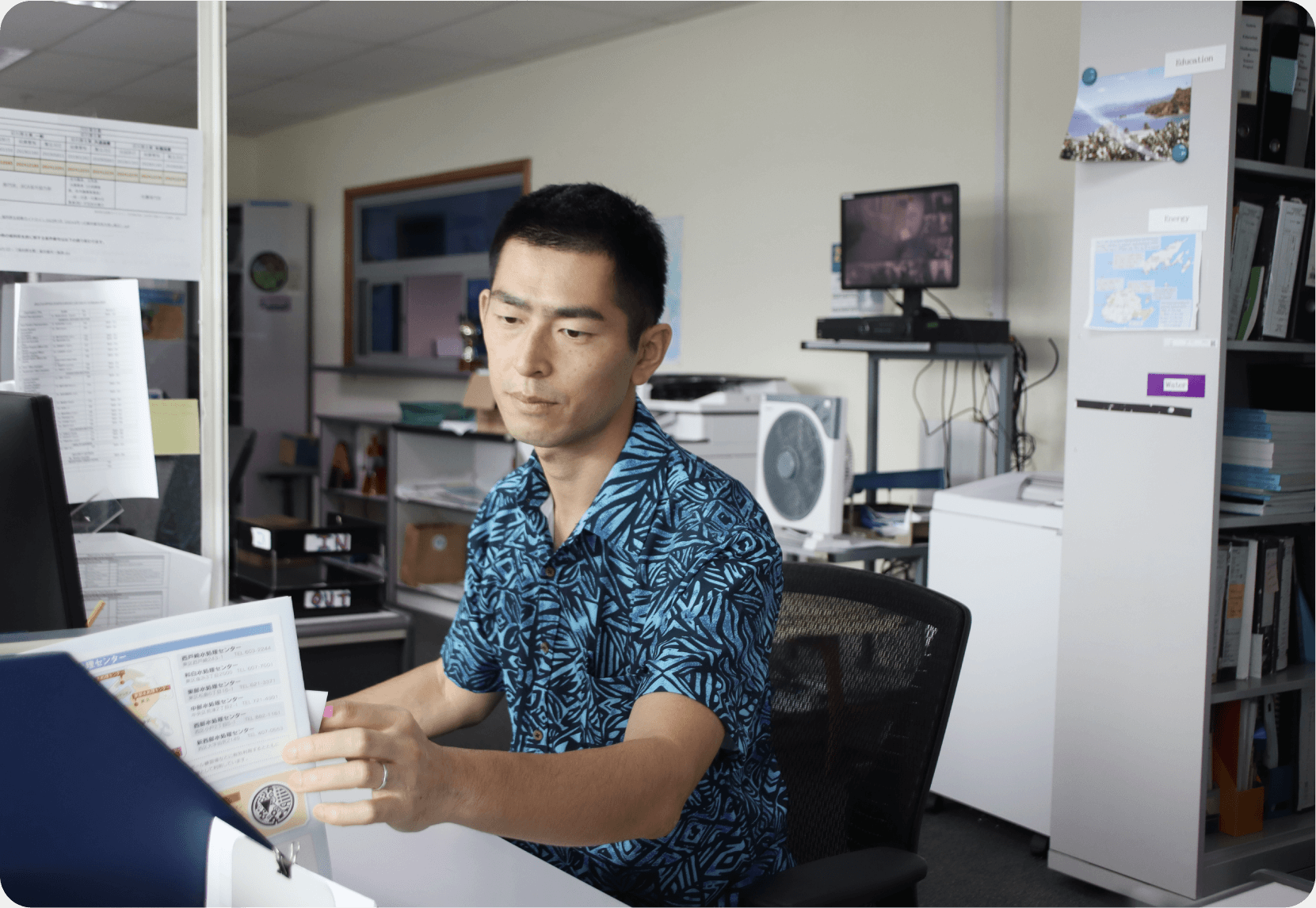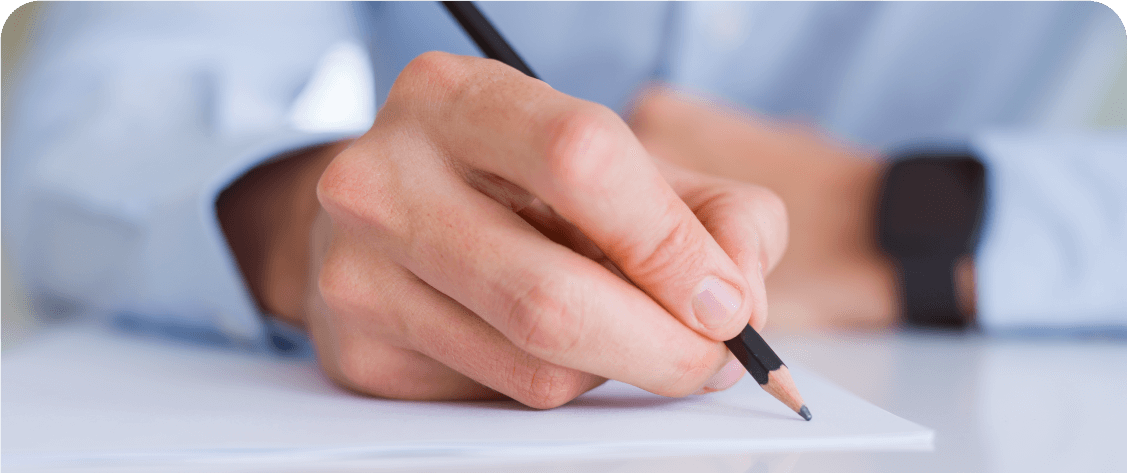国際協力を
さまざまな視点から捉える
貴重な経験をステップに
2007年、大学1年の頃に、フィリピンでのボランティア活動に参加したことがありましたが、そこで目にした光景は、私に国際協力への関心の扉を開く非常に鮮烈なものでした。“スカベンジャー”と呼ばれるゴミ山周辺に暮らす人々とその子どもたちが、昼間から学校にも行かず、生計を立てるためにゴミを拾っている。生まれた場所、環境が違うだけで、理不尽な不平等の中に置かれている人たちがいる──こうした現状を変えていくために、自分には何ができるだろうか? この時に兆した問題意識に動かされて、大学3年の時には再びフィリピンでコミュニティ開発や人権保護活動を行うNGOに参加し、卒業後は、英国University of Sussexの大学院に留学して教育と開発について学びました。大学院卒業後は国際協力の道に進みたかったのですが、開発コンサルタント等には縁に恵まれず、2015年にODA関連業務を広範に手掛ける専門商社に就職しました。この商社での経験は、国際協力をまた別の視点から捉えるうえで非常に有意義なものだったと思います。当時担当したのは、さまざまなODA事業に関連した資機材調達、アフリカ向け食糧援助プロジェクト等。JICAや外務省が発注元となる入札に参加して、案件を受注し、対象国に資機材、食糧等を輸出するという仕事です。その過程ではもちろん、メーカーやコンサルタントとの調整、意見交換を行うわけですが、ODAに関与するさまざまなステークホルダーの考え方を理解し、案件が成立していくプロセス、全体像を把握するうえでは得がたい経験だったと思います。またこの頃は、資機材の納入、据え付け等で、大洋州、カリブ海諸国、西アフリカ、アジアと20ヵ国くらいに出張しましたが、海外で働きたいという思いを強く持っていた私にとって、これは非常に楽しく、充実した業務でもありました。
環境が一変したのは、言うまでも無くコロナ禍です。2020年1月以降、海外出張はピタリと無くなり、仕事における最大のやり甲斐を失った私は、徐々に転職を考えるようになりました。そんな時に飛び込んで来たのが、一般社団法人国際交流サービス協会が運営している、専門調査員制度の人材募集でした。この専門調査員は、海外の日本大使館、総領事館といった在外公館に勤務し、任国・地域の政治・経済・文化等の研究に従事しながら公館業務の補助を行うもの。海外で働くというのは子どもの頃からの夢でもありましたから、一念発起してこれに応募し、在マーシャル日本大使館のポジションに合格することができました。この在マーシャル日本大使館での業務も、自分にとっては非常に鍛えられる、重要な体験になったと思います。政務・経済・経済協力担当として、政府要人との面談に同席することから、日本政府の外交政策を踏まえた現地での情報収集、経済協力案件の企画立案等に携わりましたが、日本の国益の増進というミッションを追求しながら、外務省、日本政府の考え方にリアルに接することができる。また、在マーシャル日本大使館は、私を含め日本人数名、現地職員数名と非常に小規模な陣容で、だからこそ、任期2年の専門調査員であっても、非常にハイレベルな情報に接することができる。学生の頃から国際協力に惹かれていた私にとって、この大使館勤務時代は、商社の頃とはまた別の意味で、さまざまなことを学んだ貴重な経験であったと思います。