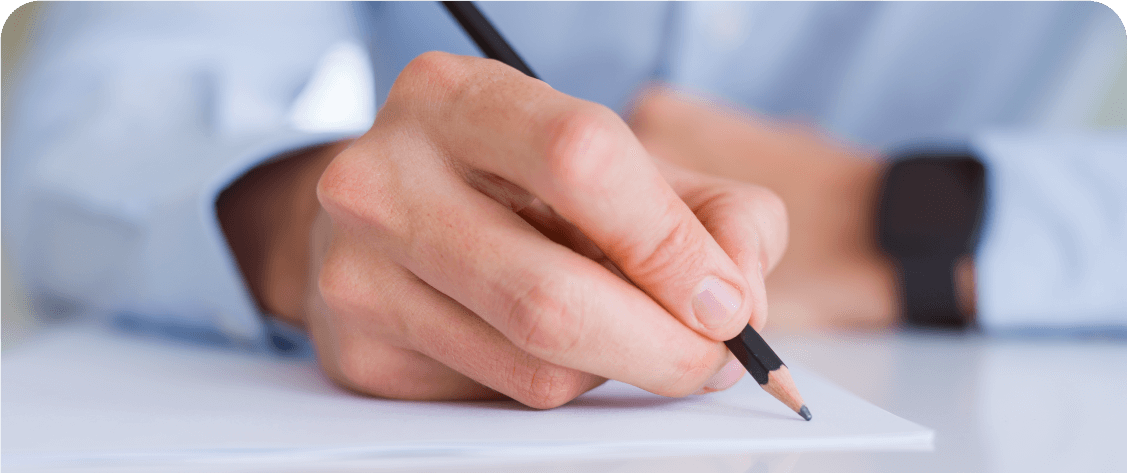チャレンジするうえで
遅すぎるということは決してない
2017年にJICAに入構し、国内事業部中小企業支援事業課(当時、後の民間連携事業部企業連携課)の配属となりましたが、ここは、優れた技術・ビジネスモデル等を持った中小企業の途上国における事業展開支援を手掛けており、まさに、私が最も興味を持っていた事業の担当部門でした。多くの先行投資を伴い、とりわけ多様なリスクが存在する途上国に中小企業が進出するには大きな困難が伴います。JICAはビジネスモデルの検討のために必要な途上国での事前調査、ビジネスモデルの普及実証と、主に二つの取り組みを行っていましたが、私が担当したのは後者。即ち、JICAが一定の予算をつけて当該企業に事業を委託するという体裁で、その企業が持っている技術やサービスが本当に対象国でビジネスになるのかを検証するわけです。もちろんJICAが手掛けるわけですから、なんらかの社会課題の解決に貢献し、かつJICAの支援が終了した後も、サスティナブルに事業を運営できる仕組みを構築していくことが重要なポイントとなります。私は、途上国の社会課題解決に取り組むうえでも、何かを“やってあげる”のではなく、常に相手国と対等の立場に立っていたいとかねてから考えてきました。そして、最も対等な立場を築けるのが、ビジネスとして成立させることではないでしょうか? ここでの仕事は、いくつかの魅力的な企業さんとの出会いもあり、仕事自体は非常にやりがいのあるものでした。と同時に、私自身のテーマを追求していくためには、JICAが手掛ける他のODA事業を俯瞰的に把握できていることが大切なのではないか、とも考えるようになりました。その後、出産〜産休・育休をはさんで、2019年に業務復帰しましたが、その際に技術協力で中核的な役割を果たしている課題部への配属を希望したのも、そうした思いが背景にあったからです。
現在は、希望がかなってガバナンス・平和構築部 STI・DX室に所属しています。STI・DX室は2020年6月に発足した新しい部署で、大きく、途上国のICT分野を支援するICT班と、JICAの組織・事業全体のDX化を進めるDX班とに分かれていますが、私はICT班に所属し、セネガルの国民IDデジタル化に向けた事業化調査や、アジア7ヵ国を対象としたデジタルディバイド解消を目指す基礎調査等に取り組んでいます。例えばセネガルの国民IDデジタル化などは、JICAにとってもまったく未経験の、まさに0から1を生むような事業。プロジェクトを成立させるためには多くの民間企業を巻き込んでいく必要があり、自分にとっても非常にチャレンジングで社会的なインパクトも大きい事業です。こうした経験を積み重ねていくことが、私自身にとっての大きな目標の実現につながっていくはずだと信じています。
育休から復職した直後は時短勤務制度を使って働いていましたが、上司も子育て中のため家庭とのバランスを大事にしていましたし、周囲の理解もあったので、まったく引け目を感じることなく働くことができました。海外出張も1週間以内に限定し、パートナーとも相談のうえで業務に取り組んでいます(※注)。JICAでは、個人の事情・状況に応じてさまざまな働き方の選択肢を持てることが素晴らしいと思いますし、そうした環境が整っているからこそ、本当にやりたいことにチャレンジできていると感じています。
あと一つ、ここでお話ししておきたいのは、挑戦するうえで遅すぎるということは決してないということ。留学を決意した時も、もう遅すぎるのではないかと少し不安を感じていましたが、行ってみると私よりもはるかに年上の学生も多く、年齢や経験を気にすることはその後まったくありませんでした。JICAも、外から来る人材に対しても非常にオープンで、挑戦を後押ししてくれる組織文化を持っていますから、国際協力や途上国に関心がある方は、ぜひ勇気をもって一歩踏み出していただきたいですね。
※注:コロナ禍の現在は、職員の海外・国内出張は、真に必要なもの以外は実施していない。