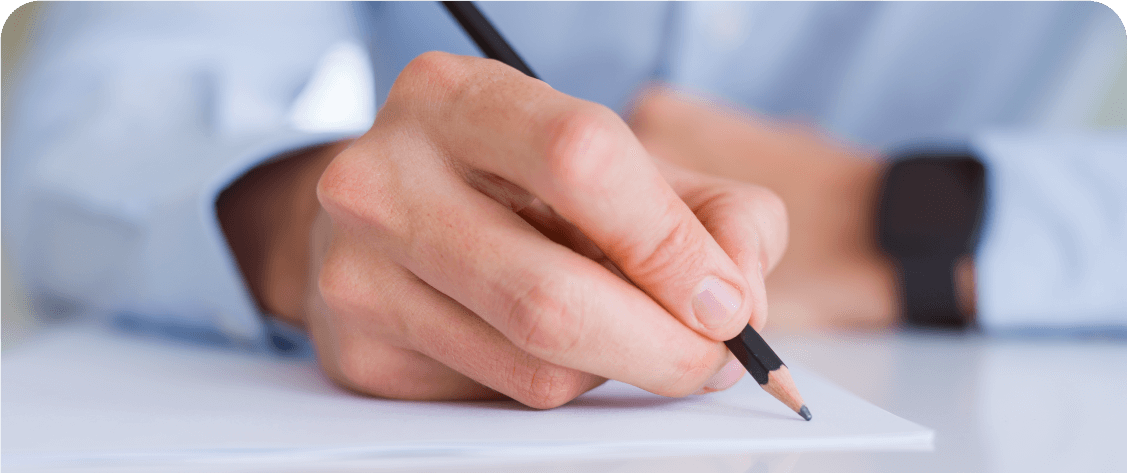“人”を起点にしながら、
さまざまな事業に
チャレンジしていきたい
2020年に協力隊の任期が終わり、帰国しましたが、“国際的な児童福祉の専門家になりたい”という自分の中のテーマが見えていたこともあり、しばらくは、その専門性を獲得するためにNGOで働くか、大学院で学ぶか、といった可能性を模索していた時期もありました。そんな時に、協力隊事務局のDX担当国内協力員の募集が飛び込んで来たのです。これは、前職での経験を活かしながら国際協力の仕事に挑戦できるまたとない機会だと考え、早速応募しました。ゆくゆくは大学院で学びたいという思いもありましたから、有期雇用職制であることはあまり気になりませんでしたね。
国内協力員の頃に担当した仕事のうち大きなものとしては、現在もJICA全体のオンライン学習システムとして利用されている“JICA-VAN”の導入があります。STI・ DX室を中心に起ち上がっていたプロジェクトチームに参加して、システムの要件定義や製品選定といった、JICA-VANのテイクオフに向けたさまざまな業務に参画しました。また、ちょうどその頃はコロナ禍で、JICA全体にTeamsが導入されたタイミングでもありましたが、協力隊事務局全体で情報共有がスムースに行えるようにTeamsの使い方を提案したり、ITを活用した仕組み作り、環境整備等をいろいろと手掛けました。やはり新しく入った人間ですから、積極的に動きながらやるべきことを見つけ、提案して、自ら仕事を作っていくというような働き方をしていましたね。そうして1年ほど活動しているうちに、上司の薦めもあって専門嘱託に職制転換することになったわけですが、部署異動はなかったため担当業務自体が大きく変わったということはありませんでした。ただ、もう少し踏み込んで仕事に関われるようになったことは間違いないと思いますし、何よりも、協力隊の起業支援事業“BLUE”を立ち上げから担当できたことは、自分にとって非常に大きな転換点だったと思います。
協力隊経験者は社会課題に対するアンテナも高く、事業・プロジェクトを推進していくうえでの精神的なタフさも持っている……そうした、協力隊経験者が備えている人間的力、スキルを、日本国内の社会課題を解決する事業創出に活かせるのではないか──そうした仮説からスタートしたのが、この“BLUE”で、私は総合職に職制転換した現在も、引き続きこの事業を担当しています。この事業化に向けたリサーチに着手したのは国内協力員の頃でしたが、事業開発に伴う大変さや面白さを全てひっくるめて体験することができて、まだ足りない、もっとやってみたいという思いが強まっていったことが、総合職にチャレンジしようと考えた直接的な動機だったと思います。また、一緒に働いている職員の方たち一人ひとりが、良い仕事とは何かを必死で考えながら行動しており、その姿、組織文化に感銘を覚えたことも大きかったですね。皆さん本当に泥臭く頑張っていて、こうした地道な作業の積み重ねの先に、かつて私が感じていた、“キラキラした”国際協力の世界がある──国際協力はここから始まるんだということを体感したことが、JICAの一員として仕事を続けていきたいという決意につながっていったのです。
私は本当に、協力隊事業に育ててもらったようなところがありますから、私にとっての国際協力の起点には常に“人”があり、その軸はこれからも持ち続けていきたいと考えています。そのうえで、これからJICAのさまざまな事業、スキームを経験し、自分なりの国際協力観を育んでいけるようなキャリアを築いていきたいと思います。特に、私が協力隊として取り組んだ社会保障の分野はぜひ経験したいですし、国際協力の裏側を支えるバックオフィスの仕事や、まさに国際協力のフロントとなる在外事務所での業務を担当することも楽しみです。将来的には、国際協力が広く日本の文化として根付いていく、その橋渡し役を担う仕事ができたらと願っています。