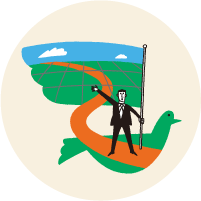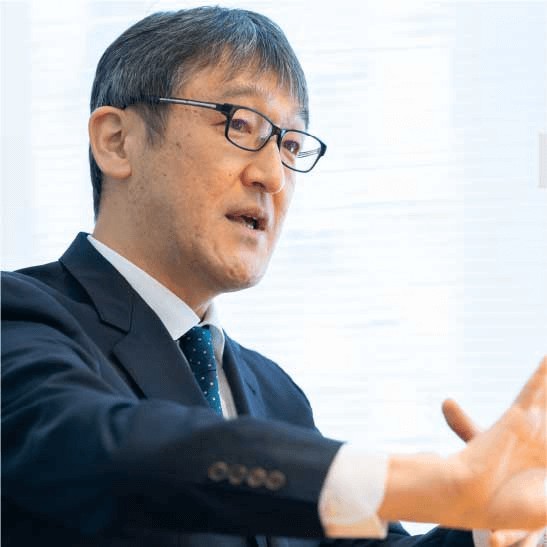JICAの事業の根幹にある、
“人”と向きあう姿勢
小林部長は1992年に大学を卒業され、青年海外協力隊(現JICA海外協力隊)に参加された後に、社会人採用という形で1996年に現在のJICAの前身の一つである国際協力事業団に入団。川淵課長は、1996年に旧OECF(海外経済協力基金、後に合併によって国際協力銀行=JBICとなり、2008年にJICAへと統合)に入行されたということですね。お二人が参画されて以降もJICAはさまざまな変化を重ねて来ていますし、お仕事の中でも数多くの経験を積んでこられたと思いますが、先ず、これまでの現場経験や出会いの中で、お二人が特に印象深く記憶されているもの、また、それが小林さん、川淵さんの中に何を遺したのか、といったあたりからお話をうかがえればと思います。
思いつく沢山のものから、一つに絞るのは難しいのですが、2010年からルワンダに駐在した際に担当したルスモ国際橋の架け替え事業は、JICAの仕事の意義を再確認したというところもあり、とても印象深いものでした。ルワンダは周囲に海が無い内陸国ですが、タンザニアとの国境に位置するこのルスモ国際橋は、タンザニアのダルエスサラーム港からルワンダの首都キガリに至る物流の要衝で、ルワンダ、タンザニア双方にとって、非常に重要な意味を持つものです。老朽化が進み道幅も狭い従来からある橋を、貿易拡大に伴う交通量増加にも対応可能な新しい橋に無償資金協力で架け替える、という事業だったのですが、これは、ルワンダ、タンザニアの2国が実施主体になるため調整が非常に難しく、技術的な難易度も高い。また、当時この2国間にはいろいろと問題が派生していて、少し関係が冷え込んでいたところもありました。そうした中で、日本から現地に入っていただいていた専門家やエンジニアの方々は、ものすごく粘り強くさまざまな調整に当たっていただき、あるときタンザニア側に住んでいたルワンダ人の方々が強制帰国させられるという事態が起こった時も、こうした日本から派遣されていた皆さんが、自らの負担で彼らの生活をサポートする、ということもあったのです。私は、こうした日本人の誠実さ、思いやりというのは改めて素晴らしいなと思いましたし、彼らがプロジェクトの意義、理念といったものに深く共感し、自らの職務範囲を超えて、事業を完遂するために力を尽くしていただいていることにとても感銘を受けました。橋の完成は私が帰国した後だったのですが、完成式典の写真を見ると、さまざまな問題を抱えていた両国の大統領が寄り添って記念撮影に応じていて、これにもとても感動しました。もちろん橋を造るという成果はすごく大切なわけですが、JICAから派遣され現地で働いていただいた方々が、そのプロセスを通じて両国の人々をつなぎ、最終的には国と国の関係もつないでいった……これこそがまさに“信頼で世界をつなぐ”ということだろうと思います。私にとってこのルスモ国際橋の架け替え事業は、人と人をつなぎ、国と国をつないでいく、JICAの事業の役割・意義といったものを再認識した仕事の一つだったように思います。

私もやはり、“人”の大切さを実感した仕事が印象に残っています。入社した1996年は、タイ、バンコクでの地下鉄整備事業へ円借款による支援を開始した年ですが、この時タイ地下鉄公社に派遣されたJICA専門家(今で言う東京メトロに所属)に、建設・運営に関する様々な技術的なご指導をいただき、バンコク初となる地下鉄が2004年に開業しました。タイはその後順調に経済的に発展し、パープルライン、レッドライン、とJICAによる新規路線への支援も続きましたが、2016年に、更なる都市鉄道網拡充のために、バンコク首都圏全体のマスタープランの改定に協力してほしいという要請がありました。そこで日本側でチームを作る際、元JICA専門家にも加わっていただき、打合せのためにバンコクに行ったのですが、その会議には地下鉄公社の総裁も出てこられた。その総裁というのが奇しくも、最初の地下鉄事業を担当されており、元専門家の顔を見るなり「また来ていただいたんですね、是非力を貸してください」と、その専門家の方の手を握り、再会をとても喜んでくれたのです。これはもちろん、この専門家が真摯にタイの地下鉄整備のために尽力されたからこそなのですが、専門性や知見を途上国の発展のために活かしたいという熱意を、20年の時を経て自分がつなぐ役割を果たすことができたというのは、やはりとても嬉しかったですね。その後フィリピンでも都市鉄道の開発を担当し、つくづく感じたことですが、タイやフィリピンの関係者が一貫して求めているのは、まさに小林さんが言う通り、専門家、エンジニアを始めとするJICAのプロジェクトに参加される方々の情熱、真摯な姿勢といったものをひっくるめた“日本のクオリティ”なのです。それを確認できるような場面に出会えることは、この仕事の醍醐味であると思いますし、誇らしい瞬間でもあります。

“人”の想い、情熱、姿勢といったものを途上国の現場につないでいくことが、JICAの事業の根幹にあるものだということ、とても興味深いお話だと思いましたが、お二人の経歴だけを見ても、JICAの組織形態、事業内容が大きく変化していることがわかります。入構以来現在までの間に、社会・世界からのJICAに対する期待、JICAが担うべき役割といったものは変わってきていると思われますか?
もともと別々の組織に入った我々二人がこうして一緒に話していること自体が、変化の証の一つだと思いますし、確かにJICAの組織体制は大きく変わり、事業内容も多様化しました。また、それに伴って職員に求められる姿勢が変わってきていることも間違いないでしょう。しかし、変わらない核となる部分も確実にあると私は考えていて、それは、我々はいつの時代も、途上国の自助努力を後押しするという姿勢で、開発協力に取り組んでいるということ。つまり、日本のODA、JICAの事業は、困っている国、貧しい人を助けてあげるということではなく、途上国自身が自らの課題を自らの力で乗り越えられるように、彼らと同じ目線で、協働しながら、お互いの信頼関係を構築するなかで推進されているということだと思います。それがおそらく、日本/JICAの国際協力の最大の強みなのではないでしょうか。複合的な危機に直面し、課題自体が重層化・複雑化している現代においては、我々が伝統的に実践してきた、一人ひとりと誠実に向きあい、彼らをリスペクトし、お互いの信頼関係を構築しながら事業を進めていくことがますます重要になってきているように思います。他方、近年では、日本国内のグローバル化や多文化共生が待ったなしに進んでおり、JICAの国際協力やそこから得た経験を国内の課題解決や活性化に活用できる機会が増えてきています。これはとても顕著な変化であり、JICAが途上国のみならず、日本を元気にすることにも貢献できる可能性がどんどん広がってきていると思います。
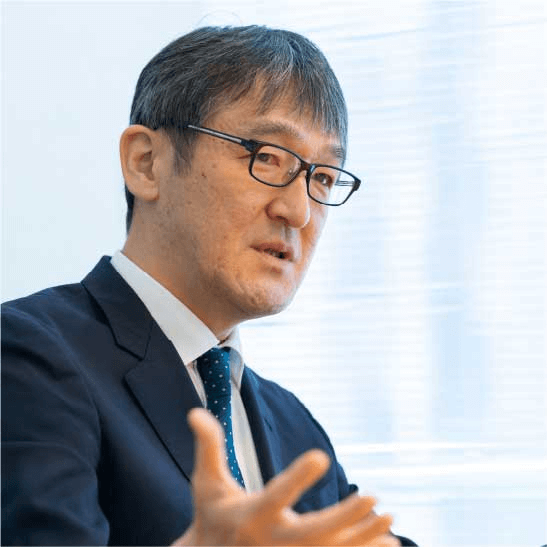
時代の変化というのは本当に凄まじいです。時々刻々と変化する国際情勢に加え、コロナ禍、気候変動、自然災害、高齢化、デジタル技術の進展など、課題も複雑化する一方です。日本だけの課題でもなければ日本だけで解決できる課題でもなく、明日、来月、来年がどういう世界になっているのか見通せないVUCAの時代において、日本と世界の橋渡しをする役割は今後ますます必要になってくる。ですから、まったく新しい課題、ニーズが現れた際に、それに対してプロアクティブに、果敢に向き合える、そうした姿勢を持つことが、JICAという組織、職員には必要になってくるのではないでしょうか。どんどん情報過多になっていく世の中で、「世の中をよくしたい」「為すべきことを為す」というブレない軸を持つことがとても大切であると思います。先に小林さんが言われた“変わらないもの”というのは、その象徴的な一つだろうと思います。