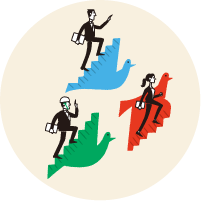子供の成長に寄り添い、
仕事にも打ち込む
2019年2月から子供を伴ってラオスに赴任しましたが、これは、我が家の中では随分前から既定路線と言うか、私は何の迷いもなく、普通にそうしようと考えていました(笑)。
赴任当時娘は小学校一年生でしたが、小さい頃からそういうタイミングが来たら行くよという話をしていましたから、彼女の中でも時間をかけて覚悟を決めたようなところがあったのだろうと思います。JICAの中では、子育て中の女性が子供を伴って海外駐在することは至極当たり前のことですし、幸いにして私の場合、夫や両親も非常に協力的でしたから、この海外赴任自体に特に大きなハードルがあったわけではありません。
ビエンチャンは、車で端から端まで行っても30分もかからないようなこぢんまりした街。私たちは、娘が通うインターナショナル・スクールの近所にあるマンションに居を構え、私はそこから、車で10分ほどのJICA事務所に通うという生活をスタートさせることになりました。こうした、物理的な距離、移動時間の短さもさることながら、感覚的な面でも、ラオスでの暮らしは仕事と生活の距離がとても近く、東京で仕事と子育ての両立のために悪戦苦闘していた頃からは考えられないような、余裕ある日々をおくることができました。それは、私の方でお願いしていたドライバーやお手伝いさんはじめ、マンションの大家さん、事務所のスタッフといったラオス人の方たちが、さまざまな形でサポートしてくれたことも大きかったと思います。また、日本食料理店を営まれている“おかみさん”に娘の弁当を作っていただいたこともありましたが、現地在住だったり他の組織で働いていたりする日本人の方たちにお世話になることも多かったですね。おかげで、子供の成長にしっかりと寄り添いながら、仕事にも打ち込むことができました。ある時娘と話していて、“今日学校で誰々がこんなことをして”と言うので、“どこの国の子?”と私が聞くと、“知らない”と言うんです。要は娘にとっては、国とか人種とかは関係なく、友達は友達だと。私たちは他者とコミュニケーションするとき、無意識のうちに国籍、人種、宗教といったフィルターをかけてしまっているところがありますが、子供はそういうものを全部取り払って、純粋に個人対個人として付き合っている。この時は、娘の中に本当の意味での多様性への理解が育まれていることを感じ、ラオスに連れてきて良かったとつくづく思いました。
仕事面では、次長としてJICAがラオスで実施しているさまざまな事業や海外協力隊事業のマネジメントを担当しましたが、コロナの流行が始まってからは隣国のタイやベトナムとの国境が閉じ、国際定期便の運航も停まってしまいましたから、移動手段がなくなる前に協力隊の隊員や専門家が日本に帰国するオペレーションはとても大変でした。また、困難な状況の中でラオス政府の方たちが、JICA、日本をさまざまな形で頼りにしてくれたのは、本当にありがたいことだなと思いました。コロナ禍によって顕在化してきた問題について、他のどの機関、国でもなく、この問題についてはJICAに相談に乗って欲しいと言われる……。これはやはり、JICAが長年にわたって築いて来た信頼の賜であり、国と国のつながりは人と人のつながりの上にあることを強く感じると同時に、JICAの仕事の意義の大きさに、背筋が伸びる思いでもありました。