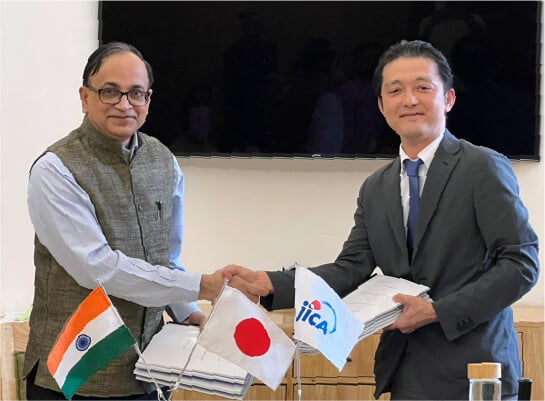“植林”の次を目指す事業を
インドは、中国、米国に次ぐ世界第3位の温室効果ガス排出国であり、その環境政策、気候変動対策は大きな注目を集めている。そうしたなか、2021年に英国・グラスゴーで開催された「国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)」におけるモディ首相の演説は、少なからぬ驚きを世界に与えるものだったと言えるだろう。それまでインドは、温室効果ガス排出ゼロを達成する期限目標を明示してこなかったが、ここでモディ首相は、2070年までに排出ゼロを達成することを明言。これも踏まえ、インド政府は2022年、パリ協定に基づく「自国が決定する貢献(NDC : Nationally Determined Contribution)」(※注)において、2030年までにCO2排出量を45%削減し、同じく2030年までに、25〜30億トンの二酸化炭素吸収源となる森林を造成していくという目標も提示。俄に気候変動への取り組みを加速させている感があるが、そこには、自然災害大国としての切実な危機感や、多様性に富んだ生態系を擁する国土を保全していこうとする、国家としてのテーマも深く関わっていることは間違いないだろう。
インドは、国土の85%がサイクロン、洪水、土砂災害といった自然災害に対する脆弱性が高いとされ、気候変動によってこうした災害が激甚化していく懸念も高まっている。また、世界で36カ所のみ指定されている“生物多様性ホットスポット(人類による破壊の危機にさらされている、生物多様性が非常に高い地域)”が国内に存在するなど、自然環境破壊に対する危機意識も強い。こうしたインドの問題意識に寄り添い、既に1990年代初めから、植林を始めとするさまざまな協力を行ってきたのがJICAである。ラジャスタン州、ナガランド州、カルタナカ州、グジャラート州……JICAが植林、生物多様性保全事業を手掛けてきた地域は極めて広範囲に及ぶが、インド最南端、タミル・ナド州において2022年からスタートした新たなプロジェクトは、インドとJICAの協働によって展開してきた森林事業をまた新たな次元に導く、画期的なものであることは間違いない。
「タミル・ナド州での事業は今回が4回目になりますが、かつてはシンプルに、植林面積の拡大を追求していたようなところがありました。ただ、はげ山だったところが本当に豊かな緑に覆われるようになったというように、これまで手掛けてきた事業は目覚ましい成果を挙げてきたわけです。また、JICAは自分たちがやりたいことだけをやるのではなく、インド側の要望もしっかりと聞き入れたうえで、いい案件を作り上げていく努力を惜しまない……そうしたJICAへの評価、信頼の積み重ねが、今回の案件につながってきていることは間違いないでしょう。インド側としても、新しい課題が出て来た時に、先ず相談すべきはJICAだろう、という意識を持ってもらえています」
 松野下稔
松野下稔このように案件成立の経緯を説明するのは、南アジア部南アジア第一課に所属する松野下稔。2009年に入構した松野下は、最初の配属が現在と同じ南アジア第一課で、新人時代にも、タミル・ナド州における植林・生物多様性保全事業を担当している。「JICAへの評価、信頼の積み重ねが、今回の案件につながってきている」という言葉は従って、松野下の“実感”の表現でもあるのだ。そして、松野下が言う“インド側の新しい課題”に応えていくために、100億円以上の円借款事業として動き始めたプロジェクトが、ここで紹介する「タミル・ナド州気候変動対策生物多様性保全・緑化事業」なのだ。
 松野下の背景、緑が生い茂っているのが、新人時代に担当した事業で植林されたエリア。
松野下の背景、緑が生い茂っているのが、新人時代に担当した事業で植林されたエリア。※注……パリ協定(2015採択、2016発効)においては、全ての加盟国が温室効果ガスの排出削減目標を「自国が決定する貢献(NDC)」として、5年ごとに提出、更新する義務がある。