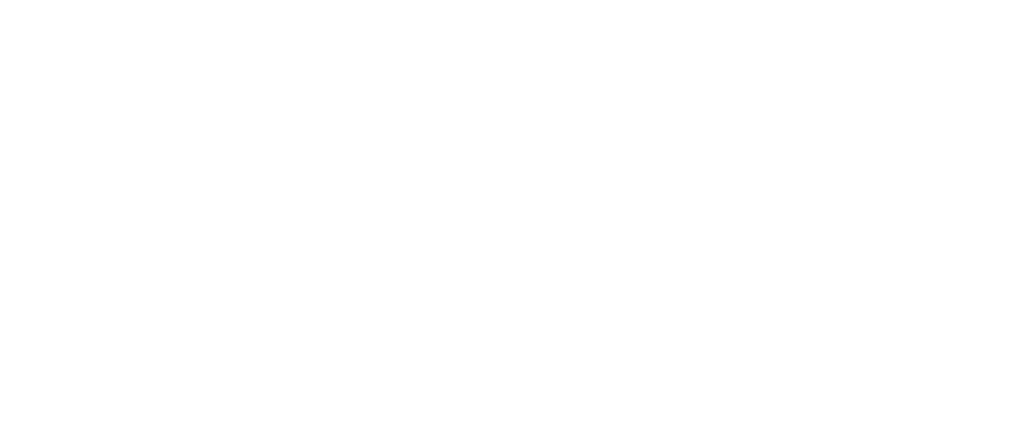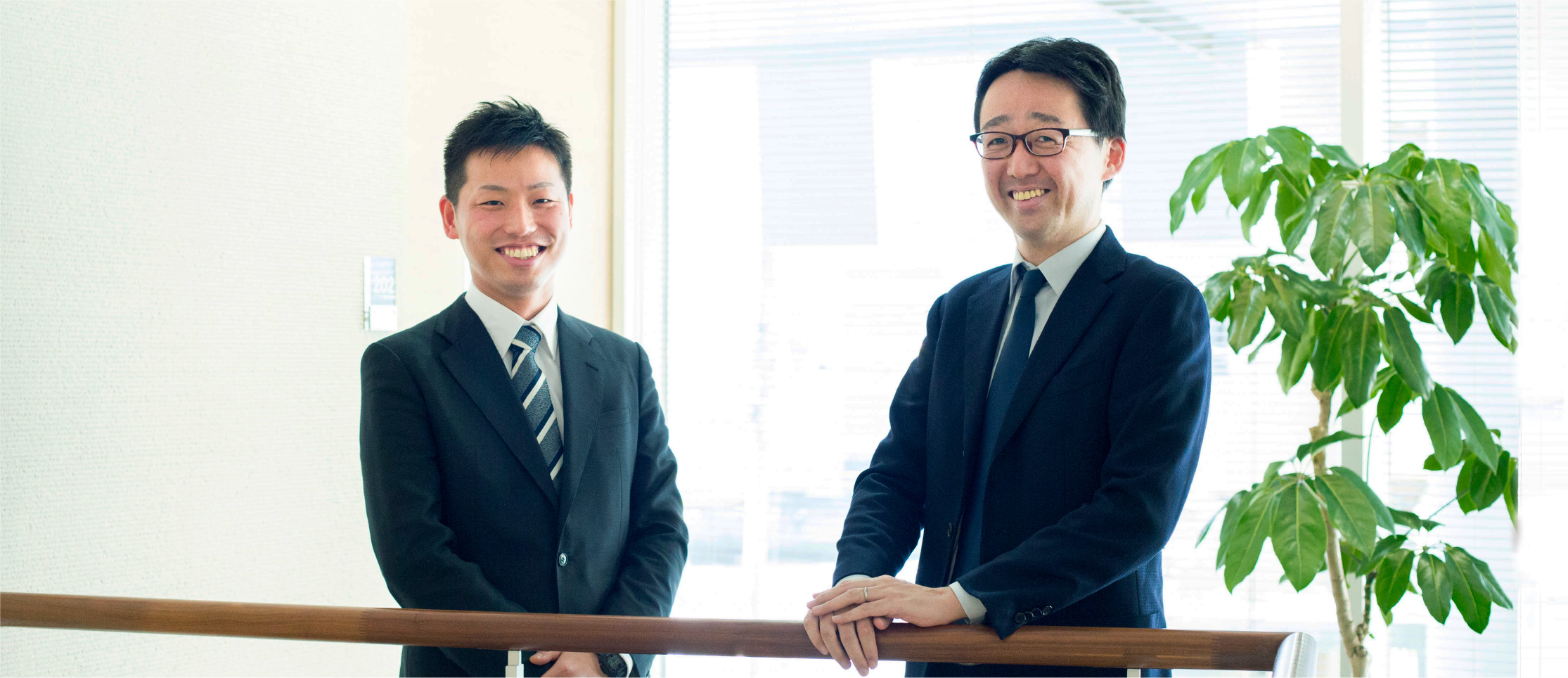全ての事業のベースとなり
開発協力の入り口となる
JICAにおける協力戦略の策定とはどのようなものでしょうか
田中:JICAでは技術協力と資金協力を組み合わせ、開発途上国に対する様々な開発協力事業を実施しています。どの国に対してどの支援メニューを用いるか、そのテーマや規模、協力形態などのアプローチを決める拠り所となるのが、支援国ごとに策定に取り組んでいる「国別分析ペーパー(JICA Country Analysis Paper : JCAP)」。JCAPがJICAの開発協力事業の戦略ペーパーです。協力戦略を医療の話で例えると、患者さんが「支援する対象国」で、医師が「JICA」、治療方針が「協力戦略の策定」に置き換えることができるかもしれません。ケガや病気に苦しんでいる患者さんに担当医が問診をしたり、様々な検査をしたりして原因を突き止め、治療方針を一緒に探っていくようなものです。その検査項目に当たるのが、JICAが収集する相手国についての政治状況、マクロ経済データ、保健医療・教育などの社会開発指標などです。また問診で過去の健康履歴を確認し、医師が患者さんに最適な医療を提供するように、その国を取り巻く環境の変化や外交情勢から、その国が今後はどのような課題に直面することになるのかを考え、より効果のある開発協力を提案していくことを目指しています。今だけ元気になるのでなく、長い目で安心して生活できる体になってもらうことに近いと思っています。例えとして少し身近な話を用いましたが、決して医者が上、患者が下、という捉え方ではありません。現代の医療現場でも医師と患者が対等な立場で治療方針を決めていくように、JICAが一方的に協力戦略を決めるのではなく、相手国と共につくり上げていくことが大切だと思います。
小林:いい例えですね。その協力戦略の策定には、まず相手国が何を必要としているのかという「分析」があるわけですが、同時に、われわれJICAが持っている様々なリソースの検討も必要です。リソースがなければ協力はできません。さらに、二国間関係をどうつくっていくのか、日本の外交戦略も意識する必要があります。
田中:確かに開発の観点から協力が必要なことがあったとしても、日本が協力する外交的な意義が伴わなければ実現できない場合もあります。われわれの事業は日本国民の税金を原資としていることから、こうしたことも含めて総合的に検討する視点が、戦略策定の重要なポイントですね。