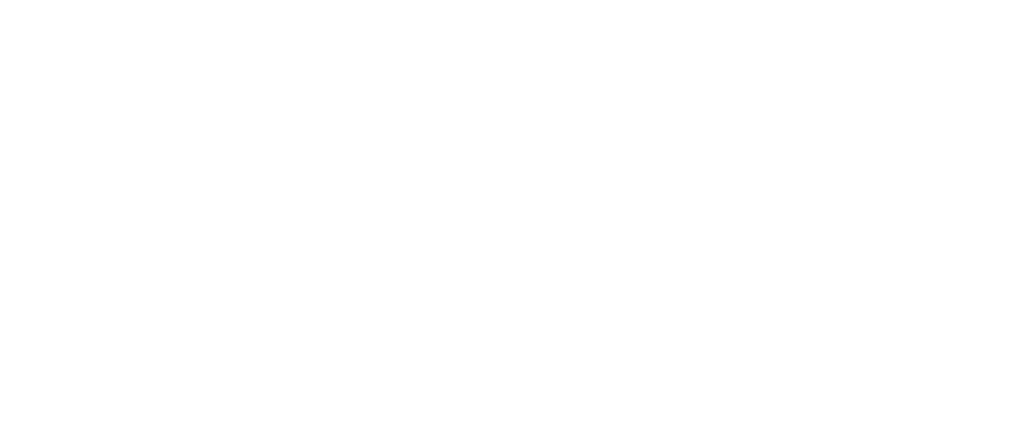「学び(ラーニング)」と
「説明責任(アカウンタビリティ)」の
2つの視点を持って取り組む
まず評価部の業務内容を教えてください
野田:評価部の主な業務である事後評価は、過去に実施されたプロジェクトがどのような効果を上げたかを検証し、そこから得られる学びを通して、プロジェクトのさらなる改善を図る業務です。同時に、日本のODA資金がどのように使われたのかについて、日本国民やJICAを取り巻くステークホルダーに対して説明責任を果たすという役割も持っており、開発協力の質の向上や戦略性の強化を図るための有用な手段にもなっています。また、事業評価は、支援スキームに拘わらず、プロジェクトのPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)と一体不可分の関係にあり、JICA全体ではプロジェクトの事前段階から、実施中、事後の段階、フィードバックに至るまで一貫した枠組みによる評価とモニタリングが実施されています。
岩崎:事後評価をどう進めているか、概要を紹介します。対象になるのはJICAが行う技術協力、有償資金協力、無償資金協力の各事業で、協力金額が2億円以上10億円未満のものを対象にした「内部評価」と10億円以上のものを対象にした「外部評価」の2種類があります。内部評価は、プロジェクトの実施監理を担った現地のJICA在外事務所員が主な担い手となり、外部評価は、より客観性を高める観点から、外部のコンサルタント会社や研究機関などに委託します。いずれの場合も、評価の視点や手法は経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)が定めている「DAC評価5項目」に沿っており、評価期間は、おおむね1年です。結果はすべてWEBサイトで公開すると同時に「事業評価年次報告書」にまとめています。
野田:その中で岩崎さんは、主に内部評価の総括担当として、評価計画や進捗管理、評価の質の向上や結果の活用方法の検討などを担当し、私は部全体の横断業務とともに、後程説明する「インパクト評価」の統括、外務省ODA評価室、世界銀行をはじめとする他ドナー機関の評価・ナレッジ部門など、評価を軸に諸大学との連携などを担当しています。