2019年11月6日
2019年11月4日から6日にかけて、「世界津波の日」(11月5日)の津波避難訓練を中心とする、津波啓発イベントが首都ポートビラで開催されました。
この啓発イベントは、「地震・津波・高潮情報の発信能力強化(Van-REDI)プロジェクト」がカウンターパートであるバヌアツ気象・地象災害局(VMGD)、国家災害管理局(NDMO)と主催し、教育省、ポートビラ市、バヌアツ警察、非政府系国際協力団体のオクスファム、バヌアツ赤十字社、セーブ・ザ・チルドレン(NGO)、バヌアツ障害者協会等に協力して頂きました。
津波の避難訓練は、ポートビラ(プロジェクト主催)、ブラックサンド地区(オクスファム主催)、メレ地区(バヌアツ赤十字社主催)で実施し、日本の支援で設置された防災サイレンや防災看板を利用して、避難経路の確認、津波が発生した際の行動確認等も行いました。
一般的な津波避難訓練は、高台への避難・経路の習熟を目的としますが、ポートビラ初となるこの訓練では、VMGDが「地震発生確認」「津波警報の発令」「避難のためのサイレンの起動」と、同時に「携帯電話に避難のメッセージを発信」し、現場では「サイレンを聞いて避難(訓練)」「高台に移動(経路の確認・習熟)」「津波警報のキャンセル(VMGD)を待っての避難解除(NDMO)」を行いました。地震発生から避難解除までのすべての行動を訓練することで、プロジェクトの成果目標の1つである「VMGD及びNDMO が国民に対して行う防災啓発活動の能力強化」に資することを目標としています。
3日間のイベントには、津波避難訓練だけではなく、ポートビラの2会場で科学・防災展、津波ビデオ放映、津波クイズ等が行われました。啓発イベントへの参加者は、避難訓練に約3,000人、その他のイベントに約1,500人で、合計約4,500人でした。
津波避難訓練に多くの方に参加頂いたほか、防災ビデオショーで放映した2011年3月の東日本大震災の津波の映像に足を止める人も多く、実際の津波の映像が有効な啓発教材となったようです。
| 場所 | 参加者数 |
|---|---|
| ポートビラ(主会場、プロジェクト実施) | 278 |
| ポートビラ(主会場、個人参加) | 150 |
| ポートビラ(主会場第2避難所、個人参加) | 200 |
| メレ地区(赤十字社実施) | 1,138 |
| ブラックサンド地区(オクスファム実施) | 1,233 |
| 合計 | 2,999 |
| 場所 | 参加者数 |
|---|---|
| 開会式典、津波セミナー | 50 |
| 防災ビデオショー(主会場) | 400 |
| 防災ビデオショー(第2会場) | 450 |
| 科学、防災展示ブース(主会場) | 240 |
| 科学、防災展示ブース(第2会場) | 240 |
| 津波クイズ大会(小中高校生対象) | 60 |
| 合計 | 1,440 |
避難訓練において実施したアンケートは次のような結果で、多くの住民が興味深く参加し、年に1~2回の訓練が必要だと答えています。今回利用した30秒のサイレンは、短すぎるという意見が多く、1分、2分、5分等の希望があり、今後の検討が必要と考えています。また今回の避難訓練で何を学んだかという問いには、避難経路、避難訓練の重要性、津波の危険性、という答えが多く出されていました。
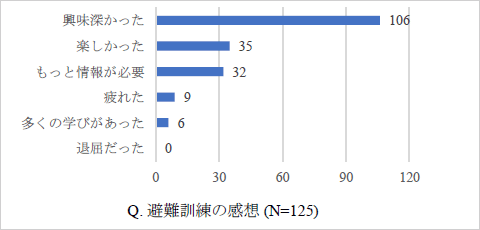 Q. 避難訓練の感想(N=125)
Q. 避難訓練の感想(N=125)
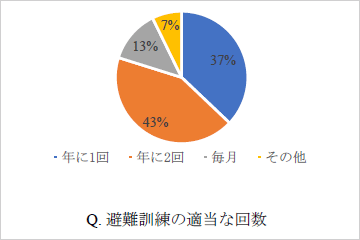 Q. 避難訓練の適当な回数
Q. 避難訓練の適当な回数
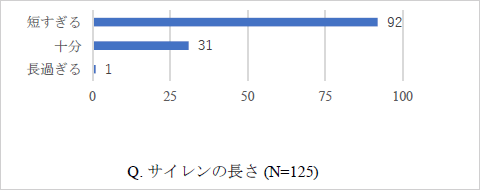 Q. サイレンの長さ(N=125)
Q. サイレンの長さ(N=125)
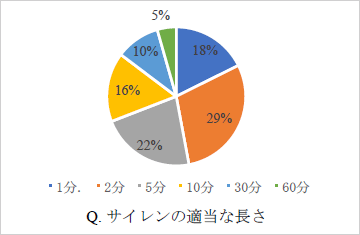 Q. サイレンの適当な長さ
Q. サイレンの適当な長さ
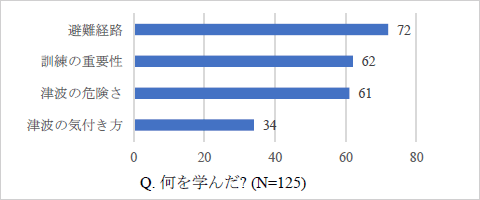 Q. 何を学んだ?(N=125)
Q. 何を学んだ?(N=125)
プロジェクトの津波解析担当である山本雅博専門家は以下のようにコメントしています。
「今回の津波避難訓練は、バヌアツ政府が初めて実施したもので、津波警報の発表をサイレンとSMSを用いて通報し、住民も整然と避難しました。最初の津波避難訓練としては、地元紙が書いているように成功裏に実施されたといえるでしょう。
津波災害から住民の生命を守るためには避難しかありません。津波避難訓練の意義は、実践的な方法で行うことで、津波浸水地域にいる住民がいち早く安全な場所に避難する方法を確認することにあります。繰り返し訓練を実施することによって、地域ごとの課題も明確になり、実効性のある津波避難体制が確立できます。
一方、明らかになった課題も多くあります。住民に対して津波に関する正しい情報を伝達し、適切な行動につなげるため、ラジオを含めた通信網の確立が不可欠です。また、津波警報が適切に発表され、全国の住民がいち早く安全に避難できるシステムを構築するためにも、訓練を毎年継続して実施することがとても大切です。」
プロジェクトでは年に1回の津波避難訓練を実施予定で、来年は首都ポートビラに加え、バヌアツ第2の都市サント島のルーガンビルも候補地としています。今回浮き彫りになった課題をプロジェクトチーム全体で解決した上で、来年のイベントには更に多くの住民に参加して頂き、地震や津波に関する啓発が促進されることを期待しています。
作成:登内 道彦(プロジェクト業務主任)、シュルツ(八坂)由美(長期専門家)

訓練の様子(1)

訓練の様子(2)

訓練の様子(3)