ラオスの森林分野への協力 ~ラオスの森から世界を変える~ 第7回美弥子所長が聞く
2024.09.30
登壇者:
‐ 江頭 英二 (効果的なREDD+資金活用に向けた持続的森林管理能力強化プロジェクト(F-REDD2)専門家)
‐ 古川 洸太郎(JICAラオス事務所所員)
‐ 虫明 悦生(JICAラオス事務所所員、ラオス研究者、ケーン(ラオス笙)奏者)
ファシリテーター
‐ 小林 美弥子(JICAラオス事務所 所長)

JICAによるREDD+準備支援を通して、GCFのREDD+成果支払いプログラム(Result-based Payment, RbP)に申請可能な状況となりました。これはラオス政府の取組及びJICAを含むドナー協力の成果である「2015~2018年における森林保全・回復を通じた温室効果ガスの排出削減」を認めてもらうものです。本成果払いの受領額は、最大で50百万ドルの見込みとなっています。
今回の対談は、GCFの外貨獲得の動きにあわせ、ラオスにおける森林と人々の関係も含めて発信します。
小林美弥子所長(以下、美弥子所長): 本日は、「ラオスの森林分野への協力~ ラオスの森から世界を変える~」という大きなトピックスになっています。プロジェクトの専門家でいらっしゃる江頭さん、それからラオス事務所のご担当の古川さん、ラオスの農村を長年に渡って研究している虫明さんにお集まりいただきました。
まず、虫明さん、ラオスにおける森林の役割と人々との関係に教えていただけますか。以前、ラオスの人々は『鎮守の森』を大切にされているという話も聞きましたが、ラオスの人々の伝統的な森の関わり方から、今のラオスの森林の実態について 教えていただけますか。
虫明悦生(以下、虫明):ラオスの村の多くは、屋敷地を中心に高み(川の上流)側に鎮守の森、低み(下流)側にお墓の森があり、それらの周辺に水田や焼畑、森が広がっています。鎮守の森、お墓の森は、そこの樹を伐ってはならないなど禁忌が多く、大きな森として残されてきました。鎮守の森の中には湧水の泉や沼があることもしばしばで、そこに棲む多くのサルやスッポンが聖なる動物として保護されており、有名な観光地となっているところもあります。また、これは特に低平地の水田民の村に言えることですが、水源林という概念もあり、低地の水田により多くの水が得られるよう生活空間が作られています。森は生活用水の確保ためにも重要ですが、現在、南部の平原地帯で特に重要だった村々の湧水がどんどん涸れてくるという問題がおこっています。これは、湧水点の背後にある水源としての森の減少や劣化が原因であると考えられています。

虫明悦生 JICAラオス事務所所員
さて、ラオスの人と森ということでは焼畑も重要です。焼畑は十分な休閑期がとれれば自然のサイクルにあった合理的な農法で、ラオスで有名な安息香(香水原料)やカジノキの樹皮(手漉き紙原料)などの森林産物も、休閑期を含む長い焼畑サイクルの中で採取されていました。
しかしながら、近年は人口増加などによる休閑期の短縮により、徐々に森林の減少や劣化が進んでいます。また、ラオスはメルクシ松やラオスヒノキ、紫檀などの巨木や高級樹の豊富さで有名でしたが、ひと昔前まで続いた商業伐採や森林を伐開してのプランテーション化などによっても、森林減少・劣化が進んでしまったのです。昔はほとんど聞いたことのなかった山間部での洪水や土砂崩れ、土石流といった災害も増えています。

ラオスの伝統的な村の様子。集落の右後ろにあるのが鎮守の森。

鎮守の森の湧き水
美弥子所長:ありがとうございます。ラオスでは、森と人々は共にあり、森は水とともにありで、信仰の対象でもあったのですね。JICAとしても長年、森林保護の観点から、2004年からラオス北部6県における焼き畑抑制のための森林管理、住民の生計向上の支援を実施していました。
現在は、気候変動に応じたREDD+という国際的な枠組みの中でプロジェクトを実施しています。このプロジェクト支援について、専門家の江頭さんに、効果的なREDD+資金活用に向けた持続的森林管理能力強化プロジェクト(F-REDD2)の成果や課題を教えていただければと思います。
江頭英二専門家(以下、江頭専門家):虫明さんがお話してくださったように、鎮守の森あるいは持続的な農村の生活があったところに、人口増加やその他の経済な要因で、森林が減少していきました。
JICAを含むドナーは2000年前後から、農村の参加を通じた森林あるいは持続的な土地利用を支援してきました。その中で公共財としての森林は公的な資金で保全していくことが一定程度必要だろうという議論が出てきましたが、公共財政が脆弱なラオスでは簡単にはいかないジレンマがありました。そこに近年、REDD+という国際的なメカニズムが登場して期待されています。
REDD+は、途上国が森林の保全を進め、温室効果ガスを減らすことで、その減らした成果に対し、先進国からの拠出金をもとにした資金機関からお金を支払われるものです。気候変動の緩和に森林が果たせる大きな役割を前にして、多くの森林を有する途上国の厳しい財政に頼るのみでなく、先進国から途上国への資金の 移転により森林保全等を成し遂げようという枠組みです。
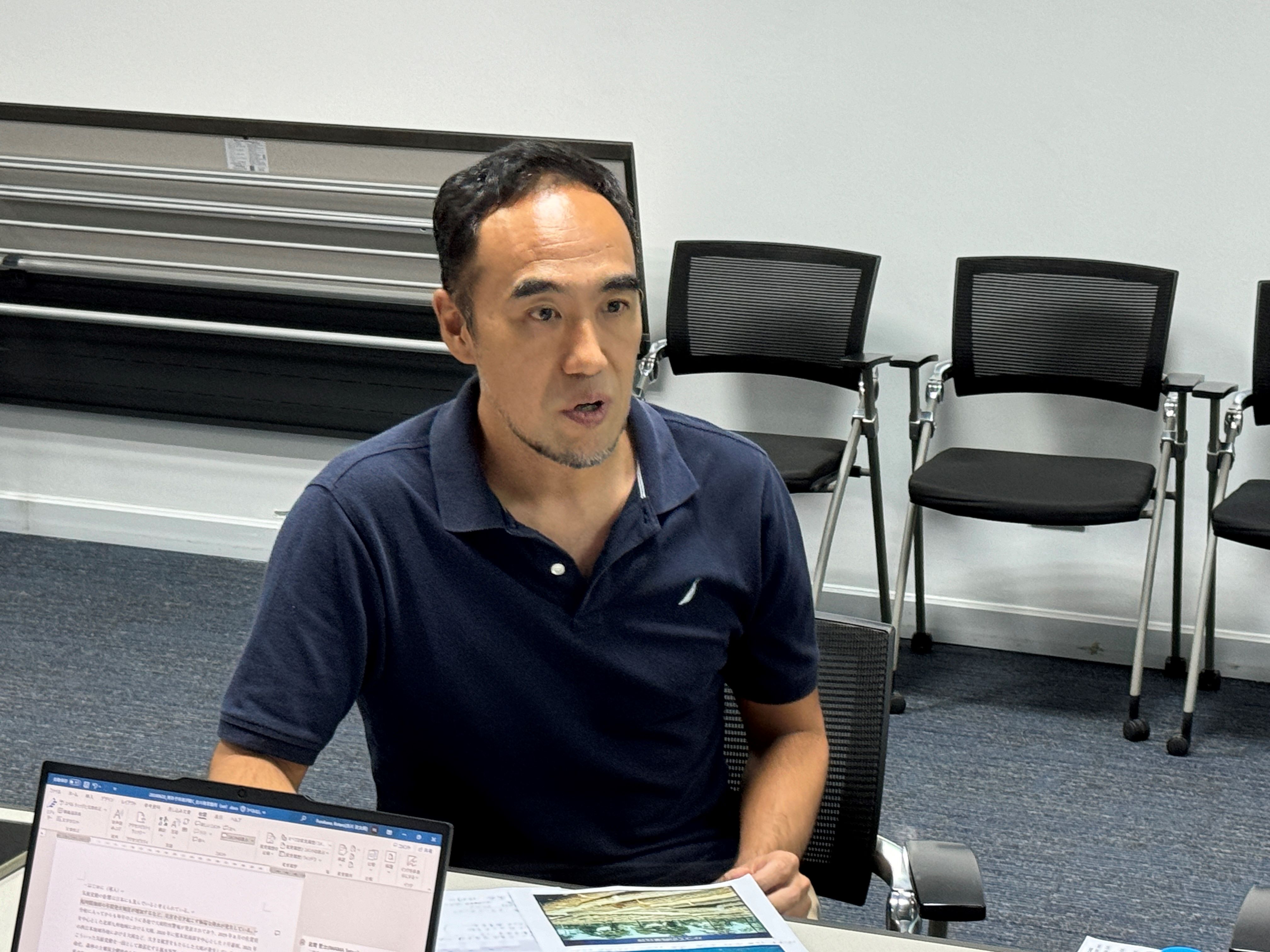
江頭 英二 効果的なREDD+資金活用に向けた持続的森林管理能力強化プロジェクト(F-REDD2)専門家
REDD+によって、住民参加型の自然管理に資金が入り、取り組みが促進され、促進された結果また森林保全が 進み、さらなる資金が入るという循環を作り出そうとしています。
例えば、世界銀行が運営しているFCPF炭素基金からは、REDD+のメカニズムを通じて約1,600万ドルの支払いがラオス北部6県の森林保全活動に充てられる段階になっています。これにはJICA森林セクターが過去に支援してきた地域が含まれており、今後この資金を使って森林保全の循環を進めるために政府の取り組みが進められています。
REDD+で資金を得るためは、透明性と正確性を持ってその成果である温室効果ガス排出削減量の計測を行い、報告する必要があるので、非常に時間がかかる作業です。F-REDD2プロジェクトでは、REDD+の資金を獲得するために、この温室効果ガス排出削減量の測定と計算を行い、国際的な要求を満たす形で報告することが、大きな柱になっています。
また、本プロジェクトの前フェーズでは、衛星データを使い、より低コストで、より早く、より精度の高い準リアルタイムの森林モニタリング方法を開発しました。これは、Provincial Deforestation Monitoring System (PDMS)と呼ばれ、他のドナーからも連携の要望を受けています。実際に、JICAが協力したルアンパバーン、ウドムサイ、サワンナケートの3県の他に、12県で他のドナーとの連携による支援が進められています。このような展開を受けて、 農林省は2024年5月にPDMSを国の公式な森林モニタリングツールとして採用することを決定しました。これにより、プロジェクト成果の持続性に大きな後押しになると期待されています。
美弥子所長:ありがとうございます。気候変動にかかる日本の取り組みも伺いたいと思います。本日は、林野庁からJICAラオス事務所に出向しておられる古川さんがいらっしゃいますので、 日本の森林林業分野の国際協力や政策について、お話しいただきます。
古川洸太郎(以下、古川):林野庁では、 途上国における森林減少・劣化の抑制を目的とした事業を行っています。例えば、日本が持つ技術や知見を活用した持続可能な森林経営への貢献、民間企業の途上国における森林づくりの促進に取り組むほか、本邦企業の森林の防災・減災に係る技術を海外展開できるような体制作りを目指し、そのための日本の技術者の育成に取り組むといったような事業を行っています。
特にラオスについてお話しすると、日本政府ではJCM (Joint Crediting Mechanism)という 2国間クレジット制度を推進しています。日本企業による途上国への投資を通じて、日本の優れた脱炭素技術やインフラの普及や、緩和活動を途上国で実施することで、相手国の温室効果ガスの排出削減や吸収の点で貢献しようという枠組みです。このJCMでも、REDD+を行うことが可能になっています。これはJCM-REDD+と呼ばれており、ラオスにおいても、このJCM-REDD+のプロジェクトが1件実施されています。プロジェクトの実施によって、ラオスにおける温室効果ガスの排出削減・吸収に貢献するとともに、 日本側はその貢献度に応じてクレジットを獲得して、日本の排出削減目標 にも寄与できるというような枠組みになっています。
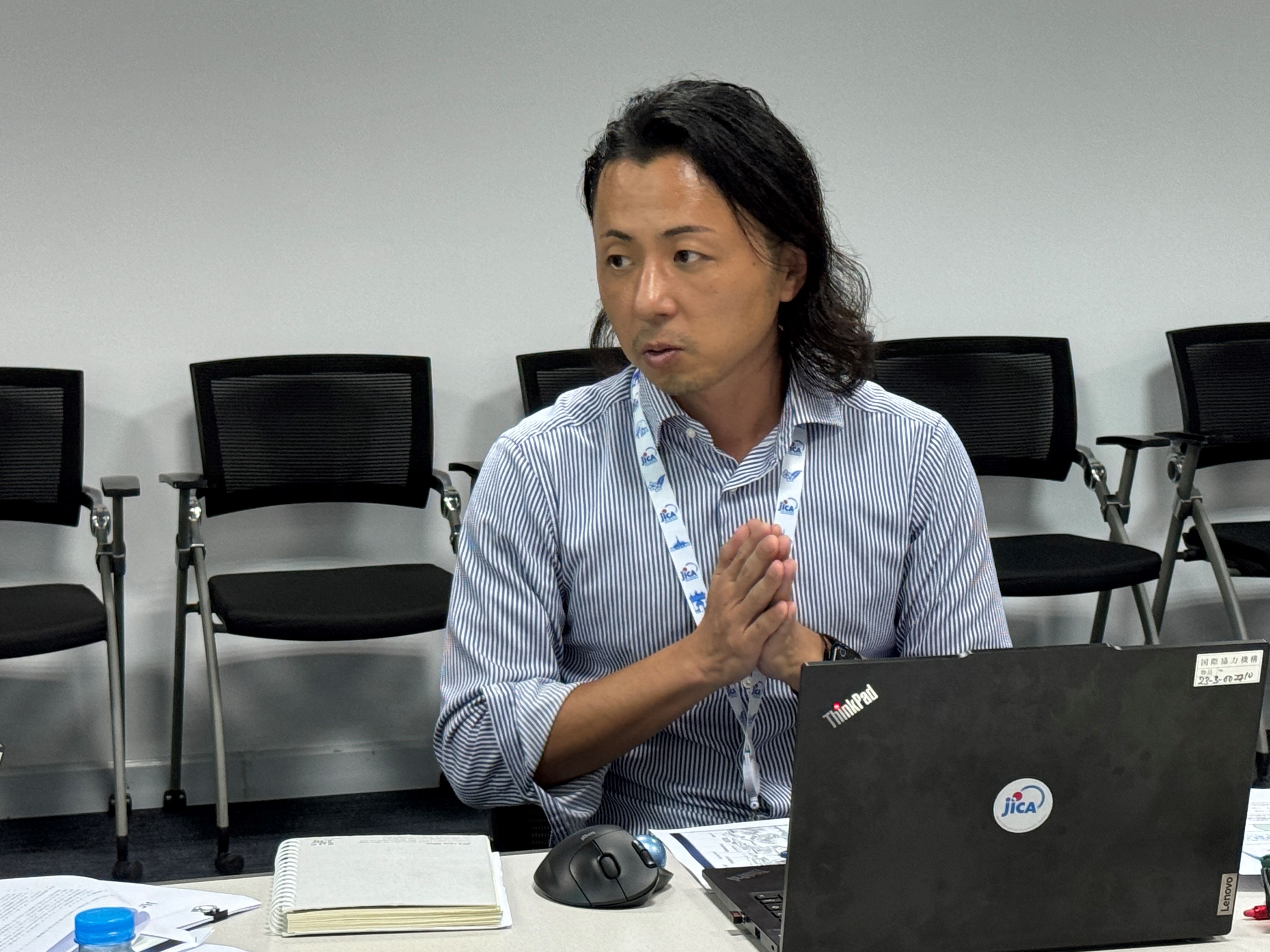
古川 洸太郎 JICAラオス事務所所員
美弥子所長:日本が持つ技術や知見に関し、具体的に教えてください。
古川:日本の知見としては、森林を活用した防災や治山の技術が挙げられます。日本は国土が急峻なうえ、台風や季節的な豪雨もあり、歴史的に非常に多くの災害を経験してきました。大雨が降るたび、台風が通るたびに、土砂崩れなどの山に関する災害が多く起こっています。このため治山技術に代表される災害防止の技術が発展し、これらの技術を途上国の防災・減災にも活用できるポテンシャルがあります。
美弥子所長:ありがとうございます。冒頭、虫明さんから森林減少により洪水が起こりやすくなっているという話もありました。この9月にはメコン川の水位が危険水域を上回り、58年ぶりにともいわれる多くの被害が発生しました。今後、日本の防災の技術をラオスに役立てたいですね。 ここまでのお話で、キーワードとなるのは「人々の生活」「持続的でサステナブルな開発と循環」ということになるかと思います。サステナブルな土地利用や循環を目指してプロジェクトを実施する中で、住民の受け止め方、特にネガティブな影響があるのかという部分についていかがでしょうか。
虫明:REDD+での森林の保護や森林劣化の予防は、かなり広域の森林に対しての政策です。 鎮守の森などはそれほど広いものではないので、その保護等が直接プロジェクトに貢献できるかというと難しい問題です。ただ、鎮守の森やお墓の森、水源林もそうですが、ラオスの地域住民は、地域レベル、村レベルで大きな森林で残しておきたい場所、森が減少・劣化しては困る場所を意識しています。 このような意識や考え方と 上手にリンクできるような活動を考えることができれば良いのではないでしょうか。
また、プロジェクトが終了しても終わりではなく、持続する仕組み作りが大切だと思います。森林保護は、住民の立場で考えた場合には、森林利用の制限となる場合もあります。例えば、焼畑をしていた人々が焼畑を制限されたり、森林産物を採取していた人々が採取できなくなったりと、それまでの生活ができなくなる場合もあります。
新しい生計をどうやって立てていくかを考えたときに、ドナー側が、新たな家畜飼育や養魚を勧める場合もあるかと思います。しかし、これまでやったことのないことを新しく始めることはそれだけでかなり難しいことです。持続性という意味では、村の人たちが森林を利用しないことではなく、森林を利用しながらの生計維持の持続性が達成されることが大切だと考えています。

鎮守を祀る
美弥子所長:プロジェクトにより人々の生活に変化が生じるのであれば、その地域に暮らしている方とのリンケージや、村の住民へなぜこの活動が必要なのかという説明が重要になりますね。
次に江頭専門家でお聞きしますが、REDD+や気候変動などの話は、地域の人々にどれぐらい理解されているのでしょうか。プロジェクトと地域に暮らされている方との関係などを教えてください。
江頭専門家:気候変動やREDD+などの話がどこまで村の住民の方々に理解されるかは難しい部分があります。途上国の主張としては気候変動は先進国が起こした問題であるという考え方ですし、温室効果ガスは目に見えないものですから、普通の人々にはピンとこない話となりがちです。 現地の人々にとってはむしろ、自分たちの生活に関係する森林や土地の利用がどのような形で持続的に維持され、豊かさをもたらすのかを示すことが大切だと考えています。
REDD+は温室効果ガスが排出削減されたことに金銭的な報酬を提供するものですが、それを住民たちと話す際には、彼らの文脈と理解できる言葉に置き換えて話すことが大切だと考えています。
成果払いによる事業対象地の上空写真

森林バイオマス調査の演習
美弥子所長:森林分野の気候変動分野では、GCFのREDD+成果支払いプログラム(RbP)により、ラオスで最大50百万ドルの外部資金獲得見込みとの朗報も入りました。これまでのJICAのプロジェクトや他ドナーの支援もあり、ラオス政府の取り組みの成果だといえます。
今日の議論では、GCFのREDD+成果支払いによって、「住民参加型」の自然管理に資金が入り、その結果、森林保全が進むというサステナブルな循環なためにも、大きな枠組みのその先にある現地の人々の生活を忘れてはいけないというのが、皆さんからのメッセージであったと思います。 このメッセージを忘れずに、今後もJICAはプロジェクトを実施していきたいと思います。
●効果的なREDD+資金活用に向けた持続的森林管理能力強化プロジェクト(F-REDD2)のFacebookページ
scroll