ラオスJICA海外協力隊派遣60周年メッセージVol.8 高畑 恒雄さん(首都ビエンチャン/農業機械/1972年派遣)
2025.08.21
今回60周年記念の寄稿依頼をいただき、改めて、こんなにもラオスに関わって来たのかと我ながら驚きました。とても指定された文字数では書き切れないので、項目にして並べてみました。
私の職種は「農業機械」。しかし、配属先の社会福祉省貧困民入植地建設センター(当時)に着任してみると、巨大なブルドーザ等の建機類がずらりと並び、私には到底扱えないと気が遠くなる思いがしました。センターの主な業務は、貧困地域の農民をビエンチャン平原に入植させることでした。当時のビエンチャンは首都とは言え、森に覆われた未開地が多く、そこを切り開いて貧困民に定住地を提供するのが主たる業務で、当時は建設の最盛期でした。
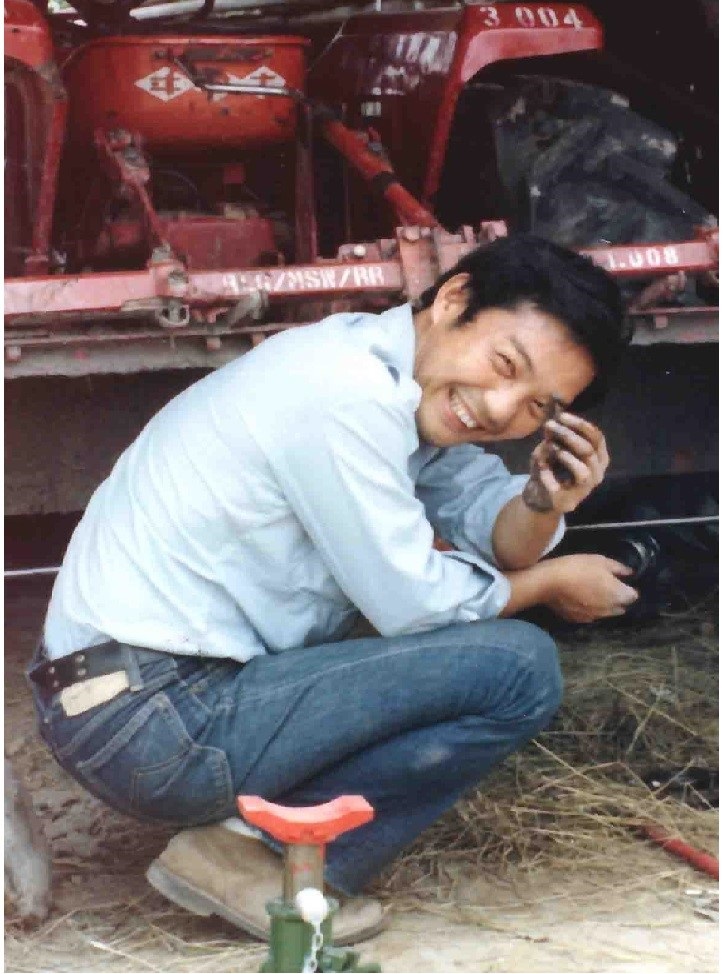
故障したトラクターの修理箇所を発見して喜ぶ高畑隊員
定住の過程で使う農機具類の操作を指導する人手が足りない状態だったので、隊員が要請されたというのを知り、ほっとしました。このセンターには、他にも「野菜」や「養蚕」などの隊員が配属され、各村で活動していました。まずは、30㎞程北に行った場所に、先輩隊員が野菜栽培を指導する入植地があり、そこに耕運機類を導入して操作法の指導を始めました。また、後には、精米所も稼働させました。
開墾したばかりの村の生活は厳しく、余裕が有るはずもないのに、入植者の家の前を通ると「飯を食ったか?」と声を掛けてくれました。彼らの温かさ、穏やかさは、私を魅了しました。彼らが、なけなしの材料で開いてくれた送別会では涙を禁じえませんでした。

開拓地でブルドーザーを使って農地造成を行っている高畑隊員

当時、往来していた運搬用牛車。農耕文化の高さを感じた

隊員支援車両の上で赤い丸(日の丸)の車が来たとはしゃぐ移民の子ら

お腹が膨らんで栄養失調と思われる移民の子
ラオス革命政権は1975年以降、西側諸国に対して鎖国状態に入りました。これにより、多くの人々が難民として国外に流出しました。インドシナ諸国からの大量の難民発生とその悲惨な状況は世界中に伝えられ、国内外で救援活動するOBOGが現れました。これに私も少なからず巻込まれました。一方で、私は、企業勤務を経て、1979年にJICAに採用されました。丁度その頃、日本政府による初の緊急医療チームがタイに派遣され、私も同行しました。この医療チームには、協力隊1期生の星野昌子さん(職種:日本語教師)が通訳として参画されていました。星野さんは後に、日本のNGOの草分けともいえる特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター(JVC)の事務局長にとして輝かしい活躍をされました。
革命政権が鎖国を緩め始めた1990年、15年ぶりにビエンチャンを再訪する機会を得ました。そこで目の当たりにしたのは人通りの絶えた街の中心部の荒廃でした。いったいあの戦争は何のためだったのだろうという思いがしました。
そこではJVCの一員として持てる技術と流暢なラーオ語力を生かして活躍するラオスOVの斎藤誠さん(職種:上下水道)や久保田初枝さん(職種:家政)にお会いする機会を得ました。そして、隊員がかつて指導した村を訪れてみると、そこでは日本式農法が定着していて驚きました。
1996年にJICAラオス事務所を開設する為にラオスに赴任しました。これより先の1992年に協力隊調整員事務所が開設されていたとは言え、諸外国との関わり方に慎重となっていたラオスの役人の心を溶かすには苦労がありました。これには、隊員時代に覚えたラオス人との接し方が役立ちました。体制が変わったとしてもラオス人の心根の優しさは変わっていませんでした。
JICA退職後、2011年に、福岡県久留米市の聖マリア病院が設立したNPO法人ISAPHの母子保健向上計画に参画する機会を得て、ラオス中部のカムアン県ターケークに赴任しました。残念ながら体調不良で半年で帰国しました。送り出してくれた皆さんにはご負担をおかけしたことが悔やまれます。
時期は前後しますが国内外の難民支援を通じて実質的活動を行っていた私たちは、2004年に協力隊派遣40周年を契機として、ラオスOV会を立ち上げました。活動としては、グローバルフェスティバルや協力隊祭りへの出展や物販を行っています。又、一般人向けのラオス関係講座を開設しました。週一回のラーオ語講座と隔月開催のラオス紹介セミナーです。余り知られていないラオスの様々な事象を紹介するトークショーを開催し、毎回30人程が集り盛況でした。講師はラオス人留学生から大学の研究者まで様々。
加えて、イベントなどで得た収益から隊員・OVへの少額資金援助を行っています。
ラオスとの出会いは偶然です。しかし、以来半世紀余り、OV等との協働により、多くの分野で日ラーオ親善と関わって来ることが出来ました。
唯一悔しいのは、政権が代わったことで、知り合ったラーオ人と連絡が取れなくなってしまったことでした。かつての同僚や友人達と言葉が交わせなくなったのは大変に残念な思いです。
しかし、今年2025年4月、1996年JICAラオス事務所の立上げ時に、ラオス外務省側で窓口だった青年が、25年の時を経て駐日ラオス大使として来日され、再会を喜び合うことができました。
協力隊の2年間は長い人生の一瞬の交差点にしか過ぎない筈なのに、時を経てまるで遠い親戚が外国にいるような感覚を覚えるというのも協力隊の醍醐味なのでしょう。
雑文への御精読に感謝申し上げます。
1972年派遣 農業機械 高畑恒雄
【編集後記】
Vol.2でご紹介した大西元隊員に続き、協力隊派遣初期のラオスの様子を垣間見ることができる貴重なメッセージでした。JICAラオス事務所開設当時のラオス側で窓口だった方が、駐日ラオス大使としてご活躍されていることも嬉しく思います。このように、先代の協力隊員たちの貢献が、今のラオスと日本の友好関係の礎となっているのだと改めて感じました。この友好関係が、またこれからの長い将来に渡り続いていくことを願います。
scroll