【草の根技術協力】「ASEANのモデルとなる低炭素社会実現に向けた人材育成とネットワーク拠点の機能強化プロジェクト」最終成果報告会を京都市で開催しました!
2024.12.23

プロジェクト関係者、登壇者との写真撮影の様子
京都市環境保全活動推進協会(KEAA:Kyoto Environmental Activities Association)は、京都市やJICAと協力し、マレーシアジョホールバル市において「ASEANのモデルとなる低炭素社会実現に向けた人材育成とネットワーク拠点の機能強化プロジェクト」を2021年10月から2025年1月までの約3年4か月間の期間で実施しています。

プロジェクト概要説明の様子
プロジェクトが来年1月に終了を迎えるにあたり、12月15日(日)に京都市のキャンパスプラザ京都にて最終成果報告会を開催しました。報告会には市内外から60名以上の市民や行政職員、市内で環境活動に携わるNGO関係者などが参加した他、イスカンダル地域開発庁のDato’ Dr. Badrul Hisham長官、KEAAの新川理事長をはじめ、ジョホールバル市スルタンイスマイル図書館の上級司書兼エコセンター専門職員、京都市、JICA関西の担当者が参加し、盛大に執り行われました。
第1部の成果報告では、大久保プロジェクトマネージャーより本事業の概要説明を行いました。また、2023年2月に、当協会が指定管理を行う京都市の環境学習施設「京エコロジーセンター」をモデルとして開設された、ジョホールバル市の環境学習拠点Sudut Lestari(マレー語で“サステナブルコーナー”の意味。通称エコセンター)で専門職員として業務にあたるジョホールバル市及びイスカンダル地域開発庁の職員がセンターの運営状況やこれまでの活動実績について報告を行いました。さらに、エコセンターを拠点としてジョホールバル市以外のマレーシア国内の他地域やASEAN地域(タイ、ベトナム、インドネシア)を対象とした研修に参加したマレーシア・サバ州Tawau市の担当者が策定した環境活動計画の発表を行いました。
「来館者をエコセンターに集めるためどのような工夫をしているか」という会場からの質問に対し、来館者が環境について楽しく学び、実践につなげられる活動を紹介することを目標に、移動型展示物の開発やSNSを活用した広報活動を行っているという説明がありました。また「エコセンター開設にあたりどのような課題があったか」という質問に対しては、図書館司書がエコセンターの専門職員として業務を担うことになったことから職員自身が低炭素や環境問題への知識を学ぶところからはじまり、センター開設に係る展示の開発など予算の確保にも課題があったと説明されました。
第2部では公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES:Institute for Global Environmental Strategies)の藤野氏がコーディネーターとなり、京都市内で環境活動を担うNGOの職員やマレーシアを題材に廃棄物削減や市民の環境意識について卒業論文を執筆した大学生、エコセンター専門職員、KEAA新川理事長を登壇者に迎え「市民が主体の脱炭素社会を実現するために環境学習拠点が果たす役割とは?」と題したパネルディスカッションが行われました。
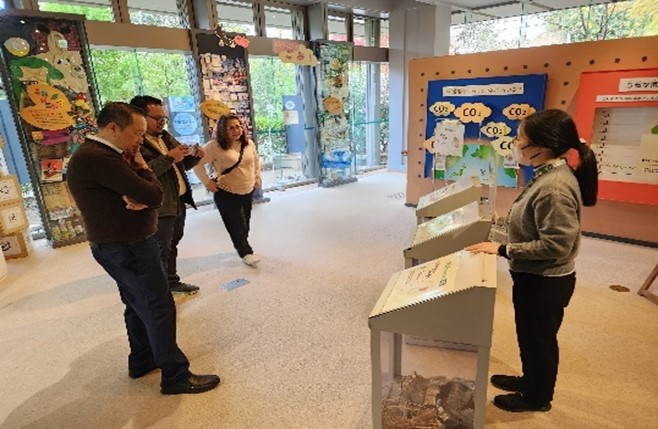
京エコロジーセンター見学の様子
今回の報告会開催に合わせ来日したマレーシア研修員6名(うち2名は自費参加)を対象に、報 告会の前後に研修も行いました。 今回が初来日となった研修員が2名いたことから、京都市における気候変動対策・環境教育や市民主体の環境活動、資源回収の取組等について知見を深めることを目的に研修内容を企画しました。これまで京都市からの講義において、説明はしていたものの実際の様子を見る機会がなかったため、今回の来日に合わせ資源回収や市民主体の環境活動の視察、京エコロジーセンターの展示案内ができたことは研修の意義があったと感じます。
加えて、プロジェクト最終成果報告会を一般市民も参加できる形で開催したことで、京エコロジーセンターで活動するボランティアを始めとする京都市民や、市内外からの自治体職員、NGO職員等にもプロジェクトの成果をエコセンター職員から直接報告することができ、京都の取組がマレーシアやASEAN地域で展開されている様子を知ってもらう機会を提供することができました。また、マレーシアで実施している本事業の成果を発表できたことで、参加した京都市民の方々の国際協力に対する理解を深めることもできました。
プロジェクトは来年1月で終了を迎えますが、これまでの取組の成果がマレーシアからさらにASEANやその周辺地域に展開され、それぞれの地域に即した形で独自の環境教育・環境保全活動が広がっていくことが大いに期待できます。
なお、KEAAではプロジェクト終了後もマレーシアジョホールバル市及びイスカンダル地域開発庁との連携した活動を継続するため、来年初夏に新たな連携協定(MOC)を締結するため調整を進めています。今後も、京都市と協力し、本事業の成果を活かして京都における環境保全活動の取り組みを海外に広げ、脱炭素社会の実現に貢献して参ります。
イスカンダル地域開発庁のDato’ Dr. Badrul Hisham長官と自費で参加したエコセンターの戦略パートナーであるSWM Environment社の職員にとっては今回がはじめての来日となったことから、12月13日(金)の午前に京都市伏見区にある環境学習施設「京エコロジーセンター」の見学を行いました。はじめにセンターの概要説明を行ったあと、館内案内を行い「見て、触れて、感じる体験型環境学習施設」をコンセプトとした常設展示・企画展示の紹介を行いました。また前回7月の訪日研修から更新のあった展示内容についてエコセンター専門職員に紹介を行いました

京都市役所表敬訪問
午後は京都市役所を表敬訪問し、松井京都市長、田中環境政策局長、細貝部長に本事業におけるこれまでの協力の御礼の挨拶を行いました。京都市長からは「事業終了後もこれまでの成果を生かしながらマレーシアとの交流を発展させるとともに、脱炭素社会の実現に向けて共に力を合せていきたい」とご挨拶頂きました。表敬終了後は、京都市のエコツーリズムや脱炭素先行地域に係る官民連携の取組について紹介があり、質疑の時間を持ちました。

砂川小学校での移動式拠点回収見学
12月14日(土)午前は京都市環境政策局まち美化推進課(伏見まち美化事務所、深草エコまちステーション)が管轄する資源の移動式拠点回収の見学のため京都市伏見区の砂川小学校を訪問しました。移動式拠点回収は、月2回、学校や公園などにまち美化事務所の職員が出向いて普段は回収されない家庭からの資源物の回収を無料で行うサービスです。この日は京都市発行の拠点回収の概要を英訳した資料をもとに京都市における資源回収、リユース・リサイクル事業について説明を行ったあと、市民が持ち寄った資源を品目ごとに仕分けする作業の様子を見学しました。マレーシアで回収される資源物が古紙や使用済食用油、ペットボトル、古着等に限られているため、電池や木の枝、小型家電、インクカートリッジなど18以上の品目が行政主導で回収されることに驚いていた様子でした。資源回収サービスをジョホール州で展開するSWM Environment社の職員から「市民が資源を持ち寄るにあたりどのようなインセンティブがあるのか」という質問に対し「他の自治体では有料で回収されることが多い資源物が、京都市では市民に身近な場所で定期的に無料で回収されることにメリットを感じる人が多い。」との説明が市職員からありました。

東山いきいき市民活動センターでの講義
午後は東山いきいき市民活動センターを訪問し、センターの機能やセンターを拠点とした地域コミュニティや市民による環境活動支援活動について、副センター長の井手氏よりお話を伺いました。東山いきいき市民活動センターは京都市内に13あるセンターの中で最も規模の大きな施設で東山区(人口約3.5万人)を管轄しており、駅からのアクセスの良さや施設の規模の大きさから、近隣住民だけでなく区外からも多くの利用者が集まり、音楽やダンス、ガーデニングなどの活動場所として活用されています。この日は特にセンターの中庭でのアーバンファーミング活動についてご説明頂き、地域に開けた施設として人々の居場所として活用される施設になるよう活動を展開していきたいとのお話を頂きました。
12月15日(日)はキャンパスプラザ京都でプロジェクトの最終成果報告会を開催しました。詳細は上記参照。

JICA関西表敬訪問
12月16日(月)午前はJICA関西センターを表敬訪問し今井次長、市民参加協力課大井課長、西原担当に本事業に係る協力・支援の御礼の挨拶を行いました。終了後はJICA関西センター1階をご案内頂き、世界各地で進められるJICA事業やSDGsをテーマとした展示物の見学を行いました。
scroll