- トップページ
- ニュース・広報
- 広報
- 広報誌
- mundi
- 難民支援 故郷の夜明けを夢見て mundi 2017年6月号
- 隣国の兄弟と支え合う ウガンダ
東アフリカに位置する人口約4,000万人の国ウガンダ。
豊かな自然に恵まれていることから、英国のウィンストン・チャーチル首相が"アフリカの真珠"と呼んだこの国には、現在、隣国・南スーダンからおびただしい数の難民が押し寄せている。
こうした中、日本は独自の難民支援に乗り出した。
写真:久野武志(カメラマン)

アジュマニ県ボロリ居住区に暮らす南スーダン難民の子どもたち
1日2000人を超える南スーダン難民が流入
壮大なヴィクトリア湖と、そこから流れ出るナイル川、果てしなく続く草原地帯−ウガンダの首都カンパラの大渋滞を抜けると、美しい自然が広がっていた。道行く人々は外国人の筆者に向かって手を振ってくれ、その表情には大らかさがにじみ出ている。
そんなウガンダは、"世界一難民に寛容な国"だといわれている。実際に第二次大戦以降、スーダンやコンゴ民主共和国、ブルンジといった近隣国から数多くの難民を受け入れてきた。2006年には、難民法を制定し、難民に移動の自由や就労の権利なども認めている。ウガンダでも、国内の紛争によって多くの難民が近隣国に逃れた歴史があり、「兄弟同士助け合うのは当たり前」という感覚を国民が共有しているのだという。
こうした中で、今、ウガンダ社会を揺さぶる大きな出来事が起きている。南スーダン難民の急増だ。11年に独立を果たし、「世界で最も若い国」と呼ばれる南スーダンでは、13年にディンカ族出身の大統領派とヌエル族出身の元・副大統領派の間で紛争が発生。戦闘が再燃した昨年7月以降は、南部エクアトリア地方にも戦火が及び、多くの南スーダン人が南部国境を接するウガンダへと逃れた。
今年4月時点で確認されているウガンダ国内の南スーダン難民の数は約88万人。現在も、1日2000人を超える南スーダン人が国境を超えてやって来ている。難民登録をすることなく、ウガンダの親戚などを頼って逃れてくる南スーダン人も多数存在するとみられ、実態はさらに深刻だ。
これを受けて、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)をはじめとする援助機関は「難民居住区」での緊急人道支援を強化。難民の各世帯に対して居住や簡単な農業のための土地を割り当てた上で、食糧や水、保健サービスといった生活に必要なさまざまな支援を行っているが、難民の急増に支援が追い付かないのが現状だ。
ウガンダ北西部に位置する西ナイル地域ユンベ県ビディビディ居住区は、昨年8月にオープンしたばかりにもかかわらず、当初想定していた5万人という収容数を大きく超える27万人もの南スーダン難民が暮らしている。居住区内には所々に白テントが張られているが、難民たちは現地式の住居を構えており、見た目は「難民キャンプ」というよりも「集落」そのものといった印象だ。
そんなビディビディ居住区の難民たちの生活は、やはり厳しいようだ。母国・南スーダンの保健センターで働いていたラスー・ジャスティンさんは、過去にも南スーダンからウガンダに逃れた経験があるが、今回の戦闘で再び難民になってしまった。ラスーさんは、居住区での生活について「南スーダンでは、私たちエクアトリアの人々が命を狙われました。ここでの生活は安全ですが、以前より配給される食料は減り、井戸も足りません」と話す。母国ではNGOで働いていたメリー・アワテさんも、「南スーダンにいつ帰れるのか分かりません。自分の力で生きていくために、ウガンダで仕事を見つけなければ」と語ってくれた。
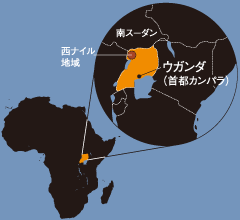
ウガンダ

ビディビディ居住区で暮らす南スーダン難民のラスーさん(中央)

ビディビディ居住区には、妊婦や赤ん坊を抱えた女性たちもたくさん暮らしている

アジュマニ県のボロリ居住区。白いテントと住居が混在しているのが難民居住区の特徴だ
地方行政の能力を高め ホストコミュニティーに支援
南スーダン難民の大多数を受け入れる西ナイル地域は、もともと都市部から離れていることや、ウガンダ国内の政治的な対立から反政府勢力の拠点と見なされたこともあって、他の地域に比べて開発が遅れている。そんな中、今回の南スーダン難民の急増により、難民に対する人道支援だけでなく、難民を受け入れる"ホストコミュニティー"の開発も切実な課題になっている。
例えば、人道支援が行われている難民居住区で暮らす難民だけでなく、そうした支援の届かないウガンダ人の集落に混ざって生活する難民も増えていることから、ホストコミュニティーの学校や病院といったさまざまな社会インフラが不足し始めている。南スーダン難民が人口のおよそ半分である23万人に上るアジュマニ県のダリリ・モーゼス副行政長は「学校が足りず、1クラスに100人以上の子どもが詰め込まれているのが現状です」と地域の課題を話す。
しかし、ウガンダ政府がコミュニティーのすべての要望に対応することは困難だ。地方自治省のカグワ・アンドリューさんは、「コミュニティーからあまりにも多くの要望が上がってくるため、予算がまったく足りていません。これらの要望に優先順位を付け、より効果的な開発事業を選択していく必要があります」と話した。
そこで、JICAは現在、西ナイル地域で地方政府の開発能力の強化に取り組んでいる。もともとは、ウガンダ国内の北部紛争の復興支援の一環として、隣のアチョリ地域で同様の取り組みを行ってきたが、今回のプロジェクトでは、これまでの経験とノウハウを生かして、アチョリ地域に加え、南スーダン難民の流入が続く西ナイル地域の地方行政官に対しても開発計画の策定を支援していく。
「プロジェクトでは、県の下にある郡政府の行政官に簡単な"開発計画ツール"を活用してもらい、優先度の高い事業の実施を促しています」と話すのは、プロジェクトリーダーを務める久保祐輔専門家だ。「各村の人口や井戸の数、道路の整備状況といったデータを分野ごとに"インベントリーシート"という紙に集約してもらいます。その上で、各村から上がってくるさまざまな事業の要望を、客観的な基準を用いて点数化し、その優先度を評価するのです」
すでに前回のプロジェクトでこれらの計画ツールを導入したアチョリ地域では、継続的なツールの活用を促しているが、西ナイル地域では、今年2月に郡の行政長と開発担当官に計画ツールを紹介する研修を行ったばかりだ。今後は、郡政府の他の行政官に対して計画ツールの活用を広げていく。

アルーア県の行政官に計画ツールの普及状況を聞く久保専門家

地元ラジオ局の取材を受ける久保専門家

パイロット事業を実施している村を訪れた今里専門家。「ここの郡は行政官が優秀でした」と話す

パイロット事業で牛を購入し、牛耕の訓練をする村人たち
ウガンダ政府も、今回のプロジェクトには大きな期待を寄せている。首相府で北部ウガンダの開発を担当するオデュール・ベナルドさんは、「さまざまな援助機関から資金をもらっても、政府が計画的に事業を実施できなければ無駄になりかねません。このプロジェクトでは、地方政府の開発能力を高め、他のあらゆる開発事業との相乗効果を生み出していくことを目指します」と述べた。
加えて、今回のプロジェクトでは、パイロット事業も実施しており、アチョリ地域では現地で伝統的に行われてきた「牛耕」を中心に、すでに28の事業が動き出している。
パイロット事業の対象グループに選ばれた、アチョリ地域のとある村では、今年3月にJICAの支援を受けて6頭の牛を購入し、牛耕に取り組み始めた。「この4頭はよく働きますが、残りの2頭は少し怠け者らしいです」と、このパイロット事業をサポートしている今里いさ専門家は、突然の来客にやや興奮気味となった牛たちを見て、にこやかに話す。
パイロット事業では、郡の開発担当官がグループの住民と一緒になって事業計画を作るのが大きなポイントだ。「住民たちはこれまで、牛がほしいという要望を出しても、牛をどう活用していくのかを具体的に計画していませんでした。そこで、この事業では、牛を使ってどれぐらいの広さの農地を耕すのか、誰がいつ牛を訓練するのか、牛の健康をどうやって保つのかといったことをきちんと計画してもらっています」と、今里専門家は話す。
今後は、西ナイル地域でもパイロット事業を行う。前出の久保専門家は「西ナイルは、アチョリと比べて民族的にも文化的にも多様です。牛耕をやってきた村もあればやっていない村もありますし、難民の受け入れ状況も県や郡によって異なります。そのため、難民をもターゲットにして、どのような取り組みを行うのか十分な検討が必要です」と話した。
稲作普及の経験生かし 難民の生計向上にも貢献
ウガンダは、もともと穏やかな気候から、アフリカの中では農業に適した国だとされている。しかし、今回の南スーダン難民の急増を受けて、西ナイル地域では食料不足が課題になりつつある。
こうした中で、JICAは、農業分野でもウガンダにおける難民支援に取り組んでいる。11年から実施しているコメ振興プロジェクトの一環として、14年からUNHCRとの連携の下、難民とホストコミュニティーに対して陸稲「ネリカ米」の普及活動を進めているのだ。これまで1400人を超える難民とホストコミュニティーの農家、農家普及員などを対象に稲作研修を実施してきた。
土地の単位面積あたりの収量が高い、生育期間が短い、さらには乾燥にも強い、といった特長を持つネリカ米は、現地の食料確保はもちろん、農家の生計向上にも役立つ。西ナイル地域アジュマニ県の農業担当職員のラリア・ジェシカさんは「昨年はひどい干ばつがありましたが、ネリカ米は十分な収穫がありました。コメはキャッサバの2倍高く売れるので、農家の人たちも喜んでいます」と話す。プロジェクトでは、稲作研修を受けた農家に対して1キロの種もみを支給しているが、これを元に最初の収穫で50キロの種もみをとることもできる。

農業担当職員のジェシカさん(左から1人目)と、居住区に住む難民の人たち。左から2人目がワランさん

日本が作った稲作普及のためのポスターを使って、難民の仲間たちに稲作技術を教えるワランさん
アジュマニ県ボロリ居住区で暮らす南スーダン難民のワラン・サイモンさんは、15年にプロジェクトの拠点である国立作物資源研究所(NaCRRI)で講師研修を受けた後、同じ居住区に暮らす難民たちに対して稲作を教えてきた。
ワランさんは、7歳から27年間、ウガンダで難民として暮らした後、13年に母国に帰国したがその直後に戦闘が発生。再びウガンダで難民として生活している。「ウガンダ人から農地を借りるのに高額なお金がかかりましたし、よその村から牛がやって来て農地を荒らすなど、大変な目にもあいました」などと、ワランさんは時折厳しい表情でこれまでの苦労を語る。
しかし、彼が案内してくれた貯蔵庫には、2年前にもらった1キロの種もみから収穫した700キロものもみ米袋が積まれていた。ワランさんがこの貯蔵庫の内壁に貼られた1枚のポスターを指し、「講師研修でもらった教材のポスターです。これを使って皆と少しずつ稲作を進めてきました」と話していると、いつの間にか仲間たちが集まってきた。この苦境を何とか乗り越えようと奮闘してきたワランさんに、仲間たちは大きな信頼を寄せているようだった。
日本は現在、ウガンダで暮らす南スーダン難民に対する今後の支援の在り方を検討中だ。難民問題が長期化する昨今では、従来の人道支援の枠を超え、難民とホストコミュニティーの生計向上をもたらす新たな視点の支援が重要になることは間違いない。
編集部 吉岡 資











scroll