- トップページ
- ニュース・広報
- 広報
- 広報誌
- mundi
- 南アジア 18億人の鼓動 mundi 2020年5月号
- 人材育成 【イノベーション】未来をつなぐもの作りの場 ブータン
ブータンの教育現場で、デジタルでのもの作りが誕生している。
社会課題の解決や産業の発展など、デジタル技術がもたらす未来に期待がかかる。
・案件名:
デジタルものづくり工房(ファブラボ)による技術教育・普及促進プロジェクト(2020年7月~2023年6月を予定)

ファブラボ、もの作りと親和性の高い「Pi-Top(注1)」に夢中になるCSTの学生。
(注1)プログラミングと電子工作学習のために作られた、ノートバソコンを自作できるキットのこと。
ファブラボに詰まった多くの可能性
人口わずか75万人余のブータンは国内市場が小さく、多くの日用品や生活必需品を他国からの輸入に依存している。また、険しい山に囲まれた土地が多く、交通の便が悪いため輸送コストが高くなることや、物資の輸送期間が長くなることが国内産業の発展を妨げる問題となっていた。
この状況を改善するためにJICAがブータン政府とともに準備を進めているのが、ブータン王立大学科学技術カレッジ(CST)でのデジタルもの作り工房ともいうべき「デジタルファブリケーションラボ」(以下、ファブラボ(注2))の設立と、デジタル技術や「オープンイノベーション(注3)」による教育モデルの開発を目指すプロジェクトだ。ファブラボには、3Dプリンターやレーザーカッターをはじめ、インターネット環境とデータがあれば誰でももの作りができる道具がそろっており、立地条件による差がない。また、低コストでプロトタイプ(原型・試作品)が作れることも特徴のひとつだ。
「ファブラボの教育モデルをとおして学生たちが社会課題を自ら見つけ、アイデアを出し、技術革新を実現していける環境をつくっていきたいと思っています。また、ファブラボは開かれた存在でありたいと考えています。そのため将来的には、地域の子どもたちの学びの場として活用してもらうほか、個人、組織、民間企業とのコラボレーションなども促進していく計画です」と、CST学長のチェキ・ドルジさんは意欲を語る。
今後数年のうちに「世界ファブラボ会議」がブータンで開催される予定で、他国からもその動きに注目が集まっている。ファブラボという産業の人材育成における新たな取り組みが、いま始まろうとしている。
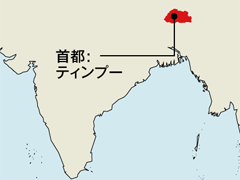
首都:ティンプー

広大な敷地を有するCST。ファブラボは電子・コミュニケーション学科に設置される予定だ。
(注2)3Dプリンターや3Dスキャナー、レーザーカッターなどの先端工作機械を備えた、誰でも利用できるもの作り工房。
(注3)組織や個人の枠組みを超えたかたちで技術、アイデア、データ、知識などを集積して技術革新を目指す方法。
ファブラボがどのようなものなのかを学生たちに伝えるため体験型の講座が開かれた

VR(仮想現実)の体験も行われた。

3Dプリンターについて学ぶ。
ブータン王立大学科学技術カレッジ 学長 チェキ・ドルジさん
学生たちがファブラボを通じて創造性のあるデザイン、製作技術、技術革新の起こし方を身につけることを期待しています。そして、これらのスキルを武器に、ビジネスでも活躍してほしいです。

チェキ・ドルジさん











scroll