- トップページ
- ニュース・広報
- 広報
- 広報誌
- mundi
- 大学連携 未来のリーダーをつくる mundi 2020年7月号
- 現地に根づく Case1 40年にわたる協力が成果を生む ケニア
ケニアのジョモケニヤッタ農工大学(JKUAT)は日本が設立に関わり、京都大学をはじめとする日本の大学が長きにわたり協力を続けてきた。
こうしたつながりが、JKUATの教育や研究のレベルを上げている。
・案件名:
アフリカ型イノベーション振興・JKUAT/PAU/AUネットワークプロジェクト(2014年6月~2020年6月)
アフリカ型イノベーション振興・JKUAT/PAU/AUネットワークプロジェクト フェーズ2(2020年6月~)

日本が提供した機材を活用し、シミュレーションを実施中。
ケニアを代表する農工学系の大学
首都ナイロビ近郊にある国立ジョモケニヤッタ農工大学(JKUAT:Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology)は、ケニアだけでなく、アフリカ域内の基礎科学・技術・イノベーション分野の拠点大学だ。日本の協力を得て高等専門学校として1979年に開校。1988年に四年制大学、1994年には大学院課程も開設し、ケニアを代表する農工系の大学となった。今では多くの学科や研究科を有し、10のキャンパスで約4万人の学生が学んでいる。
もともとケニアの大学は知識を詰め込む講義中心の教育で、学生のレベルも伸び悩んでいた。そんな状況を変え、実験や研究を行い、実学を学ぶ場にしたいという設立当初からのケニアの意向を受け、1980年代後半から教育に携わる日本の大学教員の派遣が始まった。「私は1993年から1999年まで毎年2か月ほど滞在しました。暗記中心ではなく、図などが豊富な日本の工業高校の教科書を使い、数学や物理の基礎知識を教え、演習を取り入れた講義などを行いました」とふり返るのは、京都大学大学院工学研究科教授の木村亮さん。以来30年近くアフリカに関わっている。「工学部なのに(研究のフィールドが少ない)アフリカに行く〝変わり者〟と見られていました」と木村さんは笑う。
JKUATには木村さんのような多くの教員が日本の大学から派遣され、教育や研究をサポートした。日本との結びつきも強まるこうした協力を継続するなかで、JKUATの教員や技官が日本を含む国外の大学で修士号や博士号を取得するようになり、研究をしながら学生に教える人材が育っていった。
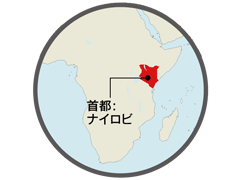
首都:ナイロビ

JKUATのキャンパス入り口。

日本の大学で学位を取得する教員も。長崎大学で環境海洋資源学について学んでいたときの様子。

鳥取大学で学位を取得したJKUATの教員は、日本が協力しているアジアの大学との連携にも積極的に取り組み中。
アフリカの知と日本の知を融合させたい
いまでこそJKUATに関わる日本の大学は多いが、木村さんによれば、当初は個人レベルのつながりで来ていたという。「アフリカは遠い。大学同士の交流は難しかったですね」。ただし研究者には違った。アフリカは農学や薬学、感染症の研究には魅力的な地域だ。たとえば薬学の研究者がアフリカで育つ薬草で薬を開発したり、生物学の研究者がマサイの村にある乳酸菌でヨーグルトを作ったり…。エボラウイルス病やHIVなど感染症の最先端に触れることも可能だった。「多くの先生が自分の研究だけでなく、アフリカでの研究・発展のために協力したいと考え、プロジェクトに参加していました」。
そうした教員の活動が、日本の大学にも変化をもたらした。2017年、アフリカ研究者が学部を超えて集まる「アフリカ学際研究拠点推進ユニット」が京都大学に設立されたのもその変化のひとつだ。「そもそも京大には、同大名誉教授であり、文化人類学者の今西錦司氏が、1958年にアフリカへフィールドワークに行った歴史がありましたし、これまでも多くの研究者がアフリカに関わっています。そこで私たちが大切にしているのは、アフリカの知と日本の知を融合させ、アフリカの地で新しい花を咲かせること。アフリカという場所と人、知があってこそできることに挑戦したい。JKUATへの協力もその流れの中にあります」と木村さんは大学とアフリカの関係を語る。

電子部品の仕組みを青木さんの指導のもと、グループワークで学ぶ学生。

日本の協力で整備されたワークショップで、金属加工の実習を行う学生。

木村さんが主宰するNPO道普請人(みちぶしんびと)の土のう活用技術でJKUAT施設内の道を整備した。
必要なのは継続した協力
今、JKUATでは新型コロナウイルス対策の研究が行われている。それを聞いた木村さんは「隔世の感があります」という。「赴任してすぐに、これは数年協力しただけではだめ、本気で取り組むのなら20年、30年という時間で協力を続けなければ意味がないと思いました。JICAも建物や機材を提供し、人の派遣を続けてきました。それが今につながっている。ここからおもしろいイノベーションが起こるのではないか、とケニア政府や日本の外務省、企業も期待し始めています。これからも日本は積極的に協力し、存在感を示していってほしいと思います」。
京都大学大学院工学研究科 教授 木村 亮(きむら・まこと)さん
教育には息の長い協力が必要です。

木村 亮さん
コラム JKUATの今!進む新型コロナウイルス対策研究
現在、JKUATは新型コロナウイルスの影響で閉鎖中だ。しかしその対策は緊急を要し、社会に貢献する研究であるために、この分野の研究活動に限って大学から施設の利用が特別に認められている。
行われているのは、消毒剤の製造や感染者の接触履歴を追えるアプリ、感染トレンド予測システムの開発。工学部では人工呼吸器の開発が、大学内のものづくりセンターで行われている。2018年から専門家としてJKUATに派遣されている青木翔平さんは、「鳥取大学での研修に参加した技官や、アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(ABEイニシアティブ)の修士課程(およびインターンシップ)プログラムの第1期生として北海道大学で学んだ技官が中心になり研究を進めています」と、日本で学んだ人材の活躍について説明する。「医療機器の開発は初めてなので、保健医療科学部の協力も得ながら、試行錯誤しているようです」。今、青木さん自身は日本に一時帰国しているが、質問やアドバイスを求められることもあり、緊密にコミュニケーションをとりながら遠隔での技術指導を行なっている。「JKUATに人工呼吸器の開発はハードルが高いかもしれませんが、必要は発明の母ともいいます。やってみようという意欲が教員や技官たちの間にあることが重要です」と青木さんは感じている。新型コロナのような世界共通の課題に取り組める大学となったJKUAT。そこには日本で学んだ多くの教員や学生たちの力がある。

JICAの協力で設立されたものづくりセンター。

学生たちに指導する青木さん(写真手前)。

人工呼吸器の製作に取り組む開発メンバーたち。











scroll