- トップページ
- ニュース・広報
- 広報
- 広報誌
- mundi
- 教育と開発 学校が変わる、世界を変える mundi 2018年4月号
- 変わる、世界と日本の教育
国連が採択した持続可能な開発目標(SDGs)では、「全ての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」という目標(ゴール4)が掲げられた。"持続可能な社会の担い手"を育てるために、これからの教育はどうあるべきか。世界と日本を取り巻く課題から考えてみよう。
世界の教育の現状と課題は?
・就学年齢に達しても小学校に通えない子どもたちは、世界中で約5,800万人に上る。近年、就学率は改善傾向にあるものの、アフリカや南アジアでの立ち遅れが目立つ。
・最近では、学校に通えていても、質の高い教育を受けることができない"学びの危機"が課題となっている
学校に通えない子どもの割合(2016年)
就学率は地域によって格差がみられる他、女子のほうが男子に比べて低い傾向にある。
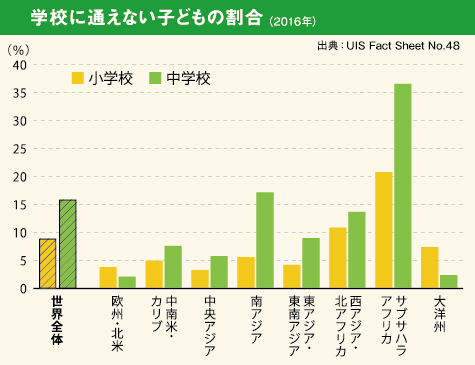
出典:UIS Fact Sheet No.48
学校に通えない代表的な理由
- 1)家計や家事を助けなければならない
世界の1億5,000万人の子どもが児童労働に従事している。弟や妹の世話をするために学校に通えない子どももいる。
- 2)紛争に巻き込まれている
世界の7,500万人の子ども(3~18歳)が紛争や暴力に直面している。
- 3)女子への教育が軽視されている
小学校に通えない女子は世界全体で3,200万人。そのうち、生涯にわたり小学校に通う可能性がない女子の人数は男子の1.5倍となっている。
- 4)障害者の教育環境が整備されていない
途上国に住む障害がある子供の9割が学校に通えていない。また、途上国に住む成人の障害者の識字率は3%にとどまる。
(注)「Global Partnership for Education」のデータをもとに作成
最終学年に到達できない子どもの割合(2016年(注)大洋州は2013年)
サブサハラアフリカでは授業についていけないことなどを理由に、小学校の3割の子どもたちが最終学年に到達できない。中学校では到達率がさらに悪化する。
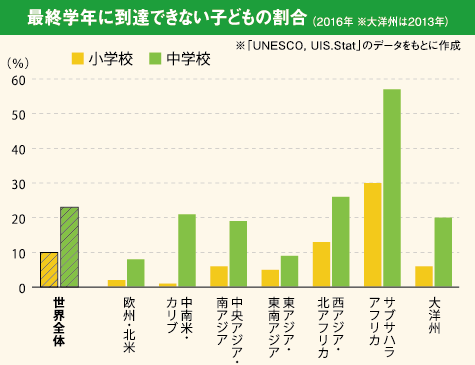
(注)「UNESCO, UIS.Stat」のデータをもとに作成
必要最低限の学力が身に付いていない子どもの割合(小・中学校の合算値)
サブサハラアフリカでは、 8割以上 の子どもに必要最低限の学力が身に付いていない。
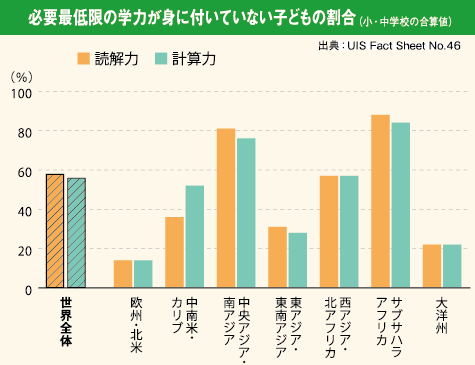
出典:UIS Fact Sheet No.46
JICAはどんな協力をしているの?
JICAが基礎教育分野の技術協力プロジェクトを実施している国(準備中を含む)は30カ国。
(注)アジア・大洋州:10カ国、中東:4カ国、アフリカ:11カ国、中南米:5カ国(2018年3月現在)
代表的なプロジェクト
- 教科書開発
日本が強みとする理数科を中心に、子供たちが主体的に学ぶことができ、かつ教師にとっても教えやすいカリキュラムと教科書の作成を支援している。
- インクルーシブ教育
民族的・言語的マイノリティーや障害のある子供も含め、だれもが通常の学校にアクセスでき、個々のニーズに応じた教育を受けられることを目指す「インクルーシブ教育」。その理念の下、教員養成の充実化や現職教員の能力強化などを支援している。
- みんなの学校
教員、保護者、地域住民の協働により教育改善を目指すプロジェクト。住民の選挙による地域に開かれた学校運営委員会を設立し、学びの現状や課題をもとに保護者や教員と対応策を議論し、さまざまな教育改善活動を実施している。
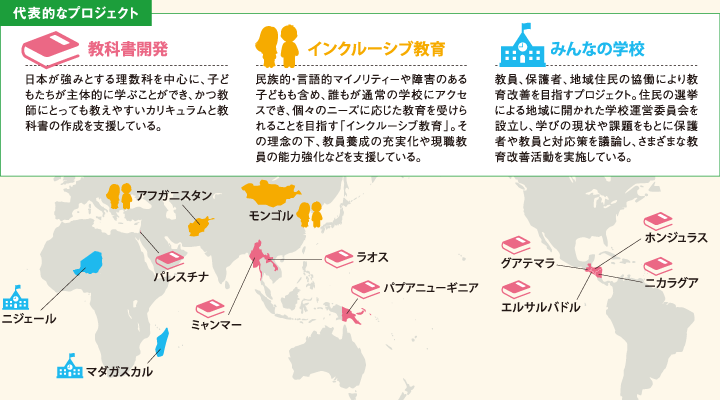
日本の教育はどう変わろうとしているの?
・近年、子どもたちの世界とのつながりに対する意識や、海外への関心の低下が懸念されている。
・文部科学省は2020年以降の新学習指導要領で、「グローバル化への対応」と「持続可能な社会の作り手の育成」を重視している。JICAは国際協力の経験を生かし、世界の課題と日本との関係を知り、自らの問題としてその解決に向けて主体的に取り組める人材を育てるための開発教育・国際理解教育を推進している。
全国の小学校4年生から中学2年生を対象にした意識調査(2017年)
- 関心事
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 日本の事を考えるべき | 54% |
| 世界全体の事を考えるべき | 45.9% 過去最低 |
出典:博報堂生活総合研究所
- 仕事
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 海外で仕事をしたい | 12.4% |
| 海外で仕事をしたいとは思わない | 87.6% |
出典:博報堂生活総合研究所
一方でグローバル化に伴い、日本と世界の結び付きは強まっている。
- 海外に住む日本人の数
| 1997年 | 76万人 |
|---|---|
| 2015年 | 134万人 |
出典:外務省「海外在留邦人数調査統計」、法務省「在留外国人統計」
- 日本に住む外国人の数
| 1996年 | 134万人 |
|---|---|
| 2016年 | 238万人 |
出典:外務省「海外在留邦人数調査統計」、法務省「在留外国人統計」











scroll