- トップページ
- ニュース・広報
- 広報
- 広報誌
- mundi
- 感染症対策 日本の技術が命を守る mundi 2018年12月号
- 備えと危機対応-「強靭な保健システム構築」をめざして- MISSION1 対策チーム
技術と知識・経験を用いて、JICAは感染症の「早期発見、早期封じ込め」に挑むためのシステムづくりを行っている。
システム構築に向けたその取り組みを見てみよう。
感染症対策チームの立ち上げ
JICAは、エボラウイルス病の大流行を契機に国際緊急援助隊(JDR(注))・感染症対策チームを設立するとともに、途上国の能力向上にも力を入れている。
(注)Japan Disaster Relief.
アウトブレイクから発足した対策チーム
2014年から2015年にかけて、西アフリカでエボラウイルス病が流行した。日本は資金や物資援助を行い、世界保健機関(WHO)を通じてJDR専門家のべ20名を派遣した。一方でJDRの医療チームは本来、地震や台風などの自然災害救援を想定したものであったため、このアウトブレイク(大流行)では派遣することができなかった。日本政府は、この経験から2015年10月にJDR感染症対策チームを新たに立ち上げ、感染症健康危機発生時に対応できる体制を整えた。感染症対策を専門とする医師、看護師等の医療従事者や研究者が200名以上登録し、海外で感染症が流行した際に、迅速に支援することができる。感染症対策チームは、疫学、検査診断、診療・感染制御、公衆衛生対応のそれぞれの専門機能と、チームとして業務がスムーズに行えるよう調整業務を行うロジスティクス機能の五つの機能で構成された。
感染症対策チームによる緊急援助
その後、2015年12月にアフリカのアンゴラで発生した黄熱病の流行は、隣国コンゴ民へ拡大。2016年6月20日、コンゴ民政府より黄熱病流行宣言が発出されたことを受け、感染症対策チームが創設後初めて派遣され、爆発的な感染を防ぐための支援活動を展開してコンゴ民政府やWHOから高い評価を受けることとなる。また、黄熱病に続き2018年5月、コンゴ民で発生したエボラウイルス病に対して、2018年6月には感染症対策チームが派遣された。迅速に現地に赴き、流行地からコンゴ川を航行する船で首都キンシャサに流入する人々に対して検疫を強化するため、臨時検疫所の活動支援や首都での検査支援を行った。さらに、必要な物資の提供とともに同国の検疫官などに技術指導を行うことで、対策チームが帰国した後も、引き続き自国で対応のできる体制の構築を支援している。
「感染症の健康危機が発生した際には、日本も国際緊急援助ができる体制を整えていますが、それ以前に、危機発生時にその国自体で対応ができるよう普段から感染症対策の能力を向上させておくことが重要です。発生を最小限にとどめて拡大を防ぐことが一番の対策と考えています」と、コンゴ民で引き続き感染症対策を進める人間開発部の山形律子さんは言う。
「強靭な保健システム構築」によって平時における対策が進行すれば感染症対策チームの派遣も少なくなるはずだ。
日本の国際緊急援助体制
人的援助
・国際緊急援助隊(JDR法に基づく派遣(JICAが事務局機能を担う))
・救助チーム(捜索・救助)
・医療チーム(災害医療)
・専門家チーム(災害応急対策・災害復旧)
・自衛隊部隊(輸送・防疫・医療)
物的援助
・JICAが実施
資金援助
・外務省が実施
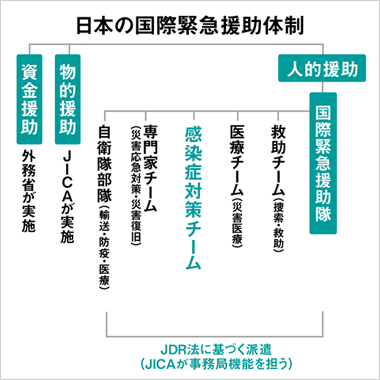
日本の国際緊急援助体制
2018年6月にコンゴ民に派遣されたJDR感染症対策チーム

コンゴ川河口の臨時検疫所で着脱訓練を行う。感染防護衣など資機材の提供も行った。

エボラウイルス病の検査をする様子。

検疫官に対して講義を行うJDR隊員(国立感染症研究所の山岸拓也さん)。

臨時検疫所でデータ管理方法を確認するJDR隊員(国立感染症研究所の島田智恵さん)。











scroll