- トップページ
- ニュース・広報
- 広報
- 広報誌
- mundi
- 基本的人権の実現 一人ひとりが輝ける世界 mundi 2020年3月号
- 権利を守る法や制度を作る Case3 コールセンターで市民と法律をつなぐ コートジボワール
身近な生活の中にある争いごとを解決するため、コートジボワールに設立されたコールセンターが注目を集めている。
・案件名:
司法アクセス強化(課題別研修)(2018年度~2020年度)

毎日、市民からの相談を受けるオペレーター。奥がアナマンさん。
法律をもっと身近に
司法アクセスへの関心の高まり
法律や司法制度が整っていても、市民が役立つと思っていない、法的情報がない、どこに相談すればいいかわからない、金銭的な余裕がない-さまざまな要因で適切な紛争解決にアクセスできない人がいる。このような司法アクセスの問題は国際的にも注目され、持続可能な開発目標(SDGs)のターゲットの一つ「すべての人々に司法への平等なアクセスを提供する」にもなっている。
こうした背景からJICAは課題別研修「司法アクセス強化」を開始。各国から研修員が参加した。研修では、弁護士会をはじめ多くの組織が司法アクセスの向上に取り組み、2006年の日本司法支援センター(法テラス)の設立に至った日本の歴史を紹介。また市民が電話などで法的な情報を容易に得られるよう設置されたコールセンターなどを実際に視察する機会も提供している。研修後、自国でも導入したいという声が多く上がった取り組みの一つがコールセンターの設立だ。
いち早くコールセンターを設立
実際にコールセンターを設置した国がある。コートジボワールだ。当時JICAから派遣されていた司法アドバイザーの協力により、2017年に開設された。現在では同国司法省が独自に運営を行い、市民からの問い合わせに法律情報の提供や適切な相談先の紹介を行っている。「コールセンターのあるアビジャンから580キロ離れている街の住民から土地の売買について相談があり、近くで対応できる窓口を紹介しました。電話だからこそ遠方の人へも情報提供ができます」と、オペレーターのアナマン・アジャベ・フィルメンさんはコールセンターの利点を語る。
コールセンターに連絡すれば法的トラブル解決に役立つ情報が得られるという認識が市民に広がり、相談件数が増えてきている。「オペレーターを増やして対応する予定です。法律が市民に身近なものになり、自分たちの生活を守ってくれるものだという理解が深まっていくことを期待しています」と民刑事局の副局長を務めるギロ・クルマ・サボレさんは語る。
司法アクセスのさらなる改善のために、2019年にはギロさんが「司法アクセス強化」の研修に参加した。日本のコールセンターを初めて訪問し、自国のコールセンターの改善に取り組むとともに、今後は法律相談や、弁護士や裁判費用などを補助する扶助制度なども導入したいと意欲的だ。
他国からの研修員に「どうやってコールセンターを導入したのか」と聞かれることも多く、「他国の司法アクセス改善にも協力していきたい」と語るギロさん。JICAはこうしたコールセンターの他国への展開を支援するための調査も準備している。

コールセンター開設にあたり、法・司法に関する情報提供を行うためのパンフレット類を作成した。

コールセンターは5人により運営。司法省民刑事局長をトップに、オペレーターやその上司である管理者などが携わる。
コートジボワール
国名:コートジボワール共和国
通貨:CFAフラン
人口:2,507万人(2018年世界銀行)
公用語:フランス語
1960年の独立後、30年以上安定した政権運営が続いたが、2002年に内戦が勃発。裁判所や刑務所が破壊され、多くの法曹関係者が出国し、司法機関に対する国民の信頼が低下した。近年では国民和解と経済復興を柱とし、さまざまな改善に取り組んでいる。
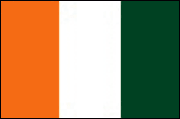

首都:ヤムスクロ
司法アクセスの向上 弁護士の地位向上で、法律を身近な存在に
・案件名:
2020年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト(2015年4月~2020年12月)
「ベトナムでは弁護士の地位が裁判官、検察官、捜査機関に比べてあまり高くありません。また弁護士の多くはハノイやホーチミンに集中していて、北部山岳地帯や中部高原など少数民族が多い地域では、権利の保障や実現に弁護士の力が必要なのに数が少ないという課題がありました」とJICAの齋藤友理香さんは説明する。たとえば土地紛争や離婚、相続、貸金をめぐる民事紛争や刑事弁護、行政とのトラブルなどを弁護士に相談できれば、泣き寝入りや不利な訴訟を避けることができる。弁護士の地位や能力の向上は、法律や人権が守られる社会の形成につながるのだ。
そこで2009年、ベトナムはJICAの協力を得て全国統一の弁護士会を設立。日本弁護士連合会と協力し、被疑者の弁護権を保障する当番弁護士制度の導入や、日本の地方の弁護士会を訪問してその活動を参考にする取り組みなどを行ってきた。ベトナム弁護士連合会会長のド・ゴック・ティンさんは「法律相談や刑事弁護など実質的なスキルや経験を学ぶことができました。とくに弁護士が少ない日本の地域での経験や政策を学び、ベトナムに合った形で導入しています」と研修の成果を語る。2019年には裁判官、検察官、弁護士がひとつのグループとして研修に参加した。それぞれの立場や役割を理解し合い、法で守られる社会に向けて法曹三者が力を合わせることの重要性を認識した。
「継続した研修で弁護士会の機能は強化され、個々の弁護士の能力向上や、地方での弁護士会活動の活発化などの動きが生まれています。弁護士が人々の身近な存在になってきています」と齋藤さん。多様化する法律ニーズに対する研修制度の確立や、著しいグローバル化の中での契約紛争の増加にどう対応するかなど新しい課題も生まれていて、これからも日本の経験はベトナムの司法に役立っていく。

ベトナム

日本での研修で行われたワークショップ。

山岳地帯の人々に向けて法律の普及活動を行うベトナム人弁護士(写真提供/ベトナム弁護士連合会)。











scroll