持続的な地雷・不発弾対策の政府能力強化とアフリカ版ロードマップを考える~地雷対策ワークショップを通じたアフリカ・カンボジア・日本の協力~
掲載日:2025.03.24
イベント |
掲載日:2025.03.24
イベント |
日時:2025年2月19~21日
場所:ザンビア・ルサカ/シアボンガ(南部ジンバブエとの国境地域)
ワークショップ概要:
地雷・不発弾は紛争中だけではなく、紛争終了後も長い期間にわたって残るため、復興・開発を妨げる原因となります。地雷や不発弾の問題に効果的に対応するためには、国による地雷対策のオーナーシップ(National Ownership、ナショナル・オーナーシップ)の向上と地雷・不発弾対策に係る国の能力(National Capacity、ナショナル・キャパシティ)の強化が重要です。
JICAは、1998年からカンボジア地雷対策センター(CMAC)との協力を続けてきました。2010年以降はCMACの知見・技術を他の地雷・不発弾被害国に共有する取り組みに力を入れ、これまでに世界各国の500人以上の地雷対策関係者に対して研修等を実施しました。2024年7月上川外務大臣(当時)より発表された「日カンボジア地雷イニシアティブ」においても、カンボジアによる地雷対策技術や組織能力についての国際的な知見共有の推進が含まれています。
JICAはCMACや国連地雷対策サービス部(UNMAS)との連携のもと、アフリカ諸国への地雷対策技術(調査・探査、除去等)や関連制度・組織運営に係る技術・知見の共有を行っています。その結果として各国の能力(National Capacity)を強化し、効果的な地雷・不発弾対策を推進することを目指しています。
2025年2月19日~21日の3日間、ザンビアのルサカにて地雷・不発弾対策のワークショップが開催されました。CMAC、UNMASと、過去数回実施されたワークショップの参加者であるエチオピア、ソマリア、ナイジェリア、南スーダンに加えて、今回はザンビアが参加しました。(過去のワークショップの様子はこちら)
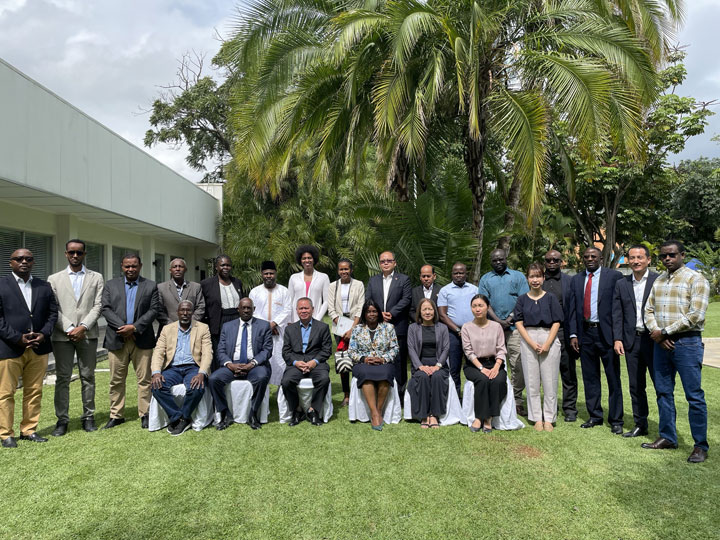
ワークショップ参加者とザンビア外務・国際協力次官の集合写真
今回開催地となったザンビアは、2026年オタワ条約締約国会議の議長職を務める予定です。本年(2025年)は日本、昨年はカンボジアが議長職を務めており、議長職を繋ぐ3ヵ国が中心となってアフリカの地雷被害国と知見を共有する場になりました。
初日はザンビア南部ジンバブエとの国境地帯であるシアボンガを訪問しました。ザンビア国内にある地雷・不発弾は1960-80年にかけての南部アフリカ諸国(アンゴラ・ジンバブエ・モザンビーク・コンゴ民主共和国・ナミビア)の独立闘争に起因しており、汚染地域のほぼ全てが国境沿いに位置しています。
コミュニティでの視察では、地雷の被害にあった女性が体験談を語りました。彼女は、小学校からの下校時に木になっているフルーツを取ろうと歩道の外に足を踏み入れたことで地雷の被害に遭い、右脚を失いました。こうした地雷による痛ましい被害を減らすため、ザンビアではコミュニティにおける地雷回避教育を実施しています。ワークショップの参加各国は、コミュニティとの強い連携のもとにこうした地雷回避教育を実施していくことが持続性のカギであると述べていました。

コミュニティにて地雷被害の体験談を話してくださった住民と、謝意を述べるJICA小向国際協力専門員
2日目と3日目は、参加したアフリカ5か国の地雷対策組織の現状の分析と今後のキャパシティ強化のために必要な活動についての協議が行われました。長年の知見を有するCMACの組織発展段階の変遷の歴史を学んだ後、参加各国地雷対策組織の現状と照らし合わせて、次に行うべきアクションについて議論しました。

ワークショップの様子
2日間の活発な議論を経て、最終的にはアフリカの地雷対策組織能力強化のためのロードマップが策定されました。ロードマップにより、今後の各組織の能力強化のための段階に応じた取組み事項が明確化され、JICA、CMAC、UNMASが検討すべき協力内容も整理されました。参加者からも、能力強化のための道筋と現状取り組むべき優先事項が帰国後共有できる文書として作成されたことや実践的な協議の内容を評価するコメントが寄せられました。
帰国後、参加者は今回のワークショップでの議論を基に、自国の地雷を自分たちが主体となって除去し、復興・開発に繋げていくことができる持続的な体制を整備することになります。JICAはそうした取り組みを引き続き支援していきます。

最終セッション終了後参加者の集合写真




scroll