ウェビナー「SICA地域における南南協力・三角協力の強化」が開催されました(2024年5月28、29日)
2024.07.04
2024年5月28-29日の両日、中米統合機構(SICA)事務総局とJICAの共催によるウエビナー「SICA地域における南南協力・三角協力の強化」が開催されました。

SICAは中米地域の統合と発展を目的として設立された地域機関で、JICAは2000年よりSICA事務総局へ専門家を派遣し、SICAに加盟する8か国(ベリーズ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国)による地域協力を支援しています。
SICA加盟国は2013年に合意された「地域協力の管理・調整・情報のためのメカニズム」に沿って地域協力を展開しており、JICAもこれを支援してきましたが、2023年にこのメカニズムを補完する「南南協力・三角協力ガイドライン」がSICA加盟国外務大臣会合により承認されました。これにより、途上国間で知見を共有する南南協力と、それをドナー国や国際機関などが支援する三角協力を、地域協力のモダリティーとして活性化することが求められるようになりました。このような背景から、SICA加盟国の南南協力・三角協力実施能力強化を目的とするウエビナーを、SICAとJICAの共催で開催することになりました。
SICA事務総局からはイングリッド・フィゲロア執行役、JICAからは小原学中南米部長、SICA議長国(ホンジュラス)からはヘラルド・トーレス外務副大臣が開会の挨拶を行った初日では、JICAの対中南米協力戦略とその中で南南協力・三角協力が担ってきた役割を秋山慎太郎中米・カリブ課長が説明しました。日本は第三国研修、第三国専門家派遣などのスキームや、それらを複合的に組み合わせた包括的な三角協力の枠組みである「パートナーシップ・プログラム」を世界12か国と締結しており、中南米地域ではメキシコ、チリ、ブラジル、アルゼンチンの4か国が該当します。その後SICA事務総局のカルメン・マロキン国際協力局長がSICAの「南南協力・三角協力ガイドライン」の概要について説明した後、メキシコ、チリ、コスタリカ、ホンジュラス、JICA、中米社会統合事務局(SISCA)、中米中小零細企業支援センター(CENPROMYPE)代表によるパネルディスカッションが開催されました。
パネルディスカッションでは、メキシコ代表が2011年に「協力法」の制定後、国際協力実施のために法的枠組みや制度を構築してきた歴史と、メキシコ-チリ協力基金やメキシコ-ウルグアイ協力基金など、南南協力・三角協力のために構築した資金メカニズムの概要を共有しました。チリ代表はメキシコ、スペイン、EUとそれぞれ持っている南南協力・三角協力基金について言及すると共に、グッドプラクティスとして、協力額全体の50%をチリがキャッシュで提供していること、また、外国からの資金を公共予算に計上することなくチリ国際協力庁が独自に管理するための法的枠組みをラテンアメリカ地域では唯一持っている点を強調しました。コスタリカ代表は、南南協力・三角協力の「受益国」から「供給国」になるために「南南協力オファーカタログ」をネット上で公開していることを紹介し、SICA議長国であるホンジュラス代表は懸案となっている「SICA南南協力・三角協力基金」の設立に向けたロードマップを作成することを提案しました。JICA代表はSICAがファシリテーターとなって域内での知見や技術の共有を醸成することへの期待と、地域機関としてのSICAがその知見を他の地域機関(カリブ共同体、太平洋同盟、メソアメリカプロジェクト等)に共有する重要性について述べました。SICAの組織であるSISCAは、すでにチリとの三角協力でSICA地域へチリの社会保障制度を共有した事例を紹介し、同じくSICAの組織であるCENPROMYPEは、中小零細企業支援というセクター横断的なテーマでは、多数のセクター機関が集まるSICAの優位性を活かし、セクター間連携による効果的な三角協力が可能であることを強調しました。
2日目は、JICAアルゼンチン事務所スタッフでプロジェクト・サイクル・マネジメント(PCM)のモデレーターであるクラウディア・シンザトさんが、「日本・アルゼンチン・パートナーシッププログラム」の枠組みで実施される案件を、PCM手法を用いて形成・実施・モニタリング・評価することで協力効果を高めてきた実例を紹介しました。次にブラジル国際協力庁のマリアナ・ファルカォン・ディアスさんは、ブラジルの南南協力実施機関が質の高い南南協力を実施できるよう、プロジェクト管理のためのマニュアルの整備や、実施機関が主体的にプロジェクトの進捗を管理するために「プロジェクト・フォローアップ委員会」を各プロジェクトに設けていることを紹介しました。最後にJICAエルサルバドル事務所のコンサルタントであるエルネスト・ノスタさん及びサルバドール・ビジャロボスさんが、南南協力・三角協力の推進そのものが、国際協力をより効果的、継続的、持続的なものにする手段となりうる点や、そのためにも成果重視の案件管理が重要であると述べました。
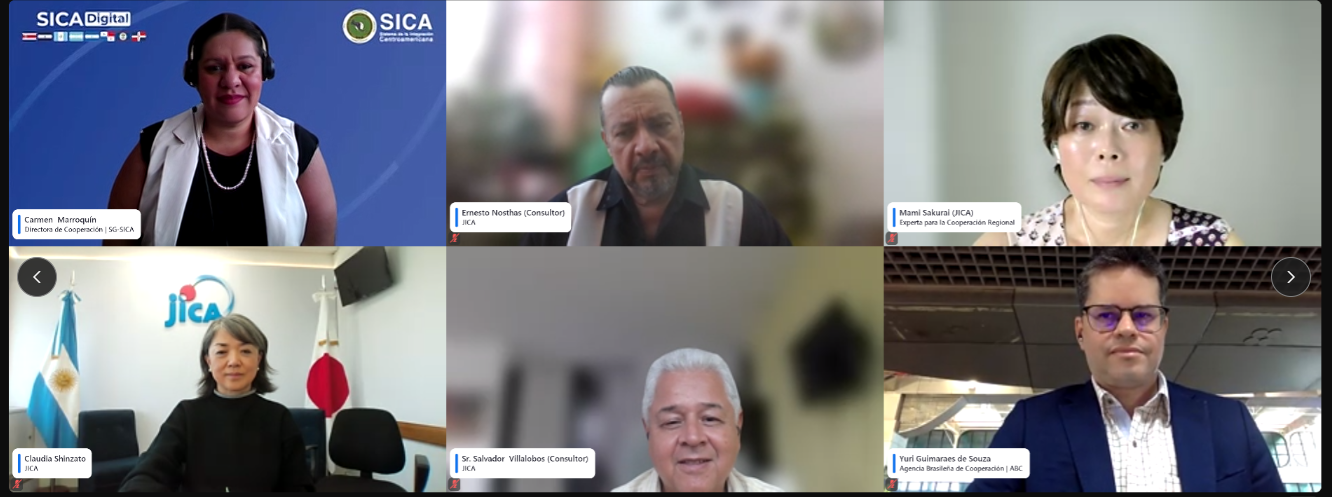
ウエビナーの最後に、地域協力アドバイザーとしてJICAからSICA事務総局へ派遣されている櫻井真美専門家より、事前に実施したアンケート調査の結果が共有されました。南南協力・三角協力を実施するために必要な4つの要素(①法的枠組みと制度、②プロジェクト管理手法、③南南協力実施機関との調整、④南南協力・三角協力のための資金メカニズム)について、いずれもSICA地域では能力強化が必要なテーマであることに加えて、南南協力・三角協力の現状や実績を把握するための地域レベルでのデーターベース構築、ニーズとオファーのマッチングメカニズム、南南協力・三角協力の成果/インパクトの情報発信などが課題と考えられていることが回答結果の分析から分かりました。この分析結果を受けてJICAアルゼンチン事務所のシンザトさんは、SICA地域の実務者に対してPCM手法を教えるためのワークショップを実施することを提案しました。一方でブラジル国際協力庁のユーリ・ジ・ソウザさんは、アンケート調査の結果はブラジルが南南協力・三角協力実施国として向き合ってきた課題そのものであり、ブラジルの経験を研修等を通じてSICA地域に共有する意向を表明しました。
セミナー後に行ったウエビナー参加者へのアンケート調査の結果では、このようなウエビナーや研修を通じて南南協力・三角協力の実務者同士の経験共有や人材育成を支援することの重要性と、南南協力を支える資金メカニズム構築の必要性、及び一連の課題を解決するためのJICAやSICAからの支援に対する期待の声が多く上がりました。この結果を踏まえて、南南協力・三角協力の日本のパートナーである国々の組織強化・人材育成にJICAとして今後どう取り組むかを、引き続き考えていきたいと思います。
scroll