- トップページ
- 海外での取り組み
- コスタリカ
- 代表的なプロジェクト
- 信頼で世界をつなぐ~メッセージ集~
- コスタリカにおける国際協力50周年記念 インタビュー 笹川剛さん
インタビュー
笹川剛さん
-
1
.
氏名:笹川剛
プロジェクト名:コスタリカ胃癌早期診断プロジェクト
プロジェクト期間:1995年4月~2000年3月
派遣期間1995年8月~2000年3月 -
2
.
コスタリカの印象
29年前、インターネットもない時代でした。当初、コスタリカと言われても、どこにあるのかも分からず、すぐに世界地図を買った覚えがあります。
「どこか南の島で原住民が歌って踊って暮らしているんだろう」本気でそう思ってました。 -
3
.
活動内容
コスタリカは日本と同様胃癌の発生頻度が非常に高い国です。しかしながら、我が国では60%を超える早期胃癌の発見率は他国同様コスタリカでは5%以下と非常に低く、胃癌の早期発見が大きな課題となっています。そこで、胃癌検診センターを設立し、日本で広く行われている胃検診システムを通じて胃癌の診断、治療技術をカウンターパートに移転することを目的にプロジェクトは行われました。私は日本側チームリーダーとして4年半コスタリカに赴任しました。その結果、早期胃癌を日本の約10倍の高率で発見し、日本と同等の手術成績を残せました。2000年にプロジェクトが終了した後も検診センターは現在も彼らの独力で維持運営され、彼らとの交流も続けられて2014年に早期定年退職後に再びコスタリカに渡りました。 -
4
.
コスタリカでの経験がご自身に与えている影響
日本では早期胃癌の発見率がなぜ高いか。
日本では胃検診で発見される早期胃癌は全体の20%ほどと言われています。それでは残りの80%の早期胃癌はどこで発見されているのでしょうか?その多くは一般病院や、街のクリニックなどの内視鏡検査、それも一般内科医や外科医など内視鏡専門医ではない医師によって発見されています。日本ではいつでもどこでも誰もが簡単に内視鏡検査が受けられるのです。
なぜ、コスタリカでは胃癌の早期診断が遅れているか。
コスタリカでも胃癌の診断は内視鏡によって行われています。そして国で2500人ほどの消化器内科医(内視鏡医)のみが検査を行います。しかしその多くが都会に集中しており、田舎では内視鏡の機器があっても内視鏡医がいないために検査ができないところも多くあります。いわば宝の持ち腐れです。
胃癌発見のために私が今、行っていること。
そこで、私は胃癌の発見数を上げるには、内視鏡検査を施行できる医師の数を増やさなくてはいけないという結論に達しました。
今、私は胃癌検診センターにおいて外科レジデントを対象に「胃内視鏡研修コース」を主宰しています。
これは内視鏡経験の全くない研修医をマンツーマン指導して4か月で安全で確実な内視鏡技術を身に着けさせるものです。
内視鏡医を対象に技術レベルを上げるコースは数多く存在しますが、無経験の者を手取り足取りマンツーマンで指導するコースは寡聞にして聞きません。
私はこれを「笹川塾」と名付け、塾生には私をJYUKUCHO(塾長)と呼ばせて一人悦に入ってます。
現在まで17人の先生が研修を終え、それぞれの赴任地で実際に検査をして胃癌を発見しており、少しずつですが、私の夢がかなえられつつあります。
微力ながら、コスタリカの胃癌の早期診断に貢献できれば幸甚です。 -
5
.
現在の隊員を始めコスタリカ協力に携わる皆さんへのメッセージ
当プロジェクトは2000年に終了後、公的な日本の経済的、技術的な援助がほぼなかったにも関わらず、彼らのみで今日まで存続、さらに大腸がん検診、肝胆膵疾患の内視鏡的治療などを行う国内唯一の施設として発展し、現在「国立がん検診センター」として認定されています。多くのJICAのプロジェクトが終了後に消滅してしまう事実を鑑みますと稀有の存在と自負しております。その理由の一つにはプロジェクト終了後にもカウンターパートと個人的な関係は続けられ、意思疎通がされていたことが大きいと思っています。
今や、コスタリカはOECD加盟国の一つです。今度は援助される側から援助する側へとなったわけです。JICAがいう南南協力、第三国研修などそれが本当に必要ならば彼ら自身がやればいいのです。この国が独り立ちをしていくためにも、これを契機に日本の援助は縮小するべきだと私は強く思っています。
実のある国際協力とは何か。JICAの姿勢が問われることになるでしょう。
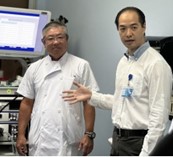















scroll