JICA Magazine
『JICA Magazine』はJICAが発行する広報誌です。世界中の開発途上国 の現状や、現場で活躍する人々の姿や活動内容を紹介します。 これまでの月刊『mundi』をリニューアルし、2021年6月より隔月刊と なり、本誌、ウェブサイト共に新しく生まれ変わりました。
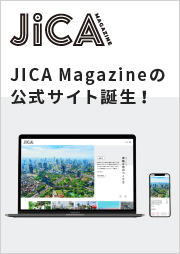
世界は可能性でいっぱい
JICA Magazine編集部のポッドキャスト番組。世界各地、多種多様な職種で活動するJICA海外協力隊員や、専門家などを毎回ゲストに迎え、生の声をお届けします。放送はJICA Magazineと連動し、隔月配信予定です。
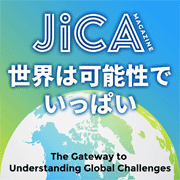
地球ギャラリー
広報誌の人気企画「地球ギャラリー」を、オンラインギャラリーとしてお楽しみいただけます。新進気鋭の写真家やフォトジャーナリストらがとらえた途上国を写真と文章で紹介しています。誌面では語り切れなかったエピソードを盛り込んだインタビュー動画もぜひご覧ください。












scroll